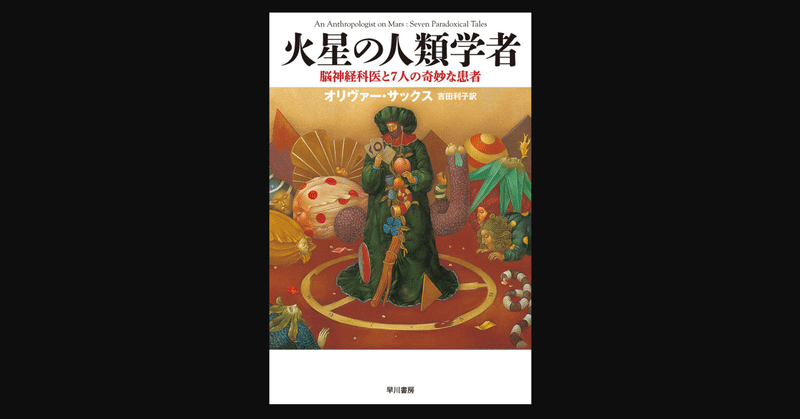
人類必読! 障害者への温かい眼差しを通し人間を理解する 『火星の人類学者──脳神経科医と7人の奇妙な患者』
ほぼ毎日読書をし、ほぼ毎日「読書ログ」を書いています。351冊目。
25年前、私がフランス料理店でコックとして勤務していたときの話。同僚にマー君と呼ばれている男の子が居た。年齢は20歳位だったかな。マー君には重い知的障害があって、障害者雇用で雇われ、仕事をしていた。
マー君は言葉が喋れないし、他の人が話す言葉も、ほとんどわからない。身体の大きな2歳児みたいな感じだった。
話しかけても「おー」とか「あー」とか答えてくれるが、多分「聞こえてるよ」といった意思表示でしかない様子だ。
彼の仕事は皿洗い。水を張ったシンクで漬け置きされていた皿を食洗器に並べ入れる、蓋を閉じる、スイッチを押す、機械が動いている間はずっと唇を指で弾きながら「ブルブルブルブルブル」と音を立てながら待つ、そのうち食洗器がピーと音を立てるので蓋を開け、綺麗になった皿を取り出し、種類別に積み上げ、皿置き場に戻す。
そして、また最初に戻る。
マー君は、知的障害のレベルでは、社会にかかわれるギリギリの線だったのではないかと思う。会話が出来なかったので、皿の洗い方を、文字通り手取り足取り、時間をかけて教えたと聞いた。
僕が店に入った時には、彼は完璧に皿洗いの仕事をこなしていた。たまに、力が入りすぎて皿を叩き割っていた(凄まじい膂力だった)が、問題らしい問題といえばそれくらいだった。
彼がお店に居てくれたおかげで、障害者を身近に感じる事ができたし、障害とはなにか、完全ではないにしろ、ある程度理解する事が出来たような気がする。皿を割ってしまうのは、彼の個性でしかない。勝手に残飯を食べ始めるのも彼の個性だ。少なくとも、店のスタッフは自然と全員そのように考えていた。
皿の割れる頻度が上がったときは、皿を置く場所に布巾を置いたり、力の入れ方を丁寧に教えたりした。それは、背の低い人向けに踏み台を買ってあげるのと同じで、相手の個性にあわせて仕組みを整えることでしかなかった。背が低いからといって怒られないし、解雇もされないように、マー君が皿を何枚割ろうが(社長以外)誰も怒らないし解雇の理由にはならなかった。
彼には、家族からも同僚からも、社会からも守られなければ生きていくことすら出来ないという危うさがあったのだけど、自己の危うさなんてものは、程度の差はあれ、私にも他の人にもあるものだし。
脳の機能、身体の機能が違えば、同じ世界を見ていても、それをどのように知覚しているのかは個々人で違ってくる。
背の低い人と、高い人では、同じ場所に立っていても見えている景色は違う。部屋の鴨居を見て、頭を狙う凶器だと感じる人も居るし、エレベータの上階ボタンが難攻不落の高山に感じる人も居る。
本書のタイトルにもある「火星の人類学者」は、高度自閉症患者である動物学者のテンプル・グランディンが自らを自称して言った言葉だ。
彼女は、人間の非言語コミュニケーションが全く理解出来ず、複雑な感情や人間同士の探り合いなどが理解出来ない。だが、非常に高い知性という個性も備えていた。
動物学で学んだノウハウを活用し、人間の表面的な動きから相手の感情を類推するためのデータを積み重ね、それによって相手の感情や考えを知り、その先の行動を予想してやりとりをしている。
それは、まるで火星人である自分が人類という生き物を観察しているようだと言い、そこで表題となる「火星の人類学者」という言葉が生まれた。
得意なこともあれば、苦手なこともある。ただそれだけだ。
本書には、テンプル・グランディン以外にも非常に個性的な人々が登場する。特に印象に残るのは、トゥレット症候群の外科医の話だ。
彼は五歩歩く毎に地面に手をつくチック症状をもっていた。また、日常生活では、自分では御しがたい衝動に行動を支配されており、気分の乱れを制御できないでいる。
しかし外科医として手術が始まると、チックも気分の乱れもピタリと収まってしまう。トゥレット症候群がその時だけ消え失せる。
手術をしていない時の彼は、あきらかに他の人とは違うのだけど、病院の同僚や患者から理解され、信頼され、良い外科医としての評価も受けている。奇妙なチック症状は、彼の個性として受け入れられている。
初めて本書を読んだのは1997年で、ちょうどコックをやめた後なのだけど、この外科医の話を読んだとき、彼が社会に受け入れられている事に深く感動をしたのを思い出す。
またマー君の話に戻るけど、残念ながら同僚の中にはマー君を馬鹿にしていじめるような人も居た。彼曰く、障害者は人間ではないという。本気で発言していて、かつ是正すること出来ないのであれば、それは、彼が抱える一つの障害なのかもしれない。それを個性として認め、許す事が出来るのかと問われると、うまく答えられない。
彼の姉がフロアに居たのだけど、彼女にとっては、マー君はかけがえのない家族であった。彼女は、年の近い弟をまるで自分の子供のように可愛がっていた。そして、マーくんをいじめるスタッフにも寛容だった。それが慣れから来るものだったとしたら悲しい話だな。
さておき、オリヴァー・サックスの本を読んで、私の人間感は大きくかわっただろうし、人への接し方も変わったように思う。健常者も、障害者も、その間に無限にあるグラデーションのどこかに居る方も、みんな人間だし、自分の生きる世界を持っている。それをちゃんと保証してくれている社会というものをしっかり継続させていかなければと感じる。
オリヴァー・サックスと聞くと映画『レナードの朝』を思い出すかもしれない。または、サックスの少年時代を書いた自伝的エッセイ『タングステンおじさん』も良い本でファンが多いが、私にとってのベストは本書である。
たまたま書店で文庫版を見つけ、懐かしくなり、自宅に取ってあった単行本を再読してみたのだけど、相変わらず引き込まれた。最高です。皆様も是非。
「それって有意義だねぇ」と言われるような事につかいます。
