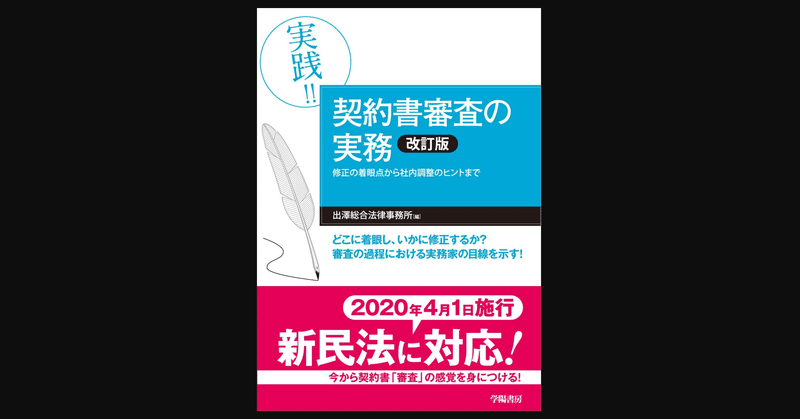
クリエイティブ、WEB制作、システム開発系の方は必読だ、受注側、発注側に関わらず絶対に 『契約書審査の実務』
私は、システム開発やWEB制作の仕事をしています。
外部との何かしらの受発注をする際、必ず発生するのが契約。毎度面倒だなとは思いながらも、契約書の内容をチェックしたり、条件をチェックしたりしています。大事だしね。
業界によっては口頭発注がまかり通っているケースもあるとか聞きますが、たいていはちゃんと基本契約を交わし、守秘義務を交わし、個別発注で金額を含めた条件を定義しているかと思います。
皆さん、お仕事は何をされていますか? クリエーティブ系ですか? WEBや、システム開発、デザインなどを商品にしていますか。それとも、それらを発注する側の立場ですか?
その際、契約書にはしっかり目を通しているでしょうか。大きい会社ほど、こっそり不平等な条文が巧妙に設定されていたりします。
知財や権利、責任の範囲、賠償責任の範囲、よく見てサインしていますか?
うっかり、へんな契約書にサインをしてしまったばかりに、発注側にさんざん振り回されて利益が出ないどころか、損害賠償まで求められてしまい倒産したなんて話は、二十数年の受託仕事人生で何度か耳にしたことがあります。怖い怖い。
本書は、法務部門で働く方向けの契約書審査のノウハウ集。法務系の勉強をしている方に強く進められたくらいなので、きっとオススメです。いや、他の実用書を読んだことがないので、比べたうえでおすすめしているわけではないのですが、完全に現場側で法律に疎い私にも理解できるし、わかりやすいし勉強にもなるし、こりゃ良い本なのではと思うのです。
本書、現場の人たちが仕事をすすめる上で知っておいたほうが良い法律知識が多く掲載されており、受託仕事、委任仕事をしている現場の方は、絶対に目を通しておいたほうが良いですよ。本当に。特にマネジメントや対お客の窓口の方。
そして、2020年4月に施行された改正民法(新民法)の内容をご存知ですか? 制作現場でよく話題にあがる「瑕疵担保責任」は、新民法では契約不適合という新しい言葉に変わっていますよ。
バグなどの対応も、かつては納品から1年たてば瑕疵担保責任が消える内容だったものが、発注側がベンダー責任の不具合を発見し、発見から1年以内に申立があれば、ベンダーは(多分、時効となるまで)その不具合に対応しなければならない、といった感じに変更されています。
そうなってしまうと、見積もりの作り方だって全然変わってくるはず。リスクを見積もりに乗せなければならない。
だって、短いサイクルで小中規模のシステム開発を多く回している会社だと、納品するたびに「なにかあったら無償で対応しなければならないシステム」が、次々にストックされていくことになります。そのためにはノウハウの継承だってしなければならない。これは、結構しんどいのでは。
受託仕事を気軽に受けることなど、もはやできやしない。いや、最初から適当にやっちゃいけないんだけど、どうしても中途半端にならざるを得ないケースってのはあるじゃないですか。納期ありきなのに、直前までクライアントが意思決定を引き伸ばして突貫工事になるなんてケースは、制作現場に居る方なら皆経験していると思います。
今後はそういった状態は全てシャットアウトするような建て付けにする必要があるのではないかな。マイルストーンをしっかり決め、クライアント都合でそれが守られなかったら、無慈悲にでもその後の工程、納期を伸ばすという約束にしておく。建前だけになったとしても、そういう約束にしておく。
だって、責任をしっかり取れるコストとスケジュールで品質担保する同意が出来なければ、ベンダー側は長期に渡って「いい加減なやっつけ仕事になってしまったものでも長期に渡り無償で修正に応じる」という大きなリスクを背負うことになる。このリスク、舐めたら会社が潰れますよ。
現場は、新民法で何が変わったのかを理解しなければ、思わぬリスクを背負い込むことになりかねない。こりゃ、ちょっと頑張って勉強せねば。
本書は、企業の法務部の方に向けた優れた実務書なので、契約書をチェックする上で重要となる点を網羅的に紹介する内容になっている。もちろん法律の範囲内、社会通念上の範囲内で収めるわけだが、その線引をどうしたらよいか、どのように調整をしたらよいか、契約相手との調整、社内との調整をどのようにすすめたらよいか、そういったノウハウが揃う。
法務部の方には便利で実践的な内容だ。
そして、これらの知識、ノウハウは、前述した通り、法務部門だけではなく現場にも必須のものである。
現場のスタッフは、自分の職責が、いったいどういった義務を負っているのか、それを現場は把握していなければならない。特にクリエーティブ職、ディレクター職、プロジェクトマネジメント職の人には絶対に必要な法的知識があり、嫌でも学ばなければならない。
請負仕事を受注すると、それだけでどんな責任が発生するのか、それを正確に理解しているひとは少ないのでは。善管注意義務や信義上の法的義務について、どのあたりに線が惹かれているのか、これを理解しているひとは少ないのではないか。まっとうな仕事をするためには学ばなければならない。
発注側だってうかうかしていられない。デザイナーやWEB制作会社、システム制作会社など、相手はベンダーでプロなんだから、放っておけば成果物が出てくるはずだし、最悪期待するものが出来なければ金を払わなければいい。なんなら損害賠償を求めたっていい。なんて甘く見ている人は少なからず居られるだろう。そういった方々は、自分にも信義則上の協力義務があり、それを満たさなければ自分が訴えられるかもしれないと考えたことなど無いかもしれない。たとえ発注側だとしても、適切な協力義務を果たさなければ自分が責任を負うことになる。
繰り返しになるが、本書に書かれている内容は、法務部門が実務に活用するのはもちろん、受発注相応の現場の方々、現場をマネジメントする方々、それらを営業する方々、すべての人が把握しておくべき内容だ。
事業規模(人数)が小さいほど、契約書はおざなりになりがちだ、発注側だろうと、受注側だろうと、事業規模が小さいほど相手の出してきた雛形に従いがちだろう。盲判でハイどうぞの世界だ。下手したら、契約書を結ばずに見積書と発注書(これすらない場合も)だけで仕事をしている場合もあるだろう。
しかし、事業規模が小さいほど、一つの案件で炎上した際のダメージが大きいことを理解しておきたい。個人事業主の方がこういったことに巻き込まれると、人生を大きく左右されかねない。要注意だ。
せめて、契約書をざっとチェックしたときに、変な条文をみつけたり、リスク事項に違和感を感じる事ができるセンサーを養っておきたい。本書はその助けになる。一度手にとって目を通してみることをおすすめしたい。
「それって有意義だねぇ」と言われるような事につかいます。
