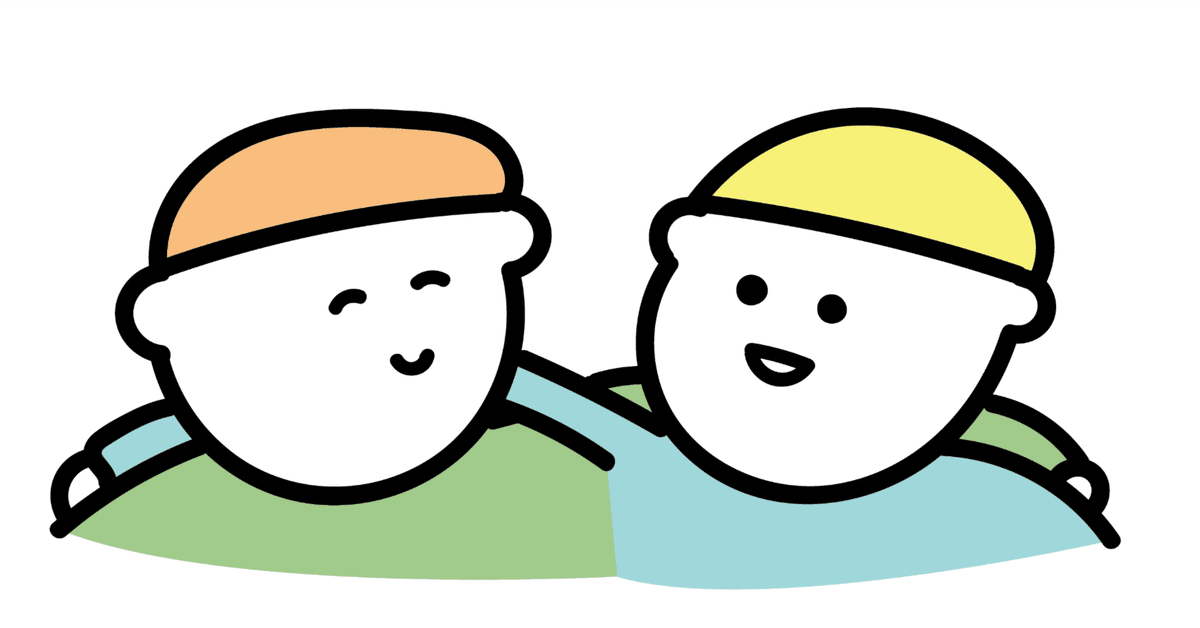
コミュニティーマネージャーと3つの視点
この世界には、たくさんのコミュニティーがある。
改めて辞書で「コミュニティー」を調べてみると、スマートに説明してくれていた。
「community」とは、共同体・共同社会・集団のことを意味する英語表現である。
コミュニティとは、共通の目的や興味、地域などによって結びついた人々の集まりを指す言葉である。この集まりは、情報の共有、相互支援、意見交換などを通じて、その目的や興味を深め、また地域の絆を強化する役割を果たしている。コミュニティは、その形態により地域コミュニティ、オンラインコミュニティ、趣味コミュニティなどと分類される。
共同体といえば、家族や親戚、学生の学級も当てはまる!!!!
やはり、私はコミュニティーが大好きなのだと改めて気が付いた。
コミュニティーについて深く知るためには、視点と思考と時間が必要。
その視点を改めて3ついただいたので、考えてみたいと思います。
コミュニティーを分解して、分析しよう!
3つの視点の一つ目は・・・
ダニエルキルの成功循環モデル
組織やコミュニティーが持続的に「結果」を出し、成長し続けるためには、一見遠回りするようにも見えますが、
①関係性の質
②思考の質
③行動の質
④結果の質
を向上させることが重要。
「結果」を紐解くとそれぞれのフェーズが良い循環(グッドサイクル)として回っているはずだ、と説いています。
関係性を最重要ポイントとして考え、悪い循環(バッドサイクル)をいかに早く気づき、食い止めて、グッドサイクルへの軌道修正ができるかが鍵となることを学びました。
企業で、上司やグループメンバーと定期的に1on1をしたり、個人面談が用意されているのは、上記の理論を根拠として関係性を深めるためだと分かりますね!
(仕事として考えると分かりやすかったため、参考にしたサイトは下記に示しておきます。)
2つ目の視点は・・・
タンバー数
ターバン?(今インドにいるので、脳内変換がおかしなことに笑)
いや、タンバー数です。初めて知りました。
タンバー数は、一人の人間が社会生活を行う上で、人間関係を円滑に保てる人数として定められています。そしてその人数により関係性が変わることを説いています。
(今はタンバー数を否定している研究もあるのだとか。)
ここで押さえたいことは、コミュニティーをデザインする時には、人数の規模感やグルーピング、メンバー構成がいかに重要かということです。
さらに、小グループを作るとしたらそのコミュニティーの理念や志を共有することの大切さを学びました。
特に参考にしたサイトを下記です。
最後、3つ目の視点は・・・
コミュニティーの焚き火理論
コミュニティーのフェーズには「焚き火」のように、工程がある。メンバー同士が影響し合いメラメラ燃えている場面もあれば、下火の時もある。
火種はあるが、空気が足りない場合も。
大学の4年間活動していた、子どもに自然体験を提供する団体では、キャンプの最終夜に必ずキャンプファイヤー、もしくはキャンドルファイヤー(雨天時)を行っていた。
①火付け役
ある国の神様や原始人、火の神などで世界観や、設定を決めます。ここで参加者の心を掴めるかが大事になります。
これこそ、コミュニティーの魅力。ここがブレているとコミュニティーが台無しです。
②ゲーム進行役
参加者の年齢やどのジャンルが好きか、判断しゲーム内容を決めます。(体を動かす・少し頭を使う・歌を歌うなどゲーム内容によって盛り上がり方が全く異なる。)
【ゲーム=イベントや企画】と捉えました。メンバー主催でも良いし、コミュマネが企画してコミュニティーを活性化させることが目的ですね。まさに、コミュニティーマネージャーの腕の見せ所だと感じました。
③火消し役
キャンプファイヤー界隈では、「落とし」とも言われます。今まで高まったテンションなど体も心も落ち着かせ、このキャンプや自然体験の中で何を感じ、何を学んだか自己内省する時間に収束させていきます。長期キャンプの場合は、班での振り返りも行います。火は焚き火のように小さくなり、暖炉を囲うイメージです。
コミュニティーも期間終了を見通して、コミュニティー運営の初めにどのような収束を見通しているかまでをデザインする必要があるのだと分かりました。
久しぶりにキャンプリーダーだった自分を思い出しました。
引用したサイトを載せておきます。
3つの視点をどのように活かそうか・・・
上記の3つの視点、いかがだったでしょうか。
この3つの視点をコミュニティーマネージャーとしてどのように活かせるか考えました。
ダニエルキルの成功循環モデル
コミュニティーやメンバー同士の関係性を俯瞰して見て、サイクルのどこにいるのかを確認したり意識してヒアリングしながら進めるよう活かしていきたい。
そして、バッドサイクルにいることが確認できた場合は、一人一人にアプローチして、改善できるかどうか判断します。
また、コミュニティー内でこの循環モデルを共有し、メンバーにも理解を促した場合、「今、行動の質が上手くいってないんだ〜」とコミュニティーの判断基準が明確になります。「行動を変えるには、イベント企画してみる?」などと助言することができます。サイクルの内容こそが、そのコミュニティーの活動、共通言語となり、メンバー同士も客観視できるようになる。それを継続することによって、グッドサイクルが回り続けるコミュニティー運営ができると考えました。
よし、早速メンバーに共有していみよう!
タンバー数
これらの数字は、「絶対数」ではなく、「目安数」としてコミュニティー運営に活かしていきたいと考えました。
理由は、一人一人、心地の良い人間関係の規模感は異なるからです。信頼関係のある小人数で満足するメンバーもいれば、浅くとも広い人間関係が心地良いメンバーもいるだろう。それぞれのメンバーを尊重することの方が重要である。メンバーのタンバー数をそれとなくヒアリングし、調整したり新たなグッドサイクルを始めたりすることに活かしていきます!
コミュニティーの焚き火理論
コミュニティーマネージャーとして、コミュニティ運営の全体像を知っていることこそが活かす場である!
特に、コミュニティーの最終形態や終わり方の理想をコミュニティーオーナーやメンバー一人一人の想いを意識してスタートから取組むことで、より良いコミュニティー運営の一助になれるのではないかと考えました。
フェーズごとにイベントの企画内容が明確になりました!そこにも活かせますね。
3つの視点をコミュニティーマネージャーの活用を考えた時、今まで参加していたコミュニティについて振り返ってみました。
TABIPPO のオンラインコミュニティーに特化してみると、世界一周ゼミでは、代表のしみなおさんが講義の1回分の時間を目一杯かけて「旅の定義」や「会社のビジョン」について説明されていた。
そのコミュニティーのビジョンが共通認識としてベースにあることが3ヶ月間の講座を通してじんわりとメンバーに広がっていったように思います。
また、POOLOではメンバー構成をが4回も変わる。タンバー数の最小値である5名を基準とし、3〜4名で構成された小グループが編成されていて、運営メンバーは、4回分のメンバーをどう構成するのかたくさんの時間を使って話し合ったそう。だからこそ、全員が納得し自立分散型のコミュニティー運営に繋がったのではと考察しています。
これからも考察を続けてゆきます。
コミュニティー運営の様々なエッセンスを考察し、言語化することで自分のものにしていきたいと感じました。
最後に、一言。
「コミュニティー」とは何かと冒頭に載せましたが、下記は辞書のに載っていた説明の最後の一文です。
なんのためにコミュニティーがあるのか。
私はなぜコミュニティーが好きなのか。
どうしてコミュニティーマネージャーになりたいのか。
どんなコミュニティーを作りたいのか。
まさにコミュニティー意味こそが真髄。
そして、真髄を詳しく考えられる3つの視点を学ぶことができて嬉しい限りです。
これからも自分の人生をアップデートし続ける手段として、
またたくさんの方の社会的な繋がりや、学び・成長となるコミュニティーに携わり続けます!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
みなさんのお気に入りのコミュニティーについてお聞かせください!
何か秘密があるかも知れませんね!
サポートしていただけると、最高に嬉しいです!今後の、更なるクリエイティブに使わせていただきます!
