
ココがおすすめ! 運用設計の教科書
運用設計の教科書の重版が決定したので、誤字脱字チェックも含めて久しぶりに読みなおしました。
その中で、著者自身が「エエこと書いてあるわぁ」と思ったおすすめポイントを紹介していきたいと思います!
1章については説明している動画があるよ!
1章~2章の冒頭までが、本書で一番伝えたいことです。
そのあたりは8/24(土)に行ったインフラ勉強会のセッション動画があるのでそちらをご覧いただいても問題ありません。
動画は1時間ぐらいありますが、「どんな内容か把握してから買いたい」「近くに本屋がないから立ち読みできない」といった方は是非ご覧ください。
運用設計の効果
「運用設計をして、いったいどういう効果があるのよ?」と聞かれることは多々あります。(私も始めた当初に色々な方から聞かれましたw)
運用設計の有用性の説明はホラーストーリーで進めると理解してもらいやすいと思います。
書籍では、運用設計をやらなかった場合に起こるであろうトラブルもまとめています。

運用でカバーするケース
諸悪の根源のように語られる「運用回避(運用でカバー)」ですが、盲目的に判断するのがダメなだけで、運用回避した方が良い場合というのもあります。
「ちゃんと考えたうえで、運用回避しようね!」ってのが、私からのメッセージです。


必要なドキュメントを作る
運用の世界では無駄なドキュメンテーションは撲滅すべきです。
ドキュメントを作成するということは、運用開始後はそれらを管理していかなければならないということです。
個人的には、ドキュメントに関しても動線を整備して、必要なものだけ作成すれば良いと考えています。
運用フロー図も盲目的に作るのではなく、情報を整理する必要があるから作るという判断をしたいものです。登場人物が二人しかいないのにフロー図は不要です。

目的・ゴールを意識した運用設計
設計をする上で目的やゴールを考えるのは重要です。
何の目的かわからない、どこがゴールかわからないまま走り出すのは、盗んだバイクで走り出すのと同じぐらい危険なことだと認識しましょう。
目的とゴールは発注者と共有して、それを合意しなければなりません。
あまりに大事なことすぎて、ポイント君も同じことを言っております。

ライフサイクルの考え方
PC管理や利用者管理に限らず、ライフサイクルがあるものは以下の4つが1セットです。
・追加
・更新
・削除
・棚卸
この4つをベースに、システムや会社独自の例外パターンを考えていくことになります。ここテストに出ますよー!

システムの正常性とは?
システムが完全に正常であることを証明するのは、もはや「悪魔の証明」デス。
・システムとはどこまでか?
・利用者の範囲はどこまでか?
・そして、正常とは何なのか?
これらを完璧に定義できなければ、完全無欠の正常性確認手順を作ることはできません。
それなので大切なのは、「正常な状態」を事前に合意しておくことです。

パッチ適用とアップデート
パッチ適用とアップデートは、考え方を分けておいた方が良いと思います。
アップデートは機能追加を伴う場合が多く、機能を利用するかどうかの検討が必要です。
パッチ適用はバグやセキュリティ対応などで、機能への影響は少ない場合がほとんどです。

定型作業と非定型作業
あくまで目安の考え方ですが、利用者やシステムに近い「一次対応」は「定型作業」が多くなります。
運用担当者が解決できなかった問い合わせを受ける「保守対応」は、毎回はじめから考えなければいけない「非定型作業」が多くなります。

運用設計時に考える運用管理
運用管理の詳しい中身(ITILとか)については他の書籍にお任せですが、設計時に運用管理をどう扱うかはまとめています。大きくは3点。
・情報を扱う際のモノサシを決める
・情報の流れと扱うプロセスを決める
・情報の報告先と内容を決める
サービス開始前にこれらは考えておきたいですね。



要件と設計の違い
あんまり運用設計と関係ないですが、どうしても書いておきたかったので載せました。
色々と検討した結果、結婚式に例えてみました。
おそらく、他のも例えられモノがあると思います。
SIer不要論とかあるとは思いますが、どんな形態になろうとも「要件を出す人」と「設計をする人」が協力しながら、時にはぶつかり合いながら新たな仕組みを考えていくという現実は変わりないと思っています。

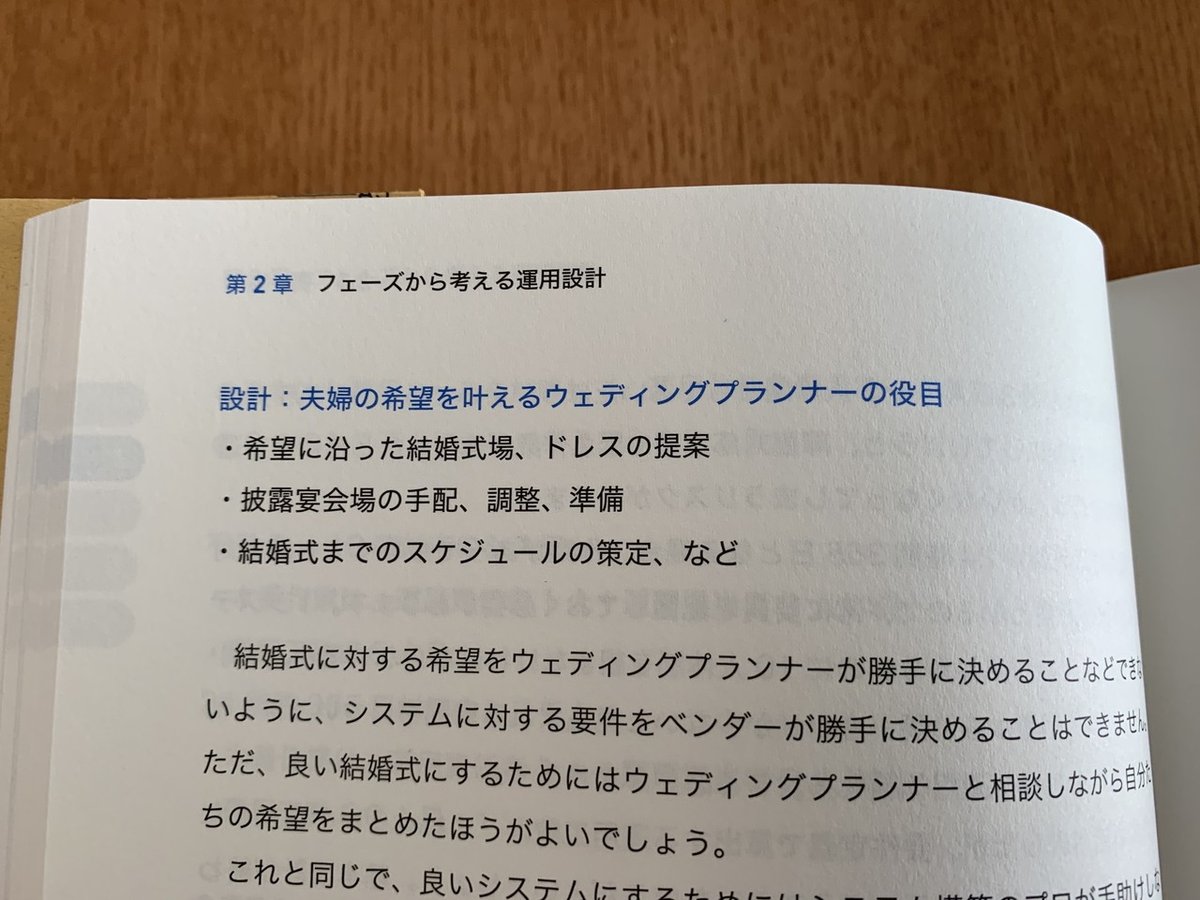
まとめ
重版記念として、これまでTwitterでつぶやいたことに加筆をしながらまとめてきました。
この書籍は実際に運用設計をしている時にこそ威力を発揮する実用書なので、内容が気になった方はあなたの設計のお供にぜひ一冊ご購入を検討いただければと思います。
よろしくお願い致します!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
