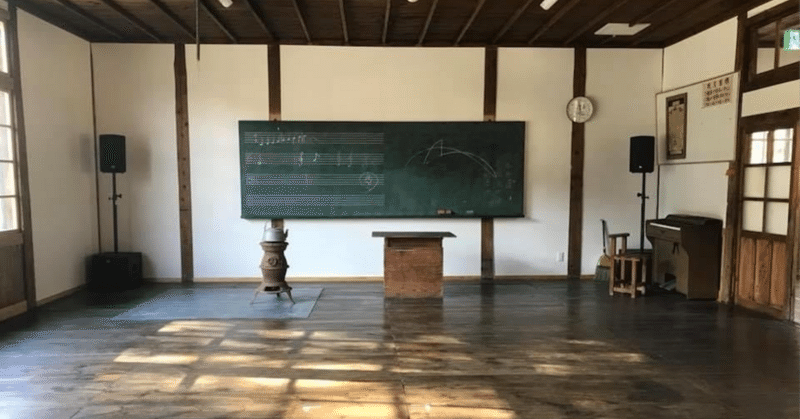
不登校を許していいのか?
ぼくは思う。
「学校に行きたくない」という子どもの意見を、本当に受け入れていいのか?
不登校を許していいのか?
結論から言えば、学校に行かないという行動は許さないほうがその子の将来のためになると思う。
行きたくないと言うのは仕方ないとしても。
そう思った過程、そう考えるに至ったぼくの学校生活についてここから紹介していく。
(先に述べておくけれど、ぼくは心理療法士でもなんでもない、ただの一般人なので、心理学的根拠は一切ない。
すべて経験談として語るものである。)
学校は行く以外に選択肢が無い場所
まずそもそも、当時のぼくの学校に対するイメージを紹介する。
それは一言で表せば、行く以外に選択肢が無い場所だということ。
つまり、行きたくないから行かない、行かなくてもいい場所という考えは欠片もなかった。
朝の時間になれば朝食を食べてランドセルを担ぎ家を出る。
そして帰りのHRが終わるまで、家に帰ることは無い。
これが当時のぼくの学校に対するイメージだ。
つまるところ、当時のぼくに『不登校』というものは存在しなかった。
存在しないというのは、ぼくが不登校にならなかったということではなく、不登校という行動が選択肢に無かった。
当時のぼくは、良くも悪くも学校から逃げるという考えが最初から無かった。
それが今思うと、結果的には良かったのではないかと思っている。
いじめはあった
当時のぼくはいじめられていた。
既に別記事で紹介しているので、どんないじめか興味がある人は↓にリンクを貼るので、見てほしい。
結果的にはいじめっ子相手に反撃し、いじめは無くなったが、いじめられていた最中、ぼくの中に「学校に行きたくない」という考えは全くなかった。
考えが無かった一因には田舎特有の見栄もあったかもしれない。
だから、当時のぼくにとっていじめは逃げられるものではなかった。
避けられるものではなかった。
立ち向かうしかないものだった。
これが結果的には、いまのぼくを作り上げる原点になったと思うと、不登校を選ばなくてよかったと思う。
逃げていれば、いじめに立ち向かうこともなかった。
いじめに立ち向かったという経験も得られなかったのだから。
逃げ場が無いことで敵に立ち向かうことを、「背水の陣」とか「窮鼠猫を嚙む」と昔の人は表現してきた。
それが当時のぼくにもあった。
学校が、逃げてもいい場所ではなかったことが、強い自分を作り上げることになった。
ここまでは、学校から逃げなかった学生時代のぼくについて紹介してきた。
ここからは、不登校という選択肢をとることが将来的にどういう悪影響を及ぼすのかを、ぼくの仮説から話していく。
不登校を許すと完璧主義になる
ぼくは不登校を許すことは、子どもを完璧主義にさせてしまう恐れがあると考える。
完璧主義とは、100のうち1でも嫌なことや損なことがあると、残りの99全てが好ましくても丸ごと捨ててしまう考え方だ。
どうして不登校が完璧主義にしてしまうと考えるのか?
それは、不登校という選択肢を選ぶ際の考え方による。
不登校というと、「学校が嫌になったから」と言うだろう。
だが、果たして学校が嫌だというのは、学校全てが嫌だからだろうか?
そんなことはないはずだ。
からかうクラスメイトが嫌。
笑いものにするクラスメイトが嫌。
えこひいきする先生が嫌。
体育の授業が嫌だと言う子もいるだろうが、内容をよく聞けばいつも標的にしてきたり、運動音痴を笑いものにするいじめっ子の存在が嫌にさせてる場合が多い。
嫌だと思う箇所は、学校全体から見ればごくごく小さな内容だ。
だけど、その小さな嫌一つで学校全部を嫌と判断する。
そして、不登校になる。
いわば、その環境から逃げる。
このわずかな汚点も許すことができず逃げ続ければ、いずれ完璧主義という考え方を育てることになるとぼくは考える。
それは、完璧でないものからは逃げていいという学習になってしまうから。
例えると、それは真っ白なキャンバスに一滴の墨汁が落ちただけでキャンバスを捨てる行為だ。
だけど、社会に出た大人であれば、嫌なことが一切無いなどということは存在しないのは経験的に分かるだろう。
次からは、完璧主義がいかに社会で生きづらいかを解説していく。
完璧主義は生きづらい
この世に、一切の不満が無い企業が存在するか?
一切嫌な点が無い、聖人聖母のような人間は存在するか?
誰もが笑顔で、その笑顔が絶対に曇ることのないコミュニティが存在するか?
少し社会で生きた大人なら、これらの問いに100%こう答える。
「そんなのは存在しない」
どんなに立派だと思う人でも、親しくなれば「ここがイヤだな」と思うところがあるのは当然だ。
イヤだと思うけど、良いところもある。
そういった多少の汚点は見逃すのが社会の付き合い方だ。
しかし、不登校を通じて完璧主義を育てあげた大人はそれができない。
イヤな点がある人間は受け入れられない。
受け入れなくていいというのが完璧主義だ。
なぜなら、不登校という経験から、嫌なことがあれば丸ごと拒否していいと学んだのだから。
しかしそれでは、誰とも付き合うことはできない。
どんな企業でも勤めることはできない。
コミュニティからすぐ離れる。
次第に社会に出ていけなくなる。
嫌なことが一切ない完璧を求めるが、どこにもない。
だから、大人になって引きこもるしかなくなる。
外に完璧なものがないから。
ここまで完璧主義が生きづらいことを解説してきた。
不登校になった子どもが、大人になったとき社会に出ていけない理由をぼくは上記のように考える。
では次は、学校から逃げなかったぼくが学生時代に得た経験を話していく。
この経験は大人になった今、ものすごく役に立っている。
学校から逃げずに得た経験
学校から逃げなかったことで得た経験は2つだ。
適応能力の向上
イヤな人間の対処
適応能力の向上
学校から逃げられないのだから、学校のなかで生きていくしかない。
学校の環境を理解し、自分を合わせなければ生きていけない。
だから、適応能力が向上できた。
それは例えば、学校内での安全地帯の確保。
(嫌なやつが校庭で遊んでいるなら、図書室は安全地帯になるなど)
付き合えるクラスメイトと、付き合ってはいけないクラスメイトの選別。
(ジャングルに例えれば、食べられる植物と食べられない植物の見分け)
この適応能力の向上は、会社勤めで大いに活用できた。
10年以上勤めたが、人間関係でトラブルになることはなかった。
トラブルになりそうな人を分別して、関わらないようにしたから。
安全地帯を確保し、イライラしても安全地帯で落ち着くことができた。
イヤな人間の対処
ぼくの記憶には、学生時代にものすごくイヤだと感じた人間が二人いる。
20年以上経ってもまだ覚えているくらいイヤな奴だけど、その二人の存在がぼくに人間の対処法を学ばせたといってもいい。
学校から逃げない以上、イヤなやつは絶対にいる。
関わらないにしようとしても、それがクラスメイトなら必ず関わるときがある。
ときにはわざわざ相手から関わろうとして来る。
そんなとき、イヤなやつとどう関わるか?
どう対処するべきか?
当時のぼくはかなり考えたのだろう。
彼らの言動を分析し、どう反応すれば彼らが刺激され、またその逆につまらなくさせるかを考えた。
(考えすぎて記憶が定着し、今も彼らのことを覚えてしまっているのは癪だけど)
その結果、ぼくはある程度どういう発言・行動をすれば相手がどう反応するのか、予測を立てる事ができるようになった。
自分の発言で相手の感情をコントロールするようになったと言ってもいい。
人をからかって面白がるタイプには真顔で応対する。
一切感情の機微を出さない。
そうすると、だいたいは白けてあっちから身を引く。
相手にとってこちらの感情が乱れることが笑いの種だから、その種をくれてやらなければいい。
以上が学校から逃げなかったぼくが得た経験、いや技術といってもいいかもしれない。
逃げないからこそ、身に付くものがある。
逃げては、何も身に付かない。
だから、不登校という学校から逃げることを許していいのか、ぼくは疑問だ。
特に子どものときは、一つの経験が今後の人生すら左右しかねない。
学校は、勉学だけでない、上記のぼくのように人間関係でどう対処していくべきかを学ぶ、学びの宝庫だ。
そこで、人間関係のなんたるかを学び損ねれば、大人になったときどれだけ苦労することになるか、ぼくには想像できない。
ここまで学校から逃げないことで得たぼくの経験や技術を紹介してきた。
次からは、もしあなたが親として子どもから「学校に行きたくない」と言われたとき、子ども視点でどうしてほしいのかを、ぼくなりに考えた内容で紹介していく。
「学校に行きたくない」と言われたら
まず子どもの気持ちに寄り添ってほしい。
「行きたくないんだね」と。
聞くのはその後。
「何があったの?」と聞いてもすぐに答える子どもはそういない。
なぜ行きたくないのかを、子ども自身分かっていないことも多いからだ。
大人のように、すぐに分析できる能力も未熟。
だから、行きたくないことを解決しようとはしないこと。
子どもに解決能力がないと決めつけて、大人の視点で解決させようとする親がいるが、これは子どもの成長を奪うという点でもやってほしくない。
子どもにはたしかに解決能力は無い。
どうしたらいいかわかっていない。
だからこそ、これは解決能力を0から育むいい機会でもある。
そもそも子どもは、親に解決してほしくて言い出しているわけではない。
ただ、行きたくないという気持ちを聞いてほしいだけ。
それなのに、『不登校』という言葉に慌てふためく親の暴走が、不登校の問題を深刻化させている。
不登校で問題になるのは子どもではない。
親である。
だから、親に求められてるのは不登校の問題解決ではない。
それは子どもが自らやることだ。
親がやるのは、家を子どものセーフティゾーンにすること。
子どもが帰ってきて、家の玄関を開けて靴を脱いでランドセルを下ろして、その瞬間学校であったことを全て忘れてしまう。
そんなセーフティゾーンが望ましい。
ぼくは家で、学校であったことを話したことは無い。
いじめにあったことも、相手の持ち物に手を出して問題が大きくなり、初めて露見したくらいだ。
だけどそれは、ぼくが家族に気を遣って言わなかったからではない。
ぼくにとって家はセーフティゾーンだった。
帰れば全て忘れた。
学校に行けばまた思い出すけど、学校にいない間は全て忘れた。
忘れたから、喋り忘れた。
家がセーフティゾーンだったのは、おばあちゃんがいたという影響が大きい。
帰って「おかえり」と言ってもらい、ランドセルを下ろして用意された茶菓子に手を伸ばす。
その瞬間、『学校』はぼくの中から消える。
何があったかなんて、全て消え去る。
家をセーフティゾーンにすれば、子どもはしっかり回復する。
学校に立ち向かう気力が回復する。
果たして、不登校になった子どもにとって家はセーフティゾーンとなっているのだろうか?
家に帰っても、心が休めていないのではないか?
家にいるのに安心できていない。
そんなことはないだろうか?
最後に
ここまで、ぼくの経験に基づいた不登校に対する考え方を述べてきた。
ぼくは実際に不登校になった人間ではない。
だけど、実際の不登校になった人の話を聞くと、自分にも不登校になりうる可能性はあった。
にもかかわらず、ぼくは不登校にならなかった。
それはなぜか?
不登校になりそうでならなかったぼくと、実際に不登校になった子どもとの違いは何か。
そういったことを考えているうちに、今回の記事を書くに至った。
参考になればうれしい。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
