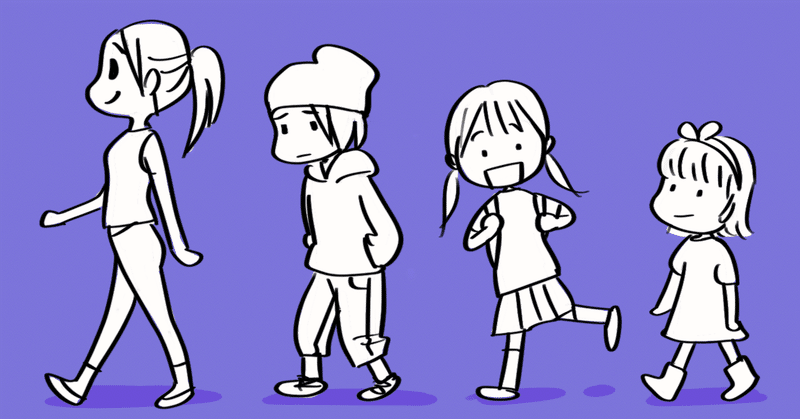
子どもが発達検査を受けて#1
こんにちは、珍獣6人を放牧しているOchoです。
3人に1人が発達障害疑いがあると聞き、随分身近な存在になりました。Ocho家では、小3次女に気になることがいくつかあり、発達検査を受けました。
今回は、検査受けることになった経緯についての思い、感じたことなどを綴ります。
個性か?発達障害か?それが問題だ
6人も子どもがいれば、せっかちさんもいれば、おっとりさんもいて、几帳面も、面倒くさがりもいます。
それは、発達の凸凹なのか、性別なのか、早生まれか、第1子か…何によるものかは分からないけれど、その子なりの得意、不得意があり、
「親の都合や価値観だけで判断してはいけない」と思いつつも、ちょっとしたことが気になってしまいます。
うちの子、変かも…
そう感じた出来事がいくつかあります。
例えば、
それまでほぼ毎日のように通ったことがあり、子どもだけで行ったこともある、自宅から10分程度の距離の最寄り駅に1人で行けず、ウロウロしているところを警察に保護され、パトカーで帰宅する。
読書に集中し過ぎていて、火災報知器が鳴っていても、気付かず、本を読み続ける。
忘れ物が多く、数分前に使っていた自分の持ち物がどこに行ったかわからない。
朝の支度に時間が掛かり、毎日遅刻ギリギリ。
靴下の履き心地や魚介類の味など特定の物を極端に嫌がる。
上げればキリがないくらい、ポロポロと出てきます。
一つ、二つなら、「そういうこともある」「成長と共にできるようになる」と思えるかもしれませんが、毎日いくつものことが重なると、やっぱり努力や成長だけではどうにもできないことがあるのかも…と不安になりました。
スクールカウンセラーとの面談
2年生になる頃には、「学校がつまらない」と時々言うようになり、忘れ物や遅刻が当たり前になってきました。連絡帳や個人面談で、担任の先生と相談しながら、自宅では、前日夜に宿題の確認をし、持ち物も一緒に準備をするようにしました。
それでも、読書への執着が強く、宿題のことなどタイミングを間違えて声を掛けると感情的に泣き叫ぶことも続き、対応に苦労する日々。
先生からスクールカウンセラーとの面談を提案され、受けてみることに。
面談は、1対1でこちらの話を聞いてもらった後、先生や学校にお願いしたいことを聞かれました。
この頃までは、子どもの成長によって改善する可能性があるとも言われ、個性の範疇なのか、固有の物なのか…モヤモヤする毎日でした。
学習支援の教室へ
筆者が産休に入って、日中自宅にいるようになると、「学校行きたくない」と行き渋るようになりました。少し話を聞き、担任の先生にも連絡して、騙し騙し登校。勉強の成績もどんどん低空飛行になっていきました。
夏休み前の個人面談で相談すると、先生側からも、授業のペースと本人のペースが合っていないと感じることがあったよう。でも、一人に対して避ける時間は限られていて、寄り添えきれていなかったようでした。
そして、必要な教科だけを少人数でそれぞれのペースに合わせてサポートしてもらえる学習支援のクラスを紹介されました。
すぐにでもそのクラスに入りたいところでしたが、時は夏休み。
筆者はちょうど出産があり、里帰り中。新学期開始と共に連れ合いが申し込んでくれていると信じていましたが、残念ながら、先生への連絡も何もやっておらず…その間にも、次女はモヤモヤする日々を過ごしていたでしょう。
結局、筆者が産後の里帰りから自宅に戻り、担任教師とのやりとりをする中で、発達検査を受けることになりました。
今回は、個性か発達障害的なものか、モヤモヤした日々について綴りました。
発達検査とその後について、続きは、また綴っていきます
最後まで読んでいただきありがとうございました。では、また
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
