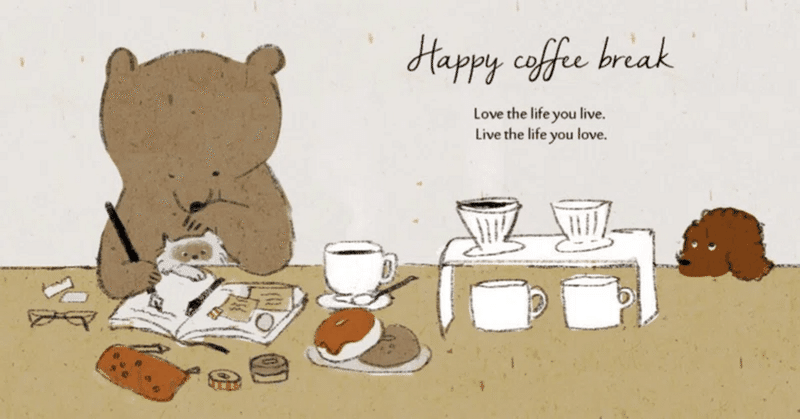
育休中のリスキリングをオススメする理由#02
こんにちは、4人の子どもと双子の赤ちゃんまみれのOchoです。
今回は、育休中にヨガ・インストラクター取得の勉強を始め、育休明けに資格取得に至った経験のある筆者が、育休中に是非取り組んでみて欲しいリスキリングについてのお話、後編です。
4.通信制やオンライン講座で無理なくブラッシュアップ
近年のコロナ禍による生活様式の変化に伴って、通信制やオンラインのみの講座が広がっています。インターネットを利用して、自宅にいたまま講師から直接、きめ細やかな指導を受けることや通学できなくても同時に受講している生徒どうしで交流しながら受講することも可能になっています。
課題についても、通信制やオンラインでも動画やレポート、質問内容を提出して、講義中にフィードバックがあったり、時間が調整できない時には授業の振り替えやオンデマンドで後から授業を視聴できることもあります。
また講座の内容によっては、土日のみ開催の講座もあるので、パートナーの協力を得安かったり、育児や自身の体調など都合に合わせられたり、自分の生活に合わせて柔軟にスケジュール調整ができるので、「時間がない」などの言い訳ができず、無理なく続けられそうです。
5.費用を抑えることもできる
育休中に高額な講座を受講するなんて、「そんなお金ありません!!」という方もいますよね。育児休業中は手当が出ることもありますが、フルタイムで働いているときに比べて、収入減が否めない休業中に、自己研鑽、ブラッシュアップのためとは言え、さらに経済的負担が大きくなってしまうのも辛いところ。
そんな時に活用したいのが、職場の教育制度や教育訓練給付金制度です。企業内でのリスキリングの機運が高まっている現在では、職場の教育制度を充実させる動きもあるようです。職場のものであれば、経済的負担もなく、復帰後の働き方のイメージもつきやすくなるのではないでしょうか。
その他にも、教育訓練給付金制度は、雇用保険の被保険者対象にキャリアアップや雇用の安定を図るための制度です。申請対象や申請要件、支給額などの詳しいことは、ハローワーク・インターネットサービスやお近くのハローワークなどから情報が出ているので、本気で考えるなら相談してみるといいかもしれません。
それらが難しければ、書籍やSNS、Youtubeなどで発信されている情報を活用するのも手軽でいいかもしれません。
6.子どもに頑張っている姿を見せるチャンス
上のお子さんがいる場合、特に小学生以上の場合、毎日仕事をしている時は、なかなか見せられませんが、育児休業中は家で過ごす時間がほとんどなので、親が頑張って勉強、自己研鑽している姿を見せてあげられる貴重なチャンスになります。
Ocho家は現在、11歳、9歳、7歳の小学生がいますが、毎日のように「宿題やったの?」「勉強しなさい!」と口うるさく言ったり、「なんで勉強しないの?大丈夫?」と不安になったりしております。
言わない方がいいのは分かっちゃいるけど、止められない親心。子どもにばかり注文して、家で授乳を口実にゴロゴロしている姿しか見せていないのに、説得力0ですね。
それでも、オンラインでヨガインストラクター取得の講座を受講してた時は、子ども達も興味津々、小学生達は一緒になってレッスンを受けたり、座学の勉強中は邪魔せずに、自分も自ら宿題を始めたり、と頑張る姿が見られました。親が真剣に、夢中に勉強している姿を前にすれば、言葉は必要なかったのかも。
7.時間管理の練習
育休明けてからは、育児、家事、仕事の3つを同時進行で行わなければならず、朝は遅刻できないし、夕方以降は残業もままならなくなります。
時間的な余裕がない中で、タスクは多くなるので、時間のやりくりが必要になります。
育休中の何かを学時間を特別に作り出すこと、やすべきタスクを上手く管理することは、そのまま復帰後の時間管理の練習になります。
優先順位やタイミングを考えて、ひとつひとつの家事や育児の作業効率を上げることで、思いがけず時間を作ることができたり、隙間時間を活用した勉強方法を考え出したりすることができるでしょう。
復帰後は、子どもの保育園のお迎え時間に間に合うように、優先順位を考えて、その日その日の作業を考え、また、次の日に負担を掛けないような事前準備をしなければなりません。
したがって、時間管理の能力は必須。是非とも育休中に身に付けておきたいですね。
今回は、育休中のリスキリングをオススメする理由についての、後編でした。
育児しながらの学び直しはハードルが高く、なかなか重い腰が上がらないかもしれませんが、フルタイムで仕事をしながら勉強するのもなかなか大変です。育休前の仕事に関わらず、今の自分が興味のあることや深く知りたいことなどを手軽なところから学んでみるといいかもしれません。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。
皆さんの経験や感想などコメントいただけると嬉しいです。
では、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
