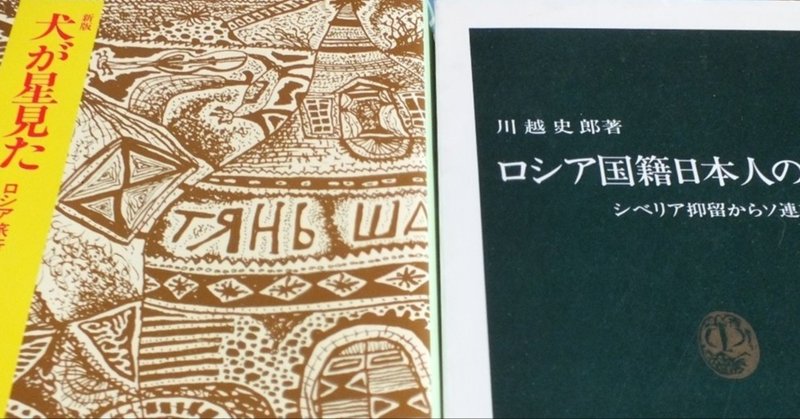
ソ連を知る本2
前回の「ソ連を知る本1」を読み返すと、少々反省すべき点があった。椎名誠「シベリア追跡」の紹介がいかにもウケ狙いというか、変な国ソ連で変な体験をしてきました的イロモノ描写一辺倒のような印象を与えかねない。本来伝えるべき魅力は、別のところであったかもしれない。シベリアの自然と生活の描写は、冬季と夏季の対比もあって面白く、おおらかな所感とあいまって心地よい。目にした風景を豊かに伝える紀行文の傑作である点は改めて強調しておきたい。
川越史郎氏は、1925年宮崎県生まれ。45年3月に召集を受け、満州国境近くの重砲連隊に入隊した。ソ連の満州侵攻に伴う戦闘を経験し、退却中に終戦を迎え、投降した。著者も一部記憶が欠落していると書いているものの、短いながら描写は詳細で迫力がある。
投降後の川越氏はシベリア抑留を経て、ソ連残留を勧誘され、紆余曲折あってモスクワ海外放送に務めることになる。似たような境遇の日本人や朝鮮人たちとともに、ソ連市民として川越氏は生きていく。一方では普通のソ連市民と同様の生活をし、もう一方では特殊な職の外国人という微妙なラインの境遇は、おそらく冷静な観察眼を培ったと思われる。
若者らしい情熱からソ連残留を決意し、時には暗部を垣間見、一方では恋愛をし、生活の楽しみを見出す。ハバロフスク裁判、コミンフォルム批判、スターリンの死、雪解けなど、歴史的な事件も描写されている。また、岡田嘉子、袴田陸奥夫、片山やす(片山潜の娘)、イワン・コワレンコなど、日ソ関係史に名を遺した人物も登場する。日本のロシア関係界という狭い世界の人々にはお馴染みの、宮澤俊一氏やボリス・ラスキン氏の名も出てくる。
本書の終盤からは、ペレストロイカからソ連崩壊、混乱の中の新生ロシア誕生を迎えた川越氏の複雑な心情と、ロシア(国家ではない、人々の住まう大地としてのロシアである)への偽りない愛情がうかがえる。
なお、川越史郎氏の長男セルゲイ・カワゴエ氏は、ソ連・ロシアの伝説的ロックバンド「マシーナ・ヴレメニ」の創設に貢献している。
とても美しいタイトルである。2018年、新版が中公文庫から復活し、好評を博した。
1969年、夫の武田泰淳、友人の竹内好らとともにソ連を旅したエッセイ。筆致はどこまでも長閑で、のんびりしている。旅先の食事を事細かに記し、旅先で出会った人々との、短く他愛ない会話を記す。カタコトの外国語だからこその楽しさというものが、あるのである。同伴者の銭高老人(関西のゼネコンの会長さんである)は旅のマスコットと化している。銭高老人が何かと感嘆の声をあげるのは、この旅の風物詩だ。このような率直な人は、旅を面白くするのだろう。武田・竹内両氏とも、実によく酒を呑む。
本書でソ連の生活を垣間見るのは困難だろう。あくまで旅の記録だ。だが、ソ連の旅というだけで、既に貴重な記録なのである。全く違う文化圏・政治経済圏の人間として旅すると、否が応にも比較や考察に傾くのは人の常であろう。本書にはそのような素振りは殆ど見られない。それこそが本書の良さであり、しかし人によっては物足りなさであろう。
繰り返しになるが、行く先々で交わされる、カタコトのロシア語のやりとりが、中々に楽しい。お互いカタコトでは、エエカッコはできないものである。なんとか欲するところを相手に伝えようと苦心努力する様は、人間関係にある種のフラットさを与えるのだろうか。旅の醍醐味なのかもしれない。
旅などもってのほか、とでもいうような時期に、これを書いている。この騒動のビフォアとアフターでは、世界は違ってしまっているであろう。また呑気な旅が土産話を運んでくれる日々の再来を、今はただ待つばかりである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
