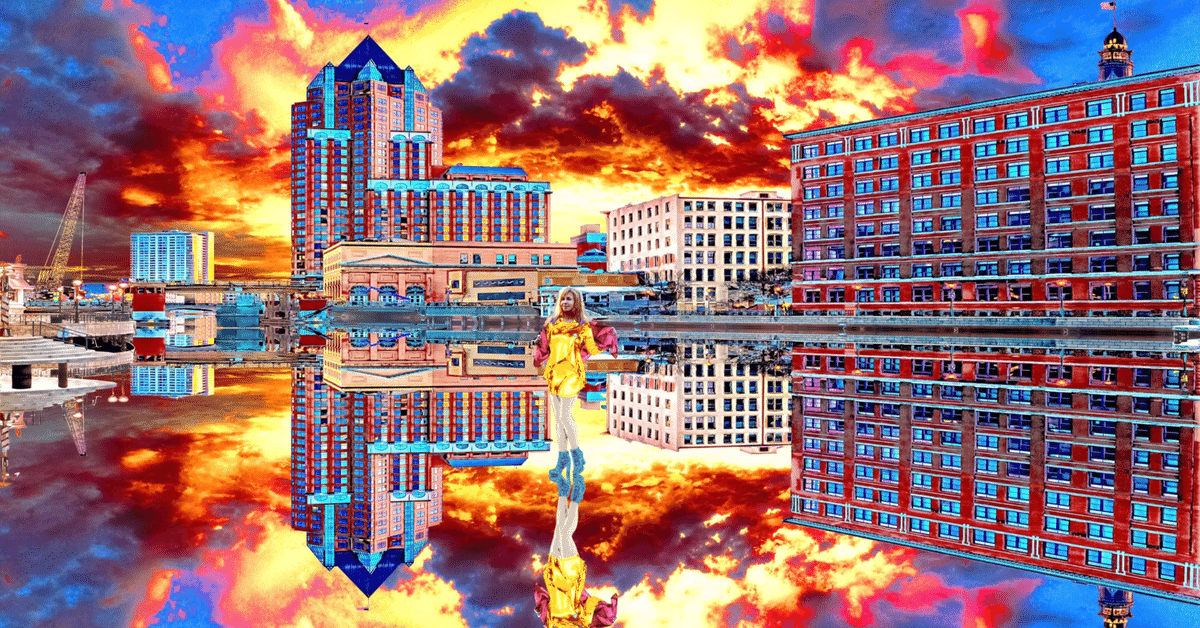
中日・日中翻訳者、通訳者に未来はあるのか(2024年編)
最近、米国株に注目しています。現在米国ではエヌビディアを始めとした半導体関連、AI関連の銘柄がバブル状態になっているのは、株を少し知っている皆さんならもうお分かりになっているのではないでしょうか。
かの有名なアップルもこのほど、iPhoneの「Siri」にオープンAI社のChatGPTを導入することを決定したというニュースが報道され、大きな話題になりました。
多くの人が持っているiPhoneでさえ、日常的かつ気軽にAIが使える時代が近く来る。このようなニュースを見て、現在の翻訳者・通訳者さんの胸中は穏やかじゃないのではと察しています。なぜならこれは、翻訳通訳がいらない世界がすぐそこまで来ているという証ともとれるからです。
おりしもオープンAI社はこのほど新バージョンのChatGPTを発表し、その新ChatGPTの翻訳の精度が格段にアップしたということで大きな話題となりました。
では、これから翻訳者・通訳者さん、特に中日・日中の翻訳者・通訳者さんのお仕事はどんどんAIに食われていってしまうのでしょうか。この「近未来」の話は以前のnoteやXでも何回かお話しているとは思いますが、今回は再びこの点について、2024年時点における未来について現職の中日翻訳者としての私の思いを少し語りたいと思います。
まず結論から言うと、中日・日中のニュース翻訳者・通訳者に限って言えば、AIに仕事が食われるという状況はもう少し先になるのではといまでも私は考えています。もちろん「最終的にAIに食われてしまう」可能性はかなり高いと言えるのですが。
理由は中国語という言語の性質です。
まずご存じのとおり、中国語というのは英語を始めとした西欧言語と比べて、時制がはっきりしていません。「了は過去形を表すよね」といわれるかもしれませんが、中国語の文法をしっかりと学んで理解した人ほど、この言説を明確に否定します。
「了」は日本語や西欧の言語のように、「過去」「現在」「未来」という絶対的な時間軸における「過去」を示すのではなく、相対的な時間の流れを「止めたり」「動かしたり」する役目を果たすにすぎません。私たちは「時制を判断する手がかり」を「●月●号」や「将」など時制を示す他の言葉に頼るしかないのです。そして、ニュース記事や文学作品などはそれすらないことも多々あるのです。こうなると「ロジック的に違和感ない」時制を「自分で探してきて」持ってくるしかありません。
AIは過去の事例を学習して蓄積するという動きは強いのですが、このような非規則的なもの、「自分で無から有に変える」という動作は、現時点の技術では極めて大きな弱点であると聞いています。ここについては、AIが中国語に立ち向かう上で克服しなければならない点と言えるでしょう。
もう一つは中国語の「主語」です。
中国語の文章における「主語の変化」についてはこれまで当noteの記事で、何回か説明してきました。特に難しいのは「複文」と言われる、コンマを挟んで文節がずらずらつながる文章の、ここの文節の主語の見極めです。各文節の主語が複雑に絡み合っており、正しく見極めないと全体の意味が把握できないへんてこな文章になってしまいます。
まぁ「了」の用法にしても、主語の変化にしても、総括して言えば「中国語はフィーリング言語」だということですね。
確固とした規範やルールが存在しない「フィーリング」。これはAIの行動様式としてはかなり手ごわいということは容易に想像がつきます。
「AIのように学習すればそのうちうまくいく」という言説もあるでしょうが、中国語文における主語の変化が変幻自在であることからしても、この当たりをしっかり把握できるAIが現れるのはまだまだ先ではないかと私は読んでいます。
◇◇
他にあえて挙げるとしたら、、ですが。
省略語。これも厄介です。組織名、肩書、政策などなど、出てくる中国語の略語は英語や欧米言語と比べて格段に多いと思っています。しかも、リーダーとなる人が「フィーリングで」その場で編み出してしまうような略語を使う場面も多かったりします。
さらには漢字の多さでしょうか。これについては、英語のアルファベットが26文字なのに対し、中国語で使われる漢字は現存するものだけでも8万字と圧倒的に表記すべき文字が多く、マイクロソフト社のオフィスなどで、リリース時期が一番遅いのが中国語版であるのはこのためだとも言われています。
ただ、コンピューターやIT技術の飛躍的な向上によって、これらの文字数の違いや初出の略語というのは今では誤差になっているのでは(または近い将来誤差になるだろう)と推測されます。
ですからこのあたりの略語や「表記のむつかしさ」はクリアすべきハードルとしてはそれほど高くはないかなといった印象ではあります。いやむしろAIには超えていってほしいまであると個人的には考えています。
総括すれば、「チャイ語」レベル、つまり観光で使うようなレベルの翻訳・通訳はグーグルアプリやiPhoneのSiriで十分でしょう。「ガチになればなるほど」まだまだ安泰ではないかというのが私の考えです。
もちろんこれはこれで通訳ガイドさんにとっては死活問題にもなり得るのは間違いありません。これからの通訳ガイドさんはむしろ、「通訳プラスアルファ」の付加価値を付けることができる人が生き残る世界になってくる可能性が高いと言えます。
もちろん「ガチの翻訳者・通訳者」も「永遠に安泰」というわけではありません。「遅かれ早かれAIに取って代わる」という状況は変わらないでしょう。「それまでにわれわれ翻訳者・通訳者は何をすべきか」AIと比べて「どんな付加価値を付けて」「どんな違いを見せられるか」。これがわれわれ生身の翻訳者・通訳者最大の課題と言えます。
サポートしていただければ、よりやる気が出ます。よろしくお願いします。
