
202405_物語について気に留めておきたいこと
6月なのに中々梅雨がこない.
晴れの日が続く6月中旬の5月の日記.
映画の物語をつくるときに考えたりしていること
5月は映画美学校の修了制作のシナリオを書いていた。
美学校では、劇映画をつくることを重視している。
この劇映画というものが自分に取っては中々うまく掴めずで、自分は物語の筋みたいなものをあまり注意してきていなかったのかもしれないと意識するきっかけになり、物語を作るうえでいろいろな発見があった。
劇映画とは何かということを自分の言葉も交えて、簡単に説明してみると「誰が何をしてどうなるのか」という物語の筋が存在する映画である。
主人公がある問題や葛藤を抱え、その問題や葛藤に対する中で周囲との関係性や内面、外面が変化していき何かしらの結末を迎えるというものであり、主人公として、物語世界の中での運命や宿命が描かれ、ある結末にいたるような物語をもった映画といった感じであろうか。
こうやって書くと多くの物語が劇映画の形式になっているのでは?と思うかもしれない。
僕自身は、それはそうな気もしつつ、以外にそうでもないというような煙に巻いてしまうような感覚なのだが、重要なのはこの劇映画の形式をかんがえることによって、登場人物、登場人物の芝居、作中世界における作品の語りを考えられることにあると思う。
最近は登場人物(キャラクター)のことを割とずっと考えているのだが、こういう人を描きたいという部分が割と少なく、どちらかというと撮りたいモチーフや視覚表象が先に来ており、イメージが先行してしまうことが多い。
-なぜだろうか?と考えるのだが、僕自身が割と許せないみたいな人が少なく、得意でない人は割といるのだが、うまく躱したりして、関わらずに来てしまったり、強く人に対して踏み込むといったことをあまりしてきていないかもなと思ったりしていて、そのあたりに何かヒントがある気がしつつ、まだよくわからないでいる。
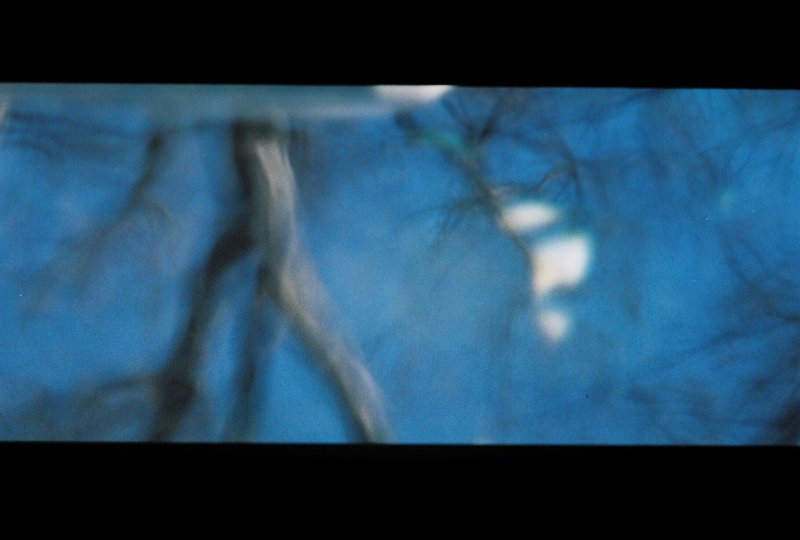
学校ではイメージ先行ではなく、劇・ドラマをかんがえましょうというフィードバックを多くもらっていた。
僕は日記を書くのも読むの好きで、そういう意味では日記やエッセイなどは劇映画的な物語は薄い。そこで何かが起こっていたとしても、それは起こった出来事が中心であり、人物が中心であることが少ないからだと思う。これは映画というものが芝居によって語られていく物語の形式だという見方をした場合により浮き彫りになってくるように思う。
あとはこの1年くらい作ってきた映画がいわゆる短編と呼ばれるもので、10-20分ほどの尺なので、その尺の中で語りうるような物語というのもある気がしている。
群像劇なものは中々難しいなとか、物語の角度を割とつけて削ぎ落とすようにプロットをつくらなければいけないだったり、プロットの外側というか、動きの気持ち良さみたいな部分で、チャップリンやキートン、ヌーヴェルヴァーグの映画群などなど、映像それ自体の身体の強さや視覚、身体表現の探求などはやはりいいな。
など、手触りはいくつかがあるが、自分の中でその物語の大きさをうまくコントロールできてない感覚があり、自分の興味のあるものや自分の経験の種から、それをうまく作品全体として調理することがまだまだうまくできない感覚がある。
特に主人公の抱える葛藤などをいかに自分の取りたいものと併せて人物像をつくっていくかということ。これに関しては、友人の映画などで俳優として出演する経験ももっと積みたいなと思っていて、今後も演劇など含め、積極的にやるようにしたい。

映画をつくることの意味は沢山あっていい
最近、小説を書いている友人と話をしていて印象的だったこと。
「小説を書くことは表現の形式というよりは、考える形式であって、自分にとってはわりとその事が重要かもしれません。」
創作をすることの意味は人によって違うのは当たり前で、むしろ創作(創作でなくとも、その行為をすることそれ自体の意味)をその人が見出していくことが重要だなと思う。
つくることそれ自体に喜びを感じる人もいれば、つくりながら考えることそれ自体が生きることと接続していたり、その理由は森羅万象、宇宙の数だけあっていいのだと思う。
そういうことで、自分が映画をつくる理由を自分の中で形作っていきたい。今はその形がはっきり見えないから、まずはつくりながら考えるという段階な気もしており、もしかしたらずっとそうかもしれないとおも思いつつ、まずは映画を撮りたいというその気持ちに嘘はつかずにやっていくことなのだと思う。
映画を撮りたいという中にも沢山の宇宙があり、それはそもそも映画を撮りたいではなく、映画に関わりたいということで、それがシナリオを書きたいだったり、映像を撮りたいだったり、演出をしたいだったり、音楽をつくりたいだったり、芝居をしたいだったり、より多くの人が持続的に映画をつくれるようにしたいだったり、自分の好きな映画をもっと多くの人に届けたいだったり、この中のどれでもない場合もあるだろう。そうやって自分で宇宙を開拓していくほかにはないのだと、今は思っている。

5月に見たもの読んだもの
・悪は存在しない
・PASSION
・セブンチャンス
・コクリコ坂から
・タロウのバカ
・あのこは貴族
・草の響き
・ブンミおじさんの森
・トウキョウソナタ
・ピクニックアットハンギングロック
・ありふれた教室
・生命式
・白いセーター
・奇妙な仕事
・夏の夜の口づけ
・ジブリパーク
・かもめ(オスター・マイヤー演出)
・ハムレット(彩の国)
まじまじと見ること/聴くこと
オスター・マイヤーの『かもめ』は本当に役者の強度が素晴らしく、あとはやはり舞台芸術は近くで見れると良いなと感じた。実際にその場に身体がそんざいするのに、それがうまく知覚できないことはその場には、身体がない状態とはやはり違っていて、その場に演者がいるのであればやはり近くでみたいというありきたりなことになってしまうのだけど、この間行ったサニーデイとイルカポリスの対バンがとてもとてもよく、青山の月見ルの会場の大きさも僕にとってはとても良くて、それは近くで見ることで演者の癖や表情など、直接見なければわからなかったものに多く気づくことができ、その気付きが感動を支えている気がした。映画は、顔のクローズアップなどカメラの力で「普段はまじまじとみることがないもの」を意識的に、劇場の身動きのとれない椅子に座った観客に向けて、ある種暴力的に、それらを見せることができる。そのことは映画の感動を支える大きな要素の一つであると思う。

🐯 🐫 🍡 🦍 🦁
