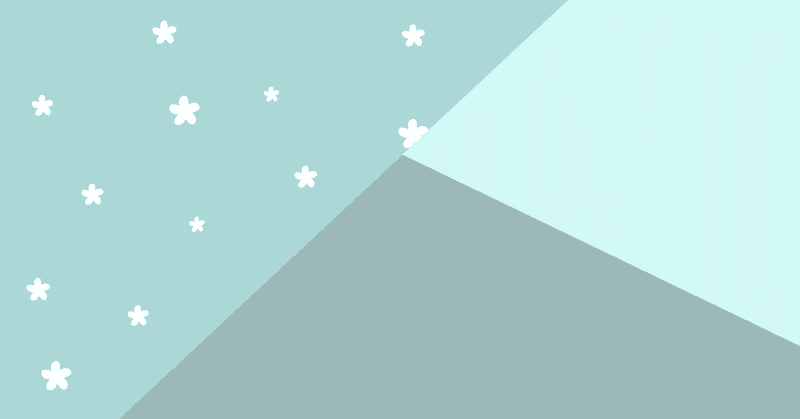
【短編小説】隣人
「突然の来客は迷惑ね。」
私が学校帰りに友達を連れてきた日の夜に、母は決まってそう言った。それに、と一言嫌味を付け加えるのもお決まりだった。
「それに、あの子なかなか帰ろうとしないじゃない。」
「それに、食べこぼしが多いわ、片づけるのは私なんだから。」
「それに、靴も揃えなかったわね。」
小さい頃の私は友達が多い方ではなかった。自分の家に招いた友達の数なんてたかが知れているのに、それが誰であったかよく覚えていない。それなのに大人になっても沢山の”それに”だけは思い出せる。変な話なのかもしれない。放課後何して遊んだかよりも、どんな文句を母にぶつけられたかの方が私にはよく響いた。
突然やって来る迷惑な客がいる。そいつは例えば湯船に浸かって力が抜けてしまった時、或いは心に余裕が無い時にまるでそれを見計らったかのようにやって来る。追い返す方法はまだ知らない。だから、そいつがやって来ると毎回考える必要があるのだ。どうやって帰ってもらおうか、と。
客はいつも無遠慮に挨拶もしないまま、ずこずこと私のスペースに入って来ては長々と居座る。追い出そうと試行錯誤したところで、私にはとても宥めることができない。ただ、頑としてそこにいるのだ。そうして私の時間をたっぷりと奪って、そいつは突然私の元から去っていくのである。
そいつの名前は”憂鬱”という。長い付き合いになりそうだから、と私が名前をやったのだった。それでも、私を訪ねて来る憂鬱を迎え入れることを許せるようになった頃には数年が過ぎていて、私はもう一人で生きられる年になっていた。
憂鬱は何も手につかず寝転ぶだけの私をただ傍観していることもあるのだが、気まぐれに酷く残虐に振る舞うこともある。そういう時、私はただされるがままに侵されてしまう。涙腺を破壊され、心も思考も引っ掻き回され、終いには身体までをもをボロボロにされる。全てが終わった後に見たケータイの検索履歴が、自殺方法で埋め尽くされていた時には流石に絶句した。憂鬱は私を侵す間、憂鬱なりに自由に悪さをするのだった。
今日も憂鬱は私の隣にいた。
『ねえ貴方ってどうしてそうなの』
私は答える。
「私だって知りたいわ。今頃大学にいるはずだものね。」
どうして学校へ向かうはずの足が、今日もベッドから一歩も出てくれなかったのか。私自身がまだ解っていない。ただ分かるのは、私が化粧も着替えもしないまま酷い頭痛に苛まれているということだけだった。
『今日も体調悪い?放課後ご飯届けに行こうか?』
同じ授業を受けている友達からのメッセージ。
「ねえ、助けて」なんて送信しようとしてやめた。
憂鬱が今日も私の所に来ているの、ねえ、助けて。
一文字一文字を消して、またゆっくり文字を打ってゆく。「大丈夫だよ」なんて丁寧に顔文字までつけておどけて、あたしは誰に頼ればいいのだろう。
カーテンの外が暑くなった頃、憂鬱による破壊は私の中身からとうとう外身へと移った。
あぁ死にたい。
苦しい。
何もかも終わらせてしまおうか。
無意識にしたことだった。思い切り首を絞めた。締めたのだけど、顔に血が溜まっていくような感じがして暫くしてやめた。
首のどこを絞めるか調べてみようかな。顔のうっ血した死体なんて美しくないし。襲い来る希死念慮の合間でふと素っ頓狂な思考が頭を過ぎる。
「ばかみたい」
独り言ちて辺りを見回すと、さっきより景色が少しはっきり見えた。憂鬱が去ったのだった。憂鬱が残していった散らかった部屋が、今日の精神状態を物語っている。こんな部屋にいることも、散らかすことも、片付けることにも慣れてしまった。
憂鬱は常に隣り合わせていて、彼からの束の間の解放の時間ですら私が狂っているという現実が私を突きつけて苦しさからは逃れられない。
それでも憂鬱は、また挨拶も無しに現れるのだった。
ふと昔の母のことを思い出す。
「お母さん、突然の来客は確かに迷惑ね」
サポートいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
