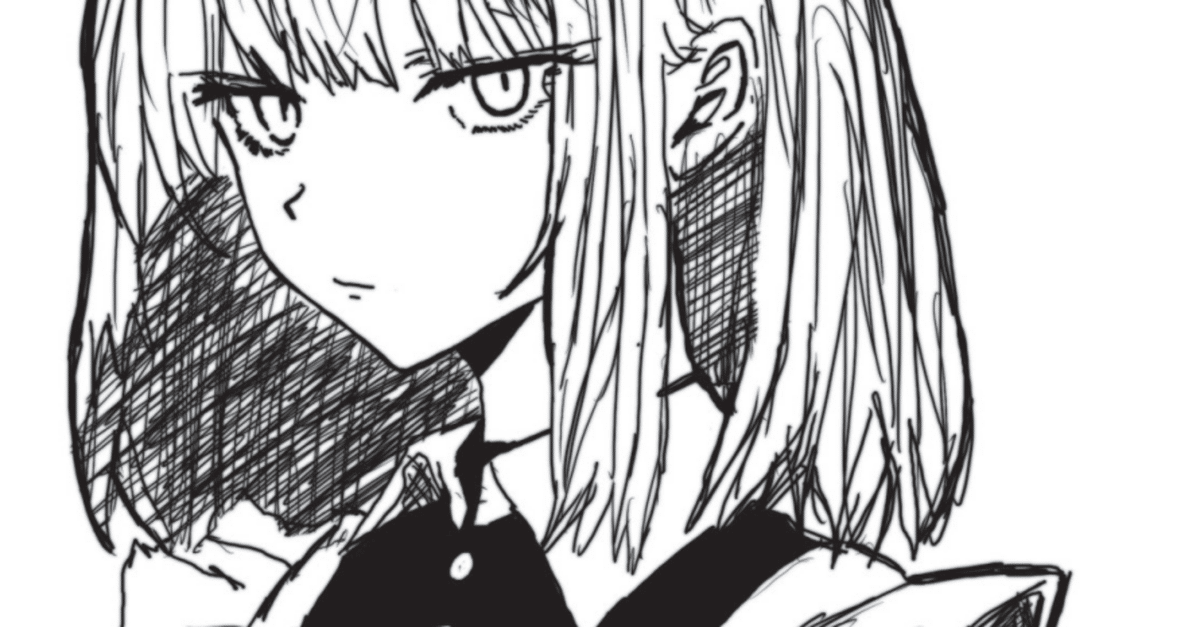
Cafe本音の光
本文
「守田、チューしたい」
喫茶店のソファーに座るメイド服姿の金髪碧眼の少女に睨まれながら、守田亘(もりたわたる)は悩んでいた。
「誅(ちゅう)したい?」
守田は読んでいた時代劇小説を閉じ、表紙を目の前の少女に見せた。
「誅殺(ちゅうさつ)じゃないよ」
「チュウってあのチュウか?」
「そう、接吻、キス、とか色々言い方あるけど物理的に他人と自分の唇を重ね合わせるヤツ」
そう言いながら、女の子は顔の前で両手の人差し指を合わせた。
「柏さん、ここはいつから風営法に引っかかる商売初めたんですか?」
古いレンガ造りの建物の内装には木製の使い込まれた調度品で固められていて、食器やドリップの道具などが並ぶカウンターバーがある。守田はカウンターバーに向かって訴える様に声を出した。
「あらあら」
「隠れていたのか巣穴から顔を出すウサギのように、カウンターバーの下から勢い良く女性が顔を上げた。
濃い緑のブラウス、髪を後ろで纏めていて落ち着いた化粧に、目が細く垂れ目の優しそうな美人の女性がほほ笑みながら顔を上げた。
店内は縦に細長く、窓が有る壁際のソファー席とカウンターバーの間には人が通れる位の幅で区切られている。
レンガ造りの躯体に磨かれて光る木製の調度がはめ込まれた古い店内、年代はわからないが古くてモノが多かった。
「どうしたの二人とも?」
落ち着いたエプロンドレス姿でカウンターから出てきた女性は目を細めながら声を掛ける。
「急に未玖(みく)ちゃんがとんでもないこと言いだして……」
困っている守田と対峙する女の子は怒っているのか、眉間にしわを寄せて守田を睨んでいた。
「どうしたの未玖ちゃん?」
「柏、私やっぱり守田のことが好きみたい」
「やっぱり」
特に驚きもせずに店主である柏貴子(かしわたかこ)は嬉しそうに手を合わせた。
「よかったわね守田さん、未玖ちゃんみたいな現役女子高生の可愛らしい女の子に告白されるなんて、なかなかのグレーゾーン案件よ?」
「店員が仕事を放棄して客に告白してる事には何もお咎めないんですか?」
「うーん別に今お店に居るのは守田さんだけだし、天気も良くて気持ちを伝える告白にはちょうど良い時間帯じゃ無い?」
何がちょうど良いのか守田はまったく理解できなかった。だが目の前の女の子、このお店唯一の従業員、店員、呼び方は色々とあるのだろうが、目の前の女の子は黒いエプロンドレスに白い襟とカフス、可愛らしいフリルが付いた組み合わせはメイド服と呼ばれる格好であった。
日中に日差しに包まれて、未玖の金色の髪が光を帯びている。だが未玖のめんどくさいし邪魔という理由で頭に付けるホワイトブリムはオミットされているので、金色の髪が目立つ。
黒と白の制服と明るい髪色のコントラストが、暗い店内では一人だけ輝いて見えた。
一方の守田は皺の残ったシャツと剃り残しのある髭、寝不足で出来た隈が深くて濃い目を際立たせていて、若々しさよりも場数を踏んだ男らしさ、悪く言えば疲弊して精気を失った中年のおじさんにしか見えなかった。
若い未玖から守田にむかって好意を寄せられるのは、なにか生きるエネルギーが高いところから低いところへ流れていくようにも見えた。
「守田は私のこと嫌い?」
「別に嫌いじゃ無いよ」
「じゃあチューして」
未玖は顎を少し上げて小さな唇を守田に向ける。
「だからなんでそうなるのか……」
頭を抱えて守田は下を向く。
「だって守田の事好きになったから、今チューしたいなあって」
「なんで急にそんなことしたいと思うんだ? こんなくたびれたおじさんに?」
「自分でもよくわかんないけど、いま目の前に座ったらそう思ったの」
ちょっと休憩といって未玖は勝手に仕事を休んで守田の机に座った。
いつもこの店員は自由だなあと、三十過ぎの守田には未玖の自由奔放さが羨ましかった。
だからつい客と店員にしてはよく話し、偶に学校の辛さや友達関係の面倒臭い話しを未玖から聞くと、守田は会社のもっと面倒臭くて陰湿な話しを聞かせて納得させたりして色々な話しを聞かせていた。
気が付くと未玖には歳の離れた友達くらいの感覚でいるらしく、守田にとっては若い学生はどこか遠くに居る物語の登場人物ぐらいの感覚だった。
だから急に肉体的接触を伴う好意を寄せられて、貴重な休日であり昼過ぎの喫茶店の店内で、守田は目眩のようなものを感じた。
どうしてこんな事になってしまったのだろうか?
切っ掛けは些細なことで単純に守田がこの柏貴子が店長を務めるお店を見つけた事から始まった。
数ヶ月前、休日に目が覚めて洗濯物を干した後に、部屋着を全部洗濯してしまったので、仕事着を着てふとご飯でも食べようかと家を出た。
独身で休日に家事をこなす事が多い守田は、仕事の忙しさも相まってほぼ休日は家でダラダラと過ごす事が多くなっていた。
守田は特に趣味があるわけではないので、どこにも出掛けずに好きな本を読んだりするだけの休日を過ごすのは当たり前だった。
ただ、その日はちょっと天気が良く暖かくて羽織っていたジャケットを手に持って、午前中から街をブラブラと歩く事にした。
その際には会社から連絡があっても絶対に出ないと心に決めていたので、会社用もプライベートのスマートフォンも持っていなかった。
だから気の向くまま、自分が住む都内の勤め先まで急行電車で四十分程掛かる郊外の背の低いアパートや一軒家が並ぶ街や、全てコンクリートで固められた川沿いをブラブラと歩いたり、今まで曲がったことの無い曲がり角を意を決して曲がってみたりしながらウロウロと歩き回った。
すると少し大きな木々が生い茂る公園が見えた。守田は少し歩き疲れたので休もうと公園の中に入ろうと思ったが、公園を取り巻く黒い鉄製の柵の向こうに赤褐色のレンガ造りの古い建物が見えた。
珍しいと思って建物の近くによる。ガラスがはめ込まれた緑色の扉、道路に面した窓の周りには鉢植えが置かれているが、所々枯れていたり、手入れされていると言うよりは道端の花壇のように適当に置かれているようだった。
お店の名前が分かる看板みたいなものは掛かって無く、なんだか商売気が無いというか本当にお店なのかも良く分からなかった。
だが、店の軒先にはよくある黒板が付いた折りたたみ式の看板が軒先に置かれていて、Cafeと英字が書かれていた。
「こんなところにカフェがあるのか……」
古そうな外観、この街に引っ越して来てから数年たったが古い喫茶点が公園の横にあるなんてしらなかった。
まあ歩き疲れたし入ってみるかと思って看板を見るとCoffeeの文字の横に「¥10000」と書いてあった。
「一万円?」
思わず守田はたじろいでしまう。
一杯一万円のコーヒーを出すお店なんてまあ都内に無くは無いような気がするが、ここは都下の住宅街で高級ホテルのラウンジでもなければ、何か最高級のコーヒー豆を使った特別なコヒーでも出してるのだろうか?
看板を見ながら守田は色々と考えてしまう。
「どうしました?」
後ろから声を掛けられて振り向くと、両手に紙袋を抱えた近くに女性が立っていた。
柔らかそうな瑠璃色の髪を後で纏めて、濃い緑のロングスカートのブラウスで落ち着いた雰囲気だが、顔は穏やかで、屈託なく初対面の守田にも笑顔を向けていた。
「えっいや、その看板を見てるだけで」
「まあ、興味ありましたらどうぞお店に入ってみてください、美味しいかどうか保証はしかねますけど、コーヒーでも飲んで行ってください」
目尻の下がった睫毛が長く大人びた瞳だが口元が少し広角に上がっていて、何かイタズラでも考えているような笑顔に子供のような無邪気さも感じた。
「さっどうぞどうぞ、お店は始めたばかりでお客さん少なくて、今ならゆっくりできますから」
初めて会った柏に急かされて、守田は一万円のコーヒーというのは毎日会社でタダのコーヒーしか飲んでない自分には贅沢すぎて分不相応だと思って当然躊躇したが、他に行く当てもないので誘われるまま店に入る事にした。
「ただいま未玖ちゃん」
「お帰り」
お店のドアを開けるとカウンターバー前のバースツールに座っているメイド服を着た女の子が居た。
一瞬で守田は「お帰りなさいませご主人様」と声を掛けてくる店なのか? と思ったがメイド服を着た金髪の女の子は無愛想なまま面倒臭そうに、高いバースツールから滑るように降りると早歩きで柏に近づいてくる。
「誰?」
未玖が柏の後ろに居る守田を見つけて不思議そうな顔をする。
髪の毛は染められるが、女の子の青い瞳はルーツが外国にあるのかと守田に思わせた。
「お客さんよ未玖ちゃん」
「このお店、お客さん本当に来るんだ」
「そうよ、今日初めてのお客さんなんだからちゃんとお願いね」
そう言うと柏は面倒臭いのか何も考えて無いのか頷きもせずにそのまま壁際の席まで歩いた。
暗い店内はレンガの暗さと古い木製の調度と合わさってレトロな空気が充満していた。こんな時代に取り残されたところがまだあるのかと守田は店の空気に圧倒されて立ち尽くしていた。
「ここで良い?」
壁際のボックス席の横で未玖がテーブルを指差す。
「あっありがとう」
言われるまま守田は壁際の席に付く。
ひんやりとしたレンガの壁と木枠に囲まれた外窓には隣の公園の木々が見えた。
使い込まれたテーブルの上には何も置かれていなかった。
「あっ柏、テーブルのメニューどこだっけ?」
「えーっと、どこだったかしらね……とりあえずコーヒーで良いかしらね?」
カウンターの後ろで買い物したモノを冷蔵庫などに入れている柏から返事があった。
「ここのお店って……」
「何?」
椅子に座った守田を未玖は見下ろす。
「いや、なんでもない」
「あっお水居る?」
「ああ、コーヒーすぐ出るんだったら要らないかな?」
「よかった準備してなかったから助かる」
女の子はぶっきらぼうに答えると未玖はカウンターにコーヒーを取りに行った。
後ろにリボンを結んだエプロン姿のメイド服を見て守田はここがいわゆるメイド喫茶、コンセプトカフェと呼ばれる、テーマに沿って整えられた体験型のお店なのかなあと思ったが、今の塩対応をみてるとそういうサービスでは無さそうだった。というよりメニューは無い、水もお絞りも出てこない、一般的な喫茶店だとしてもサービスが悪い気がする。
だが守田は学生時代行った海外のお店ではそういったサービスを見なかったので、そんなヨーロッパの雰囲気を出すために真似ているのかとも思った。
でもコーヒー代は一万円、なんだかチグハグで普通のお店には思えなかった。
店内を見渡すと古い調度の古びた照明、木製の本棚、古いレコードとオーディオプレイヤーなど色々置いてある。所々に小物が置いてあり、小さな額縁に入れられた絵が飾られていて、古い店内にはモノが満ちている。
昼前で照明が点いてなく、陽光だけで照らされた店内は明るい部分と暗い部分がハッキリと色分けられていた。
あとは何が他の店と違うのだろうか? 守田が見渡して気が付いたのは店内に音楽が無い事だった。日本のお店はだいたい無音を気にしている気がするが、このお店には音が無かった。
他に客もいないのもあるが、コンクリートやガラスと違ってレンガや木で出来たこのお店は音を吸い込んでしまう、洞窟に入って行ったような静けさがあった。
店内には柏がハンドドリップの準備をしている音だけが響く。
勢いで入ってしまったカフェの空気にすっかり守田は呑み込まれてしまった。
「はい未玖ちゃんお願いね」
「うん」
「ちゃんと銀のトレイ使ってね」
ソーサーとカップを持ってそのまま運ぼうとした未玖に釘を刺す。
ああそうかと、ミルクと砂糖の入った瓶と一緒に銀色の丸いトレイに載せて、未玖はコーヒーを運ぶ。
「はい」
すこし乱暴に置かれたコーヒーカップは白磁に金色の淵に濃い青で色づけされていて、見た目とても高価そうなアンティーク品に見えた。白いカップに注がれたコーヒーが目の前に置かれると、すこし埃っぽい店内の空気とは違う、芳醇な香りが鼻を突く。
「ありがとう」
守田が礼を言うと、あっそうかと未玖は頭を下げてトレイを抱えてまたカウンターの方へと戻って行った。
目の前に置かれたコーヒーを見て、守田はこのコーヒーが一万円のコーヒーかと飲む前にマジマジと見てしまった。
「飲まないの?」
カウンターバーの椅子に座った未玖が守田に声をかけた。
「ああ、ごめん良い香りだなあと思って」
意を決して守田はコーヒーを飲む。
守田には味の良さはよく分からないので、一万円のコーヒーと言ってもこんなもんなのかなあと違いは思いつかなかった。
確かに会社のコーヒー・サーバーにあるものよりは香りが良くて、飲みやすくてこっちの方が良いのだが、この無料と一万円の差はどうなんだろうかと考えてしまう。
「柏、コーヒーいれるの失敗したんじゃ無い?」
「あらそう?」
「だってあの人凄く難しそうな顔してコーヒー飲んでるよ?」
「あらあら、おかしいわね良い豆使って分量もいつも通りだけど……」
柏と未玖の会話は席に座ってる守田にも聞こえた。
「すみませんこういうお店初めてで、緊張してたみたいで、とっても美味しいコーヒーですよ」
守田は思わずピンと来なかったコーヒーを美味しいといってしまった。
「こういうお店?」
未玖は柏の方を見る。
「ああ、この子こんな格好してるけど別にメイド喫茶とかと違うんですよ。ただ給士の服が無くって私の家にあったの着せてるだけだから」
家の箪笥の中に何故こんな本格的なメイド服があるのか守田には分からないが、ここがメイド服を着た女の子が給仕するコンセプトカフェみたいな場所では無い事は分かった。
「でもここは高級なお店なんですよね?」
「高級?」
柏と未玖は声を揃えて言った。
「表の看板にコーヒーの値段が……」
柏と未玖の二人が顔を合わせると、未玖はカウンターバーの椅子を降りて店の外に出た。
「ついこの前開店して出来たばっかりのお店でね色々と不慣れでごめんなさい」
随分古くからある建物だからお店自体は古いと思っていた。
「ここは叔父が持っていた家の倉庫だった建物でね、もともと倉庫にあるモノを使いながら窓を作ったりして喫茶店に改装した建物なの」
柏が笑いなが話すと、守田は建物が丈夫そうでひんやりと静かな理由がやっと分かった。
ドアがガチャンと大きな音を立てて開くと、外から未玖が戻って来た。
「柏、黒板にCoffee一万円って書いてあったよ」
「えっほんと?」
今度は柏はお店の外に出て行く。
そして表に出していた黒板を持って店の中に入って来た。
「ほらCoffee ¥10,000円って書いてある、まるがひとつ多いよ」
店内に看板を置き、未玖が黒板の文字に指を刺す。
「あらあら、だから今日お客さん少なかったのね」
柏は頬に軽く手を当てて笑う。
「Coffee一万円って高すぎるでしょ、外国の人だって高いって言うよ」
「うーん多分黒板書くときに一人一万円ぐらい置いて行って欲しいっ ていう私の願望が具現がしてしまったのね」
「一万円取ろうとしたらもっとCoffeeにホイップクリームとかミルクとかキャラメルソースにドライフルーツとか色々と入れなきゃいけないんじゃない?」
「それでも一万円は高いわね、いや作る側も面倒だわ」
柏と未玖が話し込んでいるのを横目に守田はコーヒーを一口含む、値段が随分下がったコーヒーはなんだか優しい味がした。
「ごめんなさい、なんだか不安にさせてしまって」
柏が守田に頭を下げる。
「いや、自分もちゃんと確かめなかったので」
「あっそうだメニュー出しますね、メニュー」
慌てて柏がまたカウンターバーの中に消える。
「はいこれ」
未玖が両開きのバインダーに挟まれたメニューを持って来た。
「ありがとう」
「あら、メニュー有ったのね」
「柏、慌てすぎ」
守田がメニューを開くと、数は少ないが喫茶店ではお馴染みにのメニューが一通り書いてあった。
値段は喫茶店としては少し高めに感じて、学生では辛いかもしれないが独身サラリーマンには通えるぐらいの値段だった。
「このまま黙ってたら一万円払った?」
「はは、そうかもね」
守田は癖で笑った。
「こんなコーヒーに一万円も払わないよ」
未玖は冷たく言い放つ。
「でもここのお店に長居させて貰うんだったらら対価として悪くないかとは思うけど」
「そう?」
自分には分からないと未玖は首を振った。
「まあゆっくりしてね」
小さく手を振って未玖はまた自分が座っていたカウンターバーのバースツールに座った。
金色の髪色、黒と白のメイド服を着た女の子が自分の目の前に座っているのが時代錯誤というか、映画や小説でしか見た事の無い昔の風景に自分が居るようで不思議な感じがした。
コーヒーはすぐに空になってしまった。
「すみません、コーヒーをもう一杯」
「はーい、お待ちください」
柏がバーカウンターの中で準備する。
また店内にはコーヒーを準備する音だけが響く。
スマートフォンを家に置いてきたので何も見るモノがなく、ただ窓の外の公園の景色を見る。
ただぼんやりと、椅子に座っているだけなのだがなんだか勿体ないと守田は思った。ただ同時に価値のある時間だとも思った。
腕を組み直してソファーにもう一度身体を投げる。
少しソファーの外皮はヒビなどが見られるが、柔らかくて調度良い堅さだった。
お湯を沸かす音が聞こえる。
守田は明るい外を見ていると眩しくて一瞬目を閉じてしまった。
食器を動かす音が聞こえた。
高いお金を払わなくて良いという安心感なのか、それとも調度良い暖かさだったからなのか、守田はそのまま眠りに落ちてしまった。
「うん?」
目を開けると青い目が見えた。
守田の座る対面のテーブルに未玖が座ってじっと守田の顔を見ていた。
「起きたよ、柏」
「あらよかった」
「えっ?」
窓の外はすっかりと明るい色から夕日の淡い色に置き換わっていて、店内の天井のランプが点いていた。
「あれ、俺は……」
店内を見渡して、すっかり日が落ちている。
相変わらす静かに静寂に包まれている店内には自分以外の客は居ない。
「すみません、寝てしまっていたんですか?」
「お疲れでしたのね」
柏はイタズラっぽく笑う。
「すみません、お店の迷惑を掛けてしまって」
「邪魔じゃ無いよ、お客さんそんなに来なかったし」
自分がぐっすり寝ている間に他にお客が来て、寝顔を見られていたと思うと守田は急に恥ずかしくなった。
「そうそう、今コーヒー入れ直しますから良ければもう一杯飲んでいって下さいな」
そういうと柏はもう一度お湯を沸かしてコーヒーを煎れる準備をした。
「ありがとうございます」
守田の座るテーブルの上は全て綺麗に片付けられていた。
「はい、タオルあげる」
「ありがとう」
「このお店は高級店だからね」
未玖が笑いながらタオルを渡してくれた。初めて見る未玖の笑顔は随分と子供のような屈託のない笑顔だった。
守田は暖かいタオルで顔を拭くとサッパリとして、なんだか久しぶりに熟睡できたような気がした。
「未玖ちゃん、お願いね」
コーヒーの準備を終えて、トレイの上に柏がコーヒーの一式を置く。
「はい、コーヒー」
「ありがとう」
起きたばっかりで、守田はすこし喉も渇いていたのか、何も入れずにまた良い匂いがするコーヒーに口を付ける。
「一万円」
思わず守田がえずくと、未玖はトレイで顔を隠した。
「未玖ちゃん、だめよお客さんをからかっちゃ」
柏は少し語気を強めたが、未玖の笑い声が漏れて聞こえて来る。
笑われてもしょうがないと守田は淹れたてのコーヒーに口を付ける。
暖かくてとても美味しかった。
「美味い」
思わず感想を口にしてしまう。
暗い店内には暖色系の電灯の光が灯っている。
守田はなんだか満ち足りた気持ちになった。
「お会計をお願いします」
「はーい、ありがとうございます」
コーヒーを飲み干すと、すぐに守田は立ち上がってカウンターの柏に会計をお願いする。
店の入口近くにある古いキャッシャーの前で守田は財布に入ってあった一万円札を出した。
「えーとお釣りは、今回は一杯サービスしたので九千円お返ししますね」
「あのー宜しければここのまま受け取ってください」
守田は差し出がましいと思いつつも、頭を掻きながら柏に長居した礼を込めて最初に見た値段分の支払いをしようとした。
「どうして?」
「いや一日中居座ってしまったので、場所代というか……」
守田は恐縮しながら柏に頭を下げた。
「別に気にしなくても良いですよ、お気遣いありがとうございます」
柏は深々と頭を下げる。
「どうせ暇だしね」
いつの間にか柏の隣に未玖が立っていた。
「なんだか久しぶりに気持ちよく寝れたので、そのお礼ということで受け取ってください」
嫌々と手を振り恐縮する守田を見た後、柏と未来は目を無表情のまま合わせて、その後破顔一笑した。
「じゃあ、またご来店してください。お預かり金って事じゃないけど、またごゆっくり頂けるように準備してお待ちしてますね」
柏は屈託のない笑顔を向ける。
「そうですね、また来ます」
「顔は覚えたから」
そう言って未玖が取り出したスマホの画面にはソファーに寄りかかって少し口を開けて寝ている守田の顔が写っていた。
「未玖ちゃんダメよ勝手に店内で写真撮っちゃ」
「よだれ垂れそうなところ動画撮ろうとして止めたよ」
柏のじゃあしょうがないという顔を見て、守田は本当に遊びでしかこのお店をやってないのでは思った。
「ごちそうさまでした」
領収書受け取らず、守田は店を後にしようとした。
「あっ待って」
キャッシャー台から柏と未玖が出てくる。
「ありがとうございました」
柏が深々と頭を下げると、未玖もつられて頭を下げた。
守田もつられて頭を下げる。
去りづらいがずっと頭を下げたままの二人を見て、守田は意を決して店を出ようとドアノブに手を掛けた。
「絶対来い」
顔を上げた未玖は守田を睨む。
「また来るよ」
そう言って守田は店を出た。
ドアを出て数歩進んだ後、ふと後ろを振り向くと、柏が一万円札を持ってポーズを取りながら未玖がスマホで記念撮影していた。
それが守田が不思議な喫茶店に初めて入った日の出来事だった。
その日から、なんだかそこが見えない笑顔の店長と、態度が悪いが可愛い金髪メイドのこの店によく足を運ぶ事になった。
店に来る度に未玖に絡まれるようになって、下手すれば父と娘ぐらいの差がありそうな歳の差なのに、なんとなく対面で話すようになった。
「チューしないの?」
未玖に迫られて、こうなってしまった事を守田は冷静に考えていた。
ただの客としてお店に入って、お店の店長と唯一の店員に好意を抱かれるのは悪いことでは無いはずだ。
でもこんな狭い喫茶店の店内でキスを迫られている。
これは一線を越えてしまう。
なんの線なのか守田には分からなかいが、世間的には非常に不味い線だ。
からかわれているだけかと思って笑い話にしよと思う前に、窓から差し込む昼の陽光が未玖の青い眼を照らす。吸い込まれそうな大きな瞳を見ていると冗談に思えなかった。
守田は最初に店に訪れてから次に訪れるまで仕事が忙しくて二週間ぐらい空けてしまった事を思い出した。その時に優しくまた迎えてくれた柏さんとは対称的に未玖には遅いと肩に握り拳で叩かれた。
「いや、その……」
「私は本気だよ?」
未玖は背筋を真直ぐに伸ばして守田の前に座っている。
その堂々としている立ち姿は守田には眩しかった。
「はいはい未玖ちゃん。ちょっと表の花壇に水でもやって来てくれる?」
机の隣に立っていた柏が未玖に声掛ける。
「今?」
「未玖ちゃんが表でお花に水をやってる姿が見て可愛いって思ってお客さんが来てくれるかも知れないでしょ?」
柏はそう言うと未玖と守田以外に人が居ない店内を見渡した。
「分かった」
未玖は素直に店の外に出て行った。
「さてと」
溜息を付きながら未玖が座っていたところに柏が座る。
「どうするの守田さん?」
「どうするって?」
「未玖ちゃん表の花壇に水やるの雑なのよ。ホースから出る水をそのままジャブジャブと水掛けるだけだから花壇に水やりなんてすぐ終わっちゃうわ」
柏は机の上に手の平を置いて軽く叩く。
「あの子はどうしてこんなオッサンに好意を寄せてくれるんですかね?」
「人が人を好きになるのはたくさん理由があるように見えるけど、実際はただ会っただけだったりするから」
柏はそう言うと窓の外を見る。
「私、庭仕事とかめんどくさくて嫌いなんだけど、ここのお店は外の公園の緑が見えるから庭とか無くても雰囲気でて良いでしょ?」
「借景だ」
敷地外の風景を庭の一部として取り込む日本庭園などで取り入れられている方法、柏が意図してそれを使ってるのか守田にはわからなかったが、そういう手抜きは色々考えてそうには思えた。
「イチから本物を全部用意できればそれは良いけどそれができないなら、偽物でも借り物でも集めてみれば意外と本物に見えるのよ」
「何が言いたいんです?」
「ほらこういうのはそれっぽいこと言って、後は他人に任せるのが良い時があるじゃない?」
柏は口元に手を当ててクスクスと笑う。
「未玖ちゃんが水やりながら外の空気を吸って冷静になって戻ってくるとは思うけど、これ以上二人がギスギスして、私のお店にとってやっと出来た太客さんが一人減るのは嫌だなあって話」
太客というのは随分と生々しいなあと守田は思った。
この少しの考える時間は柏なりの助け船だったのだろう。
「柏、水やった」
「ありがとう。それじゃあ未玖ちゃんがどれだけちゃんとお水やれたか見て来るわね」
柏は席を立って、すれ違いざまに未玖の肩を叩いた。
「柏となにか話したの?」
「借景の話をしたよ」
「守田は難しい言葉知ってるよね。柏もよく難しい言葉を使う」
不満なのか苛立ちなのか、未玖の言葉には語気が籠もっていた。
「座る?」
「座って良い?」
「もちろん」
黒いメイド服のスカートを抑えて未玖はまた守田の隣に座る。
「隣に座って良いとは言ってない」
「隣に座っちゃダメとは聞いてない」
顔を横にしてして未玖の顔が近くにある。
髭が生えて張りが無く皺も寄っている自分の顔と対極にある・長い睫毛ときめ細かい張りのある白い肌、小さな淡い唇。飾り立てた美しさに守田は身体を仰け反らせた。
「本当に俺みたいなおじさんとチューしたいの?」
「うん」
「どこかにカメラで隠し撮りしていて、それで揺すってもお金そんなに持ってないよ」
「そういうこともちょっと考えたけど、別にお金欲しくない」
ちょっとは考えたのかと守田は少し安心した。
自分たちの年の差なんてのは、そういう金銭が発生するような関係に近い。
「なんかね、私別に柏からお金貰ってここに居るわけじゃないんだ」
「バイトじゃなかったの?」
「だってこのお店全然儲かってないよ」
守田はそうだろうと思っていたが、従業員から聞かされると衝撃的だった。
「でもね、好きなんだこのお店に居るの」
守田の方を向かずに、未玖は店内を見ている。
「それで最近はここに守田が座ってる時間が一番好き、だと思う」
「そうか……」
自分もこのお店が好きだよと言おうか守田は悩んだ。そしてそんなことを悩む時点で未玖とは決定的に違って、ただ暗い穴に閉じこもっている臆病者だと自分を恥じる。
未玖と守田は二人で対面の誰も座ってないソファーを見ている。
暗い影が落ちる古い調度品に囲まれた店内には二人だけだった。
「本当に俺とチューしたいのか?」
「ちょっと落ち着いた」
未玖はテーブルの上に両手を置いた。
「でもね、多分守田の顔見るとまたしたくなると思う」
未玖はクビを動かさずに自分の手を見た。
「右手貸して貰えるかな?」
「右手?」
言われるまま未玖は右手を差し出した。
「ありがとう、色々考えたんだけど君とチューするのは怖いんだ、情けないけど」
守田は未玖の顔を見られなかった。
「でも、君がくれた好意には何か応えたいというか、ジェスチャーするべきだと思うんだ」
守田は右手で未玖の右手の甲を自分の方に近づける。
細くて長い指、華奢な手を自分のゴツゴツした短い指の手が握って良いのかと躊躇したくなったが、このまま未玖の手を握っているのも悪いと思い、守田はゆっくりと未玖の手の甲に顔を近づける。
守田の唇が軽く手の甲に触れる。
ハンドキスをして守田はすぐに手を離してすぐに窓の外へと顔を背ける。
「ハンドキスは、男性が女性に対して敬意と称賛を示すヨーロッパの貴族社会に由来する伝統的な挨拶だ」
「ふーん、そうなんだ」
「だからその……今日はコレで勘弁して貰えるか?」
顔を真っ赤にした守田は腕を組んでソファーに沈み込むように背を預けた。
「守田、コーヒーおかわりいる?」
「今は要らない」
「わかった」
未玖はソファーから離れて、バーカウンターのバースツールへと向かう。座面に座ってからクルリと身体を動かして、守田の座っている席を見る。
そこには何か悪夢に取り憑かれているような苦悶の表情、眉間に皺を寄せて眼を閉じている守田が座っていた。
そんな姿を見て、未玖は椅子を回転させて背を向ける。
右手の甲を見て、守田が唇を付けた感触を思い出す。
未玖はそのまま右手の甲を額に当てて顔を伏せると、バーカウンターのテーブルに身体を寄りかからせ、浮いている両足をバタバタと動かすと黒いスカートがゆっくりと揺れてやがて静かに止まった。
「そろそろ決着ついたかな?」
柏は嬉しそうに店内に戻ってくると、守田と未玖は離れた場所で二人とも疲れて寝ていた。
「これは結局どういう事になったの?」
バーカウンターの中に入って、柏は未玖に近づいて聞いてみる。
「柏、私今日もう仕事無理」
「どうして?」
「恥ずかしくて動けない」
あらあらと対して驚きもせずに柏は守田の方を見る。
「守田さん、コーヒーおかわり要ります?」
「また後で頼みます」
何があったか柏は理解してないが、守田が逃げ出してないだけまあ良い方に話が転がったのではと思った。
そして注文もせずに難しい顔をして寝込む客と、机に突っ伏して仕事を拒否して寝る店員しかいない店内を見渡す。
静かな店内には若干呻き声が聞こえる。
「今日も赤字確定か……」
柏はとりあえず自分が飲む分のコーヒーでも容れるかとお湯を沸かし始める。
先ほど外に出た時にチョークで看板にコーヒー一杯100,000円と書いておいたので、当面客は来ないと思うが、扉を開けて店に来てくれたら最高に美味しいコーヒーを煎れてあげようと柏は思った。
END
あとがき
この作品は2月25日のコミティアで発表した作品なんですが、当日作ったコピー本が珍しく完売したので、いつも記念にnoteでコミティア終わった後に前開催のコミティアで発表した作品をこのnoteにアップしてたんですが、今回はまあもう在庫無いし良いかなあと思って上げる事にしました。
(コピー本なんでほぼ無限在庫なんですけどね・・・)
久しぶり、というかいつ以来かよくわかんないぶりに完売した理由がよくわかんないんですけど、もしかしてコミティア40周年記念「コミティア魂」で自分のサークルがとりあげられたからかしら?
第9章 魂を引き継いでいくために――代表交代とさわだの証言
という形で取り上げて貰って、なんだか嬉し恥ずかしいというか恥ずかしいなあという気持ちになって、当日の会場に居たんですけど自分の気持ちはともかく、それでもコミティアはいつも通りに楽しくて、色んな人の本が読めて楽しかったですね。
えーと、作品の話しでもすると、この話しは最初は「本音と建て前」をテーマにして「ソーシャルメディアが発達したおかげですっかり本音と建て前っていう便利なバリアー無くなったよなあ」という話しを書こうと思ったんですが、なんか間違った。
何が書けて、何が書けなかった自分なりに考えたんですがよく分からないのでここは最新のテクノロジーの力を借りようと深津 貴之さんが公開してたGPTSの「敏腕マンガ・ラノベ編集者お姉ちゃん」に上記全文をよんでもらいました。
敏腕マンガ・ラノベ編集者お姉ちゃん - saysay.ai
この物語はとてもユニークで面白い設定が詰まっているね!ただ、読者から見たわかりにくい点を指摘するとすれば、以下のようなところかな。
1. 登場人物の関係性:物語の始めに、登場人物たちの関係性や背景がはっきりしない部分があるね。守田と未玖、そして柏の間の関係性や、彼らがどういう状況でそこにいるのかがもう少し明確にされた方が、物語に入り込みやすくなるよ。
2. 物語の設定:カフェ「本音の光」という場所の特別な点や、なぜ一杯のコーヒーが一万円(あるいは間違えて10万円)と設定されているのか、その背後にあるストーリーがもっと掘り下げられると良いかもしれないね。読者としては、そのカフェがなぜ存在するのか、その独特な価格設定に至った理由が気になるところだよ。
3. 展開の速度:物語の展開速度が部分的に早いかもしれない。特に守田と未玖の関係性の発展に関しては、もう少し丁寧に彼らの感情の変化を描写すると、読者が感情移入しやすくなるよ。感情の起伏や内面的な葛藤をもう少し詳細に描くと、キャラクターたちが読者にとってよりリアルに感じられるはず。
4. 場面転換の明確化:場面転換が若干わかりにくいところがあるかな。特に、未玖と守田の間の会話と柏の行動が同時進行で描かれている部分では、誰がどこにいて何をしているのかをもう少し明確にすると読みやすくなるよ。
全体的には、個性的で引き込まれるストーリーなので、これらの点を少し調整するだけで、読者にとってさらにわかりやすく、楽しめる物語になると思うよ。お姉ちゃんからのアドバイスが役に立ったかな?もっと話したいことがあれば、いつでも聞かせてね!
というわけで的確過ぎてぐうの音も出ない感じがしますね。
この適切なアドバイスを元にして推敲を重ねられる人が素晴らしい作家になれるんだろうなあと20年間小説書いててニントモカントモな自分が言うと凄く説得力があるよなあと思い、コミティア魂が販売されたら会場で自分がなんで恥ずかしがっているのかの理由がよく分かりましたね。
でも、次ぎのコミティアもなんか書こう!
さわだ
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
