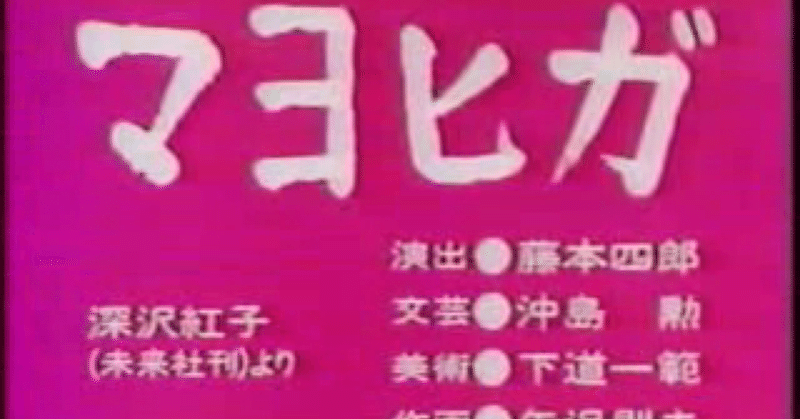
「マヨヒガ」からのメッセージ(4)(2020)
第四章 「マヨヒガ」と「福子」伝説
こうしたタッギングの方法論から「マヨヒガ」のお話を考えてみましょう。道に迷った主人公が山中で立派な謎の屋敷に遭遇する話は他にもあります。最も有名なのは『ウグイス長者』でしょう。これは「見るなの座敷」とも呼ばれ、東日本で広く伝わる民話のタイプです。
さわりだけ紹介します。山中で道に迷った男が立派な屋敷に遭遇、一晩泊めてもらおうと、門をくぐります。すると、きれいな女性が男を出迎え、豪華な料理や酒が振る舞われます。男は長居をすることになりますが、この屋敷には謎があるというわけです。
しかし、「マヨヒガ」伝承はこれと違いがあります。確かに、山中で迷った主人公は立派な屋敷を見つけます。けれども、誰も出迎えません。住んでいる気配はあるのに、主人公は誰とも出会いません。結局、恐ろしくなって主人公は屋敷から逃げ出してしまいます。
また、穀物を増やす不思議な道具の話もあります。島根県に伝わる『武上美登里』がその一例です。これは小汀松之進が再話して「鬼の杓子」というタイトルで『日本の民話12 出雲の話』に収録されています。
お話の中の関係するところを紹介しましょう。お婆さんが川に落した団子を探しているうちに、山に迷いこみ、鬼に捕まってしまいます。お婆さんは毎日鬼に命じられて飯炊きをさせられますが、渡されたしゃもじでご飯をかき混ぜると、それが倍になるのです。ある時、鬼のすきをついて、お婆さんはそのしゃもじを持って家に逃げ帰ります。その後、お婆さんは、お爺さんと鬼のしゃもじのおかげで幸せに暮らしています。
お婆さんは、確かに、鬼の所有物である杓子を無断で持ち出しています。しかし、これは鬼に拉致された上で強制労働させられた苦痛の損害賠償と捉えられるでしょう。実際、この話を聞いた隣の欲深婆さんはそれを真似したものの、鬼に食べられています。欲にかられて鬼の杓子を手に入れようとすることは盗みですから、相応の罰を受けなければならないのです。
しかし、「マヨヒガ」伝承はこれと違いがあります。主人公が苦痛を被っていません。そもそも鬼のような恐ろしい超自然的存在に遭遇さえしていません。住んでいる気配があるけれども、誰もいない「迷い家」から物品を持ち出すのは盗みと捉えざるを得ません。その行為は規範に反します。ところが、数多あるにもかかわらず、「マヨヒガ」論にこの盗みの理由を説明するものはほとんどないのです。
「マヨヒガ」伝承の謎を解く鍵は、実は、主人公の設定にあるのです。「六三」と「六四」では主人公の設定が異なっています。前者が障がいのある妻であるのに対して、後者は若い男です。そうした女性が福に恵まれ、男性は手にできません。「マヨヒガ」」の社会的メッセージは物語の構造ではなく、この人物設定にあるのです。
主人公が障がい者であることに着目した論考は少なくありません。しかし、その取り上げ方は。宮田登は『ユートピアとウマレキヨマリ 』(二〇〇六)において「神がかりしやすい傾向の持主」と解しています。これを始め解釈の多くは障碍者であるがゆえに、常人では成し遂げられない困難さを克服できるというものです。
前近代の日本には「福子伝説」と呼ばれる言い伝えがあります。障がい者は家に福を授ける幸運の人間だという内容です。昔ばなしもこの伝説を踏まえています。知的障碍や発達障害は無垢で無欲として描かれ、福を家族にもたらしたり、自由な発想により誰も歯が立たない難問を解決したりします。その際、家族を始め障がい者を支えるよき人がいます。石川県金沢市の地名の由来として知られる『いもほり藤五郎』の主人公は知的能力や情緒的関係に難がありますが、妻はその言を信じ、二人には黄金がもたらされるのです。「福子」伝説に関する合理的説明は、障がい者がいると、家族がまとまり、助け合う気持ちが強くなり、懸命に働くから、家内安全・商売繁盛というものです。
実際、寺子屋で読み・書き・そろばんを習う子どもの中で身体障碍者の比率が高かったとされています。識字能力があれば、身体が不自由でも、暮らせる場を確保しやすいからです。
家だけでなく、近世では共同体も障がい者に配慮しています。村や町、長屋などの人々が助け合い、環境を整備して、障碍者が暮らしにくくないように心掛けています。結婚の際にも、地域が障がいのある人にはそれを補う相手を世話したりすることもあります。また、寺院や庄屋などが障がい者の面倒を見ることもよくあります。お互い様と信頼の関係が強化・蓄積されていくのです。
支える人が登場するように、障がいと共に生きることの大切さを昔ばなしは説きます。三浦家の妻の障がいに着目する解釈の多くはそれを能力と捉えています。けれども、障がいは社会的環境によって生じるものです。障がいを能力として個人に還元する解釈は共同体主義の昔ばなしにはそぐいません。しかも、解釈の中には障がいを神秘化する意見さえあります。セルバンテスの『ドン・キホーテ』を代表に障がいと共に生きる姿勢を語る文学は古来より少なくありません。民衆は障がいと共に暮らしてきたのであり、そうした知識が文字文学にも反映されているのです。昔ばなしはなおのことでしょう。
佐々木の物語はこの「福子」伝説から昔ばなしにはあり得ない内容です。障がい者が人々から笑われ福を得られずに終わるとしたら、それは規範に沿っていません。障がい者にも欲深い人はいるという反論は、先に述べた通り、昔ばなしは共同体の共通理解に基づいていますから、的外れです。
「六三」の主人公はまさに「福子」です。欲がない女性で、共同体の規範に従ったよい生き方をしています。離縁しやすい江戸時代にあって、夫も障がいを承知の上で結婚生活を続けていますから、妻を支えていると推察できます。幸運はそういうよき人に訪れるものです。けれども、そんな人に限って、突如置かれた厚遇が怖くなり、そこから逃げ出してしまいます。しかし、よい生き方をしている人には、その運が改めてめぐってくるものです。浴をかいたら、運は来訪しません。
おそらく「福子」伝説の通り、三浦家が金持ちになったのは家族が助け合いつつ一生懸命に働いたからでしょう。「マヨヒガ」伝承は「福子」伝説のお話と理解するのが妥当です。
誰もいない「マヨヒガ」が待っているのは将来の主かもしれません。話からはその小国の夫婦が得た福によりどのような屋敷に住むようになったのかはわかりません。あの時に妻が遭遇した豪邸と瓜二つではないかと思わずにいられないのです。もしあの屋敷が将来の自分のものであるなら、そこから何かを持ち出しても、盗みにはなりません。そうしなかったとしても、「マヨヒガ」は自分の主と認めたよき人にそのメッセージを送ります。受け取れるのは、「福子」のように欲がなく、真によく生きている人だけです。これが伝承「マヨヒガ」からのメッセージなのです。
〈了〉
参照文献
赤坂憲雄、『増補版遠野/物語考』、荒蝦夷、二〇一〇年
安藤隆男、『特別支援教育基礎論』、放送大学教育振興会、二〇一五年
石井正己、『遠野物語の誕生』、若草書房、二〇〇〇年
石井正己他、『日本のグリム佐々木喜善』、遠野市立博物館、二〇〇四年
石井正己編、『遠野物語辞典』、岩田書院、二〇〇六年
石井正己、『「遠野物語」を読み解く』、平凡社新書、二〇〇九年
石内徹編、『柳田國男「遠野物語」作品論集成』全4、大空社、一九九六年
石塚尊俊他、『日本の民話12 出雲の民話』,未来社,一九五八年
岩本由輝、『もう一つの遠野物語』、刀水書房、一九八三年
大川悦生編、『父・母が語る日本の民話』下、鎌倉書房、一九七八年
風丸良彦、『遠野物語再読』、試論社、二〇〇八年
菊池照雄、『遠野物語をゆく』、伝統と現代社、一九八三年
同、『山深き遠野の里の物語せよ』、梟社、一九八九年
菊池照雄他、『「遠野物語」を歩く』、国宝社、一九九二年
河野正輝、『障がいと共に暮らす─自立と社会連帯』、放送大学教育振興会、二〇〇九年
後藤総一郎監、『注釈 遠野物語』、遠野常民大学編、筑摩書房、一九九七年
佐々木喜善、『佐々木喜善全集』Ⅰ、遠野市立博物館、一九八六年
同、『遠野奇談』、石井正己編、河出書房新社、二〇〇九年
同、『聴耳草紙』、ちくま学芸文庫、二〇一〇年
人文社編集部、『日本の謎と不思議大全東日本編』、人文社、二〇〇六年
高橋克彦、『総門谷』、講談社、一九八六年
同、『黄昏綺譚』、毎日新聞社、一九九六年
立松和平他、『黄ぶな物語』、 アートセンターサカモト、一九八九9年
内藤正敏、『聞き書き遠野物語』、新人物往来社、一九七八年
同、『遠野物語の原風景』、ちくま文庫、一九九四年
野村純一他編、『昔話・伝説小事典』、みずうみ書房、一九八七年
野村純一他編、『遠野物語小事典』、ぎょうせい、一九九二年
野村純一他編、『柳田園男事典』、勉誠出版、二〇〇七年
花田春兆、『日本の障害者─その文化史的側面』、中央法規出版、1997年
深澤紅子他、『日本の民話02 岩手の民話』、未来社、一九五七年
福田晃他編、『日本の民話を学ぶ人のために』、世界思想社、二〇〇〇年
三浦佑之他、『遠野物語へようこそ』、ちくまプリマー新書、二〇一〇年
柳田國男、『遠野物語』、角川文庫、一九六九年
同、『柳田國男全集』、2・7・19、ちくま文庫、一九八九~九〇年
小田富英、「初校本『遠野物語』の問題」、『國文學』第27巻、 一九八二年一月号
佐々木赳人、「マヨヒガ」伝承に込められた心意の再考 : 柳田國男・佐々木喜善を出発点として」、『 東北宗教学』 第7巻、二〇一一年一二月
野村純一編、「昔話・伝説必携」、『別冊国文学』、一九九三年六月
ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org
まんが日本昔ばなし~データベース~
http://nihon.syoukoukai.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
