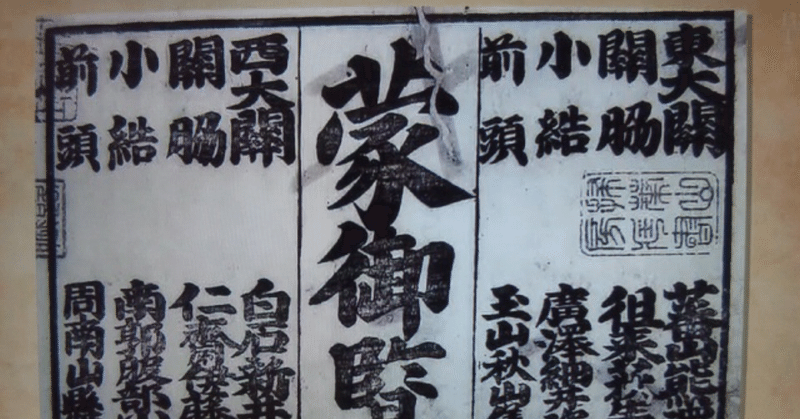
新井政談(3)(2022)
3 高度経済成長と白石
高度経済成長期には、四つの大きな景気があり、神武景気・岩戸景気・オリンピック景気・いざなぎ景気と呼ばれ、次のような期間続いている。
神武景気
1954年11月~57年6月(31ヶ月)
岩戸景気
1958年6月~61年12月(42ヶ月)
オリンピック景気
1962年10月~64年10月(24ヶ月)
いざなぎ景気
1965年10月~70年7月(57ヶ月)
いずれも日銀が公定歩合を引き上げることで意図的に終息させている。だが、前の三つといざなぎ景気では理由が異なっている。
神武景気からオリンピック景気までの場合、政府・日銀の政策判断は国際収支の悪化を懸念材料としている。景気がよくなれば、原材料や機械の購入により輸入が増加する。ところが、国際競争力のある商品がまだ十分でなかったため、外貨準備高が少なく、国際収支の赤字が増加する。その際、政府は輸出指向型工業館ではなく、国内市場を優先した輸入代替政策を進めている。この状態が続くと、日本の支払能力が疑われ、円の信用度が下がる危険性が増す。輸出先も通貨が切り下げられそうならば、それを待ってから買う方が得であるから、日本製品は売れなくなり、貿易赤字はさらに悪化する。この悪循環を断ち切るために、日銀は公定歩合を引き上げ、過熱した景気を冷ます。すると、輸入は激減し、また企業も在庫を減らすために、値引きして製品を輸出するので、国際収支は改善していく。こういう過程を注意しながら、日銀は、頃合いを見計らって、公定歩合を再び引き下げ、経済はまた好況へと向かう。昭和30年代は、このようにして好不況を繰り返している。
1965年は節目の年である。日本は、明治維新以来の悲願だった国際収支の黒字の常態化を達成する。外貨の流出を気にする必要がなくなり、経済政策の中心が金融政策から財政政策へと移行する。この年から海外渡航が原則自由化され、Made in Japanだけでなく、人も海外に飛び出していく。
今回の議論において注目すべきはオリンピック景気である。1964年10月、東京オリンピックが終了すると、政府・日銀は金融の引き締めを図る。ところが、想定外の大型倒産が相次ぐ。この年、サンウェーブと日本特殊鋼がつぶれ、翌年には山陽特殊製鋼が当時としては史上最悪の負債総額500億円で倒産する。大幅赤字に転落して、取り付け騒ぎが起きた山一證券は、田中角栄蔵相の指導力による日銀特融で何とか生きながらえる。
実は、この間、慌てた日銀は公定歩合を1%以上も下げたのだが、効果はほとんどなく、結局、65年7月に、戦後初の建設国債、いわゆる赤字国債の発行を決断する。これを受け、株価は上昇に転じ、不況から脱却する。こうして経済政策の主体が金融から財政へと変わっていく。
こういった歴史を見ると、白石の金融政策の意義がわかる。好況が持続し、経済成長を続けると、輸入が増加する。当時は加工貿易ではないので、輸出品の価格ではなく、輸入代替が十分に進んでいないことが影響する。貿易制限を強化して減少傾向にあるとは言え、金銀流出は続いている。貿易赤字が累積拡大して金銀が海外に流出、国内保有量が減少していく。この事態を改善するには、金融政策により景気を冷やすほかない。経済成長の続く社会通貨供給量の増加を求めたとしても、国際収支の都合上、当局が意図的に減らして不況にすることは高度経済成長期の例で見た通りである。
白石はインフレ対策として通貨供給量を減らす金融政策の効果を発見して実行に移す。ただし、彼が想定した引き締めのスピードより早く実施されてしまい、経済は東京オリンピック景気後と同様の不況に陥ってしまう。
補足すると、改鋳による貨幣の質の低下は貿易において厄介な事態をもたらす。1560年、イギリス国王財政顧問トーマス・グレシャムはエリザベス1世に、質の改悪によって国外に貨幣が流出していると進言する。同じ額面であっても、外国の貿易相手は貴金属の含有率の高い貨幣を受け取るが、低いものは拒否する。それにより、国内には質の悪い貨幣だけが流通している。これを同国の経済学者ヘンリー・マクロードが『政治経済学の諸要素』(1858)と「グレシャムの法則」と命名、「悪貨は良貨を駆逐する(When there is a legal tender currency, bad money drives out good money)」として知られるようになる。
金銀を用いる貿易取引の場合、代金を受け取る商人は希少金属の含有率の高い貨幣を求める。国外に良貨が流出、国内には悪貨が残る。悪貨は良貨に比べて購買力が低い。別の言い方をすると、良貨はインフレ率が低く、悪貨は高い。良貨が流出して悪貨が残れば、インフレを助長する。悪化を回収して良貨に改鋳することは、国際収支からのインフレ圧力も抑えられる。
このように、白石の経済政策は非常に体系的である。インフレと国際収支の関連の認識も政策から理解できる。確かに、諸般の事情により政策の効果について問題点が認められる。しかし、白石は理論的には現代の金融政策を先行している。
白石失脚の後も、財政赤字は慢性的で、幕府は貨幣の質を落とす改鋳を実施、インフレも頻発する。けれども、幕府の対応は、「改革」と言っても、体系的理論に基づくものではない。歳入を増やすための新田開発の他、禁欲主義的な質素倹約を呼びかけ、文化を統制、町人たちに見せしめの処罰を科して歳出を抑えようとする。これを繰り返して幕府は幕末を迎える。
白石の経済政策評価の際に、彼の家康以来の原則の言及が教条主義的と批判されている。白石は、自身の改鋳政策において、徳川家康の「貨幣は尊敬すべき材料により吹きたてるよう」を論拠にしている。また、白石は、宝永新例の中で、貿易について「外国の無用な物と我が国の有用な物を交換するのみ」と定義して「我が国の政道を害するもので、本来は外国人の日本来航を一切禁じるべきである」ところを「将軍家の恩恵で貿易を許している」と述べている。白石は、いずれも自らの政策の根拠を幕府の原則に置いている。
しかし、これを教条主義と批判するのは、前近代における政治の発想を理解していないことを露呈しているだけである。白石は前近代の政治の目的を理解し、それに忠実である。今日であれば、金融政策を実施する際、広く共有されている経済学理論に基づいていなければならない。けれども、当時はそんなものはないし、政治の発想も異なる。インフレを抑制するために通貨供給慮を減らす目的で質を上げる改鋳を行うとしたら、その論拠を規範から示さなければならない。白石は家康以来の原理原則を引用して幕府内で理解を得ようとする。前近代の政治判断を評価する際に、近代との政治の発想の違いの理解が不可欠である。彼を批判する前に、それを知っておく必要があるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
