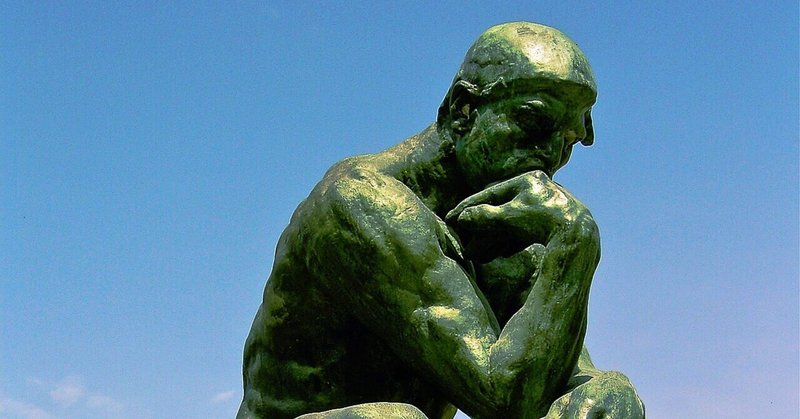
本質的思考のための考えるモデル(2)(2010)
第2章 歴史的相対化と論理的相対化
対象を絶対化して考えても、その本質は明らかにならない。それは歴史を持ち、基礎づける理論を備え、社会・時代と相互作用をし、分化している。断片的な知識だけで対象をイメージしたり、あるいは切れ切れをただ積み重ねたりすることは、恣意的な思いこみや思いつきにすぎない。本質的思考には、その経緯・実態を考慮して、二種類の相対化の作業が不可欠である。一つは社会科学的認識に基づく「歴史的相対化(Historical Relativized)」であり、もう一つは自然科学的方法論による「論理的相対化(Logical Relativized)」である。
まず、歴史的相対化であるが、歴史を遡行するときに重要なのは、「起源(Origin)」である。自明視されている対象は、その起源もそれを正当化するように思いこんでしまうものだ。ところが、いざ調べ始めると、思った以上に新しかったり、古かったりすることに驚かされる。問いは「いつ」だけではない。なぜ生まれたのか、もともとの意味や用法、位置づけはどうだったのかなども含まれる。不明の場合も多いけれども、それをどこに置くかは問題意識に応じる。例えば、コンピュータを「計算機」と定義すれば歯車式計算機、「データ処理装置」とすれば目覚まし時計に遡れる。唐天竺のことも確認しなければならないのは承知しているけれども、いずれも紀元前の古代ギリシアには誕生していたと推測されるが、定義によって起源が左右される。
また、歴史を辿る際、「前景(Foreground)」と「背景(Background)」に言及する必要がある。対象は前者、社会的・時代的条件などは後者である。最初の電子計算機ENIACを前景にするなら、第二次世界大戦中、迅速な弾道計算の必要に迫られたアメリカ軍がその開発の後押ししたというのが背景である。
「継続(continuation)」と「変化(Change)」に着目しながら、自明性に覆い隠された「歴史性(History)」を顕在化して、対象に関する認識を拡大する。なお、変化には断絶や復活も含まれる。例えば、ENIACは、真空管設計で、その内部での計算に2進化10進法を使っていたが、後継のEDVACは、設計の点は継続しているけれども、2進法の採用で変化している。
一方、論理的相対化は、「分類(Classification)」である。それは「技術性(Technique) 」を検討することであり、「内容(Content)」と「形式 (Format)」が分析の主眼である。それに着目しながら、「類似性(Similarity)」と「相違性(Difference)」を吟味して、いくつかの「基本型(Basic)」を導き出す。その上で、「近隣性(Neighborhood)」と「結合性(Combination)」を加味して、汎用性の高い総合的な分類を構築する。
今日のコンピュータがENIACの頃と違う点の一つにネットワーク機能が挙げられるが、「ノード(Node))」を「リンク(Link)」でつなぐ観点からの分類を例に論理的相対化を説明してみよう。基本型は「メッシュ(Mesh)」・「スター(Star)」・「ループ(Loop)」・「バス(Bus)」の四種類である。最初のメッシュはすべてノードを互いにつなぐネットワークである。次のスターは中心のノードに中継交換させる星型のタイプである。三番目のループは、中心を持たせず、ノードを環状に結んだタイプである。最後のバスは、バス路線にバス停が設置しているように、一本の母線に複数の子線がつながり、その先にノードが置かれたタイプである。すべてではないが、多くのノードを互いに結びつけたタイプを、メッシュと近隣性があるため、「部分メッシュ(Partial Mesh)」と呼んでいる。また、バスの始点と終点をつなげば、ループの一種になり、両者の間には近接性がある。さらに、複数のスターの中心同士をつないで系統樹的にしたのが「ツリー(Tree)」であり、ループとスターなど別の基本型を組み合わせたタイプを「混合型(Mixed)」と言い、それぞれ「結合性」を有している。
これまでの展開は定義から歴史的・論理的相対化に向かうトップダウン型であるが、逆であってもかまわない。二つの相対化から定義を導くボトムアップ型も探求の道筋である。この典型例が「漢字」をめぐる研究である。漢字を歴史的・論理的相対化を行うと、表意的でもあるし、表音的でもある。漢字を表音文字とも表意文字とも言い表せないので、その両方を兼ね備えた「表語文字(Logogram)」という新たな概念で定義している。重要なのはあくまで説得力と完成度である。
いかに核心的な定義を設定しても、それだけでは自明性を覆すには不十分で、本質的思考には至らない。対象には歴史的深みと社会的な広がりを秘めている。この二つの相対化はそれが何であるかが体系的に明確化する作業である。
第3章 定量分析と定性分析
定義と相対化によって対象の概観は理解できても、その具体的な面を詳細に分析しなければ、例えば、定義や歴史、修理を知れば「政党」というプラットフォームの全体像は認識できる。けれども、それは多分に抽象的であり、具体的な把握とは言い難い。政党がどのように経済的に運営されているのか、あるいはどう組織構成されているのかなど直裁的な疑問が次々とわいてくる。より実体的に理解するためには具体的な側面を分析する必要がある。
ただ、自明性にとらわれたまま、つまり概観をつかまないまま、具体的な問題に向かうと、断片から全体を性急かつ恣意的に拡大解釈してしまう危惧がある。そもそも、その対象に最適の分析方法を選ぶには、定義における主観性依存の有無が鍵になる。主観性非依存型定義の場合には定量分析、主観性依存型定義では定性分析がそれぞれ適している。概観を理解していなければ、対象を分析する資格がない。そんなものは本質的思考ではない。
定義が主観性に依存していないとすれば、対象は人間の意識の外部に存在すると見なすことができる。「実在論(Realism)」の範疇にあるのなら、「決定論(Determinism)」の態度をとれ、この対象には、「自然科学的(Natural Science)」な「実証主義(Positivism)」に立脚した「定量分析(Quantitative Analysis)」の方法論が適している。それは仮説を立て、その妥当性を検証する手順がる。定量データの比較や対照などを通して、「因果関係(Relation between cause and Effect)」ないし「相関関係(Correlation)」を特定する。コストと時間を念頭に置きつつ、必要もしくは可能な限に収集したデータを数量的に解析し、客観的基準に基づく一般的な結論を導き出す。
一方、主観性に依存した定義ならば、対象は人間の意識の内部に形成されていると考えられる。「唯名論(Nominalism)」の範疇に属している対象には「主意主義(Voluntarism)」で臨むことになり、「道徳哲学的(Moral Science)」な「解釈学(Hermeneutics)」に基づく「定性分析(Qualitative Analysis)」の方法論が適当である。文化人類学のフィールドワークのように、対象の固有な質的側面に着目して解釈する分析として用いる。調査して、その意味を抽出する手順を辿り、仮説を生成する。その際、アメリカの臨床心理学者カール・ロジャーズ(Carl Ransom Rogers)が提案したカウンセラーの三条件を守る必要がある。それは、「無条件の肯定的配慮(Unconditional Positive Regard)」・「共感(Empathy)」・「自己一致:純粋性(Congruence: Genuineness)」である。対象を尊重し、共感的に理解しようと努め、私利私欲に囚われ関係を不安定化させてはならない。重要なのは「文脈(Context)」の把握である。あまり偏向していないのに、同一対象でも解釈が分かれる場合がある。概して、事実関係の記述にはさほど差が見られないが、それを学説・理論の体系に位置づける際に、そうした事態が生じている。特定のテキストや人、集団、組織、事象に寄り添いつつ、その固有の状況を考慮した個別的な対応を判断する。
本論では広義で用いているけれども、狭義では、定量分析や定性分析は化学の分野における分析方法を指す。一般的に、「定性」は、「定量」と対をなし「性」は「質」の意味として用いられる。定性分析は試料中にいかなる成分が含まれているか、定量分析はその成分量はどうかを解析する手法である。前者を行った後に、後者を始めるので、両者は化一連の手順として連結している。なお、最近では、電子プローブ微小部分析法やX線解析法などを利用して同時定性・定量分析する方法・装置も開発されている。厳密さの強調から用いているが、どうしても化学との混同を避けたい、もしくは「分析」に抵抗があるのならば、これを「研究」と置き換えてもかまわない。対象によっては、定量分析と定性分析を組み合わせて考察することもある。
意識調査や世論調査などの社会調査は主観性にかかわる項目の回答を求めていることが少なくない。しかし、これらは社会のトレンドに関心があるのであって、個々人の主観性を対象にしていないので、定量分析が適用できる。
コンピュータの急速な発展に伴い、従来、定量分析とは無縁だった歴史学や地理学、考古学、文学などの領域にもその方法が導入され、画期的な成果を挙げている。1980年、トマス・メリアム(Merriam Thomas)は、コンピュータを使った定量分析によって『サー・トーマス・モア(Sir Thomas More)』の作者をウィリアム・シェイクスピアと鑑定している。シェイクスピアの文章の癖、すなわち文紋とこの戯曲のそれが一致する。もちろん、この文献学的成果は彼だけの手柄ではないし、シェイクスピア作説には異論もある。何と言われようと、主観性に依存していると、その対象の範囲や境界が曖昧になり、数量化できない。定量分析の方法を用いるために、定義から主観性依存の部分を除外するか、非依存型定義の概念に入れ替えるかといった工夫が要る。メリアムは、文体という曖昧で主観性に依存した概念ではなく、文章を解体し、品詞や単語の使用頻度などを統計データにして、比較している。まさに「定量革命」と呼んで差し支えないだろう。政治・経済・研究・スポーツにおいうて、定量分析を無視することはできない。
コンピュータの性能のみならず、ネットワークと検索機能の充実も定量分析の可能性を大きくしている。「暴走族」を例にしてみよう。新聞のデータベースにアクセスし、「暴走族」を検索する。最初にそれが見出しに登場したのはいつで、その後に使われた頻度の推移をたどることで社会現象としての「暴走族」の変遷の一面をつかむことができる。手作業となると気の遠くなる話だが、コンピュータであれば、朝飯前だ。
対象が主観性非依存型定義の概念であるにもかかわらず、定性分析を選ぶと、科学的根拠に乏しい恣意的な意見に陥ってしまう。議員の間からも、国会議員の定数が多すぎるので、削減すべきだという主張が発せられているが、これなど典型例である。議員定数は主観性に依存しない以上に、定量分析は適している。多いか少ないかは、各国の議員定数と人口比率を国際比較すれば、容易に判明する。実態と実感がずれているとしたら、さらに、議会内での活動に関する定量データを国際比較すると、その理由も明らかになる。定義が主観性非依存型である場合、定性分析では勝手な思いこみが提案されるだけである。
定量分析の進展によって、定性分析も再考を促される。かつては解釈学アプローチがとられていた感情や記憶、認知といった心理学の領域も脳研究を通じて定量的に研究されている。定性分析ならではの領域と手法を明確化することが迫れている。定量革命が起きる前は、実証性を欠いた一人合点の日本人論あるいは日本文化論が心理学者によって、社会学者や文学者も同様だが、発表されている。文芸批評家の小林秀雄は『アシルと亀の子』の中で「批評するとは自己を語ることである。他人の作品をダシに使って自己を語ることである」と言ったが、定量革命以前の定性分析はこの意見にとどまるものが少なくない。しかし、これは解釈ではない。告白だ。定性分析に必要な姿勢は、ロジャーズの三原則が示しているように、相手と息を合わせて、その話に耳を方組めることであって、自分お考えをベラベラ披露することではない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
