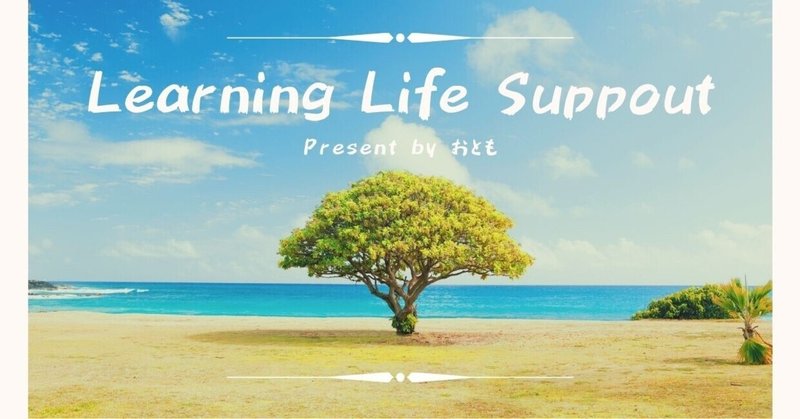
Q1.学び方を学ぶ意味ってあるんですか?

ねーねー、おともさん?
「学び方」っていうけれど、なんで今さら学び方を学ぶ必要があるんですか?だって勉強なら小学生の頃からずっとやってましたよ、私たちもういい大人になってますよ。方法なんて学ばなくても、できるんじゃないですか?


今、いいこと言ったよ!それはすごくいい疑問だ!


まじっすかー!あざっす!ってことは、この勉強法さえ知ってればテストは100点、技術も満点っていう裏技あるんですよね!それ教えてくださいよ!


それはない……!あれば自分がすでに実践して天才になってるよ。


えぇーーー?ないのか……
じゃあ、ますます「学び方」を学ぶ意味ってなんなんですか。


それは学生から社会人になったから。子どもから大人になったからだね。


それは一体どういうことですか?


それでは今から少し、僕の思う学び方を学ぶってことを説明しよう。


学び方の大事さって、なに?
なんで『学び方』が大事なのでしょうか?
改めて『学び方』と聞くと
「大学院に進学するような人たちの考えることでしょ」
「なんかの資格を取るような人たちだけ知っていればいいんじゃない?」
「普通に働く分には関係ないよね」
と感じるかもしれませんね。
しかしここでするのはそういう話ではありません。
初めに言ってしまうと、生きていくうえで重要なことなのです。
実はおとなの学びは、今までの学生の学びからダイナミックに変化します。その変化に応じた『学び方』にアップデートしないといけないのですが、この変化があることを誰も教えてくれません。あまり意識してないかもしれませんが、子どもの時の学び方とおとなになってからの学び方には大きな変化が現れます。
その大きな変化のひとつが、学習の主役が完全に自分になったことです。
子どもの時の学習といえば、先生が教えてくれて、課題を提出するとか、年間通して何をどこまで学ぶかわかっている状態でした。そしてそれらを全て(その教科や知識が何に使えるのかはわからないまま)習得してから次のステップに上がりますよね。そして進んでなければ、最低限なにをやればいいのか、どうするべきか指示してくれました。
一方で、おとなはそうではありません。おとなが勉強するのに先生もいませんし、カリキュラムもありません。基本的には学ぶのも自由、学ばないのもまた自由。そして学ばないところで自分が留年することもなければ、生きる上で赤点をとることもありません。
なので自分で主体的に考えて、動かないといけなくなります。自分で何を学ぶのか、どう学ぶのか、どうなっていきたいのかを考えることになるのです。学びの主役が自分になった以上、学び方を考えるというのは重要なことなのです。
新人のうちは何かしらの課題が出るでしょう。そのため最初のうちは、何をやるべきか、今の到達すべきレベルはどこかというものがまだわかりやすいと思います。そういった事情もあって新人時代は、学生の頃の学びとの変化を感じにくいと思います。
変化のときは、やってくる。
しかし、変化は訪れます。
変化が起きたことに気づくタイミングは人によって様々かもしれません。
就職してから「おかしい、学生の時みたいに勉強ができないぞ?!」という違和感を覚えるかもしれません。
業務を一通り覚えてから「最近なんの変化もないし、なんだか自分の成長が停滞してる…ような気がする」と、行き詰まりを感じるかもしれません。
配置換えや転勤などで「今までどうやって覚えてきたんだっけ?こんなに物覚え悪かったっけ…」と思うかもしれません。
特に医療の世界は昔から進歩が早いと言われます。5年前までの知識があっさり古いものになります。昨今では、新型コロナウイルスの各国の対応を見ても分かるように新しい知見が毎月、毎日アップデートされ続けていきます。昔はベストだと思っていたことが今ではワーストな方法だとわかることもあります。
病院で中堅どころと言われる4〜5年目くらいでいえば、4〜5年の間に自分が新人の時と比べて治療のガイドラインや蘇生のガイドラインはアップデートされていることになります。学び続けていかないと、あっという間に置き去りにされてしまう世界です。
いずれにしても、大人として否が応でも社会生活を送る上で、意図してもしなくても色々な課題に気づき、困難に直面していくものです。自分で自分の課題を見つけ、設定していく能力が重要になってきます。そして自分が見つけた課題の解決方法も同時に探っていくことになります。
ここで『学び方』が出てきます。
おとなの『学び方』って?
自分の経験の中で出てきた課題は、他の誰にも共有し難いものです。その解決に至るための道筋、その解決方法、得られる学習成果も人によって異なるでしょう。子どもの時と違って、皆が同じ課題に直面しているわけではありません。それぞれの経験の中から課題が生まれていきます。カンニングも出来ないし、他の人にとっての正解が自分にとってのベストアンサーとも限りません。
もう一つの大きな変化が、座学での学びよりも経験から学びを得ることが多くなルことです。大人としての学びの70%は経験から生まれると言われています。その経験から何を考え、何を学び、どう活かしていくのかが重要になります。
医療現場、特に看護師は『振り返り』といってその日のイベント・業務から何を感じたのか、学んだのかといったことを先輩たちとしたり、レポートを書いたりしたのではないでしょうか?
しかし、教える側も教わる側も、経験をどう活かすのか、どんな振り返りが有効なのか、振り返りそのものの知識をどう身につけるのかなどを学ぶ機会はそうそうありません。その結果、「自分がやってきた、教わってきたようにしか教えられない」ということになります。運良く効果的な方法を身につけた先輩がいて、その真似ができればラッキーです。しかし現実にはそういったことはまずなく、辛い思いをしてきた方も少なくないでしょう。
しかし『学び方』を知っていれば、どの職業でも、どの職位でも、人生のどのステージにいても、戦っていくことができるはずです。
これは単なる暗記方法や、筆記テストの攻略法というものとは異なります。そういう方法以前の考え方といえます。小手先の技術ではなく、生きる上での考え方といっても良いと思います。当マガジンでは考え方だけでなく、具体的に実現・実践できるアイデアにも今後触れていきたいと思っています。
特に医療職は、まず国家試験合格という絶対条件を通過するために勉強に励むわけですが、就職した途端にその明確な目標は無くなります。そこで「何をどうしたらいいんだっけ?全然手につかない…」と学びの路頭に迷うきっかけとなります。
(受験生が志望校合格が目的になってしまい、入学してからなんのために進学したのか目的を見失うのに似ています)
よく、リアリティショックで新人が辞めていくので精神的なフォローが必要と言われます。その中には、「今までの勉強では現場で通用しない、でもどうやっていいかわからない」という絶望もあったと思います。このマガジンがそうした不安や悩みを少しでも減らせるといいなと思っています。
ここまでの話では『成人教育』『経験学習』といったところに、ほんのちょっとだけ触れて話をしてきました。あとで少しづつこれらをどう活かしていくのかという記事も追加していこうと考えています。
これからの看護職と学び方。
さらに、看護職員の確保と質の担保のため、2021年通常国会での法改正により進められる国家資格とマイナンバーの連携についても、継続的な研さんや就業支援体制への活用といった資格活用基盤の強化の必要性を訴えました。また、多様化・複雑化する患者像に対応するため、看護基礎教育の修業年限を4年に延長することなども要望しました。
上記の文言は、リンク先の日本看護協会が厚労省医政局に関して提出した要望です。すでに言われているように超高齢化社会を迎え、それに対応する医療職は多様化・複雑化する患者に対応する能力が求められていきます。その基礎教育のレベルが上がっていくということは、先生のいないおとなである我々は自分たちで意識的にアップデートしていかなくてはなりません。
新しい知識や技術をアップデートし続けていく術を身につけることによって、新人とベテランのギャップは無くなり、互いに学び続けようとする関係が構築できるはずです。
とはいえ。
「そんなこと言ったって、勉強する時間も余裕もないよ。そもそも勉強自体そんなに好きじゃないし」という声も聞こえてきそうです。
僕自身、フルタイムで勤務し、家庭を持っていることもあってなかなかまとまった学びの時間が取れない現実があります。人にはたくさんの背景があります。家族のケアがある、自身の体調が万全ではない、経済的な困難さがあるなど、様々な事情を抱えているのもまた大人でもあります。
多くの学習法や勉強法というのは、ある程度学習環境が整った(身体的、精神的、社会的、経済的に安定している)ことが前提となっていると感じます。だからこそ、そうした困難さの中でも、実現可能な方法をなんとか見つけて一緒に考えていけるようにしていきたいと思います。
さて、学び方を学ぶ必要性や意味を整理します。
A1.学び方を学ぶ必要性は、子ども(学生)の時から変化したおとなとして特有の変化を知って対応していくため。そして学び方を学ぶ意味は、学びの主役となった大人として経験を活かして生き続けていくため。
書けば書くほど、知れば知るほど、どんどん知らないことが増えていきます。わからないことをわかること、知らないことを知るために学び続けていくんですね。
このマガジンを書くにあたって、自分も学び続ける姿勢を維持するためにこれとは別にマガジンを作りました。そちらは単に1日のなかでどんな学習をしたか、何を学んだか、感じたかをメモ程度に書いている【おとものLeaning Log】です。医療職である以上、経験したかとは書けないのがもどかしいところです。
ラーニングログの方法や目的は、読書猿氏の独学大全をご参照ください。
当マガジンでは、参考にした書籍などを紹介しております。アフィリエイトではありません。書籍の出版社のリンクを掲載しておりますので、チェックしてみてください。
📚ブックガイド📚

ここから先は

学び方、学んでいきますか?これは、おとなになって自分の学び方がわからなくなってしまった医療者のためのサポートマガジン。1記事ごとに『学び』…
