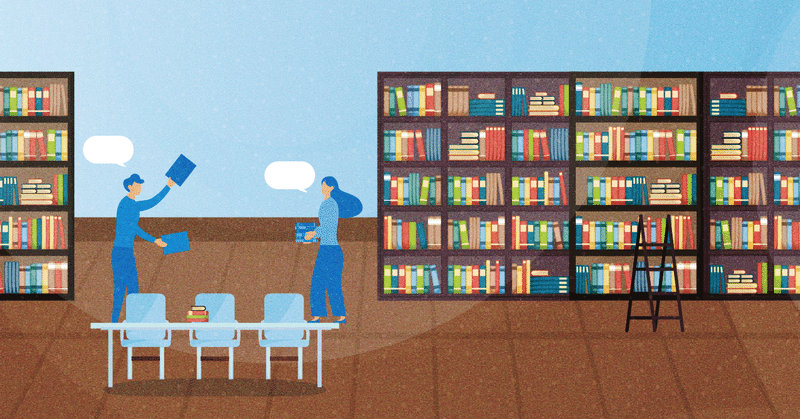
年間読書量130冊のワーママが語る、読書習慣化のコツ
「私の趣味は読書で、読書量は年間100〜130冊です。」
と言うと、
「フルタイムで仕事しながら子育てして、いつ本読んでんの?」
「何を読めばいいか分からへん…本屋に行っても、どの本がおもしろいのか選ばれへん」と言われます。
そこで、
・読書のしかた
・本の選びかた
を私なりにまとめてみました。
①読書のしかた
1日のうち、私の読書時間は1.5〜2時間です。
仕事や子育てで忙しいのに、そんなに時間確保できへん!と思われた方、多いですよね。
読書とは、椅子に腰掛けてゆったりとコーヒーを飲みながらでなくてもできます。
私が本を読むのは、主に
・通勤中(電車で片道30分)
・入浴中(湯船で15分)
・夕飯後の15分〜20分
こんな感じです。
ゆっくり座って読めるのは、夕飯後くらい。
移動中は、仮眠を取ったりSNSで時間を消費したりせず、その時間を読書に充てます。
Kindleだったり紙の本だったり、いろいろです。
ここ1、2年でテレワークが進んだ結果、通勤時間が大幅に削減されました。
それ自体は喜ばしいことなのですが、比例して読書時間が減りました。
要は、通勤していた時間を読書に充てず、そのまま労働時間に移行してしまってました。
ここは大いに改善すべきところです。
入浴中は、紙の本を持ち込んで湯船につかっている間読書をしています。
私は同時に4、5冊の本を並行して読むのですが、お風呂に入っている間は、なるべくビジネス書は読まないようにしています。
なぜかと言うと、寝る前に難しい本を読んでしまうと、頭が冴えて寝付きが悪くなってしまうからです。
逆に、もっとインプットしたいと言う欲求が働いているときは、あえてビジネス書を選びます。
インプットもアウトプットもしたくないくらい頭が疲れていて、活字を読みたくない時は、マンガやエッセイなど軽い本を読むことにしています(活字は読みたくないけど、本は読みたいという活字中毒あるある)。
②本の選び方
読書が続かない主な原因は、おもしろいと思う本に出会ったことがないからだと思います。
では、おもしろい本とはどのように見つければいいのか。
答えは、読書を習慣としている人にお勧めの本を教えてもらうことです。
ただ、年間読書量が100冊を超えるような人は、ほんの数パーセントです。
(日本人の平均読書量は、年間12、3冊です。)
身近に読書習慣のある人がいない場合は、「本屋大賞」のノミネート作品を読んでみることをおすすめします。
本屋大賞とは、書店員が1番売りたいと思う本がノミネートされていて、芥川賞や直木賞よりも読みやすい文体や内容であることが多いです。
芥川賞は日本文学であるため、読みやすさという面ではあまりおすすめしません。
読書初心者はむしろ避けたほうがいいと思います。
そして、ビジネス書よりも小説をお勧めします。
小説は、頭の中に登場人物のイメージや情景が思い浮かび、それこそが自分だけにしか味わえない感動そのものです。
また時代小説や推理小説など、ジャンルも様々で、作家の個性が出るため「好き」が見つけやすいです(私はイヤミス系、真梨幸子先生が特に好き)。
対してビジネス書は、難解な用語や堅苦しい言い回しなどがあるため、なかなかハードルが高いです。
本を読まない人は、「なんでその本選んだん?!」とびっくりするようなチョイスをしてたりします。
例えば、アドラーが流行った時は、アドラー心理学の中でもかなり難しそうな翻訳本を選んでいたり。
読書とは、難しい本を読まなくてもいいのです。
難しい本からしか学びがない、なんてことは絶対にありません。
絵本や漫画も、学べる事はたくさんあります。
そして、最後まで読みきらなくてもいいし、ド頭から読み進める必要もない。
目次を見て、気になるところだけ拾うように読んだっていいのです。
とにかく好きな本を読むこと。
これあんまり好きじゃないな、と思ったら途中で止めていい。
ただし、本を読むと言う行為自体はやめないこと。
常に、何か読みかけの本がある状態をキープし、1日のうち3分でも5分でも本を読むこと。
そうしているうちに、習慣になります。
習慣になる頃には、自分の好きなジャンルや作家が見つかっていると思います。
たった1500円前後で、ものすごい充実した時間と感動、学びが買えます。
読書ってすばらしい!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
