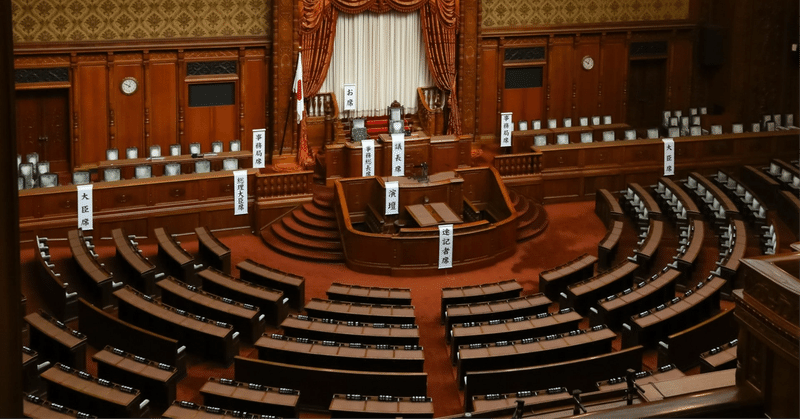
先生「みんな、どう?」生徒達「同じで〜す。」←確定演出
今まで、何百という親子を見てきました。親子の関わり方についての経験知があります。数だけでなく、人より感度も高いです。
今回は、重大な一つの定理を示します。
「答えが決まっている質問」は、思考を奪う。
「答えが決まっている質問」をするのは、相手の考える気を失せさせる素晴らしい方法です。相手を説得して「自分の思い通り」に動かしたい場面、例えば営業マンや政治家は良いでしょうが、相手に主体性を持たせる、という教育的な場面では、あってはなりません。
【例①】小学校の先生が身につけた「伝統芸」
例えば、日本の小学校には、次のような謎の形式美があります。
先生「〜そうだね。でも〜?これをそのまま答えにしては〜?いけ〜???」
生徒一同「「ない!!」」
どうですか。この文脈で「ない」以外の答えなんて?絶対に??ありえ???「ない」ですね。文脈や内容と全く無関係に、最後だけ聞いていれば答えが「ない」であることがネタバレされています。この追い込み漁のような修辞法は、特に小学校の先生が授業で大変好んで使い、多種多様なバリエーションがあります。他にも、次のような指導法も開発されています。
生徒「(自信あるから発表だ)答えは30です。」
先生「(よし、合ってるから…)みんな、どう〜?」
生徒一同「(お、合ってるんだ)同じで〜〜す!」
ホラーですね。このやり取りの問題点は甚大です。①生徒が考えなくなる。②生徒は結局何も分かっていない。③生徒は分かったと錯覚する。しかも自力で。④先生は、生徒が分かったと錯覚する。⑤先生は、自力で生徒に分からせたと錯覚する。
⑥さらにまずいことに、両者は気持ち良くなっていますから、辞める理由がなく、麻薬漬け状態になります。賢い生徒がなんか変だなと思ったとして、止める理由もありません。よって、伝統芸能のレベルに昇華しているのです。
【例②】家庭の親が身につけた「ダブルバインド」
心理学や精神疾患の文脈でよく用いられる「ダブルバインド」をご存じでしょうか。「相手に選ばせているようで、どちらを選んでも結果が同じ質問」です。つまり「答えが決まっている質問」です。
お母さん「そろそろテレビを消してベッドに行くか、お母さんの読み聞かせを聞くか、どっちにする?」
ちょっとわざとらしいですね。こんなのもあります。
上司「目標に届いてないね。ちゃんと頑張ってるの??」
「何を言っても怒られる状況」なども「結果が決まっている選択」で、追い詰められますね。もともと「ダブルバインド」は、統合失調症の研究の中で発見された概念だそうですが、現在はセールスコピーでよく使われています。相手に考えさせないためでしょう。
【進化系】野生の「プロ」が生まれてしまう
以上の通り、「相手の思考を奪う」ことは、学力や精神に影響を与える危険があります。さらに…時々、こういう厳しい質問を上手く乗り切って生活している「即興演劇のプロ」が誕生してしまいます。相手の顔色を瞬時に見極め、相手が欲しい答えしか返さないマシーンになれるのです。幼いときにこうなると、一見「やたら愛想が良くてかわいい子」が、親が見ていないところでばかり奇行を取るようになります。
【結論】大事なことなのでもう一度
「答えが決まっている質問」は、相手の思考を消します。用法・用量に気をつけましょう。
最後に、相手がこのお芝居思考に囚われているかどうかをチェックできる方法をお話しします。ズバリ、「ふーん、どうして?」と質問して答えを待つことです。これでダンマリになったり、「やっぱりいいです…」となる人はほぼ確定で「質問されたということは、怒られてるんだ」「自分の言葉で言うのは無理!」と凝り固まっています。
とっても簡単!
2023年9月3日
おいしいコーヒーが飲めると集中力も想像力も高まります。 よろしければコーヒーサポートをお願いいたします😌☕
