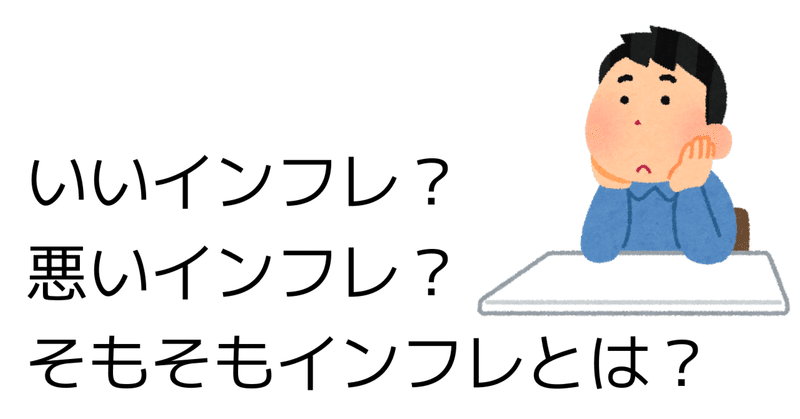
ここ最近の物価高について
日経COMEMOにこんな記事があったので、それを参照しつつ自分の意見を書いてみます。ちょうど参院選の争点でもありますね。
https://comemo.nikkei.com/n/nee62ec7c2eeb?magazine_key=mb7af516ae320
よく言われること
「今年に入っての物価上昇は、コロナパンデミック後の急速な経済復興による旺盛な原油需要が原因だ!」「ロシアのウクライナ侵攻が原因で世界の穀物倉庫であるロシアとウクライナから小麦が出荷されない。これで需給バランスが崩れている!」というものです。
現在の世界経済は、原油を中心に回っていると言っても過言ではないでしょう。自動車・航空機・火力発電所の燃料は原油から作られます。農家のビニールハウス内の温度調整も軽油が使用されています。製品素材のプラスチックや衣料向けポリエステルやナイロンも原油から生成されるナフサから作られます。
すなわち、原油価格が上昇すれば、多くの分野でコストが跳ね上がるのです。
これってインフレ?
そもそもインフレ(=インフレーション)とは何でしょうか。コトバンクで調べてみましょう。
1 一般的物価水準が継続的に上昇し続ける現象。発生原因によって、需要インフレーション・コストインフレーション、発現形態によって、ハイパーインフレーション・クリーピングインフレーションなどに分類される。インフレ。⇔デフレーション。
コストインフレーション?
コストプッシュインフレーションという用語があります。
生産コストの上昇によってもたらされる物価騰貴。需要インフレーションとコスト・インフレーションの区別を論理的に一貫して説明したものは少いといわれる。抽象的には,M.ブロンフェンブレンナーと F. D.ホルツマンの有効需要に基づくものか否かによる区別があるが,現実的には F.マハループの説が有名である。マハループは,まず需要インフレーションをコスト上昇と無関係の自発的需要インフレーション,コスト上昇の結果として生じる支出増加による誘発的需要インフレーション,完全雇用政策に伴う拡張的財政金融政策によって発生する支持的需要インフレーションの3つのタイプに区別する。そして第3番目の支持的需要インフレーション下で,賃金,原材料価格などが攻撃的に引上げられ,それが生産物価格に転嫁されて一般物価水準が押上げられる場合をコスト=プッシュ・インフレーションと呼んだ。供給側にインフレの原因を求めたものであるため,売手インフレーションとも呼ばれる。
つまりインフレとは、物価が上がること一般を指し、そのなかにコストプッシュインフレがあるわけです。
また少々話はずれますが、日本を始めとした先進国は失業率の改善を目標に、年2%前後のインフレターゲットを導入してきました。
悪いインフレ?
2022年に入って以降の物価上昇は、国の政策・賃金・国内の通貨供給に関係なく発生した外的要因の大きいインフレということができます。まさにコストプッシュインフレなわけです。
ただし、政策が関係している面も見られます。ゼロ金利政策です。日経新聞から引用しましょう。

普通に暮らしている我々にとってみれば、いきなり降り掛かった火の粉とも言える状況でしょう。特に食料品の値上げは深刻です。生活に直結するからです。ただでさえここ30年ほど、物価が急激には変わらなかった日本経済です。意図しない・意識しないインフレは財布のヒモを強く閉じさせるだけでなく、経済が弱くなってしまうことも懸念されます。
どう解消するのか
ただ手をこまねいていても現状は変わりません。日米金利差に注目して、今すぐ利上げを行え!という意見もちらほら見えます。ただ、先般の選挙前討論でも話されていましたが、金利を上げれば、お金は借りにくくなり住宅ローンの返済額も上がります。曲がりなりにも経済を回してくれる層の首を締めかねないのです。
更に上のグラフの2018年頃に注目してみましょう。日米金利差は3%ほどであったにも関わらず、円相場は110円前後で推移していました。
私は金利引き上げには慎重な考えを持っています。それよりも消費税減税やガソリン税の減税など、「消費」に関連する税金を低くし、高くなったとしても買える価格帯の維持を目指すべきと考えます。
これからの社会
原油の高騰・原料の高騰・急激な円安、この3点は実際消費者の首を締めています。生活が苦しくなった人も多いことでしょう。私もそうです。
ただ、ロシアによるウクライナ侵攻が長期化している以上、原油・原料の価格は高止まりするのではと感じています。
ある種、今の減少はデフレに悩んできた日本への黒船来航とも言えると思うのです。物価上昇は一見、悪いことのように見えます。支出が上がり財布のお金が少なくなってしまうからです。しかし、デフレデフレで過度な価格競争が行われ低価格を維持し続けたとしても、生産者側の疲弊は終わることがありません。また買う側が強いことはいわゆる「お客様は神様」志向に繋がり、無闇矢鱈としたクレーム合戦に発展しかねず、これもサービス提供者を疲弊させています。
物価は上がっていい。そして生産者・サービス提供者にもその労働に見合った対価を支払える社会。これが現在の物価高を踏まえた上で、日本が目指すべき姿ではないでしょうか。
これまでであれば、500円の壁・1000円の壁などもあったことでしょう。しかし、急激な原料高にみまわれれば、こうした壁を意識していたら赤字経営まっしぐらです。
ランチに1200円かかることも覚悟しなければならないかもしれません。しかし、いちどランチに1000円かけるのが日常となれば、レストランやコンビニは「1000円の壁」を意識しなくてもよくなるわけです。
もし過度に景気が冷え込んでしまうのであれば、通貨単位を変えるデノミ(例えば現行の100円を新1円に定義し直す)も検討材料に入ってくるかもしれません。
今回の事態は、これまで日本を苦しめてきた「デフレ」と真剣に対峙し、また「円」の価値をどう形作っていくのかを議論していく、千載一遇の契機だと考えています。
自分メインの記事もありますが、基本的には誰かの役に立つ記事執筆を心がけています。ご支援いただけたら、次お目にかかる際は、もっと進化したプロになります!!
