合意形成力
組織というのは必ず2人以上ですよね。
1人1人の価値観は違いますから、どうしても意見が割れてしまう事があります。
あなたはそのような時どうしてますか?
上司に言われたらしぶしぶ従いますか?
それとも反対意見を上げて評論家気取りになりますか?
知らないと言って参加しませんか?
組織という性質を理解し、
上司でも部下でも合意形成をしていくことがお互いにとって大事なスキルです。
合意形成力=コンセンサスとは

「コンセンサス(consensus)」とは「意見の一致」、「合意」といった意味の英語です。
また「意見の一致」や「合意」の意味から発展してその前段階や準備にあたる「合意形成」や「総意」という意味でも使われることがあります。
特にビジネスや政治の場など、
意見を一致させることが容易でない重要な問題を解決するために合意を得る際に、「複数の人の合意や意見の一致」、
もしくは「異なる立場の人の意見が一致すること」の意味で使われています。
このように「コンセンサス」は複数人の合意を意味し、
合意を得る相手が1人の場合はアグリーメント(agreement)という言葉を使います。
また、会議の場では「コンセンサス」は「単なる意見の一致」ではなく、「全会一致」の「合意」を意味しており、反対意見のない明確な状態であることを意味します。他にも「根回し」の意味で使われたりもします。
コンセンサスの必要性

集団での意思決定の場面で「全会一致」の意味であるコンセンサスを得ることは大変重要です。
コンセンサスと逆の「独裁的決定」と「コンセンサス」を比較して、
集団を形成しているメンバーにどういった面でメリットがあるのか見ていきましょう。

メリット1.納得度が高まる
意思決定を行う際に参加者が多数いて、意思決定能力が分散されているにも関わらず、参加者の意見を無視して1人で独裁的に意思決定を行ってしまうと、「反対の立場だったのに」や「詳細を聞いていない」など決定事項に対して納得できないという参加者も出てきます。
それとは逆にコンセンサスを取る場合は、
反対の意見に対しては参加者で話し合い、解決策を出し合って意思決定をします。
また、詳細についても説明し参加者全員が納得した上で意思決定を行うため決定事項に対して「納得度」が高まります。
独裁的に物事を決定するより、参加者全員の合意を取り付ける分、
時間はかかりますが、コンセンサスを得ることは参加者にとってもメリットがあることがわかります。
メリット2.実行度が高まる
決定事項の参加者の「納得度」が高いほど、「実行度」が高まります。
納得できないまま行動に移そうとしても「反対だったのに決まってしまったからやらなければならない」や
「詳細がわからないので何をしなければいけないのかわからない」など、
批判的な意見が出やすく、積極的な行動はできないものです。
しかし、問題点を洗い出し、参加者が内容を把握している事項については実行度が高くなるのは想像できると思います。
参加者全員のコンセンサスを取ることで実行度が高まることが大きなメリットです。
メリット3.当事者意識・関係性が維持される
参加者全員にコンセンサスが取れている場合、
決定事項に対して参加者も意思決定に参加しているため、
「自分が決定したこと」といった当事者意識が維持されます。
逆に独裁的に決定されている場合、「自分が決めたことではないのに」という意識が残り、蚊帳の外に置かれているように感じることもあるかも知れません。
また、参加者全員でコンセンサスを取った場合は全員で意思決定をしているので、もし問題点が出てきても全員で解決していくことに積極的になるので、参加者相互の関係性が維持されます。
独裁的に意思決定をした場合はそれとは逆に少数派や反対派に禍根が残ることが考えられます。
メリット4.意思決定の質が高まる
コンセンサスは意思決定の質を高めることができます。独裁的に意思決定をした場合、多角的に物事を見る機会がないため、気づかなかった問題点や課題が浮き彫りになることが多くあります。しかし、コンセンサスをとった場合はその過程で、参加者全員が納得するまで話し合い、問題点を出し合い、解決策を考えて合意を得て決定するため、「三人寄れば文殊の知恵」の言葉通り、全員のアイディアを出し合うため、より質の高い意思決定ができる確率が高くなるメリットがあります。
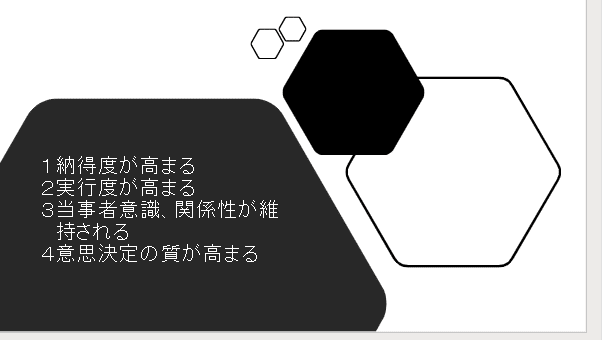
ではどのようにコンセンサスをしていけばよいのか?
合意形成のカギを握る「洗い上げ質問」
会議などでほかのメンバーへ提案内容を無理やり通そうとしたり、
説き伏せようとしたりするから、紛糾したり、見せかけの合意になったりするのです。
説得しようとせずに、進行役が質問だけをしていく方法です。
提案者が提案した後、進行役が繰り出していく質問は、次の4つです。「洗い上げ質問」「掘り下げ質問」「示唆質問」「まとめの質問」です。

洗い上げ質問」とは、
「ただ今の提案に関して、疑問や懸念を遠慮なく出してください」
「ほかに気になる点はありませんか」
「さらに問題になる点はないでしょうか」と、
質問や異論を洗い上げる質問です。
「洗い上げ質問」には、答え方が自由で答える側にストレスがかからない拡大質問のスキルを用います。
このように申し上げると、
「いきなり疑問や懸念を洗い出すなんて、寝た子を起こすことになり、紛糾する」
「そのように異論を自由に出させて収拾がつかなくなったら、どうするつもりか」というようなご意見をいただくことがあります。
そのような時には、「百聞は一見に如かず」というように、
私が何度説明するよりも実際に試していただくことこそ説得力がありますし、「『習うより慣れろ』と言いますから、
これまで意見を押し付けよう、説き伏せようとしてきた人ほど、
効果が高まります。
それは、そうした人が、日頃とは真逆のように、疑問や懸念を洗い上げようとしている姿勢こそが、合意を阻むバリアーを解消し始めているからです。
その意味で、「洗い上げ質問」を実施すること自体が合意形成のカギを握っていると言えます。
洗い上げ質問で大事なことは、疑問や懸念が出されてきても、
「その都度、応酬しない」ということです。
応酬してしまったら、まず、合意形成の難易度が高まります。
普段、様々な企業や団体で見慣れている、収拾のつかない状況になりがちです。


「掘り下げ質問」で絞り込み、「示唆質問」で結論に誘導
「洗い上げ質問」により論点を洗い上げたら、
次は、「掘り下げ質問」により論点を掘り下げていきます。
「5点の懸念点が出されましたが、最も深刻な点はどれですか」
「○○さんは、AとBの問題を指摘されましたが、どちらが緊急度の高い問題でしょうか」というように、最も重大な論点を掘り下げていくのです。
「掘り下げ質問」には答え方が限定されている、答える側にはストレスがかかる限定質問のスキルを用います。
「掘り下げ質問」のフェーズでは、
「洗い上げ質問」から「掘り下げ質問」へ移行するタイミングがとても重要です。
洗い上げに時間をかけ過ぎてしまうと、時間切れになるリスクが増大します。
掘り下げへの移行が早すぎて、洗い上げが不十分だと、見せかけの合意になりがちです。
「掘り下げ質問」により絞り込んだ最も重大な論点について問うのが、「示唆質問」です。「示唆質問」とは、例えば掘り下げた論点が、
「リソースが足りないから実施が難しい」ということでしたら、
「私が交渉して、関連部署の協力を仰いで、リソースが確保できるとすれば、賛成ですか」と、ある前提をおいて、
方向性を示唆し、その方向性へ誘導していく質問です。
「時間を捻出できないので、提案に賛成できない」という点だったとしたら、「みなさんで相談して、実施時期を調整できるという前提であれば、少なくとも反対はなさいませんか」という質問も示唆質問です。
「示唆質問」のフェーズでよくいただく質問に、
「そのような方法では、あらかじめ期待した方向へ誘導しづらいのではないか」
「どのような論点に掘り下げられるか、確証が持てないので、その場しのぎの方法になるのではないか」という意味のものがあります。
経験を重ねるうちに実感すると思いますが、
むしろ、誘導しやすくなりますし、合意のレベルも圧倒的に高まります。

単純なスキルであればあるほど応用が利く
最後の「まとめの質問」は、
結論を共有する際も、質問で行うということです。
「○○の方針を実行することに決定しましたので、従ってください」ではなく、
「○○の方針で、ほかに異論がなければ実行していきたいと思いますが、
さらにご意見があれば遠慮なくおっしゃってください」という質問を繰り出すことです。
これに対し、「そもそも『示唆質問』や『まとめの質問』など生ぬるい。しっかりと方針を打ち出して、それに従えと徹底することこそがリーダーの役割ではないか」という意味のご意見をいただきます。
方針を打ち出して徹底していく、説き伏せ方式で、高いレベルの合意度が実現できていればよいのですが、実態は、そうではないことは、既にお気付きのとおりです。
説き伏せ方式よりも、質問による合意形成の方が、高い合意度を実現できている以上、質問による合意形成を実施してみる価値はあるのではないでしょうか。
一定時間内の会議で合意形成する方法について、会議の手順を解説したり、進行の方法を説明したりしても、
「頭では分かっても実際に再現できない」
「理屈は分かったけれども、行動に移せない」という声をよく聞きます。
しかし、解説や説明は最小限にして、4つの質問を反復演習していくと、実際のビジネスの場面で進行役を担う会議で、合意形成できる確度が格段に高まります。会議で合意形成するためのスキルを、4つのスキルに分解して、反復演習することこそ、実践に役立つ合意形成力を高めるのです。
そして、この4つの質問は、会議での一定時間内の合意形成のみならず、上司と部下のパフォーマンスマネジメントの面談、営業担当と顧客との間の商談、顧客サービス担当と苦情を申し出た顧客の電話など、様々なビジネスシーンで応用できる方法です。それは、身に付けたパーツスキルが単純であればあるほど、応用が利くからです。

その知識や技術が多数の合意形成が必要な場合に大きな助けになります。
ドラッカーも評価していた日本のコンセンサス文化
現代経営学の発明者ピーター・ドラッカーは日本のコンセンサス文化について彼の著作「【エッセンシャル版】マネジメント」の「マネジメント技能」の章で触れています。ドラッカーがどのように日本のコンセンサス文化を評価しているのか、見ていきましょう。
ドラッカーはどのように日本のコンセンサス文化を見ていたか
著書「【エッセンシャル版】マネジメント」のp .150−151でドラッカーは
日本のコンセンサス文化とその後の行動について次のように記載しています。
”日本について見解の一致があるとすれば、それは合意(コンセンサス)によって意志決定を行っているという点であろう。(中略)
意志決定で重要なことは問題を明らかにすることである。
…..この段階でのコンセンサスの形成に努力を惜しまない。
この段階にこそ、意志決定の核心があるとする。
(中略)
関係者全員が意思決定の必要を認めたとき、初めて決定が行われる。
….その後の日本側の行動は迅速である。”
ドラッカーは日本のコンセンサス文化を通して組織全体での問題の共有化の重要性を説いています。
そして、コンセンサスを組織内で形成した後の行動の迅速さも評価しています。コンセンサスを取り、全体の知識を統一することがいかに全体の行動を加速させるか解説しています。
現代に必要なコンセンサスのスキル
本書は1973年に書かれており、当時とは時代の変化の速度が全く違います。結果として、課題にかかわる参加者の数が多くなればなるほど、全体的なコンセンサスをとることに時間を取られてしまい、
時代の変化に取り残されてしまうこともあります。
今の時代、スピード感をもって物事に取り組むためには全員のコンセンサスを取り付ける必要がある問題なのか、一部のコンセンサスで良いのかを見極めることも大切なスキルになります。

コンセンサスは重要だが囚われ過ぎずに
コンセンサスは全体の意思統一を図り、行動を起こす際に組織を構成する参加者が迷わず、行動に移すために重要な手段です。
一方で参加者の数が多ければ多いほどコンセンサスを取り付けるまでに至る時間が膨大になります。
現代は意思決定のスピードについても重要視される時代です。
何か決め事をする際にはコンセンサスを取る必要のある事柄なのか、
そうではなく、一部の人間で決めて良いことなのかを見極め、
必要な場合は段取りよく、全体の総意を集約できる力が求められています。
まとめ
組織は、人がいればいるほど合意形成力が必要です!
自分の意見が通らない。
みんなで決めたことなのにやらない人がいる。
会議がいつもまとまらない。
そんな悩みがある方、ぜひ合意形成力を身に着け誰もがやりたくなる風土をつくってください。
そして合意形成力で一番大事なのは、
当たり前ですが普段の業務姿勢です。
あなたの信頼残高を高める努力をしていますか?
残高がない人の言葉は誰にも響きません!
普段からギバーになり相手に分け与える意識を常に持って仕事をしましょう!






見ていただきありがとうございます。励みになりますので、良ければ”好き”を押していただけたら嬉しいです!
