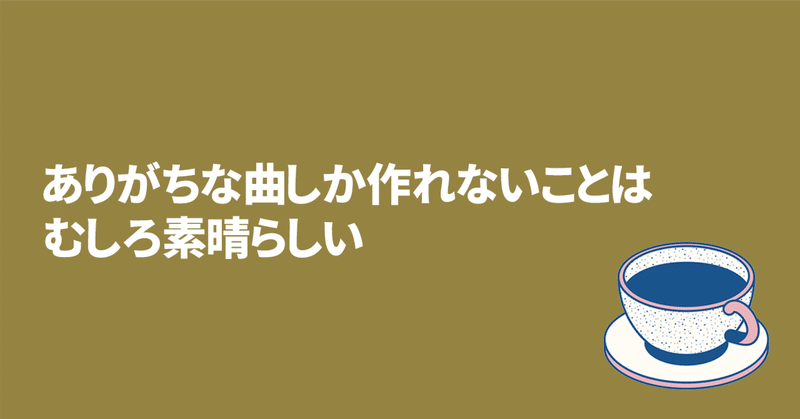
ありがちな曲しか作れないことはむしろ素晴らしい
作曲を始めたばかりの頃に「作る曲がありがちなものになってしまう」と落ち込んでしまうケースはよくありますが、私はこの「ありがちな曲」を作れるという点が、むしろ素晴らしいことだと考えています。
こちらで、そのあたりについて少し触れてみます。
※当記事はこちらのポッドキャストの内容を編集/再構成したものです。
基礎が備わっている、ということ
上記で述べた「ありがちな曲」とは、裏を返すと「音楽の標準的な要素を満たした曲」ともいえます。
そして、その「ありがちな曲」を作れるという状態は、「音楽とはこういうもの」という点が理解できている証拠で、標準的なメロディやそれに似合う標準的なコード進行、曲展開などが把握できていて、それを自分でも生み出せるという事実を意味します。
それは、実は上達を考えるうえで大きな意味を持ちます。むしろ作曲活動の初期にそれが作れているという事実が前途洋々で、その後の未来に期待しかない、と感じられます。
というのも、標準的なものが誰に言われるまでもなく理解できていて、それを自分でも作れるという状態は、「基本が備わっていること」を意味するからです。
すべての応用のもとになるのは基本=基礎で、基礎が身についていてこそ初めてそれを応用できます。普通なものを無理なく作れるからこそ普通ではないところに入り込んでいけて、そこに個性を加えられます。
これを踏まえると、作曲初期に抱える「ありがちな曲しかできない」という悩みがそこまで大問題ではないとわかります。むしろ基礎が備わっていると前向きに捉えてほしいです。
「ありがち」を構造で理解する
そのうえでやるべきことは、
「そのありがちな曲がどのような構造になっているかを理論的に理解する」
という作業です。
超初級音楽理論に相当するものを浅くて構わないためまず把握して、それを元に自分が作った曲を構造によって捉えられると望ましいです。
より具体的には、
スケールの概念
それを踏まえたキーの概念
それをコードに置き換えたダイアトニックコードの概念
などを概要だけでも理解して、自分が作った曲がどれほどその理論の基本に沿った標準的な作りになってるかを把握してみてください。
【メモ】もちろん、そのあたりの知識をすでに身につけていて、その初級音楽理論の範囲の中で曲を作っている延長として「ありがちな曲しか作れない」と悩んでいる場合もあるはずです。その場合には理論的概念を自分が曲にどう反映させているかを、ある程度把握できていることになります。
応用へステップアップする
そのような作業を経て、それらの知識によって自分の曲がいかにそういう意味で標準に沿ったものであるかを理解できたら、その次のステップとしてさらにそこから具体的に
「少し標準に反するもの」
「耳馴染みのないもの」
などを取り入れる意識によって、一部に応用を加えられます。
例えば
メロディに少し個性的なラインを入れてみる
耳馴染みのないコードを取り入れる
などがそれにあたりますが、前述した通り、これはやはり標準的なものが作れていてこそ、だといえます。
そもそもその基礎がないと、「さあ特殊な要素を取り入れよう」と曲をあれこれこねくりまわしても単にぐちゃぐちゃなものができあがるだけです。
標準的なものが作れていてこそ、その親しみやすさを維持しながら少しだけそこからはみ出すようなものが作れるのです。
また、曲を応用するうえでは「何が個性を生むのか」という点についても理解を深めるべきですが、そのためには既存の曲を弾き語ったりして、
「自分が作る標準的な曲と異なるアプローチはなにか(=このかっこいいサウンドを生み出す要素はなに?)」
というような観点でその理由を探ると、自分が取り入れるべき応用の方向性が見えてくるはずです。
*
ここで述べているような手順を繰り返すと、徐々にその「ありがちな曲」が、「ありがちではない曲」に変わっていきます。
その頃には、
「初期にありがちな曲がすんなり作れていた状態は、標準的なものが理解できているという意味で大事だったんだな」
とわかるはずなので、ぜひその状況を前向きにとらえて、無理のない範囲で満足感の高い曲作りを目指してみて下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
