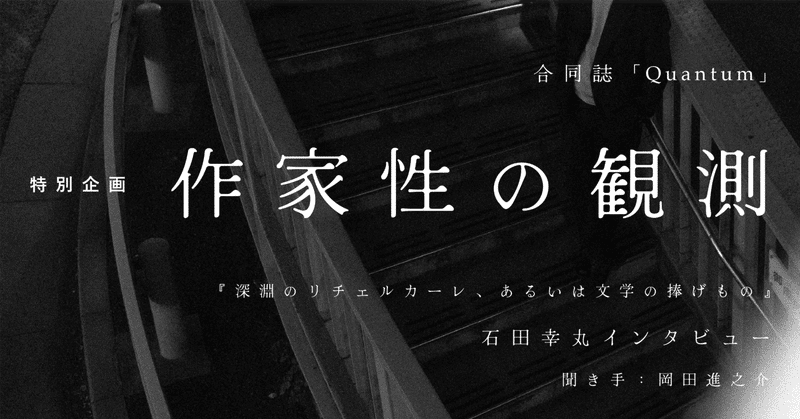
作家性の観測 石田幸丸インタビュー
文学フリマ東京38にて頒布予定の合同誌「Quantum」では、「小説を書くときいったい何が起きているのか」をテーマとして、掲載作品それぞれの書き手にインタビューを行いました。今回は『深淵のリチェルカーレ、あるいは文学の捧げもの』(石田幸丸)についてのインタビューを公開します。
石田幸丸『深淵のリチェルカーレ、あるいは文学の捧げもの』の試し読みはこちら。
インタビュー
執筆方法 最後の30%はInDesignで
――最初に作品の執筆過程を簡単に教えてください。
石田:僕はMacのPagesで基本的には書き始めて、縦書きで作品を実際に書くファイルと、推敲途中の文章をメモしておくようなファイルと2つ作っています。7割ぐらいまでそれ(Pages)で書いて、最終的にはInDesignで実際に印刷される形に合わせて書くというようなスタイルです。
――最初は部分部分で書いていくということ?
石田:多分みんなと同じで、縦書きのPagesにつらつらと小説を書いていきます。それから「ちょっとここのパラグラフを変えたいな」と思ったときに、元の文章を一度メモに移すんです。あとで見直して、「やっぱりもとの方がいいな」と思ったら戻すし、別のところに挿入することもある。メモとその縦書きのファイルと、二つ並べて書くというような感じです。
――そうするとメモに移したものを素材として再利用することがあるとことですね。面白いですね。建築とか積み木というか、パーツを組み合わせて書くみたいな感じなのか。
石田:それは結構あると思います。
――今回の作品も凝ったデザイン・形式になっていると思うんですけど、あれはどうやるんですか?
石田:InDesignですね。
――いつもの執筆でそういうことすることは多いですか?
石田:InDesignで書くようになったのは、同人活動としては前々作ぐらいからなんですが、その直前ぐらいに京極夏彦さんのやり方を知ったんです。京極さんはInDesignで紙面を調整しながら書くと。たとえば文庫版で書く時と、実際にA5の単行本で書く時と、ページあたりの文字の分量が違いますよね。文庫より単行本の方がもっと文字が入る。だから当然改行の位置とかも変わってくるんですけれども、京極さんは全部それを語句のレベルで書き換えて調整なさるんだそうです。判型ごとのベストな形に。
――では彼の作品では文庫版と単行本で中身が微妙に違うということですか?
石田:中身は微妙に違うらしいですね。それを聞いて、やっぱりプロはそこまで徹底するんだと感銘を受けたのが始まりです。それを同人誌の『筆の海』の「Note」という特集の時から自分でも始めてみました。
――ちなみになんでそういうことをするんでしょうね?
石田:やはり視覚的な読みやすさ・読みにくさも左右されるでしょうし、具体例を挙げちゃうとネタバレになるんですけど、ミステリとかエンタメの場合は、ページをめくると、次のページの1行目のここに犯人が書かれているみたいな風にして演出することもできますよね。それが非常に効果的な作品もあると思います。
――すごく読者のことを考えてるんですね。
「書きたいものを書く」と「読みたいものを書く」 AI時代の執筆
――次は着想についてお聞きしたいです。今回の作品のアイデアはどこから出てきて、何故それで書こうとしたんですか?
石田:今回最初に出てきたアイデアは、すごくコンセプチュアルなものでした。それについて説明するためには、ここのところ僕がずっと考えてたことを説明しないといけないかな。
ちょうど去年の春に「Note」の作品を書いてたときからですけど、「これだけ生成AIが出てきた時代に、小説を書くとはどういうことなんだろう」というのを、個人的に考えていました。そのときにポイントになるのが、「読み手の視点」と「書き手の視点」というのを、厳密に区別することなんじゃないかと思ったんです。「読みながら・読んで考える」ことと「書きながら考える・書くことで考える」ことは、違うんじゃないかみたいな感覚と、AIの時代に小説を書くということが、自分の中で繋がったんですよね。
純粋に「小説を読む」ということだけで考えたら、おそらく小説家が人間でなければならない必要は無いんじゃないかと思っていて。著作権の問題とかあるんでしょうけれども、技術的には、過去の作品を大量に学習してある程度の分量を持った面白い“お話”を書くのは、おそらくAIにもできる、あるいは今すぐにできないとしても、そう遠くない将来にはできるだろうと思っています。特に根拠があるわけでもないですけども。
そういう時に「小説家が書くことの意味はなんだろう」みたいなことを考えていくと、やっぱりそれは、人間が小説を書く中で、その書いてる本人が変わるとか、書いてる人間が何かを考えるみたいなところに、AIにはない何かがあるのではないかと思いました。書く人が考える、書くことで考えるということに、何かしらの意味があるんじゃないか。そんなこともあって同人のサークルでも久湊とAIを使った実験をしましたし、自分自身の問題意識としても「書くことで考える」というのを最近のテーマとして何作か書いてきています。
振り返ってみれば、自分がそれまで書いてきた作品の中でも、「書くことで考える」と「読むことで考える」の二つのモードがあったように思えた。自分が読みたいものを書くという時と、書きたいものを書くという時が、微妙に、けどたしかに違う実感があったんです。
――「書くことで考える」というのは、「書きたいことを書く」というのと対応していて、「読みたいことを書く」というのは、「想像した世界を表現する」ことになるということと対応している?
石田:そうですね。「書きたいものを書く・書くことで考える」ということを貫徹できないかなと思っている中で、それは自分の中にあるイメージされた想像の世界を文章化する作業とはおそらく違うと感じていて。自分の中にある何らかの理想的な心象風景を文章化する作業というのは、僕個人の中ではどちらかというと「読みたいものを書く」という作業です。そうではない、もっとなんだかわからないことを書くことで解きほぐしていくという作業が、「書きたいことを書く」、「書くことで考える」ことなんじゃないかというのが前提としてあります。

人間ははたして小説を“想像”できるのか
石田:それが前提1としてあり、前提2としてあるのは、AIが小説を書くということに関して「記号接地問題」という言葉を見知っていて。
――記号接地問題というのは?
石田:AIは学習データから記号の連なりを予測します。例えばXと言ったら次はこういう単語が来ると“予測”することはできる。けれども、そこで起こっていることが何か、つまり記号の連なりが表す意味を理解しているわけではない。そういう意味を理解している状態のことを、「記号が接地している」状態だと言うんだそうです。
――AIの文脈で記号接地というのは、構造主義で言う所のシニフィアンとシニフィエの結びつきの理解みたいなことなのかもしれませんね。
石田:そうですね。そういう理解がAIにはないから「AIが書いてもそこに意味はない」みたいなことを言う人もいるんだろうなと思いつつ、「そもそも人間だからといってどこまで記号接地しているのだろうか?」という感覚もあります。その疑問が今回の物語の構造にもなっている。
「「「○○がこう言った」と××が言った」と△△が言った」と…みたいな階層の入れ子構造になっている状態というのは、三人ぐらいまでだったら、その状況をリアルなものとして想像できる気がするんですけど、一〇〇人だったらどうだろうかと。Aさんがこう言った、とBさんが言った、とCさんが言った…という感じで一〇〇人登場人物が出てきたらどうなるんだろうかと。その最後の一〇〇人目が言ったということまで含めた総体として人間はイメージできるんだろうか、というのが着想のアイデアでした。ほんとは一〇〇人分書くつもりだったんだけど、紙幅とか時間的な問題もあり、二十八人で終わっています。
――いや、すごい量ですけどね。心理学の分野だと、物語を読むというのは頭の中で状況モデルを作り出すことと言われています。普通の物語はそういうことをさせてくれるけど、石田さんの作品はそうではないですね。記号接地問題という言葉でそれがかなり明確になりました。
石田:でも逆に、二十八人の入れ子構造の状況をもし本当に想像できるとしたら、何か特別なことが起こるんじゃないかともちょっと思ったんですよね。それは難しいことなんですけど……もしそれができたら、何かあるんじゃないかなみたいな。
だから「そういう構造の作品は想像できないだろう」という八割程度の予感を持ちつつ、二割くらいは「それが本当にできたとしたら、見え方が変わるだろうか」という期待がありました。
――自分が読んだ感じとしては、もう想像することを諦めさせる物量で押し通す作品なのかなと思っていました。自分の専門の話になるんですけど、美学では「崇高」という概念があります。「美」の心地良さと対になるような、想像力の限界から生じる一種の畏れに似た感性的な経験とされるものです。石田さんの作品は、その点で「崇高」な小説だと私は理解していました。でも石田さんはそれを美しさというか、心地よいものとして体験できる可能性もあるかもしれないとは考えていたんですね。
石田:ちょっとは考えてましたね。
――それは人間にできるんですかね。どうなんでしょう。 自分の脳みそではとてもできなかったんですけど(笑)
石田:逆に言うと二十八人それぞれの話者の一つ一つのエピソードについてみると、中にはナンセンスなものもあるんですけど、小説を書くときに(自分のなかに)出てくる心象風景は大切に書いています。物語性と僕は言っちゃうんですけど、物語性を感じるもの、語りの力があるエピソードが二十八個並べばいいかなとは思ってました。
自由への問い 定家、あるいはマルセル・デュシャン
――でも多分二十八人のうちのエピソードの内の一つがちょっと変わったからといって、石田さん的には別の作品になってしまうわけではないですよね。
石田:おっしゃる通り。
――根本のアイデアはそこではないということですよね。どうしても作品の内容について話したくなってしまうんですけど、もう少しずらした聞き方をしてみます。では石田さんにとって、今回の作品あるいは小説というのは、「どういう機能を持つことを意図している」んでしょうか。普通は言ってしまえば娯楽というのが一番大きいわけですよね。期待を満たしてくれるとか、快楽とか。でも、今聞いた話だとそうではないということになるんですけど。そこを説明していただけますか?
石田:なるほど。あんまり予想していなかった質問なので、ちょっとまとまらないかもしれないんですが……。まずファジーな言い方から始めますけど、自分の知らないところに連れて行ってくれるみたいなのがあると思うんです。でもそれは考えてみると不思議ですね、それは想像するんだけど、自分が知らないことを想像できるんだろうかという……。
――すみません、ちょっと横やりを入れてしまうと、その「知らないところに連れて行ってくれる」というのは、多分他の多くの方も言うと思うんですね。それが通常意味しているのは、 現実のようなリアリティを持った現実ではない世界を構築して、それを想像してもらうことによって、そこに読者を「連れて行く」わけじゃないですか。石田さんが言っているのはそういうことですか?
石田:いや、そうではない。もちろんそういう部分もあります。単純にファンタジーとして作品を享受するということは僕自身ありますし、お話の中にもそういう部分がなくはない。自分が書く小説の中にもそういうものが無くはないとは思うんですけど、知らないところに連れて行ってくれるというのは、そういうことだけではなくて……。なんだろう、物事の見え方が変わるというか……。例えば今回自分の書いた作品を読むことで、小説を書くということ、あるいはAIが小説を書くということについての見方が変わるかもしれない、とか。
――そういうレベルのことなんですね。単にその目の前のコップの見え方が変わるとかいうレベルではなくて、もう少し抽象的な事柄に対してということですかね。「見え方」というのは、「意見」とはちょっと違いますか?
石田:変わるのは意見の場合もあるかもしれないけど、もっと広いかもしれない。意見ほど明晰ではないけど、 何かが変わるということもあるかもしれない。例えば短歌だとそういうことがわかりやすい気がするんですよね。短歌だと初谷むいさん、あるいは藤原定家が好きなんです。 定家の作品の中に「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ」というすごく有名な歌があります。でも僕にとってそれで「浦の苫屋の秋の夕暮れ」の(網膜的な)見え方が変わるわけでもないし、あるいは「もののあはれとはこういうものである」みたいな問題設定に対して何かしらの意見が変わるわけでもない。でも今それを口ずさんだ前と後では、何かがやっぱり変わってる気がするんですよね。それはもっとふわふわっとした抽象的な、自分のあり方みたいなものが。だからもっと受動的なものが変わるのかもしれないですね。意見のような明確な対象に向けた能動的な自分の働きが変わるのではなくて、そういうものも含めたいろんなものに対する自分の受け止め方が変わる。
石田:あ、でも一番、十代の頃からすごく印象に残っているのは、マルセル・デュシャンの《泉》なんですよね。
サインつきの男性用小便器をどんと置いて、これが美術品ですよという。そこには芸術のあり方とか特権的な“作家”みたいなものを解体するという文脈もあるのかもしれないけれど、もっとこう「そういう考え方をすること『も』できるんだね」みたいな所で変わる気がするんですよね。ちょっと自由になるというか。
――デュシャンの話はしようと思っていたので、まさか石田さんの方から出してくれるとは思わなかったです。《泉》はすごく有名な作品ですけど、美学ではこの作品に関してはもう本当にずっと同じ話が繰り返されていて。つまり普通「芸術作品というのは本物見てこそでしょ」という話があるわけですよね。ピカソの作品は、そのオリジナルを見るとのが大事という。だけどデュシャンの『泉』は「コンセプチュアルアート」と言われるように、 コンセプトについて話を聞くだけで良いのでは?となるわけです。石田さんの作品がそれを目指すのだとしたら、じゃあ石田さんの作品を読むことの意味というのは何だろうとは考えたりしますか?
石田:面白いですね。そういう意味では、今回の作品は最終的に、じゃあその二十八人の入れ子構造の語りを想像することができるのか、ということかもしれません。自分でも蛇足かもしれないと思いながら、最後に“まとめ”をつけてるんですよね。これがどういう話なのかを明示的に書かないと、読者がちょっとイメージできないかなと。読者がみんながみんなメモを作りながら読んでくれるわけじゃないですから。自分でこの“まとめ”をつけてみたのは、 果たして実際この作品は経験できますか?想像できますか?という問いは投げかけたかったのかもしれない。そういう意味では、その問いが経験されることは必要なのかもしれない。
――なるほど。今「問い」という言葉が出て、かなり明確になった感じがします。問いを問いとして理解するためには、やっぱり作品を読まないといけないというのは確かにあるかもしれないですね。
純文学とエンタメの区別に意味はない
――最後にお聞きしたいのは、作品のジャンルみたいなことは考えたりしますか?自分の作品が所属している、 あるいは所属していないジャンルは何かということは。
石田:考えないと言えば嘘になるんですが、 ただエンターテイメントとしての小説も純文学もどちらも好きなので。僕の中で純文学というのは エンターテインメントだけじゃないものを許容するジャンルだとは思っています。エンターテインメントとしての文芸といわゆる純文学は違うとして、自分は少なくとも今回これに関しては純文学の作品を書いているとも思っています。ただ、その区分というのは便宜的に採用しただけで、そこまで意味はないかもしれない。デュシャンでもエンターテイメント的な面白さはあると思うから。知的にエンターテインされるかなと思うので、ジャンルを意識していないというと嘘になるけれども、その意識がものすごく重要なものかというとそうでもないかもしれないですね。
――今の話は少し面白くて、最初の方に言っていた「書くことで考える」 と「読むことで考える」というのは、それに対応しているんでしょうか。読むことで考える、あるいは読みたいことを書くというのはエンタメ的な態度と言えますね。
石田:そうですね、あくまで自分の創作上の区別ですが。
――そうすると「書くことで考える」というのは何なんでしょう。それを「純文学」という概念で説明されても、じゃあ純文学って何?となってしまいます。
石田:いや、僕も自分にとって「書くことで考える」とは何なんだろうというのが今のテーマなんですよね。だから逆に「芸術が作家の表現である」という考え方以外にはどういう考え方があるんだろうというのは、 僕も「書くことで考える」を説明するために勉強したいところなんです。ただ感覚としては何か違う気がしている。自分の実践における実感としては何かが違っている。ただ、まだそれを分析的に語ることができるほどのボキャブラリーを僕は持てていないです。
(聴き手:岡田進之介)
石田幸丸 ISHIDA Yukimaru
一九九〇年九月三〇日生まれ。三重県津市出身。早稲田大学政治経済学部卒業、東京大学大学院総合文化研究科(比較文学比較文化コース)修士課程修了。
二〇一六年より「文藝同人 習作派」として文学フリマに参加。
主な作品に「賓は運命のごとく扉を叩き」(2023)、「天使学」(2022)、「プロメモーリア、塵と炎について」(2021)、「夢の纜」(2019)。
その他のインタビュー
鈴木三子
那智
原石かんな
久湊有起
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
