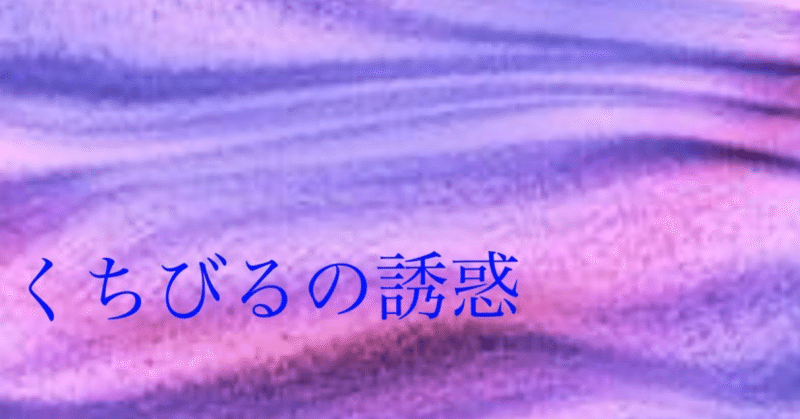
くちびるの誘惑 全文(54677文字)
1話
カクテルグラスの泡が弾けて虚飾の祝賀会が始まった。ここに集まる人々は各界を代表する著名人、権力者、大手企業の役員達が主である。
新人作家の登竜門であるA賞が発表されるや否や、各メディアでその詳細が一部始終紹介され、いっときその受賞者は時代の寵児となる。それほどA賞の歴史と格式は高く偉大なものである。これまでに多くの作家を輩出し、現代の文学者達の多くが歴代の受賞者としてそこに名を連ねる。A賞作家としての肩書は作家としての箔をつけ、ある意味それは一つのブランドとも言える。そのため、それを目指して日夜精進し格闘する小説書きはプロアマを問わず多数存在する。
一方で一時的に脚光を浴びたもののその後の作家活動が順調に進まず消えてしまった者達も実は一定数に上る。勿論、受賞しただけでも大成功の内ではあるのだが、もてはやされた瞬間からの落差は非常に大きく、現在はアルファ出版の編集者としてこの祝賀会に出席している古賀祐二こがゆうじも過去にはその当事者としてステージに立った経験がある。ただし、彼の場合はA賞ではなく、同時発表されるN賞だったわけだが、その受賞価値は決して引けを取らない。
一般的にA賞は文学作品、N賞は広くエンターテイメント作品が選ばれるという規定だと言われるが、古賀祐二が執筆した『永遠の微熱』は本人的には純文学作品のつもりで書いた。だからと言って何もN賞を不満に思ったことなどはないのだが、それ以降、何故か読者を満足させられる作品を上梓することが出来なかった。
古賀祐二が作家活動を諦めてアルファ出版に就職したのはおよそ十年前のことだ。今になってみると名刺を差し出したところで彼の名前に覚えがある者は数少ない。いたとしたらそれなりの年配の人かマニアックな人物に限定される。毎年行われるこの受賞祝賀会を虚飾のパーティーだと心の内で揶揄してしまうのもかつてはにこやかな笑顔で握手を交わした著名人や権力者達がほぼ古賀のことを記憶していないことに落胆せずにはいられなかったからだ。
うっかりしていると給仕係に間違われ、飲み干した空のカクテルグラスを手渡されるハメになる。
そんなしらけ切った気分のまま古賀は壇上で上気した顔色で受賞スピーチをする若い作家をぼんやりと眺めていた。もうすでに何度かテレビや週刊誌で見覚えのある爽やか系イケメンである。逢阪遥人あいさかはるとという名前も何度か聞いていた。受賞作品は読んでいない。古賀は現在は主にミステリー作家を中心に編集者としての仕事をしている。文学とは少し縁遠くなってしまった。
スピーチを終えた若い作家は会場に詰め掛けた多くの人達と和かに挨拶をして周り、期待と羨望に満ち溢れたライトの中で笑顔を振り撒いている。
やがてそれは古賀のいるテーブルにも近付いて来た。向こうは古賀を知る由もない。ありきたりの挨拶で、本日はどうもとか、忙しい中わざわざとか、顔面に張り付けたままの微笑で、軽くお辞儀をした。古賀も飲みかけのグラスをテーブルに置いて社交辞令を述べた後、名刺を差し出し身分を示し、軽く握手を交わした。逢阪が思いの外、冷たい手をしていたのが古賀には印象的であった。
ふと見ると逢阪の背後に寄り添うようにして、艶やかなショッキングピンクのパーティドレスに身を包んだ女性が目についた。ブロンドに染めた髪を肩の辺りでカールさせ、いくつかのアクセサリー類を身に纏い、大きな瞳の睫毛は長く頬の辺りにはその陰影が浮かび小悪魔的に見える。鼻筋は定規で計ったかのように真っ直ぐに通り鼻腔は小さめ。その下に形の良い唇に紅いルージュとグロスが塗られ綺麗な歯並びを覗かせていた。
古賀はその女性が出版社の人間でないことをすぐに察した。担当編集者ならこういう場合は大抵スーツ姿で来場するものなのだ。つまりその女性は逢阪夫人であるか、または婚約者、もしくは恋人であるかと推測される。だが、改めてここでその関係性を問う訳にも行かず、黙って会釈してその場をやり過ごした。
それにしてもと古賀は思う。逢阪遥人はイケメンには違いないが、あまりにも爽やかな好青年な印象を与える。それに引き換え、あの女性は艶やか過ぎて、二人が並んだ姿は何だか釣り合いが取れない妙な気分がした。
しかし、そんなことは相手に言わせれば大きなお世話で、普段の逢阪とその女性を知る訳でもないので、そういう些細な違和感はその場限りのもので直ぐに忘れてしまう物事のはずである。その時はそう思った。
それが後に、古賀を悩ます大きな事柄に発展するとは、その時、思いもしなかった。
その女性、後に名を知ることになるのだが、十和田彩花とわだあやかとの最初の出会いであった。
そして、その時、祝賀会場の片隅で栄光のライトの下を歩く、二人の姿をじっと見つめていたもう一人の人物がいたことに古賀祐二はまるで気が付いていなかった。
2話
杉下治郎すぎしたじろうは新宿駅西口から歩いて十分程の雑多なテナントビルにあるバー『BUZZ』のカウンター席でくだをまいていた。この店、この場所は治郎の指定席であり、週に三、四日はここで浴びるように酒を呑んでいる。
大体が一人でぶらりとやって来ては決して陽気とは言えない酒を店の営業時間がラストになるまで居座り続ける。あまり人付き合いの得意ではない彼は孤独を愛してる訳でもないが、大勢で賑やかに過ごすことを嫌った。カウンター内にいる熟年のマスターもそれを判っていて、治郎から話しかけられない限りそっとしておくのが通常であった。
しかし、その夜の彼はいつもと少し様子が違っていた。浴びる程酒を呑むのはいつものことだが、酒に呑まれることはない。静かに難しい顔をして何か考え事をしながらカランコロンと水割りのグラスを傾ける、そんな男がこの日は何度も大きなため息をついては言葉にならない呻き声を出し、何やら口の中でぶつぶつ呟いては時折片手を伸ばしカウンターに顔を伏せたりしている。
元々素行もそんなに良くなく、長く伸ばした総髪を頭の後ろでまとめて束ね、口の周りはうっすらと無精髭を生やしている。服装にも割りかし無頓着で、そんなに綺麗とも言えないデニムの上下やパーカーなどをよく身に纏っている。それが珍しく今夜はネクタイこそしていないものの一応ジャケット姿でしゃんとすればそこそこ人前に出ても上等な格好をしていた。酔ってさえいなければ割りかし精悍な顔立ちでなかなかのいい男である。
恰幅も良く温和なマスターは治郎がどういう職業をしている人かは知らない。ここでは仕事の話やプライベートに踏み込んだ会話をしないことをモットーとしている。だが、その日の杉下治郎の様子が甚だしく尋常ではなかったため、水割りをお代わりに差し出したついでに、それとはなしに、声をかけてみた。
「どうかしましたか? 今夜はやけにペースが早いですよ」
杉下は一瞬首を傾げたが、ややあってこんなことを言い出した。
「世の中はよぉ、おかしかないか? 金のある奴や、名声を得た者だけがチヤホヤされやがって」
聞き取りにくい声ではあったが、マスターは穏やかにまあまあと相槌を打つように微笑んだ。察するに何かに嫉妬したか、なかなか上手く行かない自分自身に腹を立てているようだ。仕方がない、どんな商売でも上手く行く者は一握りだ。ここ新宿二丁目の裏通りはそんなうらぶれた男達が鬱憤を晴らすための場所だ。あまり深入りはしないでおこう、そう嗜んだマスターはそっと男から距離を取ろうと定位置に下がろうとした。それを追いかけるように再び男の声が聞こえた。
「あのオンナは、ひと月前までオレのオンナだったんだ。それが、あんな腑抜けた野郎と……」
何か複雑な事情があるようだ。さらに愚痴めいた杉下の呟きはグタグタと続く。
「奴の短編、読んだけどよぉ、全く、くだらねぇ、あれでよく、あんな……、どう考えても才能はオレの方が上だぜ、あいつは今がピークで、これから先は、落ち目になるのが、見えてるぜ」
呟きは途切れ途切れの寝言のように留まることなく続いて、嘲笑なのか自虐なのか判別が付かないクックという笑い声が漏れて薄暗い店内にさざなみを打った。
やれやれ、マスターは内心、愛想を尽かした。今夜は長くなりそうだ。
翌日、杉下治郎が目覚めたのはもうとっくに昼の十二時を回った頃だった。昨夜はA賞祝賀会に顔を出した後、新宿に向かい『BUZZ』でしこたま酒を煽った。さて、どうやって家に帰り着いたものだろう? 記憶は途絶えていた。今は見慣れた自室のベッド兼ソファの上に横たわっている。
書き物机の上には原稿用紙が数枚、書きかけの状態で散らかっている。
近頃大抵の作家はパソコンを使って小説などの執筆をするものだが、杉下は原稿用紙に手書きしている。
それは以前パソコンで執筆していたかなりの量の文章を手違いで一瞬にして消去してしまった、そんな過去があるからだ。一度消してしまった文章をもう一度再現することは殆ど不可能であり、また一から書き直すにも気力体力を共に失い、暫くは呆然として何も手に付かない状況になる。
その件に関してはなんとか持ち直し、原稿の締切等、重要な問題は乗り切ったのだが、それからはパソコンを使わず、手書きの原稿用紙を利用しているのだ。
それはともかく、スマホは無事に手元にあるのかと気になって辺りを見回してみると、ソファの枕元の下に転がっているのが見えた。
良かった。これを紛失してしまうとかなり厄介なことになる。パソコンでの執筆は手書きに変更したけれど、スマホだけは他に代わるものが見当たらない。
手に取って画面を確認してみると、担当の編集者からの着信が何件か入っていた。
おかしいな。締切はまだ少し先のはずだが、小首を傾げながらリダイヤルしようとして、何かが閃くのをを感じて、待てよと手を止めた。
それから数分後、杉下はスマホのリダイヤルボタンを押して、目的の相手を呼び出した。
「あ、コガさん?」
相手の返事を聞いて、杉下はニヤリと微笑んだ。
3話
アルファ出版から刊行している週刊誌『週刊アルファ』は発刊当初こそ政財界をネタにした社説等が主流であったが、ここ数年、芸能スキャンダルや政治家の汚職、大企業からの献金などの暴露記事を中心にその売上総数を猛烈な勢いで増やしていた。
そのターゲットは各界に及び、身に覚えのある後ろ暗い有名人達はその攻撃を『アルファ砲』などと称し戦々恐々としていた。
さて、その日の週刊アルファでは次の様な見出しが新聞広告や電車の中吊りなどでセンセーショナルな話題を世間の人々に提供していた。
『新進気鋭のA賞作家の婚約者・十和田彩花(仮名29歳)は男を渡り歩く稀代の悪女だった!』さらには、『政界の黒幕との関係も浮上!』とまで。
それらがA賞作家・逢阪遥人に寄り添う十和田彩花(一応目隠しの黒線あり)の全身像が写り込む画像と共に衆目に晒されていた。
ここでその内容の主要部分をかいつまんでご紹介すると、彩花が逢阪と婚約する以前に交際していたとされる歴代の著名人の氏名が時系列順に一覧されている。そこには大物芸能人、某大手事務所の現役アイドル、若手実力派の野球選手、イケメンで超が付く程の人気サッカー選手等、約十名程が列記されていた。しかもその半数は不倫であり、数枚の証拠写真、あるいは相手とのラインのやりとりがそのまま写し取られて掲載されている。
これらは各界に激震を起こさせ、その日のワイドショーは日がな一日その話題について取り上げ、驚きを隠せない司会者やコメンテーター達が口角泡を飛ばせて激論を繰り返した。各メディアその他の報道陣達は一斉に関係者のコメントを取ろうと各社事務所前の道路に張り込み、出社する社員・関係者に盛んにマイクを突き出した。
勿論、どこの芸能事務所、球団等も寝耳に水のようなその大津波に対応しきれず、全てノーコメントで押し切っていた。
さらに一番大きな暴露記事となったのが、政界の黒幕との関係についての記事であった。その黒幕とは元財務大臣を歴任した蔵原文三くらはらぶんぞうだと推測された。
何故ならば十和田彩花が二十代半ばから暮らす高輪にあるタワーマンションの部屋の名義人は偽名であることが判明し、それを辿って行くとある人物に行きつく、それは蔵原元財務大臣の長年秘書を務めた男になる。秘書の男が自らタワーマンションのオーナーになれるとも考えられず、それはおそらく元大臣の差し金によるものであろうと推察された。当週刊アルファの紙面ではK元財務大臣と記すのみだが、それは蔵原文三以外に該当する者がいないのである。
当然、マスコミ達も蔵原元大臣を直撃した。しかし、老齢なる連戦練磨の強者は柳に風の如く、我関せずとばかり涼しい顔で沈黙を守り通した。押し寄せる報道陣達をものともせず闊歩する蔵原であったが、礼儀を知らぬ若いリポーターが目の前を遮るように身を乗り出すと、突如「道を空けなさい!」と恫喝してギロリと相手を睨み付け周囲を黙らせた。
蔵原に関してこの件は憶測の域を出ることがなく、彩花との証拠めいた繋がりを示すものは何一つ見つけられずにいた。また、当該の秘書もすでに高齢であり、現在は重病を患い入院中のため、インタビューひとつ出来ずにいた。
尚、蔵原元大臣には大企業からの献金疑惑やら某宗教団体が後援会に存在するなどといった真偽の程が定かでない疑惑めいた物事が渦巻いており、ネット上では先の首相暗殺事件でも裏で糸を引いていたのではないかとの戯言が飛び交う始末である。しかし、これらは全て証拠なきもの、アルファ出版側でも、下手に手を出せば命取りになり兼ねない危険性も充分にあり、決定的な証拠となるものを握るまでは静観する方針を決めていた。
さてそんな週刊アルファを手に取って一読した十和田彩花はフンとそっぽを向いて部屋の隅にその雑誌を投げつけた。何しろ自身の居住するマンションの前には人だかりが出来てしまい。迂闊に外出もできない状態になっていた。その週刊誌に関しては近くの書店に電話して朝早く持って来させたのだ。
婚約者の逢阪遥人とは午前中に二度ほど直電で会話をした。逢阪の方でも相当なマスコミが軒先にたむろしているらしく、あたふたしていた。それでも彩花は謝罪の言葉ひとつ投げかける訳でもなく、「そう、三日もすればいなくなるでしょ」と嘯うそぶいた。
ファッションデザイナーとしての仕事を持つ彩花は現在フリーでいくつかのアパレル企業と契約している。騒動の間は暫く出社出来そうにないため、クライアント先とはリモートで打ち合わせ等を行うことに決めた。ショッピングや日用品の買い出しなどはネットで間に合わせられたし、買い置きしてストックしているものが数多くあったので一週間や二週間くらいは生活に支障が出ることもないだろうと見繕った。
残念に思うのは夜間にどこかのパブやらバーなどに出掛けられないことだ。一日中自室に閉じこもっているのもかなりストレスのたまるものだ。それでなくても彩花は退屈を一番嫌い、常に刺激を浴びていないとイライラしてしまうタチなのだ。
それでも世間では連日十和田彩花を魔性の女呼ばわりしてネットやテレビ等を騒がせているのは、ある意味心地良かった。有る事無い事勝手な物言いをされるのは少々気に食わなかったが、今のこの状況を心のどこかで楽しんでいるのも事実である。
しかし、おそらく出版社に過去の恋愛沙汰を暴露したのはおそらくあの男であろうと当たりを付けていた。そう思うと許せない。いつかきっと近いうちにそれ相当の反撃を喰らわせてやろうと内心思うのであった。
暴露記事の発売から四日が経った。都内では別の大きな事件やニュースなどが日々当然の如く湧き上がっていたので、そろそろ彩花の住むマンションの前にもマスコミ関連の人影は以前のそれとは格段に少なくなった。
そんな時、彩花はふと思い立ち、バッグの中から一枚の紙切れを取り出した。それは逢阪のA賞受賞の祝賀会に出席した時に逢阪が受け取った出版社の社員の名刺である。あの時、彩花は逢阪からその名刺をさり気なく受け取り自分のバッグに仕舞い込んでおいたのだ。
あれから数日経ったが、名刺に書かれた名前を黙読すると、脳内にぼんやりとその時の人物の顔が思い浮かんで来る。
彩花はスマホを手に持つと名刺に書かれた携帯電話の番号をタッチした。
4話
今回の騒動で一番ダメージを受けたのが小説家・逢阪遥人だった。せっかく名誉あるA賞を受賞し、書籍も売れ始め、そのうえ十和田彩花という超絶美人との婚約を発表した。まさに人生の絶頂期を迎えたはずであった。
それが、まさかのアルファ砲による彩花の過去に起こったスキャンダラスな恋愛遍歴の暴露。しかもその半数は不倫であり、相手は各界の大物ばかり。さらに疑惑の域を超えないとは言え、政界の黒幕との怪しげな関係。
それらについて全く知らされていなかった逢阪にとってはまさに青天の霹靂、いきなり降ってわいた災難である。アルファ砲の爆撃をまともに喰らって脳震盪を起こしかねない程のショックを受けた。
そもそも逢阪本人は見た目通りの爽やかなイケメンであり、裏も表もない。性格も大人しく、これまでに人間関係のトラブルや問題事など起こしたことも無い。ただひたすら作家になることだけを目指して努力を重ねて生きてきた。
それがようやく花を開かせ、昨年とある新人賞に選ばれ文壇デビューを果たし、今回、念願のA賞受賞を果たしたのだ。まさに夢のような出来事に身も心も浮かれつつあった。
十和田彩花との出会いは数ヶ月ほど前、新刊の書籍出版に伴い出版社が催した宴席でのことだった。どういう縁があり彩花がその席に顔を見せたのかは知らなかったが、出会った瞬間、その華やかさ、魅力、色気に圧倒されて、宴席の間中片時も彩花から目が離せなかった。
特に黒目がちの大きな瞳、てらてらと濡れたように艶かしい唇、豊満なバスト、くびれたウエスト、肉感豊かなヒップライン。逢阪の人生で初めて女という異性を意識した瞬間であった。
それからのことは何がどうなったのかさえはっきりと記憶されていないのだが、夢の中にも現実にも逢阪の目の前にたびたび彩花が登場し、A賞の受賞が発表された夜には何だかんだの後、酔っ払った勢いでホテルに転がり込んだ。ふかふかのベッドの中で生まれたままの姿の彩花を抱きしめ全身にキスの雨を降らせた。次の日の朝、逢阪は彩花にプロポーズした。そして彩花は満面に微笑を浮かべて頷いたのだ。
A賞の受賞祝賀会では正式に婚約者としてドレスアップした彩花を同伴させ、会場に詰めかけた大勢の人達の前を悠々と歩いて回った。まさにこの世の春、人生の春を満喫していた。天にも昇る気分、ふわふわした夢の中を浮遊した気分で時の流れに身を任せた。
それがたった数日でこの状態だ。逢阪にとっては天国から地獄に突き落とされた気分でしかなかった。人を羨む程の美貌を持った婚約者の過去が暴かれ、怪しげな疑惑が満ち溢れ、さらに調査を進めれば第二弾、第三弾のアルファ砲もあり得るとテレビのコメンテーターはしたり顔で言い放った。
逢阪の住むマンションは彩花のタワマンと比べれば数段に小さな三階建ての賃貸マンションである。玄関前の道路もそう広くない。それでも連日何人かの報道陣やカメラマン達がうろつき逢阪の登場を待ち構えているのだった。
鳴り続けのインターフォンを無視し、逢阪は室内に閉じこもって善後策を練るのに苦心していた。何度か編集者とも電話連絡を取った。ところが彼の書籍を出版しているK社では、むしろこの騒動を歓迎していることに驚かされた。
何故ですか? 出版社として週刊アルファに抗議していただけないのですかと、逢阪はそう言って担当者に食い下がった。だが、出版社の方では暴露されたのが作家本人ではなくその婚約者、幸いなことにまだ入籍前である。十和田彩花が世間でどう言われようが、社には関係なくむしろ話題に上がればその分逢阪の小説が売れると判断したようだ。思わぬ宣伝効果にほくそ笑んでいるのが見てとれて、普段おっとりしている逢阪も流石に頭に血が逆流し、人の気も知らないで!と受話器を叩きつけるのが精一杯だった。
彩花本人とも二度ほど電話で会話した。それが彩花自身も、放っておけば? と意に介さない様子でマスコミの騒動も三日も経てば収まるからと呑気なものだ。イライラが止まらない逢阪はついに彩花にあの報道は事実なのかと問い詰めてみた。彼女の返答次第ではこの先、考えを改め直す必要があるかもしれないのだ。だが、彩花の返答はそれこそ雲を掴むようにあやふやなもので、全く要領を得ない。蔵原元大臣との関係にしてものらりくらりと逢阪の追及を余裕で躱してしまうのだった。
逢阪は疲れ果て、ベッドに倒れ込んだ。元々彩花には逢阪が踏み込めずにいる謎めいた部分が沢山あった。あれだけの美貌の持ち主だ、これまでに何かしらそれなりの恋愛沙汰の一つや二つはあっただろうとは思っていた。むしろ何も無い方が不自然だ。そうそれが当然だろうと思うのだが、まさか、不倫、それも芸能界の大御所やアイドル、スポーツ選手との交際。一体どこでどういう繋がりがあってそういう関係に発展したのだろうか、そう言えばA賞を取る以前、候補作としてノミネートされたあたりから彩花はK社の宴席に姿を見せ始めた。それは誰の紹介または招待を受けてのことだったのだろう? それも機会があれば訊いてみたいところだ。
さて、自宅に軟禁状態の今、幸いなことに作家という職業にとってはさほど不便はない。サラリーマンのように朝早く起きて定刻に出社する必要もなく、次の新作の打ち合わせ等は当分の間、電話連絡で済ますことができる。せっかく婚約者が出来たのに暫く会えそうもないことは残念であるが、事態が事態だけに仕方がない。テレビやネットも今はあまり見たくない。自室でやけに長く感じる時間だけを持て余すのみだ。読書や映画鑑賞も集中出来ず、落ち着いて観られない。こんな時こそ、次なる新作に向けて構想を練り執筆作業に打ち込めばいいのだが、書斎に籠りパソコンの画面に向かって執筆しようとしてもぽっかり穴が空いたみたいな状態で全く何の文章もストーリーも浮かんで来ない。
どうしても気がつくとアルファ砲が伝えていた彩花のスキャンダラスな過去が次から次へと文字やら映像なりが脳内を悪夢のように右から左へ、上から下へと、流れて行くばかり、その孤独な恐怖に一人耐えきれなくなり、再び枕で頭を抑えてベッドに倒れ込む。そんなことを繰り返してしまうのだ。そして何より政界の黒幕・蔵原元大臣の存在が逢阪にとっては不気味に思われて仕方がないのだ。
5話
古賀祐二の携帯に着信があったのは深夜二時を過ぎた頃だった。週末たまたまちょっとした書き物を遅くまでしていたので、それに気がついたのだが、普段ならとっくに寝ている時間帯だ。非通知設定と表示されたその画面を見入って、何かしらの胸騒ぎを覚え、何度目かのコールの後、吸い込まれるように通話ボタンを押してしまった。
相手の声を聴いてそれが誰であるか、すぐに古賀は察した。騒動の渦中の人物十和田彩花である。彩花とは逢阪遥人のA賞祝賀会の時に軽く挨拶を交わした程度で会話などしていない。それなのにその声から、あるいは息遣いでそれが彩花であると確信したのは、説明のしようもない直感としか言いようがない。
おそらく逢阪に渡した名刺を見て彩花は古賀の携帯に連絡を入れたのであろう。それ以外二人に接点はない。
彩花は「古賀さんですね」と一言尋ねたきり、なかなか次の言葉を発しない。遠くで夜の都市高速を走る車の音だけが低く響いていた。
「折言ってお話したいことがあります。出来れば人目のつかない場所で、二人だけで」
そういう彩花の声は細いながらも有無を言わさぬ何かしら脅迫めいた響きが込められているように感じて古賀の背筋を凍らせた。
それから数分の後、古賀は待ち合わせのための場所と時間を指定して通話終了ボタンを押した。実際に通話に要した時間はものの五分とかだろう。だがそれは妙に密度の濃い研ぎ澄まされた時間のように思えた。
彩花の声に背筋を凍らせたと表現したが、怖ろしいと感じた訳ではない。しいて言うなら何かを試されているというのか、心の内を読み取られ白か黒かの判断の瀬戸際に追い込まれた、そんな切迫感に包まれた気分だっだ。このことを予感していた訳ではないが、あの日祝賀会のパーティー会場で彩花の姿を見かけて以来、不思議な運命が自分に去来するのではないか、そんな思いが脳裏を過っていたことは確かである。
しかしながら彩花が古賀に二人きりで会いたいと言って来た本心はまるで見えなかった。確かに古賀は彩花と逢阪を追い詰める暴露記事を出したアルファ出版の編集者である。週刊アルファは古賀の担当ではないにしても、その部署の面々とは顔見知りであり、特にそちらの責任者をしている奥藤とは同期入社として親しい間柄だ。
十和田彩花が古賀に接近を試みるとなると、そのこと以外に理由が考えられない。だが、古賀に何が出来よう? いくら同期とは言え他部署、しかも社内でトップの発行部数を有する週刊アルファのチームに古賀が口出しすることは出来ない。あるいは何かを調べ出し情報を横流しするなどということは絶対にあり得ない。確かに古賀は週刊アルファが取り上げる芸能スキャンダルや政界の裏側を暴露するゴシップ記事にはあまり良い印象を持っていない。だからと言ってそれを否定する気持ちもない。出版業界も生き残りをかけて必死に闘っているのだ。会社を敵に回す気持ちは毛頭ない。自分は文学畑の出身で今は推理小説の編集者として勤務している、あくまで一会社員に過ぎないのである。
その夜、古賀はなかなか寝つかれずにウイスキーのロックを傾けながらあれこれ思考を巡らした。
その度に十和田彩花の妖艶な微笑、あの瞳、濡れた唇が脳裏に甦って浮かんでは消えて行くのだった。
その日は案外早く訪れた。古賀が十和田彩花に待ち合わせとして指定した場所は都内某所の閑散とした小さな駅前からひとつ裏通りに入ったところにあるコインパーキングだった。時間は夜の十時過ぎ。
ほぼ定刻通りに黒のセダンが現れ彩花が古賀に合図した。助手席に乗り込んだ彼は女の横顔をまじまじと見つめた。ロングの髪を後ろに束ねて夜だというのにサングラスをしている。唇は相変わらず艶やかに紅色に夜のネオンを反射させていた。洋服は地味目の黒っぽいパンツルックのようだったが、手足が長く、スタイルの良さが際立って見えた。
思いの外、彩花の運転は滑らかで的確だった。スピードを上げるべきところでは上げ、緩める箇所では着実に減速させる、流れるようなハンドル裁きで自由自在に車を操った。
「どこへ行くんだい?」
沈黙に耐え切れず古賀は訊ねた。
「少し遠くの方にあるホテルです。ラブホテルではありませんので、ご安心ください」
そう言って彩花は少し微笑んだ。
まさか、そんなつもりは……、古賀は言葉を詰まらせた。変なことは考えてはいないものの、もしかして、この先絶対に何も無いとも言い切れない。しかし、古賀の方から何かを仕掛けるつもりは一ミリも無かった。それよりも何故彩花が自分を呼び出したのか、その真意が掴めず、そればかりが気になっていた。まさか自分にひと目惚れをしたとは考え難い。
どこをどう走ったのか、まるで記憶にない。ただ途中で大きな川を渡った気がする。アーチ橋というのだろうか白いまるでオブジェのような大きな鉄の柱がいくつも迫り出すその真ん中をセダンは走り抜けて行った。
やがて地方の街中を抜け、静かな暗闇に隣接するような場所に五階建てくらいのビルが見えた。車はそのビルの地下駐車場へ入るとコンクリートの柱の隙間に吸い込まれるようにピタリと停まった。どうやらここがホテルらしい。
「行きましょ」
彩花に促され、古賀は無言で後を追った。地下駐車場の隅に非常階段と小さなエレベーターがあった。二人はエレベーターの箱に乗り込むとそのままフロントを通らず一気に五階まで上がり詰めた。
ドアが開くと静かに薄暗い廊下が左右に伸びていた。彩花は廊下を左に進み一番奥の部屋の前で立ち止まるとショルダーバッグからカードを取り出し、ドアノブの上の挿入口に差し込んだ。
部屋のドアは内側に開き、照明を点し、彩花は古賀を先に室内へと誘った。
部屋はありきたりのビジネスホテルのようでもあったが、セミダブルのベッドの横に割りと広いスペースがあり、応接用のソファが一式テーブルを挟んで向かい合っていた。その向こうはカーテンが下ろされ見えなかったが、テラス付きの大きな窓になっているらしかった。奥のソファの後ろにはライトスタンドが一本と観葉植物が置かれ、反対側の壁際にはバーカウンターがあり、冷蔵庫には各種ドリンク類が並んでいた。その手前の壁には大きな液晶テレビが壁に取り付けられていて、壁紙の色合いが良く、落ち着きのある部屋だった。バスルームは入り口ドアからの通路に並んだところに設置されている。
彩花は古賀に奥のソファに座らせるとドリンクの好みを訊ねた。何でも構わない、と古賀が返答すると、きれいなライトグリーンをしたカクテルを差し出し、自分はカウンターバーの上でジンジャエールをグラスに注いだ。
古賀はそのライトグリーンのカクテルを口に含みゴクリと呑み込む。さて、これから何が始まるのかなと落ち着かない気持ちを持て余した。
そんな古賀を尻目に、彩花は弄ぶように焦らしていたが、やがて、心を決めたのか、向かいのソファへ腰掛けると、サングラスを外して大きな瞳で真っ直ぐに古賀を見つめた。その刹那、彼はゴクリと生唾を飲見込んだ。
そして彩花は、ほんのりと微笑を浮かべると、唐突にこんなことを言い出した。
「実は、小説を一本書いて欲しいのです」
6話
小説を一本書いて欲しい。
十和田彩花から出たこの予想外の言葉に文字通り古賀祐二は仰天した。
聞き間違いかと思い二度ほど「はっ?」と聞き返した。しかし、彩花はしっかりと前を向いて真剣な表情で同じ言葉を繰り返した。
「いや、しかし、私は編集者で、そのセリフは私が誰かに言うことはあっても、言われる立場ではありません」古賀はそう答えた。
すると彩花は「あなたがかつてN賞を受賞された小説家であることは知っています」とそう口にした。
「けれど、私にはもう……」
「失礼ながら古賀祐二先生の作品をいくつか拝読させて頂きました。もちろん受賞作の『永遠の微熱』も拝読させて頂きました。その上でお願いしているのです」
古賀はまさかと絶句した。古賀祐二の小説など今やどこの書店に置いてあるはずもなく、古書店でもそれを目にしたことはない。
全く予想だにしなかった話の展開に混乱した古賀は思考回路が乱れて次なる言葉が見当たらなくなって、ただ唖然とするばかりだった。
彩花が澄ました顔でジンジャエールを飲むのを見て、思い出したように古賀もライトグリーンのカクテルを喉の奥に流し込んで、むせた。
「いくつか、お訊きしたい。それから先生と呼ぶのはやめてくれませんか」
「分かりました」
「何故、私に小説の執筆依頼などと突飛もないことをお考えになられたのか、それから、もし書いたところで、それが出版などされる見込みは、ほぼ無いですよ」
古賀の質問も尤もなことだった。だが、彩花は落ち着いた態度のままこう答えた。
「小説のストーリーは私が持っています」
「えっ? どこに?」
驚いて古賀は尋ねた。彩花は小さなショルダーバッグをひとつ持っている。その中にメモでもあるのか、またはスマホに文書が保存してあるのだろうか?
「それは、ここです」と言って、彩花は右手の人差し指で側頭部あたりを指でコツコツと叩いた。
再度、古賀は言葉を失った。
「つ、つまり……?」
「私が体験して来たこれまでのことを、物語として小説にして頂きたいのです」
今度は息をのんでしまう。
「あなたの、その何て言うか、自伝みたいなものを小説にしろと?」
「自伝ではありますけど、あくまで古賀さんの小説として書いて頂きたいのです。もちろん謝礼もご用意しています」
「いや、謝礼などということはともかく、何故私が? 貴女ご自身でお書きになるという選択肢は無いのですか?」
「ありません」
きっぱりと彩花は言った。そしてこう続けた。
「わたくしが書いてしまえば、それは単なる自伝、ノンフィクションということになります。でも古賀さんの作品となれば、それはフィクションとして押し通すことが可能です」
そういうことか……、しかし、
「でも、原作者として貴女の名前は……」
「無論、それは出しません。あくまで古賀さんがお考えになられた物語として出版をお願い致します」
「いや、しかし……、少し考えさせてくれないか?」
「もちろんです」
それから古賀は長い沈黙を持って熟考した。彩花は新しいカクテル(今度はさっぱりとしたレモン味の美味なる飲料だった)を古賀の前に置き、少しの間、席を外した。
しかし、そんな短時間で結論を出せる問題では無い。編集者としての立場で考えるとアルファ砲を浴びて一躍魔性の女として噂され、ワイドショーなどで注目されている十和田彩花の自伝的告白本、それがどの程度噂の真相に近付くものかは知れないものの、出版されれば、多くの人達が興味を引くであろう。ベストセラーになるかどうかは分からないにしても、企画としては面白いものになる。それに彩花のあの美貌、すでに写真集など画策している出版社もあるとの噂も耳にしている。だが、それも彩花自身が執筆、または原作者として出版されればという話だ。他の者がフィクションとして出したところで無意味ではないのか。それに問題は古賀自身が小説を書けるかどうかだ。まず第一にそれが心配だった。つまり書き上げる自信など何も無い。だがストーリーはすでに彩花の頭の中にあるという。それを文章化する?
彩花がメイクを手直ししてさっぱりした表情で再び席についた。
「いくつか訊かせて欲しいことがあるのだけれど」
「ええ、もちろんです。どうぞ何なりと」
「はじめに断っておくが、まだ結論を決めた訳ではない。あくまで執筆を引き受けた場合を仮定しての質問なのだが」
「構いません」
「貴女の頭の中にあるストーリーをどうやって私が文章化するのですか? その方法を教えてくれませんか?」
「口頭でお伝えします」
「口頭?」
「はい」
「貴女が口頭で語ったものを私が書き写して行く訳ですか?」
「わたくしの語る内容をもとに小説化して頂ければよろしいのです。もちろん古賀さん自身の文体で、構成などもお任せします」
何だか雲を掴むような話だ。
「それは大体どれくらいの長さの文章になるのだろう?」
「文字数や頁数までは判断出来ませんが、出来ましたら新刊書籍として一冊にまとまるようにお願いしたいのですが」
「一冊の新刊……、しかし、それだけの分量の話を全て口頭で聞かせて貰うとなると、かなり手間取りそうだ。例えばあらすじだとか、せめて箇条書きにするとか、他に方法はないのかな?」
「申し訳ないのですが、お伝えするのは全て口頭のみです」
「しかし、単行本一冊分の内容を語って伝えるなんて、結構な時間がかかりますよ」
「時間はたっぷりあります」
「執筆期間はどれくらいを予定しているのですか?」
「予定はしていません。完成するまで何度でも作業を続けましょう。おそらく口述筆記するのはこの場所でということになります。週に一度か二度古賀さんの許される範囲内で、何度でも必要なだけ、ただし、他の人には絶対に知られてはいけません。作るのは古賀さんのフィクションですから、わたくしとの繋がりは隠密にお願い致します」
「貴女自身の名前は絶対に表に出さないと、そういうことですか?」
「はい、作者としては、です」
「と言うと?」
「小説の語り手、つまり主人公を架空の存在として十和田彩花の名前をお使いください」
またまた驚きだ。
「え? 貴女の実名をですか?」
少し混乱した。作者として名前は出さないが、作品の中には実名を登場させる。それは、矛盾してるような、してないような……。
「はい、でもそれはあくまでわたくし本人ではありません。古賀さんのフィクションとして創り出した架空の人物にして頂きます」
「そんなこと、世間の人はそう思うかな?」
おそらくそんな小説を発表すれば、いろいろと物議を醸し出しそうだ。
「そこが狙いでもあるのです。しかし、どう思おうが、それは読者の勝手です。誰も知らない話ですから、創作であることを押し通してください」
「何故?」
「本当は、全て真実だからです」
彩花は毅然としてそう言い放った。古賀は少し動揺した。真実を小説に、フィクションとして?
「目的は、何なんだ?」
今度は少しの間、彩花が黙る番であった。
ややあって、
「復讐です」という答えが室内に響いた。
古賀は彩花の言葉を脳内で反芻した。
復讐? 誰に? 暴露記事を出した週刊アルファにか? ならば、古賀はアルファ出版の人間だ。そこに話を持って来るのか? あるいは、そうか、暴露記事をアルファ出版に提供した別の誰かがいるのだ。それは一体……。
「相手は?」
「それは言えません。知らなくていいことです」
「そのストーリーは誰かを貶めるための暴露小説になるのか?」
「そう思われる可能性はあります。それだからこそフィクションに拘っているのです」
再び薄暗い部屋に重苦しい沈黙が流れた。
「そういうことか……」
ややあって古賀は掠れた声でそう呟いた。
「今ここでお返事をして頂く必要はありません。少し期間を置きましょう。時間も遅くなりました。次にお会いする予定を決めて今夜はここまでにしておきましょう」
気がつけば、いつのまにか日付が変わっていた。二人は帰る支度をして、そのホテルの一室を後にした。エレベーターで地下に降り、パーキングの中を横切り黒いセダンに乗り込んだ。運転スイッチを彩花が押すとセダンは静かな唸り声をあげた。そして元来た道をひたすらに走らせる。白いアーチ橋の鉄の下を軽快に車は通り過ぎた。暗闇の中、青い道路だけがどこまでも続いて見えた。真夜中のドライブは心地良かったが、気分の昂まりを古賀は感じていた。二人はかなりの時間黙っていた。
やっと見慣れた街並みが見え始めた頃、古賀はひとつ息をついてこう呟いた。
「何だか夢を見ていたような気分だよ」
「そうですか」彩花は唇の端で小さく微笑した。
「それにしてもよく思い付いたね。自分の名前を主人公にして他人に小説を書かせるだなんて。なるほど、それならフィクションだか、ノンフィクションだか、誰にも判らなくなる」
「恐縮です」
ほんの僅かだけ彩花がはにかむのを古賀は横目で捉えた。
やがてセダンは、待ち合わせをした都内某所の裏通りにあるコインパーキングに到着した。
そして、その日はそこで別れた。
7話
週刊アルファが記事にしたA賞作家の婚約者・十和田彩花のスキャンダル暴露の元ネタを提供したのは、彩花の元恋人・杉下治郎である。
売れないとは言え、一応推理作家としていくつかの小説を上梓している杉下は旧知であるアルファ出版の編集者のコガから上手い具合に週刊アルファの責任者の名を聞き出した。
そして、その奥藤という男に連絡を取って彩花に関する件を持ち出した。最初は疑心暗鬼だった奥藤も相手が一応推理作家であり、同僚からの紹介ということで、話を聞く時間を持った。
そこで出された実際の写真の数々、しかもその相手が芸能界の大物だったり、人気アイドルや有名スポーツ選手といったそうそうたる顔ぶれが並ぶにいたって、奥藤は驚きを隠しきれなかった。もしこれが本当なら大変なことになる。
どうしてそんな写真(スマホ画像)を手に入れることに成功したのか、奥藤はそれを杉下に訊ねた。
すると十和田彩花とはかつて恋人関係にあったという。今はもうすでに別れてしまったが、交際中から、彩花には不審に思われる行動がいくつかあったという。
例えば、常時スマホを複数バッグに入れて持ち歩いていて、始終どこからか電話がかかって来たり、メールやラインのやり取りを頻繁に繰り返す。しかし、その内容については一切話そうとしない。普段の行動も含めてとにかく秘密の多い女性だった。交際当初はそんな謎めいた部分に惹かれもしたが、段々と不安が広がり始めたという。
奥藤は先ず、杉下が彩花と出会ったきっかけを訊ねてみた。それは、よくあるミステリー作家が集まるパーティーが出会いだったという。その時、杉下は彩花の美貌に魅了され一瞬にして恋に堕ちた。その後、彩花の行動する場所の情報をあらゆるところから入手し、徐々に接近して行った。そして会う度にどんどんその魅惑に惹かれて行き、やがて、どうにか連絡先を聞き出し、何度か個人的に食事等に誘い、杉下の巧みな話術も功を奏して、次第に彼女の方でも彼に対してまんざらでもない態度で接するようになった。二人だけでお酒を呑みに出掛けたりするようになると、その後の展開は早い。程なく二人は男女の関係になった。杉下にとっては天にも昇る気持ちだった。
しかし、どれだけ親しく関係を深めても、彩花の実態には立ち入れなかった。杉下は何度か彩花の生い立ちや故郷の話を聞き出そうとしたが、その度に話ははぐらかされる。どこかへ旅にでも行かないかと誘ってみても、仕事があるからとつれなく断られてしまう。
そのうち二人の関係は月に二度ほど待ち合わせをして食事とお酒を楽しみ、その後ホテルに泊まる。そして翌朝にはあっさりと別れてしまう。そんなことを繰り返すだけの間柄になっていた。
それでも良かったはずなのだが、杉下の思いは複雑だった。彩花にとって自分の存在とは、単なるセフレの一人に過ぎないのではないかと、疑い始めた。自分は恋人であると勝手に思い続けて来たのだが、それさえも、もしかすると単なる思い違いだったのかも知れない。そんな不安と闘う日々だった。
何度かそのことを彩花に直接問いただしてみようと思ったが、そんなことをしてもおそらく無駄であろうと判断した。こちらの質問に対して正直に答える女ではない。何かを語ったとしてもそれが真実とは思えない。そこで杉下は推理作家の能力を発揮して、いろいろと探りを入れた。
まずはスマホの中味である。杉下はいつもスマホを操る彩花の指先の動きをそれとなく盗み見て、キーロックを解く暗証番号を探り出した。そして二人でホテルに宿泊した際、彩花がシャワーの最中、もしくは深夜、あきらかに眠りの底にあることを確認した上でこっそりとバッグからそれを取り出しては中味を探った。
複数あるスマホの中から、いくつかの画像、メール、ラインのやり取りなどを自分のスマホに写し取った。まだその時点ではそれをどうするかなどとは少しも考えていなかった。ただ彩花の謎を解き明かしたい、その衝動に駆られてのことだった。
それから彩花の住むマンションも尾行して探り出した。恋人を尾行するなんてとても馬鹿げたことだと思ったが、その衝動はどうしようもなかった。
そして見つけたタワーマンション、部屋番号も調べがついた。杉下の住むアパートとは比べ物にならない程の大きさである。いくらフリーのファッションデザイナーと言えども、あまりにも高級過ぎる。何とかその謎を調べたい。そう考えた。
そこからが大変だったが、秘密のルートを駆使し、その部屋の持ち主の名義を手に入れた。ミステリー作家であるこその強みだ。しかし、その名は聞いたことも無い平凡な名前。誰だろうと思いながら捜査を続けて行くと、その男は身寄りのない老人で現在は重い病気を患い入院していて口も利けないという。しかし、手に入れたその男の履歴を辿って行くと、なんとそれはある政治家の秘書をかつて長年務めていた人物だと判明した。その政治家こそが元財務大臣の蔵原文三である。
結局、杉下の彩花に対する調査はそこまでが限度だった。推測するにマンションの名義は元秘書の男だが、本当に資金提供しているのは蔵原に違いない。それだけではない、若干二十代でフリーのデザイナーとして各社と契約を結び、仕事をしていけるのも、何かの後押しがあったからに違いない。いくら人より秀でた美貌の持ち主とは言え、それだけでやって行けるほどこの世界は甘くない。それにスキャンダルに発展した大物芸能人や各界の有名人達とはどこでどのような接点を持ったのか、それらの謎も裏で蔵原元大臣の力が働いているとしたら、全ての謎も解明出来そうだ。しかし、それは憶測の域を出ない。その関係を探るには個人の力では限界がある。大きな力でないと太刀打ち出来ない固いガードに包まれているようだった。
一方、杉下と彩花の関係はだらだらと継続していたが、特に進展もなく月日だけが過ぎて行った。その頃、杉下の作家としての評価は芳しくなく、なかなか新作として発表できるものを創れずにいた。彩花の杉下を見る目にもなんだか輝きを失っているように感じられた。それでもいつかは人をあっと言わせるようなミステリーを発表してやると心意気だけは持ち続けていたのだが。
そんな折、何かの拍子に逢阪遥人の名を耳にした。新進気鋭の文学作家で去年だか一昨年、K社の新人賞を受賞したらしい。その逢阪の今年発表した小説がA賞の最終候補にノミネートされていると聞いた。
推理作家の杉下はあまり文学の方面に縁は無かったが、同じ小説家としてそのニュースは当然気になっていた。何故かと言うと、以前にどこかで彩花がその名を口にしたことがあったからだ。はじめは単なる世間話として気にも留めなかったのだが、やけにその作家を褒め称えるような彩花の口ぶりに苛立ってしまったことだけを覚えている。
その逢阪がだんだんとマスコミで騒がれ始め、ついにはA賞受賞を確定したのと、杉下が彩花から突然の別れを切り出された時期が、偶然のようにぴたりと重なっていた。
杉下の勘はそんなところでも鋭かった。やがて十和田彩花はA賞受賞作家・逢阪遥人の婚約者として世間に注目され始めたのだ。
既にその頃には杉下の携帯からは彩花のスマホには着信拒否になっているらしく、繋がらなくなっていた。失恋のショックもあり、仕事も上手く行かず、無精髭も伸び放題、毎晩酒場を渡り歩いて自堕落な生活をした。テレビで華やかな笑顔を振り撒いている彩花の姿を見る度に腑が煮え繰り返るような怒りを覚えた。落ち目の推理作家は栄光を手にした文学者を妬み、その地位を貶めてやりたくて仕方なかった。
杉下が思い付いたのは、腹いせとしてこれまで盗み取った彩花のスキャンダル画像をアルファ週刊誌に売り付けてやることだった。
奥藤にとっては売れるネタならば、それがどんな経緯であろうと構いはしなかった。杉下が持ち込んだネタを買い取り、記事にすることを約束した。
そしてそれは大成功を収めた。
8話
小説を執筆すること、ひとつの作品を完成させること、しかも長編ともなると、それがどれだけ大変なことか、古賀祐二は経験を持って知っていた。
作家として、内容のある小説、読み応えがあり、読者を満足させられるそんな作品。これまで何度それを目指して試みたことだろう。だけど、初期の勢いでN賞を受賞するまでは良かったが、その後、第二作は不評、三作目に至っては未完のままお蔵入りになった。それ以降、長いスランプというか、むしろ、作家としての自分はそこで終末を迎えたと感じた。
人は誰でも人生の内、一作は小説を書けるとよく言われる。N賞に輝いた小説『永遠の微熱』は古賀祐二にとって最初で最後の作品だったに違いない。
それを確信した古賀はそれ以来、作家の道を断念し、編集者としての仕事を選んだ。それはそれで大変な仕事だったが、それなりに何年も続けて来られた。ある程度の役職にも就かせて貰い、あと十数年もしたら退職の時期を迎える。順風満帆とは言い難いがそれなりに充実した人生であり、仕事に一生懸命邁進して来た自負もある。おそらくこのまま年老いて、自分の人生は終焉を迎えて行くであろう。ずっとそう考えていた。そう、あの女性、十和田彩花に出会うまでは。
あの夜、彩花から申し出された小説の執筆依頼。十和田彩花のストーリー、それを彼女が自ら語り、それを口述筆記で古賀が小説にする。それらは本人にとっては真実の話であっても、出来上がってしまえば作家が創り出したフィクションの小説。
その執筆依頼を引き受けるか否か、それ以来ずっと迷い続けていた。世間にはそれを架空の物語であると主張する。ある意味世間を相手にシラを切り通し、騙すようなものである。果たしてそんなことが出来るものなのか、自信なんてものはかけらも無い。
彩花との二度目の待ち合わせは今夜に迫っていた。それでもどういう返事をするべきか、決心出来ずにいた。彼女に会ってあの瞳やあの唇を目を前にしてしまうと、何故だかその誘惑に引き込まれてしまいそうになる。それは古賀の人生にとっては二度と味わうことのない甘美な瞬間だ。もし執筆を引き受けたとしたなら、何度もそんな瞬間を味わうことになる。その上で新しい小説、たとえそれが十和田彩花の語るストーリーだったとしても、古賀としては自分で執筆した新作小説の誕生になる。
気持ちは揺れていた。結局、結論を出せないまま、当日、待ち合わせの場所に向かうことになった。
前回と同じ、都内某所にある閑散とした駅の裏通りにあるコインパーキング。車を停めると古賀は通りに出て佇んだ。ほぼ時間通りに彩花の黒いセダンが現れた。古賀の前に来てスピードを緩め停止する。助手席に古賀は身を滑らせシートに身を沈めた。彩花は前回と同じような地味な服装だが、相変わらずフィット感のあるスポーツウェアで髪の毛を後ろで纏めていた。帽子を被り歩道を走ればジョギングランナーのようにも見える。サングラスは外していた。
たぶん、前回と同じ道のり(古賀はそのルートを記憶していない)を通り、やがて見覚えのある白いアーチ橋をくぐる。それを越すと夜は一層の闇を増して異世界へ誘われた気分になる。
「誰にも見られずにマンションを出るのは大変でしょう?」
沈黙を打ち破るように古賀は問いかけてみた。彩花はふふと小さく微笑むと、「今はもうあのマンションにはいませんのよ」と言った。
「引越したのですか?」
「いいえ、一時的に別の物件に移動しただけです」
さらりとそう打ち明けたが、誰にも知られずそんなことを簡単に出来てしまうとは驚きだ。
そして再びあのホテルに到着する。地下の駐車場に車を停め、エレベーターに乗り込み五階に上がる。左奥の部屋、その間誰にも会わない。しんとした静けさが建物全体を覆っている。
部屋に入り、ソファに座る。彩花が前回と同じライトグリーンのカクテルを差し出す。自分はジンジャエールだ。ここまでは同じ展開だ。ドラマの同じシーンを繰り返し再生しているみたいだ。
「さて、どうですか?」
彩花はさり気なく切り出した。ここから新しいドラマの展開が始まる。さて、どうしたものか。
「もう一度訊きますが、あの話は、本気で言ってるのですか?」
「もちろんです」
古賀は彩花の瞳と唇に目を奪われる。心まで吸い取られそうな気になる。
「その、なんというか、それはどうしても私でないとだめなんだろうか? 世間には作家志望の人間はたくさんいる。私よりずっといい小説を書ける人は大勢いるはずだ」
彩花は古賀の言葉に黙って頷くと、少し間を置いてこうつなげた。
「そう、いい小説を書ける人はたくさんいる。その中から誰か一人、私がこの人と思う人を選べば良い。だから、そうしたの」
「え?」古賀は、言葉の意味を理解するのに数秒を要した。そしてその意味を理解し、再び彩花を見つめた。
結局、古賀は彩花の依頼を引き受けることになった。不思議なことに不安よりもわくわくする妙な期待や希望が胸の奥から湧き上がるのをうすうす感じていた。
それでも古賀はいくつか確認するべき点を尋ねてみた。
「例えば、ペンネームを考えて覆面作家みたいにしてみてはどうだろう?」
これは作品発表後に予想される騒動から逃れるための予防策のひとつとして思いついたことである。
それに対して彼女の答えはこうだった。
「別に構いませんが、この作品がフィクションであることを宣言してもらわなければなりませんので、いずれその覆面はバレて意味をなさなくなりますよ」
確かに、そう言われれば、そうなることも目に見えている。そして次に部屋の内部を見渡し、こんなことも言ってみた。
「こんなホテルの一室で何度も二人きりになるなんて危険だと思いませんか? いつ何時私が貴女に襲いかかるかも知れません」
部屋には大きめのダブルベッドもシャワールームも設置されている。こんな美女と一緒に何時間も共に過ごせば、間違いが起こっても当然の成り行きと言える。だが、彩花は平然と、いや寧ろ楽し気にこう応えた。
「構いません。そんな気になりましたら、いつでも押し倒してください」
挑発とも取られかねないその発言は古賀を圧倒した。
「小説を仕上げることが第一案件です。それに付随することは全て些細なことです。たった一つの条件は誰にも知られないという一点です。これだけは極秘でお願いします」
古賀はその時、もし誰かにうっかり知られてしまったりしたら、自分はどうなるのかと訊こうとしたが、その答えを知るのが怖くなり、やめておいた。
こうしてその日から彩花の自伝的告白本(あくまで古賀が創作した作品として発行する)の口述筆記での執筆活動がスタートした。
9話
週刊アルファを統括する責任者の奥藤は杉下から買い取ったネタによる記事を小出しにして、何週間に渡って雑誌の販売部数を飛躍的に伸ばした。
発売する度に新たなターゲットが実名で衆目に晒され、今年最大のスキャンダル事件としてテレビは大騒ぎし、ネットは大炎上した。
それによって活動を自粛せざるを得ない芸能人も何人か出現した。特に不倫問題は世論が厳しくモラルを追求したので、企業はCM契約を解除し、テレビ局はドラマ出演の降板を発表した。謝罪会見をした有名人もいたが、半数以上は黙秘を貫き、騒動が収まるまで雲隠れしているようであった。
杉下からのネタを使い切った奥藤は更なるアルファ砲を目指して、ある疑惑をちらつかせ、その真相の追及に向けて動き出した。それは十和田彩花と蔵原代議士との関係についてである。
さすがに奥藤も大物政治家を相手に根拠のない疑惑を実名で報道する訳には行かなかった。そこで繋ぎとして大物政治家Kに関する黒い疑惑という見出しで、以前から取り沙汰されている企業献金の噂、ある宗教団体との交際、そして元首相暗殺者との繋がり、これら全ては証拠の無い疑惑にしか過ぎないのだが、それらと共に十和田彩花の名前を組み入れ、証人を募った。つまり情報のタレコミを募集したのだ。
その頃からすっかりA賞作家・逢阪遥人の名前は誌面から消え、スキャンダルをもたらす張本人としてフリーファッションデザイナーの肩書を持つ十和田彩花が物事の中心人物として読者を惹きつけるヒロインとして世間の注目は移り変わって行った。
そして奥藤は政治関係の取材を専門とするカメラマン数人を呼び寄せ、蔵原代議士を写した写真、画像の類を何十年に遡り、全て提出するように求めた。そしてこれまで蔵原代議士が関わる記事を全部取り寄せ、その内容をひとつひとつ当たることを始めた。
そんなことが続いたある日、昼休みの社員食堂で奥藤は同期入社である古賀祐二の姿を見かけた。
「やあ、久しぶりだな」トレイに乗せたかつ丼セットをテーブルに置きながら、奥藤は古賀の前に腰掛けた。
「ああ、久しぶり」古賀は少し疲れた表情で返事した。
「どうした、あまり元気がないみたいだな」
「いや、そうじゃないよ。このところ少し睡眠不足でね」
「そうか、そっちも忙しいんだな。良いことじゃないか」
奥藤は声を出して笑った。
「お前のところほどじゃないよ」古賀も最近の芸能界スキャンダルの報道をたくさん目にしているが、十和田彩花の件があるので、わざと見ないようにしている。
「そう言えば、思い出した。あの男、杉下とかいう作家、俺に紹介してくれたのはお前だったんだな。おかげであれから毎号飛ぶように売れてるよ」
うん? 古賀は首を捻った。
「杉下って、杉下治郎か?」
「そうよ。お前が担当してるんだろ?」
「ああ以前はな。今は俺じゃなくて別の奴だ」
「そうか、ま、俺も名前を聞くまではそんな作家がいることさえ知らなかったからな」
「杉下がどうかしたのか?」
「あれ? 例のスキャンダルの元ネタの売り主だよ。お前から俺の名を聞いたと言ってたぜ」
「えっ、俺から?」
記憶をまさぐってみた。その時になって、ようやく古賀はある日の電話を思い出した。あれはひと月かあるいはふた月くらい前になるだろうか、そうだ、まだ逢阪遥人の婚約者のスキャンダル記事が出る前、ちょうど別の作家の新刊の件で忙しくしていたので、忘れてしまったが、前に担当したことのある作家(杉下だった)から電話があり、週刊アルファの責任者の名前を尋ねられて、奥藤の名を伝えたのだ。
それがまさかあのスキャンダル記事の提供者だったとは思いもしなかった。全く今更ながら自分の迂闊さには呆れる。
古賀は一心にかつ丼を頬張る奥藤を呆然と眺めた。
「それで……」古賀は少々掠れ気味の声を出した。
「うん?」奥藤が顔を上げる。大きな口をもぐもぐと動かしている。忙しい雑誌の編集長は食べるのも早い。もう容器は大方空っぽになっている。
「いや、それで、その記事はこれからもまだ何か続くのかい?」
古賀は十和田彩花の名を口にするのは憚かられた。接点を示唆するようなことは言えない。
「そうさな、いろいろ疑惑があってね。目下捜査中ってところだ」
「はあ、そうか、それは大変だな」
古賀としてはその捜査中のところをもう少し詳しく訊いてみたかったのだが、下手に首を突っ込めない気がしたので、その先は黙っていた。
奥藤はさっさとかつ丼を食べ終わると、ぐいとお茶を一息で飲み、「じゃあ、またな。落ち着いたらどこかで一杯やろう」と言ってスタスタと社食を出て行った。
古賀はう〜んと胸中で唸った。マスコミに登場する十和田彩花はスキャンダルをもたらす魔性の女で、そこに世間の話題は集中する。確かにあの妖しげな美貌と謎のベールに包まれた私生活は人々の興味の対象としてこれ以上の娯楽性はない。そう芸能人のスキャンダルや不倫ネタはテレビの視聴者にとってはドラマ以上の娯楽であり、その言動をいつも楽しみにしているのだ。
当事者にとっては悲劇であってもテレビの前の第三者にとっては対岸の火事、自分に火の粉が飛んで来ない限り、戦争や殺人でさえも刺激を求めて話題として楽しみ事のひとつになってしまう。
ところが今の古賀祐二にとっては、そんな興味本位の楽しみ事には決してならない。まだ今は当事者ではないが、着手しかけた小説を近い将来出版すれば、十和田彩花との関連性を巡り、自分が矢面に立たされる可能性は大きい。いくら小説、フィクションであると主張しても、それで世間を納得させられるのであろうか、それには甚だ不安が募るばかりだった。
しかし、それとは別に、古賀が知る実際の十和田彩花は、確かに美しい女性ではあるが、魔性と言われるような素ぶりは欠片も見せない。質素で落ち着いた振る舞いはまるで有能な秘書か何かのように思える。話し言葉も丁寧で上品な語り口で自分の生い立ちを語ってみせる。まだ口述筆記の執筆は序章に過ぎないが、合間合間に見せる古賀への気遣いは丁寧で優しく、とてもワイドショーを賑わせている魔性の女と同一人物とは思えないのだ。古賀はひとつため息を吐いた。
さて、奥藤はデスクに戻るとすぐに、集めた蔵原代議士の写真やパソコンに送られたデジタル画像、あるいは動画などを首っきりになって調べた。何しろその件数たるや数千件を超え一万件以上の数に上がっている。この中から十和田彩花と関連する何かを見つけ出すなんてことは砂漠の中からダイヤモンドの一欠片を探し出す作業みたいなものだ。もちろんそれは奥藤ひとりでは埒が明かず適当な社員で手分けして作業しているのだが、週刊誌の編集は忙しい。そればかりに関わってもいられない。ただ記事を出すにもタイミングというものがあるので、なんとか早く何か手掛かりを見つけたいと奥藤は執念深く一枚一枚の画像を見詰めていった。
そんな時、別の社員から蔵原代議士にまつわる一つの新聞記事を見つけたとの報告を受けた。
それは今から二十年以上も前の話である。当時の蔵原財務大臣が、ある地方都市で街頭演説の最中に発砲事件が起こり、警護中の警備員が一人亡くなった。犯人はすぐに取り押さえられ逮捕されている。記事には四十代の犯人の氏名と共に、死亡したニ十代の警備員の氏名も記載されていた。尚、蔵原大臣に被害はなかった。
奥藤はその事件に興味を持った。長年の雑誌編集者としての勘だろうか、何か事件の背景に裏があるのではないか? それから奥藤は関係者を辿ってその事件を調査してみることにした。
10話
A賞を受賞して飛ぶ鳥を落とす勢いで文壇を賑わせていた逢阪遥人であったが、婚約者のスキャンダルや疑惑が次々に発覚し、その煽りを受けて新作執筆にも筆が進まず、いらいらした毎日を過ごしていた。
当の婚約者・十和田彩花とはその後、会うことはおろか、連絡さえ途切れ、業を煮やした逢阪は一方的に婚約破棄を発表した。
そんな逢阪に対してネット上では同情する声よりもむしろ非難する意見の方が多かった。容姿だけに魅かれて婚約したはいいが、思わぬ過去の悪事が知れるとさっさと婚約破棄、自分の体裁しか考えていない、もともと女を見る目のない無能な男。そんな評判が立った。ついにはA賞も地に落ちたものだ。次の作品で評価が悪ければA賞の肩書きは返上すべきだ、との辛辣なコメントも見受けられたりした。
さすがに逢阪のマンション前からはすでに報道陣の姿は消え、何をしようとどこへ行こうと自由の身になったのだが、執筆に集中する気分もなく、どこかへ旅に出る気分にもならない。テレビやネットを観て過ごすのもいやな気がするだけなので、だらだらと毎日を持て余し気味に過ごしていた。
夜の盛り場に出掛けては酒を煽る。そんなことを覚えたのはつい最近のことであった。もともとお酒は嫌いではなかった。彩花と男女の関係になったのも酒の勢いによるもので、何かに行き詰まった時や気分が滅入った時などは酒の力を借りて乗り切るのもいいだろうと以前からそう思っていた。
当初は自宅から近い三茶あたりを彷徨っていたりしたのだが、ついつい知人や顔見知りに出会い、身バレしてしまうと話に付き合わされるハメになる。
そうなると心から楽しめないし、時には無神経にA賞がどうとか、婚約者はどうなったのか、などと聞きたくもない話題に晒されてしまう。
そこで考えたあげく髪型を変え、髭を伸ばし、少しワイルドな風貌に変装し、新宿あたりまで出掛けて飲み歩くようになった。
それが功を奏し、どこに行っても作家とは気付かれずに一人でこっそり酒に浸れることができた。帰りはタクシーを使えばいいし、気が向けばどこへ泊まろうと自由だ。たまにK社の編集担当から携帯に電話が入るが、騒動のこともあり、暫くは新作を書く気がしないと断ってあるので、それほど気にする必要もない。
禊という訳でもないが、暫く自由気ままに生活してみて、また気が向いたら作家活動に戻ればいい。
今の世の中の風潮では逢阪遥人は以前のようなファンは減ってしまって受け入れられる要素がない。
物事にはタイミングがあるのだ。この体験をプラスに変えるためには来るべき時を待ち、方策を練る、それがベストだ。彩花との一件は調子に乗り過ぎたと今にしてみれば反省点も多い。確かに婚約するには相手のことを知らなさ過ぎたし、見た目の美しさだけに惑わされて我を忘れていたようだ。
しかし、そういう反省点をあげる一方で、未だに十和田彩花の魅力、特にベッドの上での営み、その肌触りや濃厚なキス、挿入した性器に纏わり付く肉襞の感触、射精の瞬間に溢れ出る嬌声、それらがまだふつふつと胸の奥に甦り湧き出て来る。
つまり逢阪は未練たっぷりにまだ彩花のことを思っていたのだ。
そんな生活が暫く続き、何軒かの行き付けのバーが自然と出来ていった。一人で呑んでいても誰にも邪魔をされない。時間が長くなっても文句を言われない。後は何となく居心地の良い環境だとか、好きな音楽がかかっているなど、条件はいくつかある。
店の雰囲気を気に入ってしまえば、そこで出会った人とも気軽に話が出来る。煩わしさは何も感じない。向こうはこちらを何者か知らないし、詮索もされない。こちらも知ろうとしない。暗黙の了解があるかの如くだ。特に新宿駅西口から徒歩で行ける雑多なテナントビルにある小さなバーはどんな素性の者がいても誰も気にしない。
『BUZZ』という店はその中でも特にお気に入りの店だ。行く度に恰幅の良い温和なマスターが気持ち良く迎え入れてくれる。程なく逢阪はその店の常連客となった。
『BUZZ』には何人かの常連客がいた。それは曜日によって多少違うのだが、平日の人気の少ない時によく会う一見遊び人風のロン毛髭面の男がいた。歳の頃は逢阪と同じか少し上くらいに見えたが、もちろんここではそんなことはどうでもいい。
何度か見かけるうちにたまに一言二言、言葉や挨拶を交わす程度の顔見知りになった。これまで逢阪の周りには居ないタイプでかえってそこに興味を惹かれて会えば軽い世間話くらいはするようになった。
マスターも彼と親しく会話をしていて、いつもその男のことを『ジロー』と呼んでいたので、いつのまにか逢阪も彼のことをそう呼ぶようになった。因みに逢阪はそこでは『ハル』と名乗った。
基本的にはハルもジローも一人で呑むことを好むのだが、時には誰かと話をしてみたい時がある。そんな時にジローがいると好都合だ。意外にも彼は話が上手く、いろんな物事に詳しく、話術に長けていた。知識も豊富で幅広く、人を惹きつける魅力を持っている。それだけではなく、人の話もよく聞いてくれる。相槌を打つタイミングも良く、特に話のポイントをうまく掴んでくれるので、有り難い。話上手でもあり、聞き上手でもあった。
そしてジローは決してハルのプライベートに首を突っ込むような会話を仕掛けて来ない。自分がA賞受賞作家であるとか、婚約者がスキャンダル騒動を起こしてそれを破棄した、などということはそこでは誰も知らないし、考える必要もない。
日常から離れ、煩わしさからも遠去かり、何を取り繕う必要もなく、自由気ままに酒を酌み交わし、心が癒される、その時の逢阪にとって『BUZZ』は心のオアシスと思える場所であった。
しかし、幸福な日々は長くは続かない。
週刊アルファに『落ちぶれたA賞作家』として酒場で酔い潰れる逢阪遥人の現在の様子が写真入りで掲載されたのは、彼が新宿界隈をうろつき出して二ヶ月ほど経った頃だ。その頃はほとんど常連客として『BUZZ』に入り浸っている時であった。
そこにはA賞受賞の祝賀会で晴れがましい顔でスピーチしたあの好青年の面影はなく、髪の毛は伸び放題、髭面でアルコール漬けのまるでホームレスのような風体で酒場の隅のテーブルに突っ伏している。
写真は逢阪の知らない内に何枚か隠し撮られたようで、受賞式の時の栄光の写真とその写真が比較されるように並べて掲載されていた。風貌は変わっていてもそれが逢阪遥人であることは容易に判断出来る。
この報道によって再び逢阪は地獄の底に突き落とされる。十和田彩花との婚約を解消し、スキャンダル騒動からもようやく抜け出せたかと思われた瞬間、またもやこんな憂き目に晒されるとは、思ってもいなかった。
こんなものが世間に知れ渡ってしまえば、もう新宿界隈にも近付けそうにない。誰がこんな写真を盗み撮りしたのか知らないが、心のオアシスだと思えたあの店にはもう行けない。恰幅の良い穏やかなマスターや親しくしていたジローの顔などが思い浮かんで来るが、暫くはもう彼らにも会えないだろう。
やるせない気怠さを覚えて、部屋に閉じ篭もったきり、かと言って何もやる気も起きず、一日中ベッドの上で布団に包まりごろごろと過ごす毎日だった。
11話
十和田彩花の語る物語を口述筆記する作業は週に二度、深夜から明け方にかけて秘密の内に行われた。
古賀祐二は持ち込んだレポート用紙にペンで彩花の言葉を一言も漏らさずひたすら書き写して行った。
作業はそのレポート用紙に書かれた文章を自室に持ち帰り、パソコンに清書しながら入力して行く。
彩花の語る物語は生い立ち・少女時代から始まり、やがて青春期を迎え、社会に旅立つ、そこまでが第一章にあたる。東北の雪深い湖の傍で母と娘の二人暮らしは質素で慎ましく穏やかな日々が続く。
その頃の彩花はまだ家庭の事情や母の苦労には気が付かずに明るく天真爛漫にすくすくと育てられた。
それが中学、高校と進むうちに父親の不在、母の健康上の問題など、一見翳りのない青空に見えた風景が徐々に見えない何かに蝕まれて行くのを少女は知ることになる。
しかしその度ごとにどこからか救いの手が伸ばされる。運良く母は名医の手により健康を取り戻し、手取りの高い職場に復帰する。学業の成績は常に学年トップを維持していた彩花は私立の進学校に合格し、家を離れ東北の地方都市で一人暮らしを始める。その頃から彩花と母の生活をバックアップする者の存在があることに彼女は気がつき始めた。何度かそのことを母親に問い掛けてみたのだが、とうとう最後まで母はそのことについて口を割らなかった。その頃、母の体調は再び芳しくないものになっていた。
私立高校を優秀な成績で卒業した彩花は同じ系列の私立の短期大学に入学した。専攻はファッション造形学科というところで、その頃から将来はファッションデザイナーになることを夢見ていた。短期大学を選んだのは少しでも早く母親の生活の助けになりたいとの思いからであった。
ところが、思ったより早く、その日は来てしまった。母親の死を知ったのは短大在学中、卒業を目前に控えた頃であった。身内と言ってもほとんど人の居ない静謐に包まれた中で告別式は行われた。喪服に身を包み哀しみを胸に秘め、黙祷する彩花の元に、その時一通の封書が届けられた。
そこまでの物語を古賀はパソコンに入力し終えた。
彩花が口頭で語る文章は完璧で、何も手を加えずともそのまま写し取ればそれだけで、素晴らしい小説になりうることを古賀は知った。だが、敢えてそれは古賀の小説とするために多少の修正や添削、というよりは変更を加えて行った。原文にはおよそ古賀には使えない比喩表現や語り口があるので、申し訳ないとは思いつつ、自分なりの表現方法を用いることを採用した。
それらの作業は未知なる体験でもあり、かつてN賞を受賞し、作家として夢と希望に燃えていた頃の日々を古賀の胸に蘇らせた。
もう新しい小説は書けないと、一度は筆を絶ってしまったのだが、このところ少しずつだが、日記程度の物事をノートに書き留めたり、創作とまでは行かないが、ちょっとした日々の思い付きを気ままに書き綴ったりしていた。
どこか胸の奥に睡っていた小さな残り火が、ある出来事をきっかけとして、再び新たな火種になることがある。もしかすると、これがその兆しの始まりではあるまいか、そんな想いを過らせながら、彩花の語る物語を必死に書き留め、その世界を共有しようと没頭した。
そして何より週に二度ある彩花との密会。これは心躍る体験としか言いようがない。会う度に夢心地、あの白いアーチ橋を越えた向こうの世界は非現実の夢の世界であるかのような錯覚にとらわれた。
古賀はペンを走らせながらもじっと丁寧な口調で澱みなく語り続ける彩花の口元、そのくちびるの動きに身も心も吸い寄せられて行った。
車での移動中は寡黙である彩花も部屋の中では柔らかな表情を見せ、作業前後にひと息入れるドリンクタイムでは笑顔で雑談にも応じた。
もちろん古賀の方でも人目など充分に注意し、マンションを出る際や、帰り道、誰かに尾行されてはいないかなど気を使ったが、無名の一編集者に彩花との関連性を疑う者など誰もいなかった。
それでも普段の生活、特に仕事中などにたまに同僚と世間話などする際には常に気を配った。どうしても仕事をこなした上で深夜の作業をしていると疲れが溜まって睡眠不足にもなる。古賀はなるべく他人に不審がられないように最善の注意を払って無難に日々の生活をこなし続けた。
ある時、古賀は彩花からちょっとした調べ物を依頼された。それは週刊アルファに掲載された最新の逢阪遥人の落ちぶれた様子の記事についてだった。
逢阪と言えば、彩花の元婚約者でありA賞を受賞した文学作家である。今その書籍は私生活での話題もありベストセラーになっている。けれどその週刊誌では新宿の某酒場で酔い潰れて醜態を晒す姿が隠し撮りされていた。見た目の風貌も爽やかな好青年のイメージは崩れ、それは酷いものだった。
彩花に依頼されたことは、その写真を誰が隠し撮りして週刊アルファに売り込んだのか、もし機会があれば、それとなく探ってみてくれないかというものだった。
古賀には週刊アルファを手掛ける部門責任者の奥藤がいるので、そんな機会は簡単に作れそうな気がした。だけども怪しまれないように、何かのついでにそれとなく聞き出してみる、そんな注意が必要だ。うまく行くかどうかは分からないものの、以前に奥藤が、落ち着いたら呑みに行こうと言っていたことを思い出していた。
その機会は直ぐに訪れた。
以前と同じ社食で昼食を摂っていると、再び当の奥藤が来合わせたのだ。奥藤は週刊アルファの売れ行きも良いこともあり、いつもより明るい顔をして古賀の向かい側に座った。
世間話をして、昼食を終えようとした頃、良ければ仕事終わりに一杯どうだいと持ち掛けてみた。以前にはそんな事もよくあったからなんの躊躇いもなく口に出来た。奥藤もそうだなと一瞬予定を考え込んだが、よし分かった、たまには良いだろ、今日でも明日でも構わないぜと返答した。
首尾は上手く行った。以前よく立ち寄った居酒屋の半個室のテーブル席で、奥藤は次から次にといろんなことを喋った。もともとお酒好きのよく喋る賑やかな男だから、やりやすい。けれども流石に仕事絡みのシークレット事項については素直に口を割らないはずだ。頃合いを見て、さり気なく、古賀は同業者として逢阪の落ちぶれた姿に心を痛めたと言い、
「一体誰があんな写真を盗み撮りしたのだろうな」とわざと憤りを見せてみた。
すると奥藤は、さっと顔をしき締め辺りを確認すると古賀に顔を近づけて囁いた。
「ここだけの話だ。お前だから言うけどな」と前置きし、奥藤はその名を口にした。
その次、例のホテルの一室で口述筆記の作業を終えると、古賀は奥藤から聞いた名前を彩花に告げた。
黙って古賀の言ったことを聞いていた彩花は、ひとつため息を吐いて、
「そうなの、ありがとう。やはりそうだったのね」と応えた。
「ひとつ訊いても良いかい?」
「ええ、どうぞ」
「その男と貴女は何か関係があるのかい?」
彩花はすぐには返答しなかった。
しかし、やがて、
「そうね、それは、いずれわかるわ」と、伏し目がちにそう呟いた。
12話
週刊アルファの発行責任者・奥藤は今、二十年以上前に起こったある事件について捜査を進めている。それは蔵原代議士が現職の財務大臣を務めていた期間で、その頃蔵原はある宗教団体からの献金問題で多くの野党から攻撃されていた。
それについては単なる疑惑を上回ることはなく、蔵原自身も「知らぬ存ぜぬ」という回答で押し切り、その言葉が当時の流行語にもなった程だ。
さて、その事件というのはそういう疑惑の渦中において当の蔵原本人が何者かに生命を狙われているとの憶測がまことしやかに流れ始めた時期と重なる。蔵原またはその秘書達は常に警戒し、私設SPを護衛に配し万全の体制を整えて蔵原の政治活動を支えた。
しかし万難を排して各地で精力的に現地視察や演説等を繰り返していた蔵原の目の前でその悲劇は起こった。地方選挙区の応援演説のため街頭に立った蔵原の背後で一人の男が手製の拳銃を発砲した。その銃弾は代議士の警護に当たっていたボディガードの青年を直撃した。犯人は直ぐに取り押さえられたが、ボディガードの青年は運ばれた先の救急病院で死亡が確認された。
新聞、その他当時の雑誌には犯人と亡くなったボディガードの実名が写真入りで掲載されていた。
奥藤は亡くなったボディガードの方に興味を持った。手元にある資料で判ることは、伊藤良樹という名前と埼玉県浦和市(当時)の出身で二十五歳という年齢だけであった。
奥藤は週刊アルファ担当の記者から数名を選び出し、この伊藤良樹なる人物について調査を進めることを指示した。
十和田彩花の語る物語は第二章を迎えた。ここでは彩花が産まれて以来母娘の暮らしを何かと援助して来た謎の人物を捜索して行く話がメインであった。そしてそこでこれまで知ることの無かった父の話にも到達することになる。
母の告別式の時、突然現れた初老の男から、預かり物として、少し厚みのある封筒を手渡された。その中から出て来たものは一通の手紙と預金通帳だった。手紙を開くと達者な毛筆で、母の死を悔やみ、これまでの苦労を労う言葉が並び、今後の彩花の幸福と活躍を祈るとともに、これからも今まで通り、必要に応じて援助の手を差し伸べると綴られていた。
だからと言って、それで有難いと納得して、何も知らないまま生活して行く気にはなれなかった。封筒を手渡されたその時は、突然のことで訳が分からず呆然と去って行く初老の男を呼び止めもせず見送ってしまった。後になってそれを後悔した。その手紙の主、預金の作成者、そして十和田家との関係、そこまで援助すること、何故に陰なる存在に徹するのか、それを知りたかった。
手掛かりはその封筒を届けに来た人物のみ、その風貌はぼんやりと記憶しているものの、封筒の中の手紙にはどこにも連絡先や名前の類は記入されていなかった。
そこで思いついたのが、預金通帳が発行された銀行の支店に出向き、口座開設者が誰であるかを尋ねることだった。本来なら本人でない限り預金口座を作成することは出来ないはずだ。自分が十和田彩花本人であることを証明し、事情を伝えてみたものの、なかなか要領を得る答えを訊きだせなかった。
明確な返答を得るまで彩花は何度も銀行に赴いた。最初は支店長、次には本店から常務取締役までが姿を見せた。しかし、ある事情でお話することが出来ないとその役員はまるで何かの文書を朗読するみたいに述べるのみだった。
そこで彼女は今後、知人でもある高明な弁護士を立てて交渉すると宣言をしてその場を立ち去った。実はこれは単なる虚勢であり、知り合いに高明な弁護士など居なかった。
その一週間後、彩花の元へ銀行本部から、日時の指定があり、本店までお越し下さいとの連絡が入った。
指定された当日、銀行本店の頭取室にて会談は行われた。そこには銀行関係者と共に初老の男性が同席していた。それはおそらくあの時封筒を持って来た人物に違いない。その人は自分を代理人であると述べた。
しかし、その時の会談で彩花は自身の父と母の物語、そして陰なる援助者について知ることになる。彼女はその援助者を自身の父ではないかと僅かな期待を抱いていたのだが、事実はそうではなかった。
だが決してその話に悲観はしなかった。彩花はそこで初老の男にその援助者による陰なる援助は短大を卒業する迄で終わりにして欲しいことを願い出た。
初老の男はただ一言「お伝え致します」と小さな声で呟いて頭を下げた。
やがて短大を卒業した彼女はあるファッションデザイナーの下でアシスタントとして修行を始めることになる。そのデザイナーの先生は東京に事務所を構えていたので、それを機に家を離れ上京することになる。
卒業と同時に社会人としての一員となった彩花は援助者からの庇護を打ち切りにして、これからの人生は自分自身で切り開いて行こうと心に決めた。
ここからが独り立ちした十和田彩花の新しい人生の始まりとなる。それは今から約八年前、彩花二十歳の春であった
そこまでが第二章である。
古賀は彩花の物語の半分を文章として整え、パソコンに入力する作業をひたすら続けた。この先の展開を週刊誌などの報道で知っている事実と照らし合わせて推測してみると、妙にそわそわして胸が昂まるのを感じた。人の一生はそれだけで一本の大河小説である。まさにそんな展開だ。
かつてN賞を受賞し、作家として野望に燃えていた過去が胸の内に沸々と湧き上がる。古賀はこの小説執筆に確かな手応えを感じていた。もう一度、作家としてやれて行けるかも知れない。文章を紡いで行く内に、そんな気持ちが風のように心の中を吹き始めた。けれども先ずはこの作品を無事に完了させることが第一である。まだまだ小説の出版に漕ぎ着けるまでには、しなければいけない作業はたくさんある。作品が発表されれば、世間の風評とも闘わなければいけないだろう。それにはしたたかな強さが必要だ。
したたかな強さ。
そうだ、古賀が初めて十和田彩花に出会い、それ以後ずっと感じていたのは、美しさの内面に秘めたしたたかな強さであった。常に彼女からは凛とした強さを感じる。それは容姿や佇まいだけではなく、人としての強さ、オーラとでも呼ぶのか、それは時として近寄り難いほどのバリアをも張る。その刹那は多少の恐怖さえ感じてしまうことがある。年長者である古賀が歳下の彩花にそんな畏怖を感じてしまうのは、不思議でもあるが必然なのかも知れない。彼女の語る物語に一番興味を持っているのは当の古賀自身であることに彼は気付いた。
その頃、逢阪遥人のマンションの郵便受けに無記名の四角い封書が紛れ込まれていた。切手が貼られていないところを見ると誰かが直接投函したようだ。
逢阪は誰かのイタズラかと思いながらもその封筒をテーブルの上に置いて、暫くそのままにしていた。
週刊アルファにて世間の目に晒された落ちぶれた作家の姿は、一時的に逢阪に打撃を与えたが、それほど長くは人々の話題には上がらなかった。ネット上の評判でさえも当初は嗤い者として扱われたが、時が経つ内に同情する声も上がり始めた。
そもそも逢阪は文学作家である。これまでにも破天荒な作家はたくさんいる。むしろその荒んだ生活の中からより良い文学作品が生まれるとの意見も少なくない。ネットの掲示板の中には、今まで以上に興味を持った、これからの作品に期待したいとの書き込みもいくつか見られた。これは逢阪に勇気を与えた。
イケメンで好青年として頻繁にメディアに登場するタレント作家、それがA賞受賞するまでの逢阪遥人であった。だが中にはそれを嫌う文学愛好者もいた。
今や逢阪は酒に溺れた生活破綻者である。今後は作品で勝負するしかない。文学者としてはそれが真っ当なことではないか、そう思うようになった。
そんな訳で、逢阪の生活は再び、酒浸りの日々に戻りつつあったが、心の奥で次作の作品の構想を密かに練っていた。毎日の生活に活気を取り戻し、楽しい日々を送れるようになると思われた。
そんな時、ふと思いついてテーブルの上に投げ出してあった無記名の封書を覗き込んだ。徐に手に取って中身を取り出してみる。そこには一枚の紙切れが入っていて、無機質なワープロ文字でこんな風に書かれていた。
『落ちぶれたA賞作家の写真を盗撮して週刊アルファに売ったのは、推理作家の杉下治郎』
13話
杉下治郎はいずれにしても良い気分にはなれなかった。新作で出した推理小説の売れ行きは芳しくなかったし、次の作品の依頼も途絶えていた。尤も新しい作品を書くにもさっぱりネタ切れで一行も筆は進まずにいた。
腹いせに売り込んだ十和田彩花のスキャンダル騒動も本人は雲隠れしていないし、相手として浮上した有名人達も事務所や協会の圧力でもあるのか、ワイドショーでも最近は取り上げられなくなった。
唯一、逢阪遥人が婚約を解消したことだけが胸のすく思いであった。それに当の逢阪本人と新宿のバー『BUZZ』で偶然に出会ったのは幸運だった。向こうはこちらを知らないだろうから、何度か見かける内にちょっとした会話を交わすようになった。その頃の逢阪はA賞祝賀会で見た時とは打って変わってかなりやさぐれていた。スキャンダル騒動はかなりのダメージを与えたようで酒を浴びるように呑んではクダを撒いている場面を見ると、いい気味だと内心ほくそ笑んだ。
何度か出会う内にそこそこ親しくなって、こちらも得意の話術で酒場の楽しさを味合わせてどんどん深みに嵌め込んでやろうと思った。案の定、逢阪は杉下の前でも呑んだくれ醜態を曝け出した。マスターがジローと呼びかけるのを聞いて名前を知られてしまったのは予定外ではあったが、まあいいだろう、ここでは誰も出会う人間の身元調査などしない。
だから酔い潰れてぐだぐだしている逢阪の写真をスマホで盗み撮りするのは、簡単なことだった。
それをまた週刊アルファの奥藤に売り付けに行ったのだが、前回のスキャンダルネタほどは高い値で買ってもらえなかった。
それは仕方ない。まあ良い。杉下は逢阪が世間的にも落ちぶれてしまうところを見て楽しみたいと思っていたのだ。それは一時的には効果があった。
だが、だんだんと世間は落ちぶれた逢阪に同情するようになって文学者としての彼を支持するような声が多くなって来た。これは計算外であり、杉下にとっては不愉快な現象であった。
それで気を取り直したのかどうか知らないが、風の噂で聞くところによると、以前より明るく楽しそうにしているという。
それが面白くなかった。
逢阪は婚約破棄したとはいえ、元恋人であった十和田彩花を杉下から奪った張本人である。しかも作家としての才能もかなりの隔たりがある。
執念深い杉下としてはなんとかもう一度策を練って隙あらば逢阪を地獄の底に突き落としたいと心底思っていた。そのためには信頼され心置きなく何でも話せる呑み仲間という立場を維持しておきたい。いずれいつか何らかの形でボロを出す時が来る。それまでは、当面良い気分にはなれないけれども、その時が来るのをじっと待つしかない。おそらくその内、また『BUZZ』にも顔を見せるだろう。その時を待とう。
ミステリー作家というのは綿密な構成と伏線を張り巡らして作品を構築するものだ。探偵が犯人を追い詰めるのも緻密な推理を駆使した上で成り立つ。下手に根拠のないことを書いてしまえば間違いを指摘されたり、時にはアンフェアだとも言われたりする。前に誰かが書いたトリックなど使おうものなら、何と言われてしまうか、たまったものじゃない。それだけの苦労を重ね苦心して作品を書いているんだ。
世の文学者気取りの輩ども、よく聞け、何の変わり映えのない日常をたらたらと訳の分からない文章で埋め尽くし、何をか言わんばかりにやれ行間を読めだの、読後の世界観を味わえなど、いい加減なことを言うな。文学などくそくらえだ。まやかしだ。よく聞け、行間などには何もない。そこにあるのは無地の空白だ。頭を使え、頭を!
と、いつもこんな調子になる。
杉下は文学作品を読み解く能力を持ち合わせてはいなかった。
その封筒から出した用紙に書かれた名前を見ても逢阪遥人には何も思い当たる人物の顔が浮かんで来なかった。
もう一度その文書を見てみる。
『落ちぶれたA賞作家の写真を盗撮して週刊アルファに売ったのは、推理作家の杉下治郎』
落ちぶれたA賞作家というのは、多分、自分のことのような気がする。しかし、今は落ちぶれたとは思っていない。むしろ本物の文学者に近付いた気がして箔がついたかと気を良くしていたくらいだ。
だが週刊アルファに盗撮写真を売り付けたという部分は引っかかる。それが推理作家の杉下治郎という。誰だろう?
ネット検索してみたら確かに推理作家として数冊のミステリーらしき作品を出版している。
全く聞き覚えのない無名の作家らしい。写真さえ出て来ないとなるともうそれ以上検索のしようが無い。
その文書自体が単なるイタズラの可能性もある。
逢阪はその文書を封筒ごと丸めてゴミ箱にポイっと捨ててしまった。
それから暫くはああでもないこうでもないと次回作の構想を考え込んでいた。テーマがなかなか思い付かずにいたが、そうだ文学者は自分の日常を作品に昇華させるのが一番だと、最近の出来事などを寝転びながらうつらうつらとぼんやり考えていた。
その時、ハッと閃いた。待てよ。逢阪は再び這っていってゴミ箱の中にある丸めて捨てた封筒と文書を見た。封筒は白紙なので必要ない、文書の方だけをもう一度取り出す。
杉下治郎、『すぎした』という苗字には心当たりは無いが、治郎? 逢阪は迂闊にもこれを『はるお』と読んでしまっていた。いや、改めて見てみると、どう見てもこれは『じろう』じゃないか。
『BUZZ』で呑んだくれてる写真を撮ったのが治郎? 『BUZZ』と治郎、じろう、ジロウ、ジロー、そこまで繰り返して、やっとジローの顔を思い浮かべた。
いや、まさか、あのジローが推理作家の杉下治郎だなんて、嘘だろ、とてもそんな風には見えない。それにそんな話を一言も聞いたことはない。
いや、しかし、『BUZZ』では誰もその人のプライベートには触れないのが暗黙のルールだ。
しかもジローには逢阪の酔い潰れた写真を撮る機会はたくさん有った。何故今までそれに気が付かなかったのか、けれども、まさか。
ええ! あのジローが!
逢阪は再び文書を顔の前に広げ、目を見張った。
十和田彩花が語る物語は第三章も終盤に入っていた。
ファッションデザイナーに弟子入りした彩花は主にドラマや映画で使われる衣装などのデザイン及び製作などに携わった。
事務所は個人事務所であったが、大手のプロダクションとも交流があり、仕事は絶えず忙しかった。
彩花は先生の下でアシスタントとして毎日遅くまで仕事に追われた。特に先生に気に入られた彩花は何度もドラマや映画の撮影現場にも連れて行かれて、その場で衣装の手直しや採寸などもおこなった。
そんな事が一年も続けば、彩花の美貌が誰の目にもとまる。
仕事にも少し余裕ができ始めた頃には、現場の人達とも気軽に会話を交わすようになった。
やがて誰彼ともなく食事やお酒の席などへお誘いの声が掛かる。
だが、そう簡単に誘いに乗って出掛ける訳にはいかない。修行中の身で現場で出会った俳優達と遊びに行ったりするのは絶対に許されない。先生からもそう教えられていた。もし、そんなことでトラブルを起こしてしまったらクビどころでは済まないよと釘を刺された。
もちろん彩花にもそんな気持ちは寸分も無かった。
だが、あるとき、某大御所俳優が着る衣装の仮縫いをした時、まち針を取り忘れて、知らずにそれを着ようとした俳優を怒らせてしまった。
その日の予定を全部キャンセルしてホテルに帰ってしまった大御所は、自分の部屋にミスをした彩花本人がひとりで謝罪に来ることを要求した。
それを伝え聞いた時には彩花も青くなって震えたという。
さすがにそれは先生が間に入って話をつけ、大御所俳優もようよう腹に納めることとして、何とかことなきを得た。けれどそこで先生と大御所俳優との間でどのようなやり取りがあったのか、彩花は知らない。噂によると相当な屈辱を味わったのではないかということだったが、先生は頑としてそれについて一言も口を割らなかった。
たったひとつの小さなミスが命取りになる。そのことを知った彩花は、それからどんな仕事も完璧にこなすようになった。
そんな彩花が夢中になるほどの恋をしてしまうとは、そのとき本人でさえも予期していなかった。
14話
彩花が恋した相手は歳上の中堅俳優だった。清々しい爽やかな印象でお茶の間でも好感度の高いスターだった。きっかけは他愛もない撮影の打ち上げの時に渡されたメモに携帯番号が書かれてあった。
戸惑いながらも最初は電話で挨拶をしたり近況を語り合う程度だった。それがそのうちラインに代わり、やり取りの頻度は増して行った。
もう現場で一緒に仕事をする期間は終えていたので、彩花も比較的気軽に考え、休日に軽くランチに誘われた時は、夢見心地で浮かれ気分で出掛けて行った。それが恋の始まりだった。楽しい恋の期間は半年ほど続いた。もうその頃にはキスもして、ひとつのベッドでお互いの身体を求め合ったりしていたものだ。
だが、ある日、ふとしたことで相手がすでに結婚していることを他の誰かから聞かされた。
激しく動揺した。彼に確認すると、平然とした顔で、なんだ知らなかったの? と、応えられた。
結局、それがきっかけで彩花の内部から何かが弾け飛んだ。その俳優ともそれから暫く割り切った交際をして、そのうち、彩花の方にもっと素敵な若いタレントが現れ、彩花は最初の恋人を振った。
ちょうどその頃、先生が引退を発表し、それを機に彩花はフリーのファッションデザイナーとして活動を始めることになった。仕事は先生からの引き継ぎだったので、それほど苦労もせず、継続してたくさん舞い込んだ。それは彩花の才能でもあり、またその美貌のせいでもあった。
そこから先の彩花は恋多き女としていろんな世界を渡り歩いた。それはまるでこれまで抑えつけられていた欲望が一気に噴出したかのように彩花の生活はどんどんと社交に満ちた華やかなものへと変貌して行った。交際相手は、アイドル、歌手、プロゴルファー、野球選手、サッカー選手などと様々に入れ替わった。だが、彩花から声を掛けたことは一度も無い。全て最初のきっかけは、相手からであり、彼女は差し伸べられた手を掴んだだけだ。その中にはやはりすでに結婚している男も少なからずいたようだ。また倒錯した性癖を持っている者も多数いた。緊縛趣味やアナルフェチ、野外露出に幼児退行癖、いっさい手出しはせず卑猥なポーズだけひたすらさせる者とか、一皮剥けばアブノーマルな正体を曝け出す。テレビやマスコミに流されるイメージとは随分かけ離れた者達ばかり。虚飾に満ちたエゴイスト達の集団、そんな世界だった。
そのためか彩花の恋愛はいつも長続きしなかった。大抵三ヶ月から半年経つと彼女の方から別れを切り出す。たまに付き纏われる場合もあったが、上手く乗り切った。
そしてある出版関係の縁で杉下治郎という売れない推理作家と出会う。その話が次のラストの第四章になると古賀は告げられた。
「杉下治郎は実名で書くのですか?」
一瞬戸惑って古賀は尋ねた。これまで交際相手は全てイニシャル、もしくは仮名を使って筆記していた。
「そうしてください」
彩花は抑揚のない声で答えた。
週刊アルファの奥藤は黙って部下の記者が調査した報告を聴いていた。銃弾に撃たれて亡くなった伊藤良樹の件である。
埼玉県浦和市は現在さいたま市に名前が変わっている。二十年以上の歳月が経ち、しかも伊藤などというありふれた姓。また当時の発砲事件の詳細を知る人も少なく、捜査は困難を極めたという。
さらに当時警護を務めた警備会社も今はもうすでに無く、経営者、社員などもまるで見当がつかない。
しかし、やがてひとつの小さな手掛かりから少しずつ伊藤良樹の生前の様子が判明して来るのである。誰かが言っているように、手間さえ惜しまなければ大抵のことはわかるものなのだ。
それは卒業生名簿での確認。ご存知のように個人情報保護法が出来てからなかなかそういうものは簡単に見せては貰えない。けれど、伊藤良樹の年齢と住んでいた地区がある程度限定されるので、そこにある小学校、中学校、もしくは高校などをしらみつぶしに周り、年齢から割り出した卒業生名簿の中に亡くなった伊藤良樹の名前が有るか無いか、適当な理由をでっち上げ、出版社の名前も明らかにし、身分証明書を見せて、それだけをひたすら訊いて回った。
そして見つけた母校。U中学校という。そしてその伊藤家が今でも有るかと尋ねると、もう今はないとの返事。それでも元有った家はどの辺りかを訊き出し、その周辺に向かう。
今は大きな駐車場があり、前にはコンビニがある。比較的新しい。記者は周辺にあるなるべく古い家を選び、昔この辺りに住んでいたと思われる伊藤家をご存知ないかと聞いて回った。
ヒットしたのは七件目、まさにラッキーセブンだ。
確かに伊藤家はかつて存在し、良樹という人がいた。そしてその事件当時のことも記憶していると言う。しかし、そこの宅の住人には良樹と同年代の者はいない。だからそれ以上の詳しいことは分からない。そこで伊藤良樹と同年代の人がこの辺りに住んでいないかと尋ねてみると、親切にもあれこれ電話までかけて調べてくれた。
そして紹介されたお宅を訪ねる。大きな古いお屋敷だ。玄関に出られたのは五十代半ば頃に見える男性。突然の訪問を詫びて当たり障りのない簡単な事情を話して、古い事件を調べていると説明した。
するとその男性は伊藤良樹と同級生だと判明。まさについてる。しかし、付き合いはそれほど無く、何も知らないという。そこで誰か彼と親しくしていた人を知らないかと尋ねてみる。そこで名前のあがったクラスメイトに連絡を取ってもらった。
そして伊藤良樹と仲良くしていた同級生Mにたどり着いた。
Mさんの当時の思い出話は果てしなく長く続くので大部分を割愛して重要なところだけ切り取ると、伊藤良樹は中学を出た後、隣町の東高に進み、W大に進学したという。高校大学と陸上をやっていたことも有り、卒業して直ぐに警護会社にボディガードとして採用された。Mさんとは就職後もたまに会ってドライブやカラオケ、スキーなどに出掛けて遊んだ仲だという。
さて、ここからが大事な話になるのだが、当時良樹には『さえちゃん』という恋人がいて結婚の約束もしていたのではないかとMさんは話した。
その『さえちゃん』について詳しく尋ねてみると、Mさんは記憶の隅を探るように、何だっけかな、東北の方出身で苗字が確か、あちらの方の湖と同じで、猪苗代? 違うな。田沢湖かな? 惜しいな、少し近付いて来たような気がする、もう一つ何か無かった? 湖。
記者は答える。十和田湖とか?
Mさんの記憶の中で何かが弾けてパッと目を開いた。
そうだ! それ、思い出した。十和田冴子!
かくて記者は東北地方に飛ぶことになった。
15話
十和田彩花の物語は最終の第四章に入った。
彩花が出版関係の会社とも親しくなり始めたのはファッションだけでなく、様々な分野のデザインにまつわる仕事を引き受けることを選んだからである。そのひとつが新刊本のブックカバーのデザインであり、概ね好評を博していた。
仕事は順調に増えたが、忙しさも増した。スマホはひとつでは事足らなくなって二つ三つと増えて行った。それらを使い分け、頻繁に関係者との打ち合わせや連絡を取り合った。無論、プライベートのお誘いなどもそこにはまり込む。
ある日、ミステリー関連の作家達の集まるパーティーがあるからと誘いを受けた彩花は、興味本位でその会場に出向いた。そこで出会ったのが杉下治郎だった。
彩花は推理作家としての杉下治郎の名前を知らずにいたが、相手は話題が豊富で話の組み立てが上手く、楽しい雰囲気で会話をリードした。風貌はあまりパッとしないが、目付きが鋭く男っぽいワイルドな印象を受けた。ミステリーでも少しハードボイルド系の作品を書きそうなイメージだった。
その日から、偶然か故意によるものなのか判別し難いが、何かと彩花が出向く先々に杉下が姿を現した。
そんなことが続くうちに、食事に誘われたりお酒に誘われたりし出した。見た目はともかく、その話口調や声のトーンには惹かれ、何度目かのお誘いに応じて彩花はディナーを共にすることにした。
決して恋愛感情を感じていた訳ではないが、杉下の巧みな話術に彩花は次第にリラックスを覚え、何度かお酒の相手にも付き合った。彼はお酒が好きだった。
その夜、彩花は仕事のトラブルなどがあり、ストレスを抱えていた。そんな時に杉下の語る軽い作り話のようなクスリと笑えるエピソードなどに心を癒されてしまった。飲み過ぎたお酒に酔ったせいもあり、肩に手を回した杉下に軽く身を預けてしまった。
そこからはいつものよくある恋愛パターン、連れられて行ったラブホテルで彩花は杉下に抱かれた。杉下はセックスにおいて女性の扱いが上手かった。
優しく撫でるように触れたと思ったら、激しく息が出来ないほどの力で抱き締める。焦らしたり激しくしたり不意をついたり気を揉ませたり、あらゆるテクニックを駆使する。特に全身を隈なく愛撫する微細なる舌先の動き、それらは女を今まで感じたことのない絶頂へと導いた。
これまでいろんなタイプの男性と交際したものだが、女の悦ばせ方については彼がナンバーワンだ。
そしていろんなパターンを持っているので、その日その時で体位を変えたり、あの手この手を使う。何かにつけてマメで相手を飽きさせないそういう種類の男だ。
けれども彩花は杉下に対し、恋愛感情は芽生えなかった。単に彼から与えられる性行為の虜になってしまっただけだった。
その感情は自慰行為と同じで、仕事や日常の煩わしさから自分を解放するのに上手く作用した。
そのため彩花は定期的に杉下と会い、ストレス解消のための性行為を繰り返した。
しかし、杉下の方ではそんな関係に少々の苛立ちを感じていた。とにかく彩花は仕事が多忙過ぎて、二人でゆっくりとどこへも行けない。会っている最中も盛んにスマホでやり取りが入り、得意の話も、腰を折られることばかりで欲求不満が募った。夕食を共にし、ホテルで一夜を過ごしセックスする。そして朝になればさっさと別れる。それだけの関係に不満を覚え始めた。
杉下が隙をついて彩花のスマホの内部を写し取ったり、行動を監視し、尾行などを繰り返していた事に彼女は全然気が付いていなかった。
そんなある日、別の出版社の宴席で新進気鋭の文学作家の逢阪遥人と彩花は出会う。
逢阪は杉下と違って清潔感に溢れた好青年で顔立ちも整っている。まさに彩花の好みのタイプの男性だった。
A賞候補にノミネートされた時、嬉しさも手伝って、うっかり杉下の前で逢阪遥人は凄いと褒め讃えてしまったことがある。
その時の杉下の様子。みるみるうちに顔を真っ赤にさせ、まるで人が変わったように訳の分からないことを叫び出し、手当たり次第にそこらのものを投げつけた。
いきなり彩花の胸ぐらを掴むと力任せに顔面を殴りつけた。咄嗟に顔を背け手で庇ったが、彩花の身体は部屋の隅まで吹っ飛んだ。
杉下は尚も床に倒れた彩花に容赦ない罵声を浴びせた。俺はセフレじゃねえ、お前のような淫らな女にはいつか天罰が降りるなどと、全ての不満を爆発させて一方的に怒鳴り散らした。
その日、彩花は杉下と別れる決意をした。実際には興奮している状態の時にそれを持ち出すとまずいと判断し、正式に別れを告げたのは後日のことである。
ちょうどその頃と時を同じくして逢阪遥人のA賞受賞が決定した。関係者と共に祝杯をあげるメンバーの中に彩花も加わっていた。
逢阪と関係を持ったのはその日の夜のことだった。
翌朝、逢阪は彩花にプロポーズして、彼女もそれを受託した。
数日後、婚約指輪を持って現れた逢阪は彩花に婚約者としてA賞受賞祝賀会に参加して欲しいと懇願した。
もちろん彩花にはそれを断る意思など持ち合わせていなかった。
そこまでの話を聞き終え、休憩のためペンを置いた古賀祐二は静かにため息を吐いた。場所はいつものホテルの一室である。
「波瀾万丈な人生だね」率直な感想だった。
「驚いたでしょう?」
「いや、一応アルファ砲なども読んでいたからね、ある程度のことは覚悟していたよ。でも何て言うか、最初に感じたイメージとは違うような気がするな」
「そうですか、それは、どんな?」
「うん、なんて言うか、マスコミではあなたのことを魔性の女とか稀代の悪女呼ばわりまですることもあった。でも実際、あなたの真実の物語に触れた者としては、そうは思えない」
「そうでしょうか、ありがとうございます。でも悪女と言われても仕方のない部分はあるのです」
「これまで数十回あなたとこうして二人きりで過ごさせてもらって、私のあなたへの印象は、運命に翻弄されながら、いや、それは幸運もあったとは思います。正直に言うと、普通は陰の援助者などという者は存在しないから。それはそんな中で懸命に生きて来た結果だと思えるんです。運を持っていたというか……」
彩花は黙って古賀の話を聞いていた。
「持って生まれた美貌は神があなたに贈り物をしてくれたのでしょう、きっと。総体的に言うとあなたはいつもついている。もちろんそれぞれの場所で苦労はしたのでしょうが、才能と言うのか、不幸な身の上だったにも関わらず、今は成功して生活は上手く行ってる。恋愛に関しては上手く行ってないのかもしれませんが、一般の人が経験しないような事柄や世界を体験して来た。それはある意味羨ましく思います」
彩花は何を思っているのか、小さく微笑を浮かべた。
「ところで、物語はここで終わるのでしょうか? これから先のことは私も多少知ってはおりますが、どのような結末を持って来ますか?」
少し考えた末、彩花はこう答えた。
「結末とタイトルは古賀さんにお任せします。それから出来れば、書籍が完成した後、ひとつだけお願いしたいことがあるのです」
「ええ、何でしょう?」
「わたくしと少しドライブに付き合ってもらえないでしょうか?」
古賀は多少、面食らった。
「それは別に構いませんが、だけど……」
「もちろん、他人には見られないよう極力努力は致します」
「そうですか、で、行き先は遠くですか?」
「それほど遠くではありません」
「どのあたりですか?」
「さいたま市です」
16話
逢阪遥人は深い困惑の中で喘いでいた。
『落ちぶれたA賞作家の写真を盗撮して週刊アルファに売ったのは、推理作家の杉下治郎』そんな匿名の密告書を受け取ってから三日経つ。
ネット上では見つけられなかった杉下の写真をK社の編集者に頼み、作者の写真付きの著作を送って貰った。『憎しみの果て』というそのミステリー書籍は逢阪の知らないものだった。本文はともかく巻末の著書写真を見る。それは知っているジローよりは随分こざっぱりして若かった。だが、明らかにそれは『BUZZ』で見かけるジローに間違いない。
それでもなお、その密告文を信じる気にはなれなかった。そもそもジローはハル(そこでの逢阪の愛称)のことを逢阪だとは知らないはずだ。それに外見は変装してかなり変えている。マスコミに出回っている逢阪と同一人物だとは誰も気が付かないはず。もちろん週刊誌に載ったように二つの写真を並べて見れば判るかも知れないが、新宿の小さなバーで呑んだくれてる汚い姿の男を逢阪だと判かる者はいない。あのマスターだって気付いて無いと自信を持って言える。逢阪本人を以前から知ってでもいない限り、そんな事に気が付く者はいないだろう。
以前から知っている? ジローが杉下治郎なら同じ作家仲間ということである。これまでパーティや祝賀会などで出会った作家の顔と名前を記憶しているだけ引っ張り出してみたが、そこに杉下治郎なる人物は現れて来ない。
半信半疑な状態で、それでも夜になるとふらふら出歩き、逢阪はいつもの調子で久しぶりに『BUZZ』の扉を開けた。
いつもの一番奥のカウンター席にジローはいた。
マスターの「いらっしゃいませ」の声がかかる。少し躊躇していると、ジローの方からハルを見て、少し驚いた顔で、「よぉ、久しぶり、最近、来ないからどうしたかと思ってたぜ」といつもの調子で声がかかる。逢阪もハルとしていつものテーブル席に着く。ほぼジローの真後ろ辺りだ。
暫くはお互い一人で好きな酒を呑む。ジローはいつもの水割りかなんかを呑んでいる。つまみはピスタチオとサラミだ。
ハルも好みのカクテルを口にした。つまみはベーコンチーズだ。
他の客も数人ちらほらいた。リラックスするには良い雰囲気だ。気取る必要もない。ジローもハルもそれぞれ自分の世界でお酒を楽しんだ。
ハルは何かの拍子にジローがスマホを手にする動きを見た。少し背を伸ばしてその手元を見る。ロックを解除するその指先の動きを記憶する。何かのニュース画像みたいなものをチェックした後、ジローはカウンターの上にスマホを置いた。
店内に流れる洋楽に耳を傾けてまた時間が過ぎる。やがてジローはトイレに立つ。カウンターの上にはそのままスマホが置かれている。マスターは向こうの端で客と何やら話しながらカクテルを作っている。
ハルは何気ない動きでカウンターに移動する。そしてさり気なくジローのスマホを手にする。記憶したロック解除のナンバーをタッチする。
保存した画像を開き、中身を確認し、スライドさせて行く。様々なネットの拾い画像やたまに風景写真が入る。それらを見ながらさらにスライドさせて行く。そして、
見つけた!
週刊誌に掲載されていたハルが酔い潰れた画像だ。さらに以前の画像をスライドさせてみる。やがてそこに十和田彩花の画像がいくつか現れる。どれも皆盗撮したものだ。街を歩く後ろ姿。タクシーに乗り込む瞬間、ホテルの室内、など。そして週刊アルファに掲載された写真の元画像をそこに見出した。
ハルはスマホを元の位置に置いて、テーブル席に戻る。そんな姿をチラリとマスターは横目で見ていた。
その数秒後、席に戻ったジローは何も知らない。マスターはチラリと彼を見る。
何食わぬ顔でハルはそうそうに会計を済ませ、いつもより早い目に『BUZZ』を出た。
あの密告文書に間違いは無かった。彩花も逢阪の件も盗撮したのはジローこと杉下治郎だったのだ。
それほど酔ってもいないのに頭がくらくらした。
この先、どうするかはその時点では何も考えていなかった。
週刊アルファの記者は十和田湖のほとりに来ていた。ネットで調べた情報によると十和田姓は全国で160人程いるだけであり、その多くは岩手県、もしくは北海道に居住する。もちろんその周辺、都会や別の地方に移住した家族も多いだろうが、由来は十和田湖から来ているとの説もある。
とにかく記者はその周辺に住む十和田姓の家庭を探すことを始めた。ここではその経緯、道程について詳しく書き記すことは省略する。とにかく、記者はいろいろ探り回ったあげく、十和田冴子の実家と思われる家屋を探し当てた。冴子の年齢は現在ならば、五十を少し過ぎたあたりになる。ただその家に住んでいるとは限らない。
果たしてその家屋は現存し、果たせるかな表札には『十和田』の文字が見てとれた。
呼び鈴を押しても応答がない。玄関のドアを叩いて、その名を呼びかけた。それでも返事はない。留守か空き家か、判断はつかない。平日の昼間である。
そこで隣家を数件訪ねてみる。結構な田舎だ、どの家も相当に古く件数も多くはない。誰かがいれば十和田家について聞き出せる可能性は大だ。
何軒か回って聞き出した情報は、冴子は数年前に病気で亡くなったこと、今は冴子の従兄弟にあたる中年男性が一人暮らしをしていて、夜にならないと帰らないという。
冴子が既に故人となっていて記者は落胆したが、それでも従兄弟から何か話が聞ければと思った。
夜になり再び十和田家を訪ねた。出て来たのは四十代後半頃の真面目そうな男性だった。
冴子が亡くなったのは今から約十年程前の事で、娘(彩花)が東京に出て行ったため、空家になった家屋を従兄弟の父親が引き取り、現在はその従兄弟が一人で住んでいる状況であるとのことだ。
そこで記者は、その従兄弟から冴子について知っている限りのことを聞き出した。
週刊アルファの発行責任者の奥藤は記者を前にし別室においてその話に耳を傾けた。
記者が調査した十和田冴子に関する回答は次のような物であった。
その地で過ごした幼少期や少女期の頃については割愛する。話は冴子が東京のW大に進学してからのことに絞られる。
そこで冴子は二つ年上の伊藤良樹と出会い、交際を始めた。細かな経緯までは分からない。全ては冴子の従兄弟が聞き知っている情報だけなのだ。
その交際は大学を卒業後も続いたとみえ、冴子は都内の会社に就職する。それより一足先に社会人になった伊藤は関東地方を拠点とする警護会社で主に政府要人などを警護するボディガードとして勤務していた。
その伊藤がテロリストの銃弾に撃たれた時、冴子は既に身籠もっていた。二人はまもなく入籍することを予定していた。
当時は別の市で暮らしていたその従兄弟には、そこから先のことはあまり詳しくは知らないがと前置きした。しかし、時折父親達が話すのを小耳に挟んだことがあるという。その事柄から推測すると、冴子は一人で出産し、仕事をやめ、この屋敷に戻って来て子供を育てたという。その当時は冴子の両親がまだこの屋敷に住んでいたからだ。生まれた子供は女の子とまでは聞いたが、名前は覚えていない。それから数年の後、冴子の父親が死んで、そのまた一年後くらいに母親も死んだ。この屋敷に残ったのは冴子とまだ幼い娘の二人きりになった。
けれど、冴子のそれからの生活については、保障があるから大丈夫だと話すのを聞いた覚えがあると、その従兄弟は言った。
その保障という言葉が何を意味するかは具体的には分からないものの、総合的に判断すると、こんな風に推察出来る。
事件を起こした犯人は蔵原を狙っていた。それは後の裁判でもそう語っている。その銃弾を伊藤良樹が被弾したのだから、つまり、蔵原文三の身代わりとなって彼は生命を絶った。おそらくそれが無ければ、その時、蔵原はテロリストに暗殺されていただろう。
蔵原は亡くなった伊藤青年に内縁の妻が存在し、子供を身籠もっていることを知り、その生活を保障すると約束したのだと考えられる。
そして、十和田冴子の娘は十和田彩花に間違いない。彩花の住むマンションがかつて蔵原の第一秘書をしていた男の名義であることも、それは前後の事実からある程度の推察は出来る。
奥藤はそれが闇で動いた資金でないことを願わずにいられなかったが、そこは調べようがない。
さて、この件をどうするべきか、週刊アルファに美談は似合わない。
熟考する奥藤の携帯アラームがその時、突然鳴り出した。出てみると別の記者からの直電である。
それは衝撃的なニュースだった。
通話ボタンを切った奥藤は前にいる記者にこう伝えた。
逢阪遥人が杉下治郎をナイフで刺したらしい。
17話
その日、新宿のバー『BUZZ』のマスターは朝から妙な胸騒ぎがして落ち着かなかった。その理由はさっぱり分からないのだけれども、なんだか嫌な気分がしていた。
それでも店はオープンさせなくてはならない。そろそろ開店準備に出掛ける時間だ。
店に来る常連客は様々だが、大体それぞれが来る曜日がある程度決まっている。
ハルは気まぐれで、来る時は曜日に関係なく突然現れるタイプだ。
ジローの場合はその逆で、大抵決まった曜日に顔を見せる。火曜と金曜だ。
そして、今日は金曜日。
先日、火曜の夜、ジローが席を外した隙にハルがジローのスマホを手に取り、中味を覗き込んでいた。その表情は、なんというか、言葉では言い表し難い、いつものハルではないやるせない顔つきであった。
マスターは客のプライベートには踏み込まない。それをモットーとしている。だからジローのこともハルのことも何の職業をしているか、また二人に何か関係する事柄があるのか、それは知らない。
ただ二人に共通して思うことは何かの業界に属した人間であるかと察せられる。二人からは何か独特の同じ匂いを感じてしまうのだ。
店内で会話を交わしている雰囲気から察すると店以外での面識は無さそうだ、そう思っていた。
しかし、あの時のハルの顔つき、そして時々見せるジローの鋭い目付きは、二人の間に何か不穏な動きがあったのではないかとそんな予感がしてならない。それは長年この仕事をして来た者の勘である。
勘はあくまで勘であって、それ以上でもそれ以下でもない。下手に先手を打ってこちらから動きを見せるととんでもない失態をしでかす恐れがある。何か起こるまでは静観するのが得策である。
何かあったとしてもマスターとしてやるべきことはひとつ、マスターとしての立場でなすべきことを熟すのみ。それだけだ。
そしていつものように店に向かい、開店準備を始めた。
金曜日、店はそこそこ賑わいを見せた。ジローはいつも現れる時間に姿を現し、指定席であるカウンターの奥の席に腰掛けた。特に変わった様子はない。
その後も特に変わったことは無く、ハルは姿を見せず、時刻は深夜の時間帯になった。『BUZZ』は夜通しやる店ではない。午前を迎えたらそろそろ閉店準備に差し掛かる。
そんな時刻に扉が開いた。入って来たのはハルだった。ジロー以外にもまだ数人の客がテーブル席に座っていた。
ハルの顔はかなり蒼白な色を成していた。
マスターはハッとしたが、狼狽は見せず、「いらっしゃいませ、やけに今夜は遅くですね」と言おうとした。しかし、後半は言葉になったかどうか今となっては定かではない。
ふらふらとジローの元へ向かったハルは、そのまま何事かと立ち上がったジローの真ん前に立った。
そして、懐から何かを取り出すとそれをジローに突き付けた。瞬間ハルの身体が大きく波打つのが見えた。全ては一瞬の出来事だった。
大きく目を見開き、何か言おうとするジローはそのまま壁にもたれた格好でずるずるとその場にしゃがみ込む。
刃渡り二十センチはあるかと思われるナイフがジローの腹部に突き刺さっていた。
あっと思うまもなくジローの着ていたシャツとズボンは真っ赤な血で染まり、床に血溜まりが出来始めていた。ハルは二度三度ナイフを抜いてはまた刺したようだ。その目はいつものハルでは無く、狂人としか思えなかった。
居合わせた客が騒ぎ出して、扉を開けて表通りに何かを叫んだりしたので付近は大騒動になった。
119番と110番に通報したのはマスター自身であった。
ハルはその場に立ち尽くし、床に倒れて激痛に呻くジローの姿をただ茫然と見下ろしていた。ほんの少し唇の端に微笑を浮かべて。
それから後のことは、ただ慌ただしくいろんな人々が入れ替わり立ち替わり動き回りしたので、記憶を整理するのが大変だ。ジローは横たわり救急隊の担架に乗せられ運ばれて行った。ハルは駆け付けた警察官に現行犯逮捕で連行されて行った。
マスターも警察に呼ばれ、ことの経緯について事情聴取を受けて、正直に詳しくありのままを話した。
そのニュースは翌日の午後には各テレビ局で大きく報道された。その時になってマスターは二人がそれぞれ杉下治郎、逢阪遥人という小説家だということを知った。
週刊アルファではこの事件の詳細を大々的に取り上げ、犯罪者へと変わり果てた元A賞作家の転落ぶりを扇情的な記事にして誌面を賑わせた。
一方被害者である杉下治郎については過去のスキャンダルネタの提供元であったことは伏せ、酒場でのトラブルが原因ではないかと推測する程度に留めた。
だが、奥藤は悪事を働いたのは杉下治郎の方であって、逢阪遥人こそ本当の被害者であるとその心中を思いやった。もちろん刑事処罰を受けるのは逢阪であり、罪を犯したことに間違いない。
他人のスキャンダルを盗み撮りし、そのネタを持ち込んだとしても杉下に処罰は求められない。それを記事にして雑誌を売り上げた週刊アルファもまた、処罰を受けるものではない。
殺傷事件にまで発展したことは少ないが、奥藤はこんなことをこれまでには何度か経験して来た。真面目な人ほど、秘密が暴露されると精神状態の抑えが利かなくなるのも知っている。逢阪はその典型的なタイプだ。気の毒に思う。
婚約者のスキャンダルから転落人生の始まりだったのだが、その婚約者・十和田彩花が悪女だったのかと問われると、そうとも言い切れないと彼は思っていた。
逢阪の精神が弱かったとの意見もある。犯罪を犯すに至ったことを考えると確かにそうであろう。十和田彩花はマンションから消え、その後雲隠れしたままだ。こういう仕事をしている限り、杉下と同じように誰に恨みを買い、いつ復讐されるか判らない。
今度の事件は奥藤でさえ、嫌な気分になった。様々な事件やスキャンダルの暴露記事を出す度に、雑誌は販売数を伸ばし、嬉しい気持ちはあるが、どこかでやるせない想いにかられる。
因果な商売であると思う。東北まで記者を走らせて調査したのに十和田彩花の母・冴子の人生は週刊アルファでは記事にしないことを決断した。蔵原代議士との関係も憶測の域を出ない。一万枚にも及んだ写真や画像からも記事にするような決定的な物事は見当たらなかった。全く骨の折れる商売だ。
テレビのニュースを観ながら奥藤はそんなことを思い続けた。
18話
逢阪が事件を起こしてから約二ヶ月が経った。幸運にも杉下は一命を取りとめた。逢阪遥人は殺人者にならずに済んだ。
この先、作家としてやっていけるのかどうかは定かではない。でも、もし彼が次の作品を執筆したのならば、興味を持つ人も少なくないと思う。この出来事を経験したことを文学者してプラスに働かせて欲しいとの声もちらほら見かけたりする。
一方でアルファ出版からこんな新刊小説が出版された。タイトルは『華麗なる女』著者は古賀祐二という。その新刊本の帯には十和田彩花の名前が見られ、それが話題になった。
古賀祐二というのは過去にN賞を受賞したことがある作家で、その後一時は筆を置き、編集者として働いていたという。久しぶりの小説を出版した訳だ。
世間では十和田彩花の名前はまだ忘れ去られていなかった。彼女が一躍、時の人となったのは、権威あるA賞を受賞した逢阪遥人の婚約者として、その麗しく圧倒的な美貌を持って祝賀会に登場し脚光を浴びたところからである。そしてその後、世間を騒がせる一連のスキャンダル報道を巻き起こした当事者として、その名は人々の記憶に深く刻み込まれていた。またファッション業界でも一流デザイナーとして活躍している。
古賀祐二の小説が同名の十和田彩花を主人公として用い、『華麗なる女』というタイトルからも連想されるように、十和田彩花の実話を小説化したものではないかと評判が立ち、各マスコミ、メディアから著者の古賀祐二に質問が殺到した。
だが、いずれの質問に対しても古賀は、この物語はフィクションであるとのことを強調して繰り返した。
だが、そんなことで憶測は止まらない。誰もがそれを実在する十和田彩花の物語として捉えた。それゆえに書籍は売れた。
書籍の中で当時週刊誌やワイドショーで取り上げられた不倫問題や有名人との恋愛沙汰が、小説形式で詳細に書かれ、実名ではなくイニシャル書きされてはいるものの大体あの人だなとの推測が持たれ、読者の興味を誘った。
実際にとある芸能事務所から抗議文が出版社宛に届いたものの、小説は全てフィクションによるもの、と一貫して解答した。
この小説のフィクションノンフィクション論争はある程度繰り返されたが、決定的な要素は何もなく、また登場人物が実在する人物を想起させても、それは水掛け論のようにして徐々に終息して行った。
なお、杉下治郎も実名で登場するが、書籍では逢阪による傷害事件までは触れられておらず、彩花との関係は元々誰も知らず、杉下自身からも抗議は無かった。
それともう一点、噂された蔵原元大臣との関係についても、物語内では彩花との接点は無く、陰の援助者としての存在がそれであろうかと推測されたが、週刊アルファの責任者奥藤の予見通り美談は人の噂に成り難かった。
さて、その日、人目を避けるように古賀祐二は自宅マンションを後にした。深めに帽子を被り、眼鏡を装着し、マスクを着用した。服装は黒っぽい地味目のジャケット姿。肩からは書類入れのような鞄を提げている。
小説が売れたと言っても、古賀自身の顔が世間に広く知れ渡った訳ではなく、どこかの記者につけ回されることも無かった。
ただ万全を期して用心の上に用心を重ねた。メトロを乗り継ぎ都心に回り、タクシーを使い、誰にも尾行されていないことを確認した。
彩花との待ち合わせは以前よくした都内某所の閑散とした小さな駅前だった。改札を出るとすぐに彩花の黒いセダンが停車されているのが見えた。
古賀は近付いて行き、助手席のドアを開けるとシートに身を預けた。彩花は最初に出会った時と同じサングラスをしていた。古賀を見るとニコリと微笑んだ。
「お久しぶり、いろいろ大変でしたね」彩花はそう声掛けた。
「いや、こちらこそあんなにたくさんの謝礼金を振り込んで頂けるとは思っていなくて、正直驚きました」
数日前、書籍が出版された直後に彩花から古賀の口座に多額の謝礼金が振り込まれていた。
「いえ、こちらこそ要らぬ苦労とお世話をお掛けしましたから、あれくらいは当然のことです」
古賀は黙って頷いた。確かに苦労はしたし、出版後のマスコミへの応対も苦心した。だが、やったことに対して後悔は無かった。少なくとも新刊本を出版したことにより、作家としての生き甲斐を見出せた。それに今後の希望が湧いて来たのを感じ、作家としての意欲を再び持ち始めた。これは今回の件が無ければ、沸き起こらなかったはずの消えかけていた炎だった。
それはともかく、セダンは真っ直ぐに延びる国道を快適に走り続けた。
「行き先はさいたま市でしたね」
「そうです」
「それは物語で聞いたあなたのお父さんにまつわる場所ですね」
「はい、その通りです」
「お父さんがお亡くなりになられてから、まもなく三十年になるのではないですか?」
「そうですね。わたくしが産まれる前のことですから」
「そこにはまだ何かが残されているのですか?」
「家はもうありません。ただ、伊藤家のお墓があるだけです」
「それでは今日はお墓参りということですか?」
「そうですね。後ろの座席を見てください」
古賀が振り向くと後部シートにお供え用の白い花束と線香の類が置かれていた。
「なるほど」古賀は頷いた。「でもどうして私と一緒に行こうと思われたのですか?」
少しの間をおいて彩花はこう話した。
「父と言いましても戸籍上の繋がりはありません。あちらのご家族ともお会いしたことは一度も無くて、お墓に行くのも今日が初めてです。けれど……」
「けれど、何ですか?」
「いえ、それはまた後ほど」
「そうですか、分かりました」
「貴方はわたくしの物語の全てを知っている方です。小説はいろんな方が読まれるのでしょうけど、わたくしの口から直接聞いた人は、古賀さんただお一人です」
そう言われてしまうと古賀は照れるしかない。
「光栄です。それでお供をと言う訳ですか」
「ご迷惑で無ければ、傍にいてください」
その言葉は胸に響いた。
「もちろんです」
それからしばらく、二人は黙って風を感じた。
「今回は白いアーチ橋を渡らないのですね」
ややあって愉快そうに古賀はそう呟いた。
「ええ、方向が違いますから」
彩花は澄まして微笑する。
なるほどと心の中で呟いた。
「そうだ。ひとつ聞き忘れていたと思ったことが有ったんです」
「何でしょうか?」
「あなたは短大を卒業すると同時にもうそれからは陰の援助者からの援助は受けないと言ってましたよね」
「はい」
「では、どうして蔵原代議士の元秘書がオーナーになっているマンションに住んでいたのですか? いや、言いたくなければ無理にとは……」
一瞬、余計なことを詮索し過ぎたかと脇の下に汗が滲んだ。
「ああ、そのことですね」彩花はサラリと応えた。
「信じてもらえないかも知れないのですけど、実は全くの偶然なのです」
「偶然ですか? それは本当に?」
「ええ、三年前に賃貸で借りる契約をしたのですが、その時は気が付きませんでした。その頃はデザイナーとしてわたくしも一本立ちしていたし、知人の紹介で決めたのですが、そのことは後から知りました」
「そうですか、確かに、それは信じて貰えそうもない話ですね」
彼女はひそやかに笑った。「もう少しで到着しますよ」
車はさいたま市の郊外へと向かっていた。
見晴らしの良い小高い丘の上にその墓地はあった。案内表を確認して彩花は花と線香を、古賀は水桶を持って、細かい砂利道を小さな音を立てて歩いた。
目的の墓は直ぐに見つかった。綺麗な青空の清々しい日だった。
敷地の中には二つの墓石が並んでいた。一つは古いもの、それには伊藤家之墓と刻印されている。その隣に比較的新しい墓石が建てられていた。その墓石に刻んである文字を見て古賀は少し驚きの表情を見せた。
そこには伊藤良樹の名前とその横に並べて十和田冴子と刻印されている。
「こ、これはあなたが建立されたのですか?」
「ええ、手配は代理の者を通じて業者にお願いしました。写真では確認していましたが、実物を見るのは今日が初めてです」
そうか、後ほどと言ったのはこれの事かと納得した。
花を生け、線香に火を着ける。そして二人して水を注いだ。
墓石の前に跪いて手を合わせて黙祷した。
そして彩花は古賀に、
「古賀さん、あれをお持ちくださいましたか?」と尋ねた。
古賀は肩から提げた鞄を開け一冊の新刊本を取り出した。しっかりと透明のビニールで包んである。
本のタイトル『華麗なる女』の文字が見える。
彩花はそれを有り難そうに受け取ると静かに墓石の前に供えた。
そして再び手を合わせ目を閉じると、胸の中で語りかけた。
ーー今日はお二人にご報告に来ました。わたしは元気にしています。世間の人に言わせるとわたしはしたたかな女であるらしいですーー
古賀はなんだかその場に崇高な気配を感じて、数歩退いて彩花の背後に身を潜めた。その無言の後ろ姿を見ていると、何故だか彼女の心の声が胸に響いて来るように思えた。
ーーでも勇敢だった父と、一人でわたしを育ててくれたお母さんの強さに比べれば、まだまだです。
これまでのわたしの生きて来た道はこの書籍に書かれている通りです。
けれど、それはまだほんの第一部にしか過ぎません。
これからも、わたしはわたしらしく、したたかに生きて行こうと思っています。だから、心配はしないでくださいーー
墓石に向かって蹲る彩花の背中は今までになく小さく見えた。
これが彼女本来の姿なのであろう。
ふと空を見上げると、大空が果てしなく広がっている。
宇宙はどこまでも続いている。
青空の中をゆうゆうと白い雲は流れていた。
この先、どう生きるか、彼はそこに無限の未来を感じて立ち尽くした。失ったと思っていた可能性を教えてもらった気がする。
再び彩花に目を戻した古賀は、そっとその肩に右手を添えた。
エピローグ
帰り道、古賀は何度か彩花に尋ねてみようとした。
彼女は以前、この自伝的小説を出版するのは復讐のためだと言った。
それについて、その企みは成功したのかどうか、それを訊いてみたかった。
復讐の相手は杉下だったのか、週刊アルファだったのか、それともマスコミか世間か、あるいは、これまで出会った人々だったのか、もしくは、全く別の……。
しかし、ハンドルを握る彼女の泰然とした横顔を見るたび、その質問の愚かさに想いが至り、言葉にすることを憚られた。
まあいい、それはもうどうでも良くなった。おそらく彼女もそう思っているだろう。
別れ際のさっぱりとした明るい笑顔を見て、やはりそれは聞かないでおくことが正解だったような気がした。
次に会うことが、あるのかどうか、それさえも今は判らない。そんな別れだった。
遠去かり小さくなって行く黒いセダンの後ろ姿を見送りながら、古賀祐二はいつまでも十和田彩花が華麗なる女でいてくれることを心から祈った。
終
※ 最後までお読みくださり、ありがとうございました。
尚、この物語は全てフィクションです。
「誰が何と言おうと全部フィクションです」 by 古賀祐二
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
