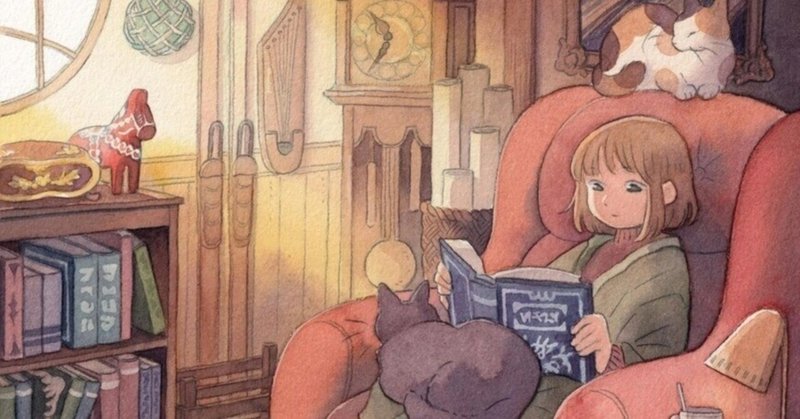
ペット税や免許を考える多事争論2
ペット税や免許を考える多事争論1の続きです。前回、ペット税について触れたので、この投稿では免許について触れて見ます。
免許とは一般には禁止または制限されている行為を,行政官庁が特定の場合に特定の人だけに許すことです。許可が得られた人には免許証が発行されます。運転免許証とか危険物取扱などがそうですね。動物飼育に免許制を導入するのは猛禽類なら危険性があることからまだわかりますが、一般的に危害の少ない愛玩動物の飼育を禁止するのは無理があります。

なお、現在でも動物取扱業には第一種(ざっくりいうと営利目的の場合)と第二種(ざっくりいうと非営利で譲渡など行う場合)の登録が必要な場合があります。第一種の場合は責任者を指定しなくてはなりません。それ以外にも能力を認定する公的資格、民間資格がいくつかあります。
仮に免許制にしたとします。免許の場合は無免許に対する取り締まりが必要になります。実効性が保てないと免許制にする意味がありません。足立家ではネコを保護し飼育しています。前回の投稿の中でネコの入手についてノラネコを拾った割合は多いという資料を掲載しました。免許を持っていないと目の前に衰弱しきったノラネコがいたとして拾って飼育するのは違法になってしまいます。道理としておかしいです。現実的にあり得ません。
なお、私が免許制を徹底したほうがいいと思っているものがあります。捕獲器の取り扱いは本来、狩猟免許のうちわな猟免許が必要なはずです。
これは参議院に請願されたものを示す一覧の内「小動物捕獲器の規制」について取り上げています。悲惨な出来事として「動物虐待」が幾度となく報道されます。中には捕獲器で捕まえて熱湯や火器で殺傷するという事件も起きています。これらを規制するために使用を制限するのはいいことだと思います。例外として行政や獣医師が取り扱いを許可されるのは判ります。でも「動物愛護団体」が入っているのはなぜ?「動物愛護団体」といっても千差万別です。法人格を持っていない団体も数多くあります。「動物愛護団体」であることを以て無条件に信用するわけにはいきません。陳情で自分たちだけ優遇される制度をつくるはおかしいと思います。法定化されていない以上、動物愛護団体は誰でも名乗ることができます。信頼に値する団体とは限りません。
そこで「わな猟免許」です。個人的には動物愛護団体の方は軒並み「わな猟免許」を取得すればいいと思います。面倒だからじぶんだち(愛護団体)だけ優遇するのはおかしな話です。仮に愛護団体だけ特例的にという話になった場合、TNRなどの保護活動はすべて団体で責任をもってやるべきという話になります。よく地域猫団体では「わたしたちは支援するだけ」という文言を使用されますが、それは通用しなくなると考えます。

話はそれますが、個人的にはTNRの活動にはこだわりません。足立家のミケは爪とぎも排せつも敷地内で行っています。「ネコの居場所づくり」にはエサの管理をしっかりと行う方が大事だと考えます。
置きエサを放置してあることにより、ネコの居場所が判明し虐待事件に発展する例は後を絶ちません。以前、職場がネコで有名な公園が隣接していたこともあり、行政である公園管理者や警察署と共同して置きエサする人の取り締まりを行ったことがあります。愛護団体の方はこういう虐待事件を招きかねない悪質な事例を取り締まることにも積極的に動くべきだと思います。行政だけでは手が回らないことも十分考えられます。後ろ向きな活動ではありますがそれこそ協働するべき事案だとみています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
