
プロレス撮るならこんなカメラ ~SONY α7Ⅲを選んだ理由~
こんにちは、さかやきです。少し前の話になりますが、しばらく放置していた質問箱を再開しようと決めたので「カメラや写真に関する質問があれば質問箱まで!」とツイートをしましたら下記のような質問がきました。

よくある質問ですね。(質問してくれた方、ありがとうございました!)、写真・カメラを趣味にしている人なら”他人がどんな機材を使っているのか気になる”というのは極めて当たり前のことだと思います。実際、私もそういう人間です。
プロレス会場でゴツい装備をしている人を見かけると「この人なに使ってるんだろう?」と気になります。
ある日のプロレス会場で、投稿を見て「この人すごい上手いなぁ」と思っていた方が隣の席になったことがありました。
その時、横目でチラ見しながら手元の機材を確認して「なるほどこのカメラとこのレンズの組み合わせは確かに凄い!」と心の中で納得したこともありました。
(当方、人見知りにつき声を掛けることが出来ず)
そしてつい最近ですが、ツイッターのアンケート機能を使って「これまでの機材遍歴か、現在使っている機材の紹介のどっちが読みたいか?」というアンケートを取りました。
結果は3分の2の割合で「現在使用している機材を紹介して欲しい」という声が占めました。
ありがたいことにちょくちょくツイッターや実際に会場でお会いした方から「どんなカメラを使ってるんですか?」と聞かれることが増えました。
というわけで今回は、私が現在メインカメラで使用しているSONY α7Ⅲについて「購入を決めた理由」「使ってみた感想(良かったところ、悪いところ)」「後継機に望むこと」の大きく3項目に分けて書いていくことにします。少しでも参考になれば嬉しいです。
前置きが長くなりましたが、本日の目次です。
私がSONY α7Ⅲを購入した理由
さっそくですが、本題の前に私は以前「プロレスを撮るならこういうカメラがあったらいいな」をテーマに記事を書きました。
その記事の中で理想とするスペックを書いたので、まだ読んでいない方はこの記事を踏まえると私がこのカメラを選んだ理由がより分かるかと思います。興味とお時間があれば読んでもらえると嬉しいです。
というわけで本題を始めましょう。
まずはこちらの写真からどうぞ

見たまんま、そのままの「SONY α7Ⅲ」の本体ですね。
それでは次の写真ですが、私が実際にプロレスの試合を撮影する際のカメラの状態がこうです。

ある程度カメラに詳しい人が見たら何ということは無いのですが、カメラに詳しくない方は本体の下部に違和感を感じたと思います。
この下部に付いてるのは「バッテリーグリップ」もしくは「縦グリップ」と呼ばれている製品です。「なぜこれを付けているのか?これを付けるメリットはあるのか?」というのは後述しますので、とりあえずこんな製品があるんだ程度に覚えてください。
それでは本当の本当に本題を始めます。
まず購入した理由をいくつか書き出すことにします。
○フルサイズミラーレスが欲しかった
○交換レンズが充実している (純正もサードパーティも)
○オートフォーカスが早い (フォーカスポイントも多い)
○瞳AF機能が使える
○フリッカーレス撮影が出来る
○ダブルスロット (SDカードが2枚挿せる)
○純正のバッテリーグリップが使える
○コストパフォーマンスが優れた機種
○いずれはオールドレンズも使ってみたい
では上記の理由を1つずつ、今回はあくまで簡単に説明していきます。
○フルサイズミラーレスが欲しかった
まず、フルサイズが欲しかった理由。それはまず「背景を大きくボカした写真が撮りたかった」から。次に「照明の環境が悪い会場でも良い写真が撮りたい」そして「フルサイズを持っている」という所有欲を満たすためです。
続いてミラーレスを選んだ理由。それは「写真の仕上がりをリアルタイムで確認しながら撮れる」これが一番の理由。続いて「背面モニターで撮る際にAFが早い」ということです。
1番目の理由については「そうなんだ」程度に覚えておいてもらって、なぜそういうことが出来るのか詳細が知りたいという人は調べてもらえばすぐに出てきます。もしくは気が向いたら詳しく記事で書くかもしれません。
2番目についても「じゃあ、ファインダーは覗かないの?」と疑問に思われるかもしれません。プロレスに限って言えば座席が遠いとき、選手同士が密着しての攻防をしっかり撮りたいと思った時はファインダーを覗きます。しかし残念ながらα7ⅢのEVF(電子ビューファインダー)は若干見づらい感じがあるので時と場合によって使い分けています。
では、背面モニターにこだわる理由は何かというと「マスクをしながらの撮影はファインダーが曇る」ということに嫌気が差したからです。

新型コロナウイルスが流行する以前から、2019年の年末年始にかけてプロレス界ではインフルエンザが流行し会場ではマスク着用での観戦が勧められました。その頃からマスクを着用しながらファインダーを覗くと、マスクから蒸気が上りファインダーが曇るのが気になって仕方ありませんでした(これはマスクをしてると眼鏡が曇るのと同じ原理です)
はっきり言います。試合中にファインダーを拭いていると必ずと言っていいほどシャッターチャンスを逃します(経験談)
そして、本格的にコロナが流行し始めたころから各プロレス団体では必ずマスク着用での観戦を義務付けられ、それは現在まで続いています(2020年10月現在)
「じゃあ、一眼レフでも背面モニターで撮ればいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、残念ながら私が以前使用していたニコンの「D7500」というカメラはライブビュー撮影時は絶望的なまでにAF速度が遅かったのです。スポーツ撮影においてフォーカススピードが遅いというのは命取りです。覚えておきましょう。
あとは背面モニターだと目線よりも高く(低く)撮影しやすいというメリットがあります。以上がミラーレスを選んだ理由です。
※ちなみにプロレス会場では目線よりも高くカメラを構えるのは禁止です。気をつけましょう。

○交換レンズが充実している (純正もサードパーティーも)
次に交換レンズが充実しているという理由です。
「純正レンズ?サードパーティーレンズ?」という方に分かりやすく言うならば「カメラ本体がSONYならばSONY製のレンズは純正レンズ、それ以外はサードパーティーレンズ」と呼ばれます。(メリットデメリットなどは別記事にて)
当初、SONYのフルサイズミラーレスカメラが発売されて間もない頃は純正レンズばかりでラインナップが少ないと言われていた時代があったそうです。しかしながら、現在ではTAMRONやSIGMAといったサードパーティー製でありながら性能的にも優れているレンズが増えてきたためレンズ選びの幅が広がりました。
ちなみに私も試合撮影には「TAMRON 70-180mm F2.8 Di Ⅲ VXD」というサードパーティーレンズを使用しています。

こちらのレンズは2020年5月に発売されたのですが、むしろこのレンズを使ってみたいがためにNikonからSONYに乗り換えたと言っても過言ではありません。本体と同時に買いましたが、非常に軽くて写りも良いので自信を持って勧められるレンズです。

○オートフォーカスが速い (フォーカスポイントも多い)
フォーカスの速さを文章で伝えるのは色々と搭載されているシステムなどの話になってくるので詳しくは割愛します。現状使っている感想としては速さは概ね満足しています。
ただし、このフォーカススピードについては本体の性能だけでなくレンズ性能にも左右されるのでプロレスなど動きの速い被写体を撮るならAFが速いレンズを選んだ方が幸せになれます。
フォーカスポイントが多いというのはこちらの画像を参照ください。

「。。。つまりどういうことだってばよ?」と思われた皆さん、とりあえず「画面の隅々までピントを合わせられるのはすごいことなんだよ!」ということだけ覚えて帰ってください。
あとは言えることとしたら、「(個人の見解ですが)フォーカスポイントが多ければ多いほどロープにピントが合う失敗を防げるよ」ということを伝えておきます。
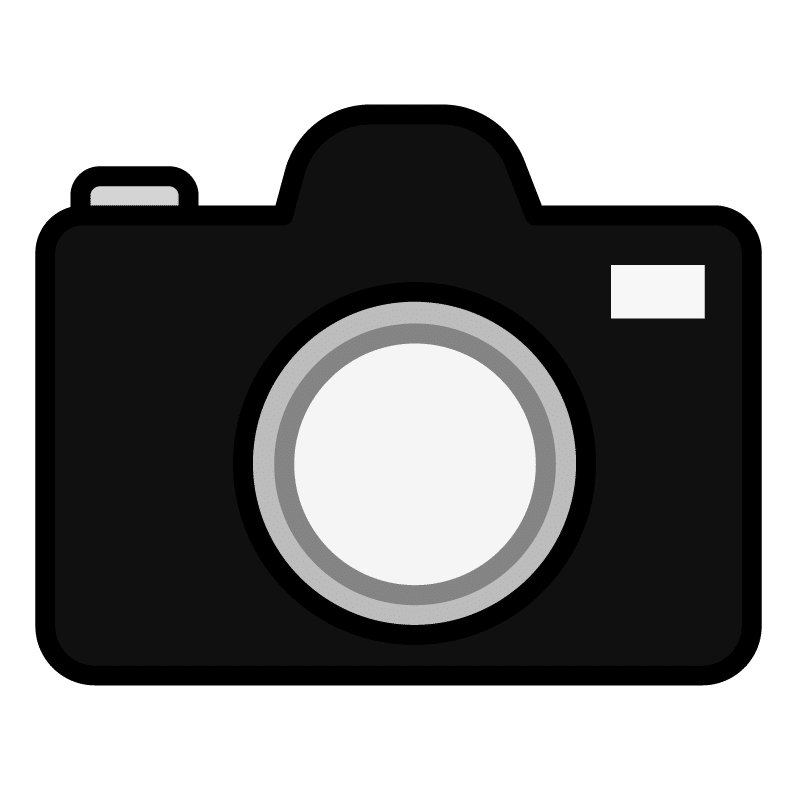
○瞳AF機能が使える
カメラに馴染みのない方からしたら「なにそれ?」と思われるかもしれません。簡単に言ってしまうと顔認識のグレードアップ版みたいなもので「人間の瞳(または一部の動物の瞳)に自動でピントを合わせる機能」ということです。
文章で説明するより動画で見たほうが早いと思うのでリンク貼っておきます。
本来はポートレート撮影など止まっている人物の撮影を行う際に重宝される機能なのでプロレスではあまり使わないかなーと思っていたのですが、これが実は凄く便利だったので後で書きます。

○フリッカーレス撮影が出来る
はい、ここにきてまた新たな単語が出てきましたね。
ではまず、フリッカー現象という単語について説明します。
フリッカー現象:蛍光灯などの人工光が連続点滅すること。
皆さんご存知の蛍光灯というのは常に発光しているわけではなく、人間の目では確認出来ないスピードで点滅しています。
屋内でのスポーツ撮影時に高速でシャッターを切り続けていると、「明るさの設定を変えていないのにやたら暗い写真が混じっている」といった経験をされた方はいるでしょうか?
それは、ちょうど蛍光灯が暗くなるタイミングとシャッターを切るタイミングが重なったことで発生する現象です。
それをカメラ側で蛍光灯の明るさを感知して、シャッターを切るタイミングを自動調整してくれるのがフリッカーレス撮影という機能となります。
特にプロレスを撮る機会の多い方は屋内撮影がほとんどだと思うので、カメラ選びの際にはこの機能が使えるカメラをオススメします!

○ダブルスロット (SDカードが2枚挿せる)
デジカメを所有している皆さんは撮った写真を何に記録していますか?おそらくほとんどの方がSDカードに記録しているはずです。
α7ⅢはそのSDカードを本体に2枚挿すことができます。(対応規格はSLOT1のみUHS-2対応、SLOT2はUHS-1のみ)

SDカードを2枚挿せるメリットを3種紹介します。
1.1枚の写真を同時に2枚のSDカードに記録できる。(同じ写真でもRAWとJPEGと違う拡張子を同時に記録する。または、バックアップ用として2枚記録する)
2.一方のカードには写真を記録する、もう一方のカードには動画を記録するといった分割記録が出来る。
3.1枚目のSDカードの容量がいっぱいになった場合、自動的に2枚目のSDカードに記録をし始める。
以上は設定で変えられるのですが、私は3番目の用途で使用しています。
「そんなプロじゃないんだからSDカードの容量いっぱいになるまで撮らないよ」という方にも伝えたい実体験から得たダブルスロットの利便性を後で書きます。

○純正のバッテリーグリップが使える
この記事の冒頭で私は以下のような写真を載せました。

そして、私はカメラにバッテリーグリップを付けていると説明しました。
ちなみにこのバッテリーグリップはSONYの「VG-C3EM」という製品です。
製品単独だとこんな感じ。

α7Ⅲより以前に使用していたニコンのD7500には純正バッテリーグリップが無かったので、密かにバッテリーグリップへの憧れがありました。そして実際に使ってみるともう手放せなくなりました。プロレスの写真を撮っててSNSに投稿している人はバッテリーグリップ持ってると便利ですよ。
ちなみにAmazonなどでD7500にも使える互換バッテリーグリップはあったのですが、個人の見解としてはメーカー純正のバッテリーグリップが発売されているのであれば多少価格が高くても純正が良いと思っております。

○コストパフォーマンスが優れた機種
ここまで書いておきながらあれですが、このα7Ⅲというカメラは今更私が良さを説明する必要が無いほどめっちゃ売れてるカメラです。
元NikonユーザーですがNikonからも「Z7」や「Z6」とフルサイズミラーレスの機種は発売されていましたが、交換レンズが純正レンズしかなくこれまでのFマウントからZマウントとマウントを変える必要があるならこの際SONYに乗り換えてもいいのかなと購入を決意しました。
そしてSONYのフルサイズミラーレスのラインナップならスポーツ撮影に適しているのは「α9Ⅱなどのα9シリーズ」ですが流石に予算的に厳しかったので、機能面と価格面を考えてα7Ⅲを選びました。
実際に使ってみてもこの機能面を考えると本体価格が20万円台前半で買えるというのはお得だと思いますし、手が出しやすい価格設定もこのカメラが爆発的に売れた要因だと思っております。

○いずれはオールドレンズも使ってみたい
これは完全にプロレスの撮影とは関係ない話なのですが、カメラ好きの間では以前からオールドレンズブームが起きています。
オールドレンズとはその名の通り古いレンズ、つまりフィルムカメラの時代に製造されたレンズのことを言います。
オールドレンズの特徴はマニュアルフォーカスで自分でピント合わせが必要だったり、写りも最新のレンズと比べると細部までくっきり映るというより少し癖のある写真になるのですがそれが逆にオシャレということで人気になっています。オールドレンズとミラーレスカメラの親和性が高く、そういう用途でα7シリーズを使用している方も多いのです。
プロレスの写真も上手くなりたいところですが、せっかくカメラを持っているなら色んな写真が撮れるようになりたいのでいずれはオールドレンズも試してみたいなぁと思っております。

使ってみて分かったこと
私がこのカメラを使い始めたのは2020年の8月なので、これを書いているのが10月末なのでおよそ3ヶ月が経った頃です。
実際に3ヶ月使ってみて「良かったポイント」、「イマイチなポイント」を書いていきます。購入の際の参考になれば幸いです。
良かったポイント
○追従性能が良い
○瞳AFが早くて正確
○ダブルスロットは便利
○USB-Cケーブルでデータ転送と充電が出来る
イマイチなポイント
○動作の処理がたまに遅い
○AFは早いけど、精度はもうひとつ
○バッテリーの減りの速さが気になる

良かったポイント
○追従性能が良い
追従性能とは「ピントを合わせた被写体が動いても、その被写体にピントを合わせ続ける」ことを言います。
2020.8.23 DDT 後楽園
— sakayaki @プロレス写真 (@skyk_pwphoto) August 23, 2020
遠藤哲哉 選手
サスケスペシャル!!#ddtpro #KOD2020 pic.twitter.com/PXvaY1N82a
我ながらこの3枚を撮れたのは感動しました。空中ですごい速さで立体的に動く遠藤選手を捉え続けられたのはこのカメラの追従性能が良いことが分かっていただけると思います。
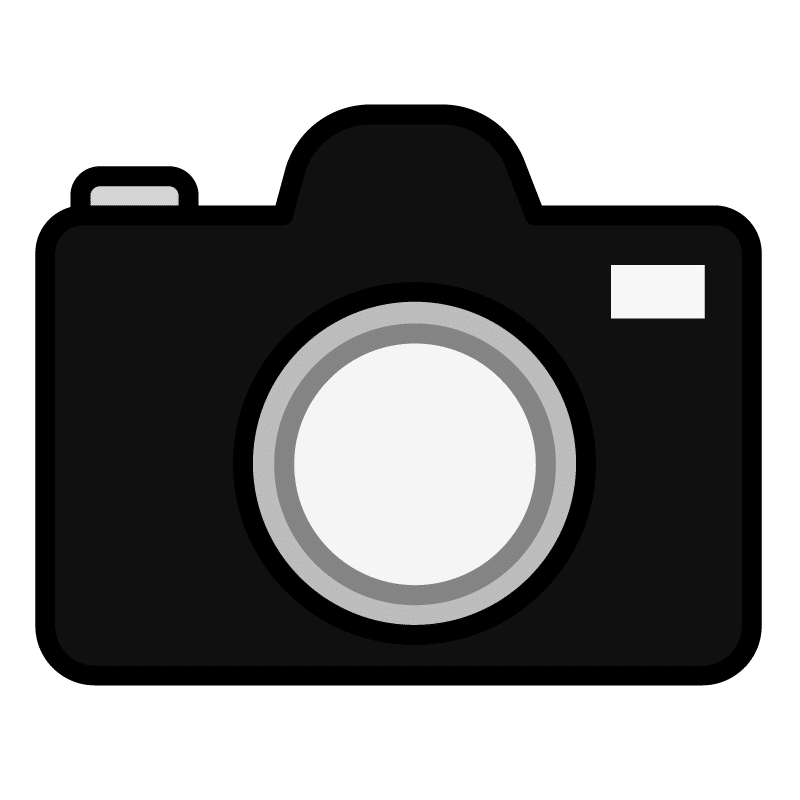
○瞳AFが早くて正確
正直なことを言うと「プロレスの撮影で瞳AF使わないよなぁ」と思っておりました。

それが実際に使ってみたら「瞳AFめっちゃ便利やん!!」と手のひらを返すことになりました。
2020.10.17 #tjpw 新木場
— sakayaki @プロレス写真 (@skyk_pwphoto) October 19, 2020
難波小百合リングアナによる前説からスタート
ちなみにこの日が誕生日前の最後の大会でしたね。 pic.twitter.com/xasqjqAXLr
もちろん動きの早い場面では無理ですが、こういう前説など動きの少ない場面では的確に瞳にピントを合わせてくれるのですごく便利なのです!
あと個人的には割と離れた位置からでも瞳を認識してくれることが驚きでした!

○ダブルスロットは便利
プロレスに限らずスポーツ撮影はカメラの連写機能が重要になってきます。ちなみにα7Ⅲは10コマ/秒の撮影が可能です。
連写が速いとなるとそれだけ撮影する枚数も増えます。大容量のSDカードを使用していても、私のように試合中の写真もRAWファイルで撮影しているとすぐに容量不足に陥る可能性があります。
試合中の容量不足を避けるために普段はこまめにPCにデータを移動させたらSDカードを初期化して空の状態にして次の大会に臨むようにしています。
しかし、ある日の大会で前回の大会のデータを残したまま撮影を始めてしまい気づくと1枚目のカードは限界まで記録されていました。それでも2枚目のカードにほぼタイムラグ無しで切り替わっていたのは驚きました。
もし、昼夜2大会行くことが多い方やそもそも撮る枚数が多くなってしまうというかたはダブルスロットの恩恵を得られるはずです!

○USB-Cケーブルでデータ転送と充電が出来る
α7Ⅲを購入する際の注意事項にバッテリーの充電器が付属していないことがよく不満点として挙げられます。
「じゃあ、どうやってバッテリーを充電するの?」というと、本体側面にあるカバーを開いてマイクロUSBもしくはUSB-Cケーブルを挿して充電します。(もちろん別売りで充電器は売られています。)

最初は違和感があったのですが、慣れるとこれがすごく便利に感じます。
バッテリーを本体に積んだまま充電できる=家にバッテリーを忘れるリスクを回避できる
家を出た直後に気づけばまだいいのですが、会場に着いてからカメラの電源を入れようとしたら電源が入らなかったときの絶望感。。。こういったうっかりを防げるだけでかなりありがたいのです。
また、写真データをPCに転送する際はこれまでAnkerのUSB-Cカードリーダーを使用していました。

もちろんこの製品も転送速度が早くて便利なのですが、あまりSDカードを本体から抜いたり挿したりするとSDカード自体の消耗が激しくなりそうなので極力避けるようにしています。
そこでSDカードを本体に挿したままUSB-CケーブルでPCと接続し、データ転送を行うという手法を取っています。
転送速度ではAnkerより劣るものの、大量のRAWファイルを扱っていることを思えばまぁ許容範囲かなと。

イマイチなポイント
○動作の処理がたまに遅い
続いてイマイチだったポイントを述べていきます。
動作の処理が遅いと書きましたが、主にボタン類の効きが悪くなるというか動作が鈍くなるのが連写で撮った写真をSDカードへの書き込み終えた直後などにMENUボタンや再生ボタンが効かなくなるという現象が起きます。
自分でも使い方が荒いのは分かっていますし、少し待てば良いだけの話なのでそこまで気にすることは無いのですが、他のαシリーズではどうなのでしょうか?

○AFは速いけど、精度はもうひとつ
確かにAF速度は速いです。速いですが、ピント合わせまで全てカメラ任せにしようとすると失敗写真を量産することになると思います。
プロレスの写真における失敗写真の代表例は「ロープにピントが合ってしまう」ことだと思います。カメラのAF機能というのはよりレンズに近い被写体にピントを合わせようとします。
プロレスにおいては選手より手前に必ずロープが写ります。プロレスの撮影における最大の敵はロープです。
その中で選手にピントを合わせるためにはある程度手動でピントを合わせる作業が必要になります。
失敗例1:手前のロープにピントが合っている

失敗例2:奥側のコーナーにピントが合っている


○バッテリーの減りの速さが気になる
α7Ⅲに採用されているバッテリーは「NP-FZ100」といいます。
このバッテリーが採用されたことにより、実は前世代のα7Ⅱからかなりバッテリーに関しては改善されたと言われています。

しかしながら、私は本製品からのαユーザーなので比較することは出来ませんが気持ち的にはもうちょっと持ちが良ければなーと思っています。
旅行やスナップ程度の利用頻度であれば2~3日くらいは持つくらいの容量だとは思いますが、プロレスなどスポーツ撮影となると一回の撮影で数千枚撮ることになります。
しかも、高速連写でRAWを撮りまくるという一番カメラに負担の掛かる使い方をしているのでおよそ2時間半~3時間の興行でも終わる頃にはバッテリーが半分程度まで減っていることが多々あります。
一日に1大会のみの撮影であれば問題無いかと思いますが、昼夜2大会で途中に充電が出来ないとなればバッテリー1個ではかなり不安です。
なので私はバッテリーグリップを付けることにより、バッテリーを常に2台積んでいる状態にしています。
本体が重くなるのでバッテリーグリップを付けたくない人も予備バッテリーは持っておいて損は無いと思います。

最後に ~後継機 α7Ⅳに望むこと~
ここまでが私がどうしてこのカメラの購入に至ったのか、そして実際に使用してみての感想でございます。
良い点も悪い点も全部ひっくるめて、この記事を最後まで読んでくださった皆さんにα7Ⅲの魅力が伝わっていただければ幸いでございます。
そしてもしα7Ⅲの購入を迷っている方がいましたら「購入はちょっと待ったほうがいいよ」という話をします。
何故なら、「来年もしかしたら後継機が発売されるかもしれない」という情報が出ているからです。
もしくは今よりもっとα7Ⅲを安く購入したいと考えているなら、後継機が発売されると型落ち品で本体価格は下がりますので狙い目になると思います。
それでは、この章では「α7Ⅳ(仮)に期待すること」を書いていきます。
○本体の握りやすさの改善
これは恐らく改善されるでしょう。α7RⅣやα9Ⅱのボディを採用してくれたら私としては十分です。
○画素数の向上
あまり高くなりすぎると高画素機のメリットが無くなるのと、1枚あたりのデータが大きくなってしまうのでα7RⅢくらいの画素数を適用してくれると嬉しかったりします。(およそ4000万画素くらい)
○連写速度の向上
α9程は望みませんが15コマ/秒くらいまで増えるといいなぁ
○CFカードの採用
ベーシック機ということを考えると難しいのかなぁと。それが無理ならダブルスロットで両方UHS-2が挿せるようになったら嬉しい。
○頭部検出AFの追加
顔認識とか瞳認識は正面を向かないと検出されないので、後ろ姿とか横顔でも認識してほしいなぁと。
○ブラックアウトフリー撮影に対応
優先度は低いけど、あれば使ってみたいなぁ程度です。あまり期待はしません。
○電源オフ時にシャッターを閉じる
これって今すぐアップデートで対応できるんじゃない?って思ってることです。(α9Ⅱはアップデートで対応済み)
レンズを外したときにセンサーがむき出しの構造が怖いので是非とも対応して欲しい。。。
という訳で、次世代機に期待することを書いたのですがもはやベーシック機に望むレベルでは無いですよね。。。全部盛りがあるとすればα9Ⅲはモンスタースペックを期待したいですが価格もモンスター級になりそうな予感がしています。
「それでもSONYなら...」「SONYならきっと何とかしてくれる...!!」と陵南高校の仙道彰ばりに期待をしてしまうのが今のSONYのカメラの完成度なのです。

それでは次回の記事でお会いしましょう!ありがとうございました!
サポート受け付けます!いただいたサポートは今後の活動費に充てさせていただきます。
