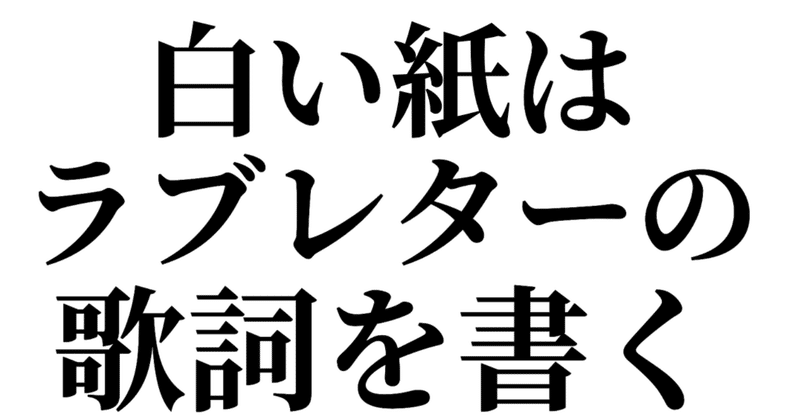
A. 「光る地図」はラブレターである
1.はじめに
にじさんじ所属バーチャルライバー、月ノ美兎。
彼女のファーストアルバム「月の兎はヴァーチュアルの夢をみる」は名盤である。
それぞれの曲が、彼女の様々な面に光を当て、多様な魅力を表現している。
「ウラノミト」では、二面性がありながらもそれらが渾然一体となった「ひとつのカオス」として存在するバーチャルyoutuber月ノ美兎の魅力を、恋愛における裏と表に擬えながら捉えている。
「NOWを」ではステージのスポットライト(光)を「細いひと筋の月の光」に例え、ステージの外での孤独(闇)を歌った上で、
アイドル月ノ美兎がモーゼのように闇を切り開いて進み、てっぺんを目指す力強さを表現している。
このように、各曲が月ノ美兎のファンソングとして非常に優れている。(歌詞だけでなく、歌詞と曲調がマッチしているのも素晴らしいし、歌詞抜きで曲だけでも素晴らしいし、そもそもシンプルに曲の作り込み、歌唱が素晴らしいのだが、今回の趣旨とはズレるので割愛する)
しかし、こうした曲たちの中にあって、一際歌詞の解釈が難しいものがある。
「光る地図」だ。この曲の歌詞は他の曲と比べてズバ抜けて抽象度が高く、解釈が困難だ。表題曲「月の兎はヴァーチュアルの夢をみる」も解釈困難だけど、あの曲は歌詞を解釈するとかしないとか出来ないとかそういうものではない
また、作詞・作曲を手がけた長谷川白紙さん曰く、
わたしが誰かに向けて歌詞を書くと絶対その人に向けたラブレターになってしまうため、今回も月ノ美兎さんへのラブレターになっており恥ずかしいです
— 長谷川白紙 (@hsgwhks) August 10, 2021
とのことで。
この記事では、アルバムの中でも一際解釈困難な長谷川白紙さんの「ラブレター」を読み解いていく。
※さん付けではなく「長谷川白紙氏」と呼ぼうと思ったが、読みにくいので
こう呼ぶことにした
2.この記事の流れ
この記事では、次のような流れで歌詞の解釈をする。
3.では、曲を①〜⑤までの部分に分けて、それぞれの部分について歌詞の文構造の解釈をし、構造の解釈だけで決まることにはその場で解釈を与え、決まらないものは疑問として取り上げる。
疑問はQ1.〜Q25.まで上げた。また、①から⑤の目次の名前として、
歌詞の該当部分の核心と思われる疑問を付している。
4.ではこれらの疑問に対して、私なりの解釈で順不同で回答していく。基本的には上から順に読むことを想定している。特にQ18. , Q16. , Q.4. で議論している内容は以降の回答でバンバン使っている。
5.では、以上の解釈をまとめて、「光る地図」という曲を振り返る。
ここを読むだけでも、今回組み立てた解釈のことは理解できるだろう。
12000字あるので、手早く他人の解釈を摂取したい人・そもそも読む価値があるか判断したい人は一番下から読むのも良いと思う。
この解釈の妥当性・組み立てる過程が知りたい方は是非上から読んでほしい。
3. 歌詞の分割・文構造の解釈・文構造の解釈からわかること・わからないこと
3-① Q.「忘れている息」は誰の息?
ここで 忘れてる息は
Wi-Fiにまぎれて
囲われためとめと
鱗
星座に鱗
貼り合わされたら
動き出す 由の上
文構造の解釈:
AはBとCをDに貼り合わされたらEを動き出す
A:ここで忘れてる息
B:Wi-Fiに紛れて囲われた「目と目」
C:鱗
D:星座
E:由の上
Q1. 「ここ」とはどこか?「ここで忘れてる息」とは何か?
Q2.「Wi-Fiに紛れて囲われた目と目」とは何か?
Q3. 「目と目と鱗を星座に貼り合わされる」とはどういうことか?
Q4.「由の上」とは何か?
Q5.①の内容を解釈せよ
3-② Q.「それ」を見ていたいのは「わたし」?「僕」?
話す全て
お伽話 だから
そうだよね
まだ 近くても遠くてもいい
見えている誰にも わからない
たしかなものがなくなり 光りだす
それを見て いたいのです いつもただ
文構造の解釈:
「そうだよね」の「そう」が何を指すかは文構造のみから判断はしない
(直後の「まだ近くても遠くてもいい」に掛かってると考えるのが自然だが、「お伽話だからまだ近くても遠くてもいい」と言われても、解釈なしには意味がよくわからない)
最後の行は「光りだすのを見ていたい」と解釈する。(「そう」は「光りだす」を指すと解釈する)
Q6.何が「近くても遠くてもいい」のか
Q7.「見えている誰にもわからない」とはどういうことか
Q8.「たしかなものがなくなり 光り出す」とはどういうことか
Q9.「そうだよね」の「そう」は何を指しているのか
Q10.②の内容を解釈せよ
3-③ Q.「僕の話だね」と言った後に長い間奏が入るのは何故か?
ピンが 研ぎ澄まされて
いずれの動きも 座標の川になる
ほらね 星座と鱗
裏返るところ ひとめで見えたから
これは僕の話だね
文構造の解釈:③の文構造は明らかなので略
Q11.「ピン」とは何か?
Q12.「いずれの動きも座標の川になる」とはどういうことか
Q13.「星座と鱗 裏返る」とはどういうことか?
Q14.「僕」とは誰か?「これ」とは何か?「これは僕の話だね」と言っているのは何故か
Q15.③の内容を解釈せよ
3-④ Q.「光る地図」とは何か?
とてもたくさんの位置で 放たれて
景色をつれていくし
わたしの地図が光って話すときは
皆のも 見たいのです
文構造の解釈:
【何が】放たれるのか?
【何が】景色を連れていくのか?
これら2つの【何が】は同じものを指している。
そして、後ろも読めばこれは「光」のことだと解釈出来る。
「とてもたくさんの位置で【光が】放たれて」いて、
では【何が】とてもたくさんの位置で光を放っているのかといえば、
【地図が】光っているのだと解釈する。
次に、「とてもたくさんの位置で」が何を指すかに関しては、文構造からは解釈しない。
つまり、
a)「地図の色々な場所が」光っている(同じ地図内のオーストリアとか日本とかアメリカとかブラジルとかトルコとか、色々な場所が光っている)
b)「色々な場所の地図が」光っている(本棚に置いてある地図とか机に置いてある地図とかAさんが持ってる地図とかBさんが持ってる地図とか、色々な地図が光ってる)
のどちらの意味なのかに関しては、文構造だけでは解釈を決定しないことにする。
以上に書いたことから、
④は以下のような文構造だと解釈する:
地図が光ると景色をつれていくので、
わたしの地図が光って話すときには、
皆の地図も見たいのです
ただし、
a)地図の色々な場所が光っている
b)色々な場所の地図が光っている
のどちらかは文構造からは決定できない
Q16.「わたしの地図が光って話す」とはどういうことか
Q17.「景色をつれていく」とはどういうことか
Q18.「わたし」とは誰か?「皆」とは誰か
Q19. a)とb)、どちらの解釈を採用するか
Q20.以上を踏まえて④の内容を解釈せよ
3-⑤ Q.【何故】わたしはどこにでもいれるのですか?
明かりが重なるところ 骨たちと
スキンが できていく
雲を搾ったみたいです みたいなので
わたしはね いれるのです どこにでも
文構造の解釈:
AにBができていく様子がCなので、わたしはどこにでも居られる
A:明かりが重なるところ
B:骨たちとスキン
C:雲を絞ったみたい
Q21.「明かり」とは何か?「明かりが重なるところ」とは何か
Q22.「骨たちとスキンができていく」とはどういうことか
Q23.「雲を搾ったみたい」とはどういうことか
Q24.「わたしはどこにでも居られる」とはどういうことか
Q25.以上を踏まえて⑤の内容を解釈せよ
4.回答例
Q18.「わたし」とは誰か?「皆」とは誰か
この曲は大きく2つの部分に分けられる。①〜③、④〜⑤の2つだ。
これらは間奏によって隔てられていて、
前半は「僕」、後半は「わたし」の視点で描かれていると解釈できる。
長谷川白紙さんのtweetも踏まえれば、「僕」や「皆」は長谷川白紙さん自身やリスナーたち、「わたし」は月ノ美兎を指すと解釈できる。
A18. 「わたし」=月ノ美兎 「皆」=リスナー
Q11. 「ピン」とは何か?
この曲中には「星座」という言葉が繰り返し登場する。
また、題名や曲の後半では「地図」という言葉も使われている。
「星座」「ピン」「地図」。これらの言葉からは、
「星座早見盤」が連想できる。また星座早見盤の解釈を踏まえると、
歌詞中に度々登場する「鱗」という言葉も解釈出来るので、
ここではこの解釈を採用する。
非常に乱暴にいえば、「光る地図」=「星座早見盤」のことである。
「地図」に関する問は④部分で多くあるので、更なる解釈は④の問(Q16〜Q20)に回答する際に与える。
A11.「ピン」=「星座早見盤の中央にあるピン」
(先送りにした問:では「星座早見盤」≒「光る地図」は何を意味しているのか?)
Q13.「星座と鱗 裏返る」とはどういうことか?
「星座が裏返る」では意味がわからないが、
「星座早見盤が裏返る」ならそのままの意味である。
さて、星座早見盤には色々なタイプのものがある。紙製のもの、プラスチック製のもの、金属製のもの……
中には星を点字のように出っ張らせて、星座の象る線も彫ってある星座早見盤もある(はず)※
そうした星座早見盤をひっくり返して裏面から見たら、星は目立たずに星座の線だけが目立って、線に囲まれた図形たちが並ぶ様子は「鱗」のように見えるだろう※
A13.「鱗」=星座早見盤の裏面の、星座の線に囲まれた部分。
つまり星座早見盤をひっくり返しただけ。
※:手元に星座早見盤がないため、推測と曖昧な記憶がソース
Q2.「Wi-Fiに紛れて囲われた目と目」とは何か?
Q3.とも関連するが、ここで「目」は2つの意味を持つ。
一つは「星」、もう一つは「(主にリスナーの)目」だ。
「目」を「星」に擬え、「Wi-Fi」(が情報網を為す様子)を星座を象る「線」に擬えてみれば、
どこかから飛んできた電波を受けたPCの前で、
月ノ美兎の配信を見ているリスナーたちは、
上空からみれば星座のようになっているだろう。
A2.「目と目」=リスナー(特に「僕」)の両目。Wi-Fiを星座を象る線に見立てると、まるで星座早見盤で星々が色々な線に「囲われて」いるように見えるため、「Wi-Fiに紛れて囲われた目」と言っている
※※※「星」について注意※※※
ここでは「リスナーたち」のことを「星」と見立てて解釈した。しかし、
以降では「星」を「リスナーたち」以外の意味で解釈する時がある。
先走っていうと、「楽しいこと・もの」という解釈をする。
しかし、この歌詞においてリスナーが星なのは「月ノ美兎の配信を見ている時」、つまり「楽しい時」なので、リスナーのことも「楽しいこと」も両方「星」に擬えても矛盾しない。
ここでは取り敢えず、後で「星」=「リスナーたち」以外の解釈をするのだな、とだけ把握しておけば良い。
Q3. 「目と目と鱗を星座に貼り合わされる」とはどういうことか?
Q2での議論よりすぐ従う。
A3.目を星に見立てて、Wi-Fiを線に見立てると、まるで星座のように見えるということ。
Q4.「由の上」とは何か?
ここだけかなり異色な解釈をする。まず、この曲を通して星のモチーフが現れているのはここまで述べてきた通り。
では、「由の上」とはなんだろう?
星空を、宙(そら)を眺めて見るとわかるのではないか?
そう、由の上にはウ(ウ冠)がありますね。
まさにウ宙(宇宙)ってことなんですね。知らんけど。
他にも色々な解釈があると思うが、「由」の意味をどう解釈しても
真正面からは解釈しきれないし、何らかの言葉遊びはあると思う。
A4.宇宙のこと。youの上(頭上に広がる宇宙)のこと。
理由なんて飛び越えていること。筆者の知る由もないということ。
※後で見る(Q8. , Q6.などで見る)が、「僕(長谷川白紙)」にとって、「由の上」は「楽しいこと」で溢れた世界、「月ノ美兎の世界」のことでもある。
上にある注意「『星』について注意」で見たように、
「星」=「楽しいこと」と解釈すれば、
「由の上」=宇宙=「星」が沢山ある場所=「楽しいこと」で溢れた世界
と解釈するのは自然だ。
※※※以降の回答をする前に注意※※※
ここで少し注意するのは、間奏を挟む前後では「僕」と「わたし」で視点が違うことだ。
「僕」は星たちを「星座早見盤」に見立てている(「ピン」、裏返すなどの表現から)。
「星座早見盤」は「星を【見る】ため」のものである。
つまり僕にとって、「星」は「見るもの」である。
一方、「わたし」は「光る地図」に例えている。
つまり私にとって「星」は「実際行く場所」である。
それどころか、
⑤の部分では地図どころか星たちをもっと立体的なものに捉えている。
詳しくは⑤の問に答える時や、Q14.に答えるときに述べるが、簡単に触れると、「僕」は星座が「目(星)」と「鱗(線で囲まれたもの)」を貼り合わせてできていると見ていて、
「わたし」は「骨」と「スキン」でより立体的に組み上げられていると見ているのだ。
(そして作詞者にとって、「わたし」=星座そのものでもある、⑤参照)
平面に囚われた「僕」と、そうではない「わたし」。この対比は頭の片隅に置いておいてほしい。
Q16.「わたしの地図が光って話す」とはどういうことか
これはもっと後ろも含めて見るとわかりやすい。
わたしの地図が光って話すときは
皆のも 見たいのです
ここまでの考察を踏まえてこの歌詞を見ると、月ノ美兎のあの発言を連想する。
結構わたくしは、やりたいこととかをね、色々やって、楽しく人生をさせていただいているので。
みなさんも何か楽しそうなものとかがあったらお裾分けをしていただけると嬉しいなって思います。
(中略)
みなさん、楽しそうな場所を見つけたらお裾分けをしてください。
一緒に人生やりましょう。
一緒に人生をね、神ゲーにしようかなと思いますわ。
リスナーさんたち。
」1:16:25〜、
リンク:https://www.youtube.com/watch?v=sRhF6OiD31k&t=4585s
A16. 一緒に人生を神ゲーにしよう
「地図」=個々人の体験してきたこと、人生
「光る地図」=楽しかったこと、人生
つまり、「わたしの地図が光って(わたくしが)話す」とは、
月ノ美兎が体験談をリスナーに話すことである。
※体験談に限らず、例えばゲーム実況などでも独特な視点が現れることがあり、それも「地図」に含まれるのかもしれないが、大意が変わらないのでここでは割愛する
※これは、この部分での「光る地図」の解釈である。
上に見たように、リスナー(や月ノ美兎)を星と見立てて、それらが電波で繋がっている様子も「光る地図」に擬えていると思う。つまり、マクロな「光る地図」とミクロな「光る地図」が入れ子構造になっているし、
Q22.で見るように、ミクロだと思った「光る地図」もまたマクロな「光る地図」抜きには語れない。大雑把にいうと、ミクロな地図がマクロな地図の貼り合わせで出来ているかのような、何重もの入れ子構造があると思う。
もっと雑にいうと、「光る地図」って色んな意味で使ってるから気をつけてねということ。
Q17.「景色をつれていく」とはどういうことか
A17. 自分の体験を他の人にも共有すること
Q19. a)とb)、どちらの解釈を採用するか
a)「地図の色々な場所が」光っている
b)「色々な場所の地図が」光っている
A19. 両方(色んなリスナーの色んな体験があるため)。
Q20.以上を踏まえて④の内容を解釈せよ
とてもたくさんの位置で 放たれて
景色をつれていくし
わたしの地図が光って話すときは
皆のも 見たいのです
A20. 「わたし(月ノ美兎)」が「みんなで一緒に人生を神ゲーにしよう」と思ってること
Q1. 「ここ」とはどこか?「ここで忘れてる息」とは何か?
①の最初も最初。「僕」視点であることに注意。
Q16やQ2,Q3,Q4を踏まえると、次のような回答が妥当だろう。
A1.
「ここ」=「僕(長谷川白紙さんやリスナー)」の自宅(など、月ノ美兎の配信を見てる場所)
「ここで忘れてる息」=月ノ美兎の配信を見て思い出すもの、例えば人生の楽しさのこと。
Q5.①の内容を解釈せよ
ここで 忘れてる息は
Wi-Fiにまぎれて
囲われためとめと
鱗
星座に鱗
貼り合わされたら
動き出す 由の上
A5.
仕事などの日常生活の中で、「僕(長谷川白紙さんやリスナー)」は息を忘れてしまう(息を忘れてしまったかのように、人生の楽しさを忘れてしまったり、心の余裕がなくなってしまったり、息苦しくなったりしてしまう)。
しかし、月ノ美兎の配信を見ていると、忘れてる息は動き出す(人生の楽しさを思い出すし、心の余裕を取り戻す)。
その様は、リスナーたちが星座のように繋がって、宇宙に飛び出していってるかのようだ。
※※※②の部分の回答をする前に注意※※※
ここまでは、A16の解釈さえ組み上げれば、瞬時に回答できる類の問だったが、②は別の見方が必要なのでここで組み立てる。
というのも、A16は「わたし」視点の話だからだ。
②では「僕」視点なので、少々見方が変わる。
「わたし」視点では、「わたし」も「皆」もそれぞれが「地図」を持っていて、それらは光っていて見せあって、話すことが出来た。
しかし「僕」は月ノ美兎の配信を見て、ようやく忘れてる息が動き出して由の上に行けるのだ。
つまり、「わたし」にとっては「皆」の地図も光っているが、
「僕」にとっては「光」は「わたし」のこと、
ひいては「楽しいこと」のことだ。
①ではリスナーたちを星に見立てて、星座を象ったが、
「月ノ美兎の配信を楽しんでいる」から「星(楽しいこと)」だと思えば、
一貫して「光」や「星」は「楽しいこと」のことを指している。
(上の注意「『星』について注意」も参照のこと)
また、「僕」にとっては、「僕」側が話すことは想定外なので、
「話す全て お伽話」とは「『わたし』の話」のことである。
それを踏まえて以降の回答をする。
②の歌詞(再掲)
話す全て
お伽話 だから
そうだよね
まだ 近くても遠くてもいい
見えている誰にも わからない
たしかなものがなくなり 光りだす
それを見て いたいのです いつもただ
Q7.「見えている誰にもわからない」とはどういうことか
上の注意を思うと、回答はこのようになる。
A7(?)
「わたし」の話が本当かどうかが、「僕」含めて誰にもわからない。
しかし、この回答はナンセンスだ。もっと踏み込んで解釈するなら、
「見えている誰にも わからない」とは次のように解釈できる:
A7
月ノ美兎の話から伝わってくる彼女の見ている世界は、息を忘れてしまうような自分の世界とはかけ離れている。そのため、まるでお伽話のようである(≒本当かどうかわからない)。
※「誰にも」という部分から、「他の人の世界だって月ノ美兎の世界からかけ離れてるでしょう」という気持ち、つまり月ノ美兎を特別視する気持ちも読み取れる。
Q8.「たしかなものがなくなり 光り出す」とはどういうことか
「たしかなものがなくなり」=「見えている誰にもわからなくなる」
A8.
月ノ美兎の話は、本当かどうかわからなくなるほど「僕」の世界とはかけ離れていて、「僕」にとって楽しいということ
※月ノ美兎の世界=「由の上(宇宙、理由を飛び越えた場所)」
「僕」の世界はその反対である。
Q6.何が「近くても遠くてもいい」のか
A6.
「僕」の世界と「わたし」の世界。
※「【まだ】近くても遠くてもいい」と言っていることから、
いつかは月ノ美兎が話すような楽しい世界に自分の周りの世界も近づけば
いいなと「僕」が感じていることもわかる。
Q9.「そうだよね」の「そう」は何を指しているのか
「話す全てお伽話だから 『そう』だよね」の「そう」のこと。
文構造的には、直後の「まだ近くても遠くてもいい」を指している。
また、これで解釈が出来るのでOK。解釈については次のQ10.を参照。
A9.「まだ 近くても遠くてもいい」
Q10.②の内容を解釈せよ
話す全て
お伽話 だから
そうだよね
まだ 近くても遠くてもいい
見えている誰にも わからない
たしかなものがなくなり 光りだす
それを見て いたいのです いつもただ
A10
月ノ美兎の話が全て「僕」にとってはお伽話に聞こえるほど、
「僕」の世界と月ノ美兎の世界とはかけ離れている。
いや、「僕」だけじゃなく誰にとってもそうに違いない。しかし、
だからこそ、お伽話を聞くときにその真偽を気にしないのと同様に、
そんなことはどうでもよくて、月ノ美兎の配信は楽しいし、
「僕」はいつもただそれを見ていたい。
Q12.「いずれの動きも座標の川になる」とはどういうことか
「僕」の視点であることに注意が必要。
川を思わせる表現は「わたし」の視点でも出てくるが、
「僕」は「座標の川」、「わたし」は「雲を絞ったみたいです」
と見ている。
「雲を絞ったみたい」の方が「由の上」の表現で、
「座標の川」というのは如何にも理屈に囚われた感がある表現だ。
(余談だが、どちらの表現も歌詞として書けてしまう長谷川白紙さんって「わたし」でないにしても「僕」でもなくない??と思う)
「星座早見盤」は「僕」にとって「月ノ美兎の配信」の象徴である
(星=リスナーたち、線=Wi-Fiなどの通信、それらが象る「星座早見盤」)
しかし、「僕」はどうしても「僕」にとっての現実世界の中にいて、
星座早見盤が表すような「由の上」の住人にはなりきれていない。
「ピン」や「座標の川」という表現はその顕れだと思う。
A12(?)
「座標の川」とは、「座標(星座早見盤には方角とかが書き込まれているので多分それのこと)」が回転する様子のこと。
「星座早見盤」の意味も含めて解釈すると、以下の通り:
A12
「星(楽しいこと)」に集中できずに、「星座早見盤(『僕』にとって、月ノ美兎の世界の象徴)」に書かれた「座標」が回転する様子が気になるなど、
結局「僕」が「由の上」には行き切れていないということ。
Q14.「僕」とは誰か?「これ」とは何か?「これは僕の話だね」と言っているのは何故か
この部分はQ12.の箇所と概ね同様。一つ注意が必要なのは、
曲中で「僕」が出たのはここが初めてということ。
つまり、今の今まで「僕」は、歌詞の語り手が「僕」であることさえ忘れている……とも言える。「これ」の解釈は色々あるが、ここではこの視点に則って解釈する。
A14.
「僕」=長谷川白紙さん(やリスナーたち)
「これ」=ここまでの歌詞
本来「星(楽しいこと)」を直に見ているならば意識するはずのない「星座早見盤の裏表(=星座と鱗が裏返るところ)」を見てしまったので、
「由の上(宇宙、理由を飛び越えたところ、楽しい世界)」にいる月ノ美兎ではなく、自分が「僕」であることを思い出した。そのため、
「これは僕の話だね」と言っている。
Q15.③の内容を解釈せよ
ピンが 研ぎ澄まされて
いずれの動きも 座標の川になる
ほらね 星座と鱗
裏返るところ ひとめで見えたから
これは僕の話だね
A15.
月ノ美兎の配信を楽しんでいて、「僕」は現実の大変さから少し離れて、人生の楽しさを思い出していた。しかし、「僕」はやっぱり(「僕」にとっての)現実世界に住んでいて、月ノ美兎が話してくれるような楽しい世界には入り込めていないことを自覚してしまった。
※※※⑤の部分の回答をする前に注意※※※
(上にある注意「以降の回答をする前に注意」も参照のこと)
以上のように、「僕」は「由の上(楽しい世界、月ノ美兎の世界、宇宙、理由の上の世界)」の住人ではなく、配信を見て楽しく思っても「星座早見盤」、「お伽話」のように感じている。
一方で、「わたし」は(作詞者にとっては)「由の上」の住人で、
楽しいことは実際行ってみれば体験できるもので、楽しいことたちは「星座早見盤」に書かれた「星」ではなく「地図」の上に書かれていて光っているものだ。
それどころか、⑤では「星座早見盤」は勿論、「地図」という平面すら飛び出していく。まさに「宇宙そのもの」と思った方が解釈しやすい。
また、「光る地図」という曲自体が非常に抽象度が高い歌詞だが(だからこんな記事を書いているわけだが)、
⑤の部分は輪をかけて抽象度が高いので注意。
長谷川白紙も「わかりやすさ」ではなく、月ノ美兎の「わからなさ」を表現したかったのでは、と思いたくなるくらい抽象度が高い。
⑤の歌詞(再掲):
明かりが重なるところ 骨たちと
スキンが できていく
雲を搾ったみたいです みたいなので
わたしはね いれるのです どこにでも
Q21.「明かり」とは何か?「明かりが重なるところ」とは何か
A21.
「明かり」=楽しいこと・場所
「明かりが重なるところ」=楽しいものがたくさんある場所
Q22.「骨たちとスキンができていく」とはどういうことか
「スキン」とは、皮膚のこと。特にここでは皮膚片のことと解釈する。
皮膚片は一つ一つが「地図」のように思える。
また、「骨」それぞれが、乱暴にいうと「線」のような形をしている。
このことから、①で僕が「星(リスナーたち)」と「線(Wi-Fiなどの情報通信)」が「星座」を作り出していると表現したものが、
「明かりが重なるところ(=『星』、楽しいものがたくさんある場所)」から「骨(=線)」が出来て、表面を「皮膚片(=『地図』、楽しいものがたくさん書いて光り輝いているもの)」が覆っていって、【何か】を作り出している。
この【何か】が「わたし」であること、作詞者にとって「月ノ美兎」その人なことは明らかだ。
A22.
楽しいことが「僕」にとっては「星座」を成すように、
楽しいことが沢山集まって「わたし(月ノ美兎)」が形成されていること。
Q23.「雲を搾ったみたい」とはどういうことか
これだけ星々の話が出た時に「搾ったみたい」といえば、ミルキーウェイ(天の川)を連想するだろう。
「僕」が「座標の川」を見ている間、
「わたし」は「雲を搾ったみたい」なものを感じている、というのは、
先にも書いたように両者の視点の違いの顕れだ。
さて、Q22.で、骨と皮膚で「月ノ美兎の身体」が形成された。
その後の文脈で、「川のように流れるもの」が現れたら、何を想像するか?
「血液」ではないだろうか。
(月ノ美兎に限っては、天の川という概念を経由せずとも、雲は流れるものだ)
A23(?)
楽しいことたちが「わたし」の血液のように機能していること。
血液のように機能している、というのを更に踏み込む。
A23.
「楽しいことたち」があるから「わたし」は生きていられるということ。
※更に踏み込むと、「わたし」にとっては「僕」や「皆」もまた光る地図を持っているので、「楽しいことたち」の一部は「リスナー」たちで出来ている。「皮膚片」=「皆」の「光る地図」だという解釈とも合致する。
Q24.「わたしはどこにでも居られる」とはどういうことか
【楽しい場所の】どこにでもいられること。「いれる」=「生きられる」とも取れることを踏まえると、解釈は次の通り。
A24.
「わたし」は楽しいこと・場所を知ることができるし、楽しい場所に行けるし、楽しいことを出来るということ。また、「わたし」が生きていけるということ。
Q25.以上を踏まえて⑤の内容を解釈せよ
明かりが重なるところ 骨たちと
スキンが できていく
雲を搾ったみたいです みたいなので
わたしはね いれるのです どこにでも
A25.
作詞者(長谷川白紙さん)にとって月ノ美兎は、
星々が星座をなすように、楽しいものたちが集まって形成されている。その楽しいものたちの中には、リスナーたちが共有する人生・経験も含まれている。
月ノ美兎は楽しいこと・場所を知ることができるし、楽しい場所に行けるし、楽しいこともできるし、生きていける。
そして、配信活動もその一助になっている。
(雲が流れているので わたしは いれる)
5. Q.「光る地図」とはなんだったのか?
以上をまとめて、この曲の解釈を振り返ろう。
①
「僕(長谷川白紙)」は、「わたし(月ノ美兎)」の配信を見ることで、
普段忘れる息も動き出すし、地上の世界(恐らくは煩わしいものが沢山ある)から「由の上(宇宙、理由を飛び越えた世界、楽しい世界、月ノ美兎の世界)」に行くことができる。
②
月ノ美兎の話は、「僕」にとっては現実味が薄くさえ感じる「お伽話」で、だからこそ、それが自分の世界に近いかどうかなんて気にせず、いつもただ月ノ美兎の楽しいものを見ていたい。
③
でも、やっぱり「僕」は地上の世界に住んでいて、月ノ美兎が話してくれるような楽しい世界には入り込めていないことを自覚してしまう。
(長くて劇的な間奏、ここで視点が「わたし」に変わる)
④
自分の体験した楽しいことはみんなで共有できるし、
「わたし(月ノ美兎)」も皆に楽しいことを話すから、
皆にも楽しいことを共有してほしい。
一緒に人生を神ゲーにしよう。
⑤
そうやって、楽しいことをたくさん経験して、「わたし」自身が再構成されて、生きていけます。
この歌詞の「僕」の視点も「わたし」の視点も、「長谷川白紙」が書いている。しかもゴリッゴリの長谷川白紙ミュージックに乗せて。
じゃあ、「光る地図」とは何だったのか。
わたしが誰かに向けて歌詞を書くと絶対その人に向けたラブレターになってしまうため、今回も月ノ美兎さんへのラブレターになっており恥ずかしいです
— 長谷川白紙 (@hsgwhks) August 10, 2021
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
