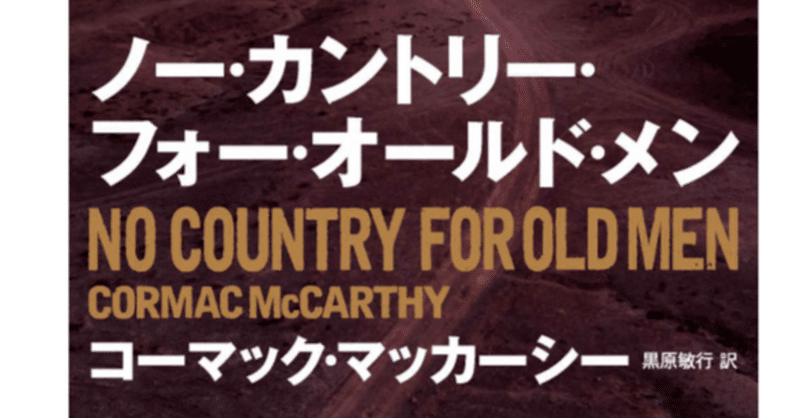
コーマック・マッカーシーの文章を読むと、「物語において必要な情報への感覚」が変わる。
いま「ノー・カントリー・フォー・オールド・メン」(以下「ノーカントリー」)を読んでいる。
めたくそ面白い。
ハードボイルドのような余計なものを切り詰めた端的な文章が好きなので、マッカーシーの文章も好きだ。
「ノーカントリー」はマッカーシーの他の作品と比べても、「そこを削る」という感覚がなかった部分まで削られている。
「ここまで削るのか」と驚いた。
例えば殺し屋のシガーが、ホテルで対立する殺し屋のウェルズを待ち伏せして部屋に連れ込むシーンだ。
(前略)それから受信機を廊下の窓敷居に置いて階段を降りロビーに戻った。
そこでウェルズを待った。普通の追手ならしないようなことだった。
革張りの肘掛け椅子を玄関と廊下の両方が見張れる隅に置いてそこに坐った。
ウェルズが十一時十三分に入ってくるとシガーは腰をあげ読んでいた新聞でショットガンをゆるく包んであとから階段をのぼった。
階段の中ほどでウェルズが振り返り眼を向けてくるとシガーは新聞を落としてショットガンを腰で構えた。
やあ、カーソン、とシガーは言った。
二人はウェルズの部屋に入りウェルズはベッドにシガーは窓ぎわの席に坐った。
こんなことはしなくていいのに、とウェルズは言った。
これを読んだ時、ぶっ飛んだ。
「そうか、これでいいんだ」と思ったのだ。
シガーがウェルズを「わざわざ」脅したり、すごんで見せたり、睨みつける描写や逆に狂気じみた感じを出すために笑ったりする必要はない。
ウェルズが驚いたり「やられた」と思う感じを出したり悔しがったり顔を青ざめさせたり諦めたりする描写もいらない。
第三者(書き手)視点でシガーやウェルズという人物を装飾したり、判断したりしなくていい。
シガーが「普通の追手ならしないような方法」で待ち伏せする。
ウェルズが「階段の中ほど」で後ろを取られていることに気付く。
すぐにシガーはショットガンを出す。
二人は特にもめることなく部屋に入り、一見普通な感じで会話を始める。
ここまで描写を削ることで、二人がどういう世界でどうやって生きてきたか、どういう背景を持つどういう人間かがむしろくっきり浮かび上がってくる。
脅したり睨んだり焦ったり余裕を見せたり笑ったり怒ったりする描写は蛇足どころか、それを書いてしまうと二人がどういう人間かがぼやけてしまう余計なものなのだ。
「ノーカントリー」はすべての描写が上記の引用文のように、情報が極限まで削られているので展開が凄く早い。
端的な説明だけで話が進み、風のように過ぎ去るストーリーの中で、ところどころ読み手の記憶にしっかりと留まる重要な印象が重しのように沈められている。
その「重し」の下ろしどころも、他の話とは違う。
主要登場人物は「撃たれた」「射殺された」「死んだ」のひと言で次々と死んでいく。余りにあっさり死ぬので、うっかり読み落としてしまうこともあるくらいだ。
「登場人物たちの死」は、「ノーカントリー」の中でフォーカスすべき重要なことではないのだ。
俺がお前の人生に登場したときお前の人生は終わったんだ。それには始まりがあり中間があり終わりがある。今がその終わりだ。
もっと違ったふうになりえたということはできる。ほかの道筋をたどることもありえたと。
だがそんなことを言ってなんになる?
これはほかの道じゃない。これはこの道だ。
シガーがカーラ・ジーンを殺す直前に言ったこの言葉通り、重要なのは「死」という結果ではなく、「その結果に至らしめたもの」なのだ。
「その結果に至らしめたもの」は何か?ということ以外の「死そのもの」は、「射殺した」の四文字で端的に表記されるだけで終わる。
カーラ・ジーンを死という結果に至らしめたものは何か?
恐らくは章始めに挿入される、ベルの語りだと思う。ベルの語りがシガーが言う「この道」なのだ。
自分もこういう枠組みで物語を書いて語れたらなあ。(小声)
*全体の感想。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
