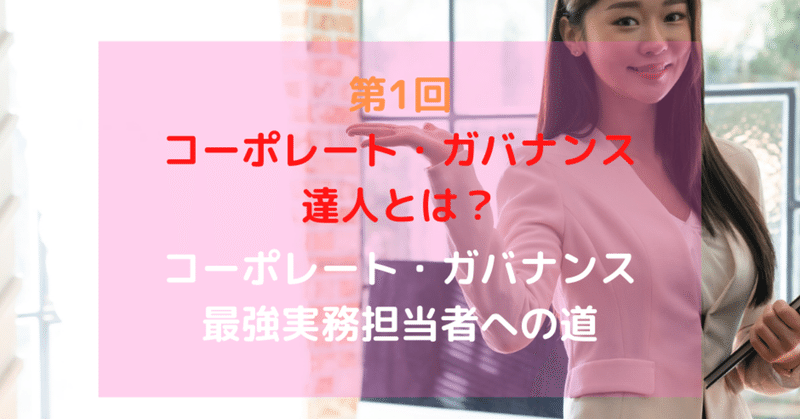
第1回:コーポレート・ガバナンス達人とは? コーポレート・ガバナンス最強実務担当者への道
こんにちは。
T&Aフィナンシャルマネジメントのさいとうです。
本連載は、上場企業でコーポレート・ガバナンスの充実に係る実務を担っている経営企画や総務関連担当の方を対象にした、「コーポレート・ガバナンス達人」を目指すためのものです。
世の中は2021年6月公表の新コーポレートガバナンス・コードの公表もあって、上場企業を中心にコーポレート・ガバナンスの話題が多く取りざたされています。
本質的なコーポレート・ガバナンスについては学者の方や当局からの解説書なども存在しますのでそちらに譲るとします。
実務家、特に中堅以下の上場企業の経営企画や総務担当の方にとっては、そんな本質的な「あるべき」コーポレート・ガバナンスというよりも、時代のトレンドに従って「やらなければならない」タスクとしてとらえられている節も強いかと思います。
それもそのはず、世の中には4,000社近い上場企業が存在しますが、いわゆる大企業といわれる、時価総額1兆円以上規模の上場企業はごくわずかで、多くは中規模以下の上場企業であり、かつ実際にはオーナーの意向が多分に影響を及ぼしている企業が大半を占めています。
そんな中規模以下の上場企業にとっては、あるべきコーポレート・ガバナンスを追求するというより、少しずつ、オーナーの顔色をうかがいながら時代のトレンドにあった姿に変えてゆくという姿が本当のところだと思います。
本連載は、大企業向けの本質的なガバナンスを論じるものではありません。
中規模以下の経営企画、総務担当が、その実情に見合ったガバナンスの姿を少しでもトレンドに合わせて変えてゆけるようにしてゆく指南書としての位置づけです。
連載のタイトルを「コーポレート・ガバナンス達人への道」としましたが、むしろ中規模企業特有の意思決定プロセスをへて、一つ一つのガバナンスを巡るイシューを「こなしてゆき」、少しでも世間が求めるガバナンスの姿に変えてゆくための連載です。
ガバナンスは会社の体質そのものです。
なかなか一朝一夕に担当者レベルで変えられるものではありません。
ただ、時代が求める上場企業へのガバナンス水準は上昇してゆく一途です。
なんとか時代が求めるガバナンス水準に近づけるべく、一緒に考えてゆきましょう。
≪T&Aフィナンシャルマネジメント≫
T&Aフィナンシャルマネジメントはベンチャー企業に特化した経営財務支援、クライアント目線に立った中小規模M&Aのご支援をしております。
また、上場企業をはじめとする大企業~中堅企業の経営企画をはじめとする経営管理部門のサポートなど、幅広なご支援をご提供しております。
コーポレート・ガバナンスを巡る実務的な課題
世の中のコーポレート・ガバナンスの本質的な論文などを読むと、「エンロンやワールドコムといった米国におけるガバナンス強化の潮流が日本にも~」的な文脈が語られていますが、中堅規模の上場企業担当者にとってはコーポレート・ガバナンスの「生い立ち」など、正直どうでもよいと思われます(言い過ぎでしょうか??)。
表面的と思われてしまうかもしれませんが、中堅規模上場企業担当者にとってのメインテーマは、以下の通りかと思います。
新コーポレートガバナンス・コードの公表とともにいくつかの「課題」が提起されている
「課題」を期限までに解決するために準備とともに社内調整をしなくてはならない
将来本質的な議論をするために、まずは体裁だけでも世の中的なガバナンス体制の構築が必要
では、新コーポレートガバナンス・コードによって提起された「課題」を列挙してみましょう。
ちなみにコーポレートガバナンス・コードは法律ではなく、金融庁、東京証券取引所が公表した指針に過ぎません。
従って、それを充足しないことで何かの罰則を受けたり、何か不利益をこうむったりすることは直接的にはありません。
しかし、上場企業はコーポレートガバナンス・コードの遵守状況をコーポレートガバナンス報告書で「コンプライ(遵守)」するか、「エクスプレイン(説明)」するかが求められており、かつ2022年に予定されている東証市場区分変更における最上位市場であるプライム市場への上場においては、基本的にコード全項目にコンプライすることが求められています。
このことから、指針であるとはいえ、上場企業にとってはコーポレートガバナンス・コードを無視することはできないものと考えられます。
【新コーポレートガバナンス・コードによって提起された「課題」】
・議決権電子行使プラットフォーム
・SDGs対応、サスティナビリティ、ダイバーシティ対応
・社外取締役登用の拡大
・スキルマトリックス
など
電子議決権行使プラットフォームといった、導入するだけでよいものから、若干の社内調整が必要なスキルマトリックスなどがある一方で、SDGsやサスティナビリティといった全社を巻き込んだ深い論点など、様々な課題が改めて提起されることになりました。
先ほども申しました通り、ガバナンスは会社の体質であり、本質的にガバナンスを変革しようとおもったら、正直数年の議論を要するかもしれません。
また、本気で意義あるSDGs対応やサスティナビリティ対応を行おうと思った場合、コストも莫大にかかりますし、何よりも企業のサプライチェーンそのものを根本的に見直す必要もあり、簡単ではありません。
担当者としては、トレンドに即したガバナンス体制をまずは表面的に構築し、本質的な議論を後追いでできるための仕組みづくりを早急に整える必要があると考えています。
本連載では各々の課題について、まずは担当者としてどの水準まで早急に到達させるべきかのマイルストーンを提示しながら、その到達点へ向けての実務的なハウツーをご説明してゆこうと考えています。

まとめ
コーポレート・ガバナンスの充足は時代のトレンドです。
企業が上場している限り、ガバナンス強化の圧力から逃れることはできません。
しかしながらここでもご説明した通り、本質的な議論ばかりしていては、いつまでたっても前に進むことはできません。
実務的にはまずはトレンドに見合った制度を作ってみる、というスタンスが肝要かと思います。
この考え方に賛同できない人も少なからず存在するかとは思いますが、しかし中堅規模以下の上場企業の企画部門の実態を踏まえて、賛同していただける方も多く存在するものと思っています。
決して本質的な議論をないがしろにするつもりはありませんが、限られたリソースで走っている中堅規模以下の上場企業担当者にとって少しでもお役に立てればと思い、この連載を進めてゆきます。
次回以降にご期待ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
