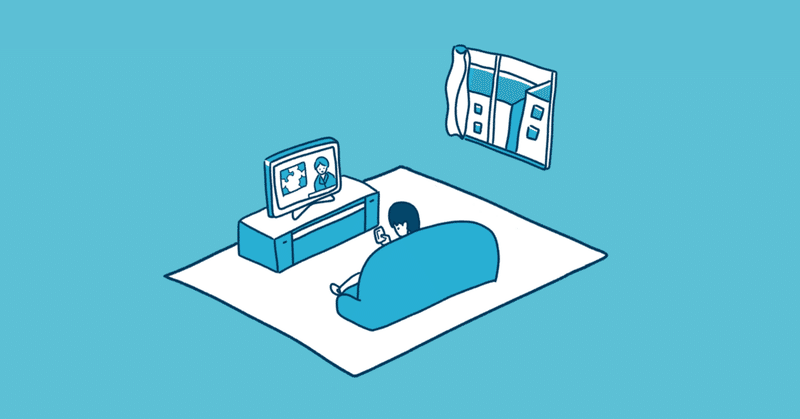
自分自身との対話
◆こんにちは。小学校教員のねこぜです。教育現場では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて試行錯誤が続いています。この対話的という文言についても様々な議論がありますが、一つに対話の相手は誰か?ということがあります。子どもの学びですから、友達との対話もあれば、先生との対話もあります。加えて自己との対話、ものや教材を通して先哲との対話も含まれるでしょう。学校であれば、このようにある程度限定的にポジション決めができます。一方、生活に目を向けると学校外の人間や物事も対話の相手に入ってきます。家族、親戚だけでなくSNS上の人々…インターネットが普及し、今では誰でもスマホを手にし、常時接続された世界を生きています。常に対話の相手に囲まれているといってもいいでしょう。谷川嘉浩さん著『スマホ時代の哲学』を用いて学んだこと考えたことを書いていこうと思います。
1.失われていく自己内対話
以前、対話的な学びをする際に安易にグループ活動を取り入れる危険性を指摘したことがあります。「話す」ことは普段他者に向かって行われます。しかし、独り言が思わず出たり、心の中で「ああかな、こうかな」と考えることが大事だと思います。この心の中でゆっくり考える時間が失われているのではないかと谷川さんは指摘します。対面で誰かとランチしているときでさえも、スタンプや短いテキストでLINEを送ったり、ソシャゲで周回したり、TwitterやInstagramの投稿を流し読みしたりしています。このちょっとした注意の分散、反射的コミュニケーションによって<孤立>が失われているというのです。ここでの<孤立>は<孤独>とは違います。これに関しては臨床心理士である東畑開人さんの『聞く技術 聞いてもらう技術』に詳しく書かれているのでまたの機会に触れていきたいと考えています。
さて、先程のようなマルチタスキングによる注意の分散をアテンションエコノミーという消費社会による発現と捉えることができます。オンラインサロンやYouTubeチャンネル、ウェブ広告などによるクリック数や売り上げといった経済活動につながるものです。注意を引こうと競走している状態はあえて炎上するような発言をTwitterに流したり、サムネイルを工夫した動画などを想起してもらえれば分かることでしょう。しかし、このような状況に陥ってしまったのは企業やインフルエンサーの人たちのせいだけではないというのが谷川さんの主張です。
私たち自身が、日夜スマホを通じて注意を分散させる試みに喜んで参加していることを進んで認める必要があるでしょう。スマホを触りながらの対面コミュニケーションでは、相手の会話は薄く聞くだけ、小難しい内容は無視する、何か聞かれたら生返事、そんなやりとりが関の山でしょう。こんな環境で、「消化しきれなさ」「モヤモヤ」「難しさ」の類を抱えておくなんてやってられないとしか思えないはずです。
学校の教育ではまさにこの「消化しきれなさ」「モヤモヤ」「難しさ」をこそ大事にした対話的な学びを目指すべきなのだと考えます。ところが、スマホを通じて注意を分散することに慣れ切った私たちは、スマホを使っていないときでさえ、気もそぞろで対面のやりとりをしているのではないかというのです。スマホを一旦置いてじっくりゆっくり自分と対話することすら、困難になってきているということです。
2.ネガティブ・ケイパビリティに慣れる
先程のような「消化しきれなさ」や「モヤモヤ」「難しさ」を抱え込んでおくことをネガティブ・ケイパビリティと言います。正確な定義づけではありませんが。ネガティブ・ケイパビリティとは、イギリスの詩人ジョン・キーツが提起しています。ケイパビリティにネガティブという消極的な意味を付け加えられた単語で、「結論づけず、モヤモヤした状態で留めておける力」という表現で解釈できると思います。
物事は複雑化して考えた方がよいのですが(内田樹先生がそう言っている)、世の中は単純化して考えたがります。「要するにどういうこと?
?」「じゃあどうすればいいの?」「簡単に説明して」という言葉で溢れています。140文字で表現するTwitterも写真だけ投稿するInstagramも、スタンプや短いテキストを送り合うLINEも単純化したメディアです。バンッと一目で分かる広告やサムネイルの動画、リールが受けるのも、単純化した方がいいという私たちの慣れの果てです。
一旦留保する、難しく考えてみることを手放すことの危険性を直視したい。ネガティブ・ケイパビリティをもたらす教育が一つの手がかりになるのではないかと考えています。例えば、「これでいい!」と自己を固定せず、「これでいいかな、やっぱこうしようかな」と右往左往する自分を肯定できるような。ここでも「ハッキリしなさい!」とか「端的に言いなさい」のような教育者(親も教師も)の姿が立ち上がるわけですが、自己内対話とは自分の心の中にどれだけ多様な他者を住まわせておけるかだと思います。先のような教育者の在り方もきっと「こうあるべき」が先行しているのです。
結論を急がず、自分と対話すること。それには何より時間が必要だと思います。デジタルデトックスをする人もいますが、どうせすぐ戻ってくるので、そうではなくうまく距離を置くこと。スマホが嫌になってから距離を置きだすのではなく、上手な付き合い方を模索するために距離を置くこともありだと思います。
長くなってしまったので、中途半端ですが終わります。自分が「モヤモヤ」してうまく言語化できない証拠ですね。一旦思考を寝かせることもまた(外山滋比古先生流に言えば)一つの手なのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
