
#0001
スープ缶とドル札、エルヴィスにマリリン、音楽と映画、銀髪と眼鏡。
自分の身の回りを悉く「自分色」に染め上げて行ったアンディ・ウォーホルというアーティストはあまりにも強烈な印象を周囲に残し、何だか空っぽなのに尊大だという、つまりはアンディ・ウォーホルだとしか表現出来ない不思議な偶像をその生涯で作り上げてみせました。
そのレガシーは凄まじく、現代でも最も人気のあるアーティストの1人でありその作品は高値でやり取りされ、世界中のどこかで常に回顧展が開かれる。ファッションの一部としてグッズが販売され、また模倣品も大量に生産・消費されています。
築き上げられた名声は不動のものとなり、挙句には彼が言わば片手間に製作した一連の映画群に於いても「前衛映画・アート映画・アンダーグラウンド映画」など適当なレッテルを貼って評価するというのが一般的な世間の潮流となっている始末です。
しかし映画作家としてのアンディ・ウォーホルは一体それほど優れた表現者だったと言えるのでしょうか。ここでは「アンディ・ウォーホル」という虚構の中から映画作家アンディ・ウォーホルの実態を取り出し、その影響を映画史の中に位置付け点検してみたいと思います。

さて彼の作品と言えばポップ・アート、特にキャンベル・スープ缶を大量に並べた版画が特に有名かと思います.
人工的な商品、消費対象物であったスープ缶をわざわざ「芸術品」と銘打ってギャラリーに並べ、また版画という製作手法のアドバンテージを活かし文字通り作品を量産することで彼の「芸術品」はキャンベル缶と奇妙な並行関係を築くことになるでしょう。
ありふれた消費対象物が芸術となることでそこに投げかけられたイメージ(意味)もまた消費対象物となるのであり、この時人口に膾炙した有意味=無意味な芸術、ポップ・アートが誕生するのです。少なくともアート・ワールドではこの様に理解するのが定説ですね。
ここで注意しなくてはならないのは、ウォーホルのポップ・アートに見出される大量消費社会の風刺をポップ・アートの価値と等価に結んではいけない、ということでしょうか。本人が生前繰り返し語っていた通りウォーホルにとっては表層こそが全てなのであり、何でもない消費物をウォーホルが手掛け、購入されるからこそ、そこに価値が生まれるのです。つまりはポップ・アートがあればそれはウォーホルなのであって、ウォーホルが風刺を込めて作った故にアートに価値が生まれるのではなく作品とウォーホルの持つイメージは殆ど不可分、ウォーホル自身が消費される意味そのものなのだ、ということです。
ちょっと分かりやすく考えてみましょう。
ヴィレッジヴァンガードか、何処かそうした雑貨屋に行くとウォーホル風、ポップ・アート風のイラストがプリントされたマグカップやポスターを見ることがあるかも知れません。或いは貴方がふと訪れたアメリカン・ダイナーの壁紙にプリントされているかも知れませんし、GUやZaraのTシャツ売り場でそれを見かけるかも知れません。電車で隣に座った女子高生のスマホカバーにウォーホルが手がけたマリリン・モンローが微笑んでいることだってあるかも知れない。
ポップ・アートの「ポップ」なイメージ。これは時代を超えても引き継がれ国境を超えて人々の間で生き残り続けています。
「アンディ・ウォーホルってカッコいいよね、オシャレだよね、カワイイよね。」
皆がこう考えているということ、皆がウォーホル印のポップ・アートに夢中になっているということですね。彼の最大のマジックはこの「ウォーホルが」皆を夢中にさせるという点にあり、即ちウォーホルが自分自身を1つの大きな意味の中に投げ出したということ、消費されるイメージの中に自分を結びつけたということの結果が彼をポップなアイコンたらしめています。従ってアンディ・ウォーホルはウォーホルであるからカッコいい/オシャレ/カワイイのであり、故にウォーホルの作ったカッコいい/オシャレ/カワイイは面白い、ということになります。
似たような議論としてデュシャンのいわゆる泉問題がありますが、あちらは嫌でも高尚な概念論議に発展せざるを得ないのに対し、ウォーホルの場合はウォーホルだから、何となくカッコいいから、ポップだから、で解決させてしまうのですね。
件のスープ缶についてウォーホルは1962年にTIME誌上で取り上げられたことをきっかけに彼は初めてギャラリーで自分の作品を展示。そこから彼の名声は鰻登りに高まり、一気に時代の寵児・スーパースターと目されるようになっていきます。
そうした中で1963年、ウォーホルはスタジオを設立。エルヴィス・シリーズなどを製作する傍ら最初の映画、”Sleep"を発表するのでした。

これは上映時間5時間21分にも及ぶ作品で、その内実は眠る男のクロース・アップをループで見せ続けるだけというこれまでの映画規範からは(否、現代の映画規範からも)考えられない、退屈極まりない作品となっています。
アカデミックな文章を読むと「ウォーホル流の実験映画。彼がポップ・アートで実践したのと同様それまでのアートの慣例に逆らい、工業化という視点を映画に持ち込んでフィルムの全てのショットが等価になるようにという意図の元に製作された」云々などと書かれているでしょうか。
彼がスープ缶という日常を量産したのと同様、睡眠という日常に目を向け、それを繰り返すことで量産させてみせた、という文脈でこの映画は捉えられているようです。同様にエンパイアステート・ビルディングを8時間5分にわたって写し続けた"Empire" (1965)という映画も発表しており、この2本は今では彼の代表作となりました。
しかしながら私はここで1つの疑問を呈したいと思います。
眠る男の姿を写し続けること、何も変わらないビルの姿を写し続けること、映画の慣例に逆らうことは果たして「ポップ」なのでしょうか?
アンディ・ウォーホルのポップ・アートはそれまでギャラリーなどで富裕層、一口に言ってしまえばブルジョワ向けに製作・展示・販売されていたアートを一気に無知な庶民でさえもが何となく良いと思うような、そして挙句には量産され彼らが購入出来てしまうような、ロウ・ブロウなものへと変換する試みでもありました。ここで先ほどの「アンディ・ウォーホルってカッコいいよね」というイメージ戦略が生きてくる訳ですね。
対して映画は遅くとも1930年、40年になる頃には完全に庶民、国民全体が楽しめる娯楽として発展を遂げており、更に言えばアメリカでは1910年頃からNickelodeon(ニコロデオン)映画館が全国に展開し、ワンコインで気軽に鑑賞できる道楽として普及もしています。
もちろん芸術としての側面はあれど、庶民が愛した映画に対してアンチを突きつけた彼の作品は概念上はポップ・アート的であっても果たして本当に「ポップ」として成立したのか、大きな疑問が残る部分ではないでしょうか。

これは恐らくウォーホル自身も感じていた部分だったようで、初期こそこのような観察的映画、"Sleep"、"Andy Warhol films Jack Smith filming 'Normal Love'"、"Haircut"などなどカメラを極力動かさず、何らかの日常的行為を観察するアンチ=映画的映画を製作していた彼ですが、1963年に"Kiss"、そして1964年に"Blowjob"を製作し、創作の方向性を若干修正していったように見受けられます。
"Kiss"については後述するとして、まずは”Blowjob"について見ていきましょう。これは36分の映画で、カメラが切り替わることもなく淡々と1人の男の表情をクロース・アップで写した作品になります。
タイトルから暗示されている通り、男の様子は「口でされている」と思われるものですが、それは本当かどうかは分からず、また相手がいたとして男によるものか、それとも女によるものかも分かりません。
撮影手法自体は”Sleep"や"Haircut”と変わらない固定カメラ、監視カメラ的なものですが、以降何度も現れる性的モチーフの現れという意味で極めてウォーホル的であり、想像に頼るという点も多少の映画性をフィルムが獲得したという所から作風の微妙な変化が分かるのではないでしょうか。
1960年という時代に於いてウォーホルは数少ない同性愛者であるとオープンに知られていた人物であり、彼自身が何度も男性のヌードを作品のモチーフにしたように、自分のイメージの一部としてウォーホルも敢えて強く否定する、隠すということはありませんでした。
このことを踏まえると”Blowjob”という作品は自身の理想とする量産型/等価的フィルムの路線を継続しながらも、スキャンダラスなイメージ、性的にオープンでよりコンテンポラリーなイメージを取り入れた作品だとして見ることが出来るのではないでしょうか。つまりはウォーホル印をより深く刻んだ、ということですね。男の顔だけが映され観客に想像による補完を要求するという点からも一切の観る楽しみを奪った"Sleep"からはかけ離れているように思います(「ポップ」かどうかという疑問は残るとして)。
そして同じ1964年、彼は"Screen Test"と名付けられたプロジェクトを開始します。63年から後に「ファクトリー」と呼ばれるスタジオを設立し、様々の著名人やアーティスト、パトロンたちを招いては混沌の中で自身のカリスマ的イメージを増幅していったウォーホルですが、そのファクトリー内で友人であるスーザン・ソンタグやニコ、バーバラ・ルービンなどを招いて製作した一連の短編映画がこの"Screen Test"に当たります。
具体的には一切の問いかけやセリフ、アクション、全ての指示を取り払った状態でカメラを対象の人物(役者)に向け、すると大抵の人物は一分程度で沈黙に耐えきれず煙草を吸い始めたり、微笑んでみたりする訳ですが、そうした生のアクションを撮ろうというのがこの企画の趣旨、このことから分かる通りやはり固定と日常をテーマにしていながらも、ウォーホルの興味関心はより映画的な方向性へと修正されています。
ここでウォーホルは前衛映画として新たな映画表現を構築する試みに取り組んでいる訳ですが、その性格はアンチ=映画的なものではなく、寧ろ「映画の中で何が出来るか」というものに変化していると言えるでしょう。
”Sleep”が映画規範に逆らい映画的な楽しみを剥奪した作品であったとすれば、”Screen Test"の中では「どういった表現ができるのか、最も生のアクションとは何か、その結果どういった感想を観客は持つのか」といった疑問を立てて表現を追及している作品なのです。一般の観客にとって観る楽しみがある作品ではないかも知れませんが、それでも映画であることには変わりなく、また被写体が著名人ばかりだったということも相まって時代の主人公的なカリスマ性を持っていたウォーホルのウォーホルらしさがより前面に表れていると言えるでしょう。
つまりは当初映画に手を出したウォーホルは自身の「ポップ」を失って退屈な作品作りに終始していましたが、"Kiss"、"Blowjob"を経て”Screen Test”でウォーホルらしさ、「ポップ」の演出にも挑戦し始めたと捉えられる訳です("Empire"や"Eat" (1964)など完全に当初の路線を放棄することはありませんでしたが)。
1965年には"Vinyl"、1966年"Kitchen"、そして"Chelsea Girls”と劇的性格、ドラマ性のある実験映画を製作していることからも分かるように、彼のポップ路線への回帰はやはり明らかであるように思います。
"Vinyl"は『時計じかけのオレンジ』を原作に(それを現場では放棄して)、1人の暴力的、反社会的な男性が如何にして矯正され、貶められていくのかという過程が描かれます。この間カメラは殆ど動くことはなく、挿入されるカットもただの一回。全てのドラマ的要素は単一の画面に圧縮され、起伏は無に還り、エロティックでサディスティックな拷問の様子も平板な背景の一部へと呑まれていってしまうでしょう。
これはウォーホル自身に付き纏ったアンダーグラウンド、新時代的イメージの活用であり、ショットの取捨選択、つまり映す/映さないという関係について実験した映画でありながら、それをウォーホル的なポップさで表面的に時代に投げかけた作品だと言って良いと思います。この手の映画としては非常な好評を博したのもそれ故でしょう。
"Sleep"ではカメラに映るもの=男の顔が如何に等価になるかということに意識が向けられていましたが、それは既に指摘した通り非映画的な試みであり、解体不要なものを解体しようとしていたのでした。対して"VInyl"は既存のドラマに載せることで映画というメディアにギリギリで留まりながらもそのフレーム内をなるべく等価で無意味なものになるよう製作されています。ウォーホルの芸術家的関心とポップ・アート的試みが上手く交わった映画となっており、客観的に本作は最も優れたウォーホル映画として現代に伝えられています。

翌年の”Kitchen"はウォーホルが撮影前に初めてリハーサルをしたと言われている作品で、”Vinyl"にも出演した当時のミューズ、イーディ・セジウィックを主演に迎えた本作はドラマ的性格が一層強化された作品となっています。
スタッフの立てる雑音がそのまま録音されている、カットは相変わらず忌避される、台詞が場当たり的で不明瞭など確かに実験映画的側面は残していますが、演出の中心に居るのは明らかにイーディその人で、彼女の憂鬱、魅力、そういった美観を基盤にこの作品は成り立っています。
一言で言ってしまえばウォーホルが自分のミューズを迎えて彼女が如何に美しいか説明した映画、ということなのですが、これも”Sleep”の頃の彼の作風からは全く考えられない進歩であり、またイーディがVogueなど当時ファッション誌の表紙を飾る売れっ子モデルだったことを踏まえると、相当にポップな映画だと分かるでしょう。現代で喩えればスカーレット・ヨハンソン見せたさに映画を撮っていた2000年代のウディ・アレンといった感じでしょうか。
"Chelsea Girls"ではミューズがイーディからニコ(Nico)へと変化する中でより直接的に「ドラッグ&ロックンロール」的なイメージを前面に打ち出していきます。分割された画面、圧倒的なカオス、そこに描かれているのはファクトリーの実体そのものであり、つまりはウォーホル印のポップ、彼のカリスマ的イメージです。人によってはウォーホル作品の中でも最も鑑賞しやすい(入手難易度は別にして)と評価もされる本作ですが、それはスープ缶やマリリン・モンローなど現代で一般に広まっているポップ・アーティスト、アンディ・ウォーホルのイメージに一番適っているからではないでしょうか。
総括です。アンディ・ウォーホルというアーティストの作風・個性を考えた時に彼を最も適切に表現する言葉はやはり「ポップ」、ウォーホルだからカッコいいと何となくも思わせる力、それに尽きると思います。
このことを踏まえて彼が手がけた一連の映画群というものを見ると、確かに作風の根幹は最一作”Sleep”に見られる普遍性/等価性にあると考えられるものの、そのすぐ後からウォーホル自身がより多様な作風を手がけていること、そしてウォーホルというアーティストが自己ブランディングに意識的だったことも考えると、映画作家としての彼は”Vinyl"であったり”Chelsea Girls"に見られるような「ファクトリー」の喧騒をそのまま写した様な作品を追い求めていたと考えられるでしょう。そもそも現代では「ファクトリー」的な価値観が共有されておらず、また参加した人物のクールも感じにくいところではありますが、60年代当時には「ファクトリー」こそがNYカルチャーの最先端であり、従ってウォーホルのカリスマ性を象徴する機関に他なりませんでした。
ですから狂乱過ぎ去った現代、オープンな性、トランス・カルチャーなどに「クール」や「最先端」といったイメージは伴っておらず、従ってそれらを「クール」として表現していたウォーホルの映画は魅力的に映らないと言うことは可能でしょう。一番優れていると言える"Vinyl"でさえ正直に鑑賞にはかなりの苦痛を伴います。
それでは映画作家アンディ・ウォーホルの名前は今後忘れられていってしまうだけなのか。私としては3本、鑑賞に堪える面白さを持ち尚且つ映画史的にも重要な作品が存在すると考えています。最後にその3本を紹介して終わりとしましょう。
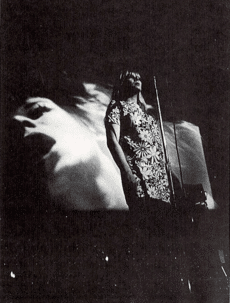
1本目は"Exploding Plastic Inevitable"、これは正確にはウォーホルが主催したイベントの名前であり、映画として残されているのはロナルド・ネイミス(Ronald Nameth)がその内の1日をカメラに収めたものになります。監督アンディ・ウォーホルとしてはクレジットされていませんが、出演者は前述のNico、そしてウォーホルがプロデュースを手掛けたThe Velvet Underground、彼自身も自作の映画を背景に流したりと「ウォーホル印」が至るところに貼り付けられたものとなっており、ここではウォーホル作品の1つとして数えたいと思います。
映画自体はサイケデリックなライトに照らされたライブ映像に過ぎず、カメラもブレブレ、質としては全く酷いものです。しかしながらこの”Exploding Plastic Inevitable"というイベント、世界で初めてのMidnight Movie(深夜上映)だと言われているんですね。
映画研究の中で普通Midnight Movieと言えば深夜の映画館でロングラン上映されカルト映画となり1つの文化を形成した作品のこと、例えば『ロッキー・ホラー・ショー』(1975)であったり『イレイザー・ヘッド』(1977)が有名ですが、こうした映画のような深夜に何度も上映され、ひいては観客が歌ったり、踊ったりと鑑賞体験にアクティブに参加する、そうした作品の先駆けとなった作品のことですが、その元祖となったのがこのイベントでした。具体的には映画を背後に流しながらライブ・パフォーマンスがあり、照明があり、観客が踊ったり、お酒を飲んだりする。そうしたコミットメントを見せた、それが映画史上では初めてだったと言われているのです。
これには実は少しミスリーディングな部分もあり、きっとこうしたコミットメントというのはジョナス・メカスが主催したシネマテークなどで通常に行われていたことではないかと思うんですね。ただそれが明らかに認知される形で実施されたのは”Exploding Plastic Inevitable"が初めてであり、またウォーホルのカリスマ性もあって映画史上初と語られるようになったのではないかと考えられます。
いずれにしてもそうした確固たるレガシーを本作は保持しており、その点で今後も定期的に参照されることになる映画なのではないでしょうか。

次いで2本目は1969年にウォーホルが監督した”Blue Movie"を取り上げましょう。これはアメリカで広く劇場公開された長編サウンド映画の中で初めて露骨な性的行為を含む作品として記録に残っており、ポルノ映画、MIdnight Movies、エクスプロイテーション・映画、ジェンダー・スタディなど様々な側面から参照されることのある作品です。
上映時間105分に対して実際の性描写は30分ほど、残りはテレビを見たり、歌を歌ったりという退屈な行為が並べられ、その中でセックスは或る夕下がりの行為の1つになってしまうでしょう。役者2人の会話も絶え間なく、政治、ベトナム戦争といった話題からよりカジュアルな話題、例えばブラを着けないことについてなどに及びます。
ポルノ映画という触れ込みからはエロチックな性行為を想像しがちですがそこはウォーホル、セックスも極めて実験的なものとなっており、女優がカメラの写りを気にするような発言をし、いわゆる「第四の壁」(映画と実際の観客の間に存在する壁のこと、普通映画はこの壁を超えず、役者はカメラに撮られているということを意識しない)を破るなどの試みがなされています。
先述の通りジャンル映画、ジェンダー・スタディという観点から興味深い作品であることも事実ですが、この映画、ウォーホル作品の文脈を踏まえてみても面白い作品であり、というのもこの”Blue Movie"は一連の”Screen Test"の延長となっているからです。
”Screen Test”は演技を求めないことによる生のアクションについて観察するものでしたが、所で映画は喩えそれがアマチュア役者による即興演技出会ったとしても、カメラを用いて撮影される以上全てのアクションは演技の一形態にならざるを得ません。詰まりは”Screen Test”とは演技と自然が表裏一体で連なる不思議な状態を作り上げていると理解することも出来る訳ですが、その演技=即興芝居という表現を拡大し、1つの日常を描こうとした試みがこの”Blue Movie”にあたる訳です。
役者は脚本を与えられず、実名と同じ役名で殆ど即興の芝居を延々と繰り広げるのですが、その中で思いつくままにカメラの位置についても言及してしまいます。それは観客にとって極めて不自然なことであり、しかし同時に役者はリラックスした、自然な状態でいるのであって、自然と不自然が歪にオーバーラップしていくでしょう。その自然な行為の一部として、我々が常に関心を持ちながら社会の下に隠してきたセックスが取り込まれているのでした。

3本目、最後に取り上げる映画は1963年の”Kiss"です。正直ウォーホル作品には注釈付きの評価でしか面白さを語れない部分がありますが、この映画だけは文句なしに彼の最高傑作であると、そして同時代の実験映画/前衛映画の中でも最も優れたものの内の1つであると手放しで賞賛したいと考えています。
スロー・モーションを織り交ぜて13のカップルがキスをする様子をクロース・アップで捉えただけの本作ですが、2つの観点から革命的な意味を持っており、その1つはまずは単純に「キス」をしている、ということでしょう。ハリウッド映画に於いてこの時代はまだヘイズ・コードが健在だった時代でもあり、従ってセックスというのは表現の対象外にありました。また性描写に対する許容範囲(tolerance)も現代とは比べものにならないくらいに小さく、必然的に男女(敢えてこう書いています)が親密さを見せる描写も少なくなりがちでした。
その中でキス・シーンというのは決定的なパンチライン、ゲームで言うところの必殺技のようなもので、特に重要な場面でしか用いられることもなく、そして実際にキスを見せる際にはそれはセックスの暗喩となっていることも多い。絵本の中の食事シーンのようなものですね。
このようにハリウッド映画の中で特異な位置付けをされていたキスを作品の中心に据えるということ、それは即ち暗喩的ではない、表面的な行為としてのキスそのものを見せているということです。
これが何故重要なのかと言えば、もう1つの意味ですが、本作が映画史の総括/再構成を行っていると言うことが指摘されます。キスと言えば最も初期のサイレント映画に”The Kiss" (1896)と呼ばれるトーマス・エジソンの作品があるのですが、これは世界で最初にキスを収めたフィルムであり、つまり映画史の初めからキスはその内にあった行為でした。しかしながら半世紀以上が経った1963年の時点でも映画は特にアメリカでは殆ど進歩を見せておらずキス・シーンは多重の意味を伴う行為、つまりは「見せられた隠された行為」であり、その隠されている部分は肥大するばかりだったのです。それをエジソン的な素直な眼差しで捉えることによって、60年ばかりのハリウッドの歴史を表面だけで一直線に並べているというのがこの映画の本質でありました。
そして更に言えばこれ以前のキスは男女間のヘテロセクシャルなキスに限定され、それも白人の男女が殆どでした。そこをウォーホルは映画が生まれたエジソンの頃に遡ってキスという行為を取り上げながら、その中に男性同士のキスや異人種間のキスを含めてみせることで一気に時計の針を前に進めてみせたのです。これは非常に革新的なことであり、67年の映画史を総括しながらその後に展開されるだろう人種、ジェンダーの拡大までを予言したのでした。
映画ファンであればこの説明を聞いて『ニュー・シネマ・パラダイス』のエンディングを思い浮かべるかもしれませんが、正しくその通りでこのウォーホルの”Kiss”という作品は言ってみれば『ニュー・シネマ・パラダイス:サイドB』、本家が正当な映画史をなぞったのだとすればB面はそこから排除されていたものを含み未来を予言していたのです。
この総括と予言という部分は実験映画に於いての肝であり、この2つがどれだけ高いレベルで行われていたのかという点が作品の評価に直結する訳ですが、その意味で”Kiss”という作品は満点に値するでしょう。時代遅れであったり、鑑賞の意味を見出すのが難しいアンディ・ウォーホル作品ですが”Exploding Plastic Inevitable"、"Blue Movie"、そして何より”Kiss”は紛れもない映画史上に残る傑作であり、今後も繰り返し鑑賞されることになって欲しいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
