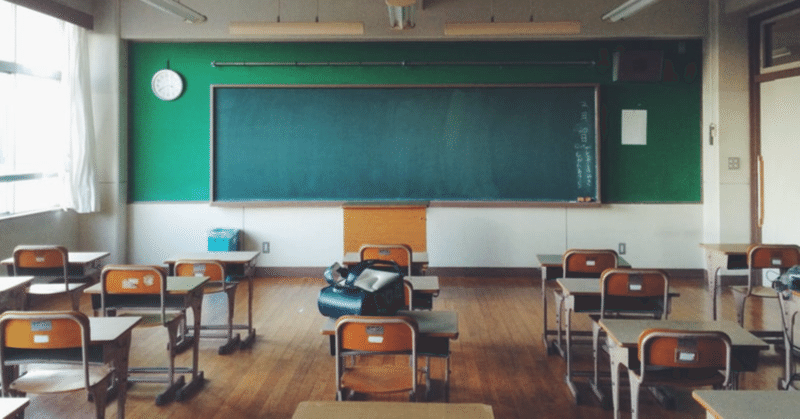
「そうだよ、だって、男の子だよ。」
たった1年間だけ同じクラスだった女子のAはとてもボーイッシュだった。私たちは特に仲が良かったわけではないが(現に私は彼女の名前をもう覚えていない。イニシャルも実際はAではないと思う。)、ベリーショートでスポーツ万能、話しぶりもさっぱりとしたAは、私にとって風のように心地よかった。
ある時、クラスメイト何人かで話をしていて、そこにAはいなかったがたまたま話題になり、私は思っていた事をそのまま口にした。「Aさんって、なんであんなに男の子みたいなんだろう。」
すると、以前からAと同じクラスだったという2人が即座に、毅然として、
「そうだよ、だって、男の子だよ。」「うん、そうだよね。」
友だちがLGBTである、と認識する経験はこの時初めてだったが、彼らがとても自然だったからか、私は「あ、そっか。」とストンと納得して、それきり違う話題になっていった。その後もとりわけ仲良しではなかったが、やはりAは風のように心地よい存在だった。
今になってみて、あらためて思うことがある。
Aは、私が出会う以前に、友人へのカミングアウトを経験していたのだろう。男子たちと女子たち、大人たちとの狭間で、悩み、怖れ、考える、そんな経験をしてきたことだろう。その時、ともに悩み、考えていた存在が、同級生の彼らなのだ。そして当時の私のように、誰かが「Aさんって…」と言う度に、彼らは共感と連帯をもって、自然とAの代弁者となってきたのだ。
学校という社会の日常の中で、私には気づけなかったような困難が、きっと幾つもあっただろうと思う。
でも、もしかしたら、私自身もいつの間にか自然の流れのように、その共感と連帯の中に、いたのかもしれない。自分で気づかないくらいに自然に。そうであったならとても嬉しい。
もしかしたら、まだ大人になりきっていなかった私は、自分の中にある性のゆらぎ、曖昧さを、Aとともに自分にも発見し、自分を癒し、そういう意味でも共感していたのかもしれない。
もちろんクラスがいつも団結していたわけではない。とりわけ私は学校生活が根っからの苦手だったし、毎日何を考えていたやら、何をやっていたのやらよく分からない、少なくも私にとってはそんな日々だった。けれど、例えばコミュニティの質というものがどのようにして作られるのか。そのヒントのようなものを、彼らは見せてくれたと思う。
学校は苦手、と書いたけれど、
Aの名前も覚えていない、と書いたけれど、
私は良い友に恵まれたと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
