
ピアサポートってなんだろう? // キセキ30
こんにちは。
幸紗チサ(さちさちさ)です。ご訪問ありがとうございます!
この記事は、こちらのマガジンの記事です。
👈前の記事 / 次の記事👉
2月もあっという間に終盤ですね。春一番が吹いたと思ったら、雪が降りだしたり…⛄ 寒暖差だけでなく雨も多いこの時期は、季節の変わり目そのもの。この時期に咲く梅や沈丁花の香りは、春の訪れを一足先に教えてくれるので、私はとても好きです。
さて、皆さまは「AYAweek2024」をご存じでしょうか?AYAweekとは、若い世代のがん啓発週間で、ピアサポートの活動も含まれます。2024/3/2(土)〜2024/3/10(日)の期間に、関連するさまざまなイベントが開催されます。
そこで今年のAYAweek2024に先がけ、イベントとも関連が深いピアサポートや、ピアサポーターについて語らせていただきたいと思います。今回は原点に立ち返り、「そもそもピアサポートとは?」「どんな活動をしているのか?」といった内容を、なるべくかみ砕きつつ掘り下げてみたいと思います。
では、どうぞ!
ピアサポート・ピアサポーターとは?

ピア(Peer)は英語で「仲間」「同僚」「同輩」という意味をもちます。ここでは、同じ経験や状況を共有する人々を指し、お互いに支援し合うことができる仲間や同輩を表します。
ピアサポートとは、そんなピア(同じ経験や状況を共有する人々)同士が、お互いに支援し合う活動を指します。特定の問題や状況に直面している人が自らの体験に基づいて、同じような境遇の人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動のことです。
ピアサポートの対象は、多岐に渡ります。例えば、精神疾患、アルコールや薬物などの依存症、慢性疾患、心身の障害、生活の変化や困難な状況(喪失体験、当事者の家族など)など、幅広い分野に展開されます。私たちの行っているがんピアサポートは、慢性疾患のひとつに含まれるわけです。

がんの治療は人それぞれで、がん種や年齢などによってまったく異なります。たとえば、入院、手術、放射線治療、薬物治療、移植など治療に関する経験や心境の変化など、当事者にしかわからないこともたくさんあります。そして、ひとくちに「がん患者」といっても、例えば希少がんや若年層の患者の場合、日常生活では経験を分かち合う機会にすら恵まれないことも多いのです。
そんなとき、ピアサポーターの出番です。ピアサポーターとは、ピアサポートを行う人のことを指します。がんピアサポートは、全がん種を対象にするものから、特定のがん種や年代を対象とするものもあります。例えば、今回のAYAweekは、まさしくAYA世代(15~39歳)が主役のイベント。こうしたイベントやサロンなどに参加してみることで、ピアサポーターと出逢うことができるのです。
このような機会は、専門家の指導や治療とは違いますが、同じ境遇の当事者にしかわからない苦しみや生きづらさを共有する機会となり、不安や孤独感を少しでも緩和できるかもしれません。また、今後の治療や生き方に関するヒントを得たり、同じ苦しみを抱えながらも懸命に生きる人たちから勇気をいただくことも多くあります。ピアサポートは、こうした精神的な支えとしての役割も大きいのです。
ピアサポーターの活躍の場

さて、ピアサポーターが活躍する場であるピアサポートの活動内容はとても幅広く、いろいろな活動があります😃 そんなピアサポートの世界には、どのような場があるのでしょうか?一般的な例を挙げてみましょう。
グループサポート:
同じ問題や状況を抱える人々が集まって、お互いにサポートし合います。患者サロン、患者会などがその例に当てはまります。患者さん同士で集まり、どこかへお出かけしたり、お食事したりするイベントなどもあります。
個別サポート:
一対一で行われるピアサポートで、個別にじっくりとお話を伺います。医療機関などでの、対面や電話でのピアサポートがこれに当てはまります。
オンラインサポート:
インターネットやSNSを通じて、オンラインサロンなどのピアサポートが提供されることもあります。場所や時間の制約が一気に緩和されますので、最近はこれがとても多いと個人的には思います。また、個人が自分の経験をSNSで発信するような活動なども、これに含まれると思います。これからのピアサポートには不可欠!
これ以外にも、ピアサポーターの活躍の場はたくさんあります。言い換えれば、ピアサポーターの数だけピアサポートがあると言っても過言ではないと思います。このように、とってもフリーダムなのです😆
ピアサポートで大切なこと
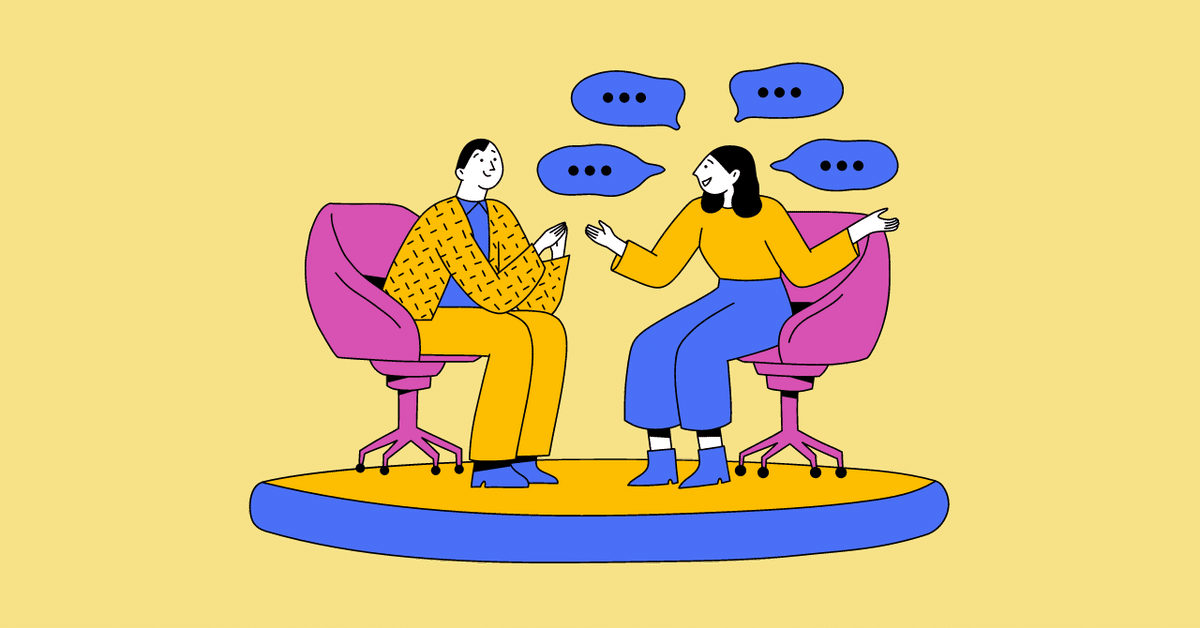
ピアサポートは自由な活動ですが、ピアサポーターとしてひとつ上を目指すには、必要な心構えを理解することも大切です。関連する知識はたくさんありますが、今回はその中でも聴く力と話す力についてお話させていただきたいと思います。
ピアサポートでは、相手の話を聴く力と話す力が非常に重要だと思います。
お話を伺う上では、その人の言葉でその人のことについて語ってもらうことがとても大切です。なぜなら、その人の心の内はその人にしかわからないからです。「今、私はこんな風に感じていたんだ」とか「これって自分にしかない強みなのかな?」と言葉に出してみて、初めて気づくことだってたくさんあるのです。
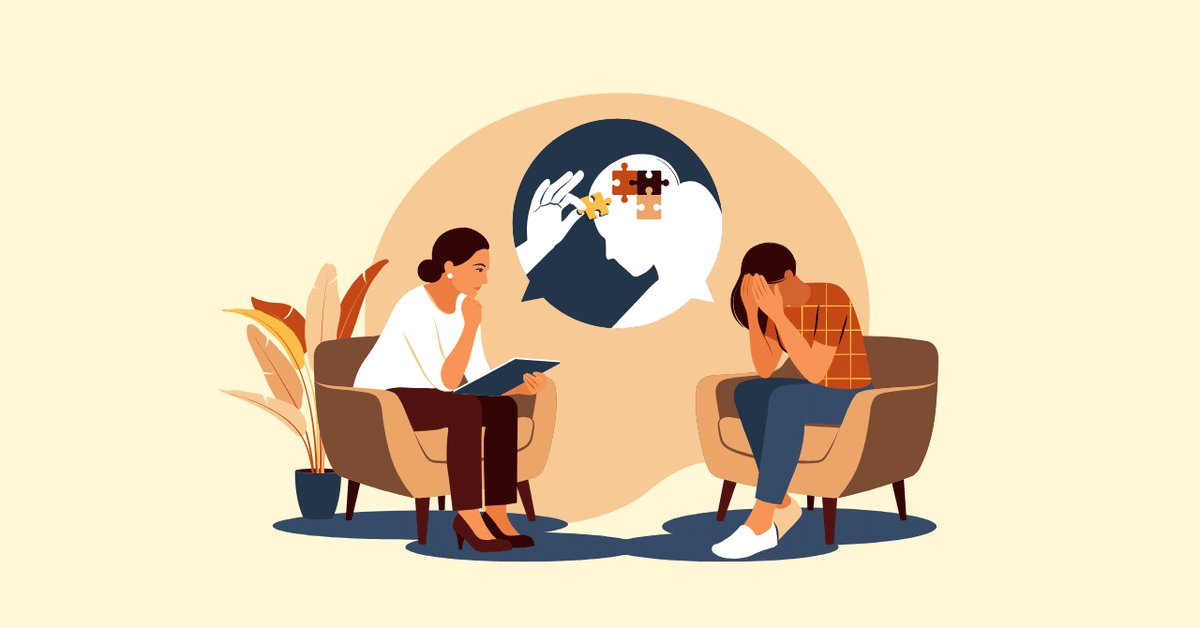
安心してご自分のことをお話いただくには、相手のことを考えながら真摯に向き合う姿勢や、質問などにより相手から言葉を引き出したり、引き出した言葉から「こんなことがあったのですね。それはお辛かったですね」と相手へ寄り添う姿勢、また話しやすい雰囲気づくりなどがとても大切です。また、多様な価値観を受け入れる姿勢や相手を批判しない姿勢も重要です。
どうすれば、「この人はきちんと話を聴いてくれているので、安心して話せるな!」と思っていただけるのか、私も常日頃から考えながら活動しています。会話を通じて、その人の強みを引き出し、気づきを得るきっかけへつなげていくことができれば、とても良いピアサポートになると私は思うのです。
他にも必要な知識は、まだまだたくさんあります。ご自身でも学んでみたい方は、次に紹介する研修も良い機会だと思います😊
ピアサポーターになるには?

がんのピアサポーターになるには、特定の資格が必要なわけではありません。当事者であれば、誰でもピアサポーターになれるのです。
しかしながら、医療機関などが提供するピアサポートは、ピアサポーター養成講座といった研修を受けていることを条件としていたり、特定の団体に活動を委託しているケースも多いです。また場所によっては、その地域(都道府県)で実施する研修を条件とすることもあります。
研修にご興味のある方は、「がんピアサポーター 研修 (地域)」で検索してみてください。きっと、一歩踏み込んだ深い知識を身に着けることができ、活動の幅もさらに広がることでしょう。
あなたもピアサポートへ!

いかがだったでしょうか?
がんは治療が長期に及ぶことが多く、なおかつ年代を問わず発生する病気でもあります。そのため、同じ境遇の人とつながる機会であるピアサポートが、今後の人生を自分らしく生きるためにも大切だと思います。きっと、初めての方でも温かく迎えていただけるのではないでしょうか。
もし、AYA世代のがんについてご興味のある方は、ぜひAYAweek2024のサイトで、開催されるイベントをチェックしてみてください!ホームページの下のほうにイベント情報はあります。
その他にも、ピアサポートに関連する活動はたくさんあります。一部ではありますが、こちらの記事の末尾でもご紹介していますので、よろしければご覧になってみてください🥰
皆さまのご参加をお待ちしています😍
👈前の記事 / 次の記事👉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
