
「能」「狂言」っておもしろいの?きっちり確かめる
■そもそもおもしろいの?
断言する。
この記事のタイトルを見て本文に入ってくれた人は、能・狂言に多少は興味を持っているはずだ。
しかし、実際にチケットを買って足を運んだことのある人は、ほとんどいないだろう。
少なくとも、私の周りで「観た」という人は聞いたことがない。というか、周りの一部は、来年2023年2月に行われるらしいレッド・ホット・チリ・ペッパーズ来日公演に今から浮かれている。
ということは、だ。
彼らにとっては、能や狂言を観ることより、東京ドームで米粒ほどの大きさしかないアンソニーを見ることの方が断然、価値があることになる。
たとえチケット代が、能・狂言:約5000円、レッチリ公演:1万8500円(最安席)と、3倍以上の開きがあったとしても。
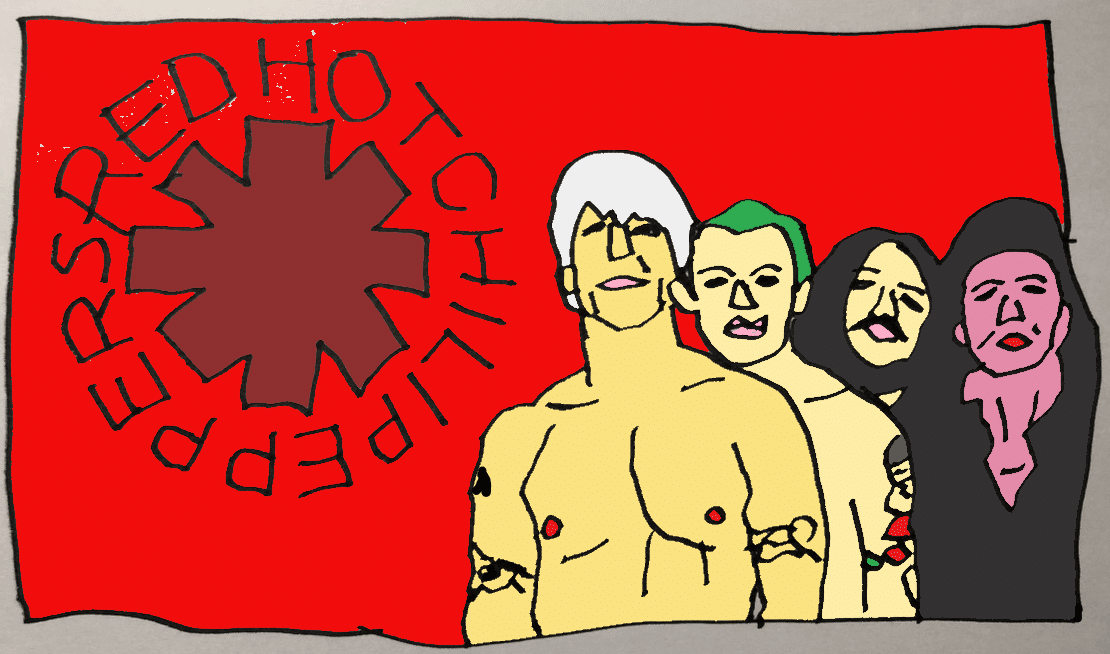
能・狂言にいまいち食指が動かない理由は、大きく2つあると思う。
教養がないと、理解できないかもしれない
理解できたとしても、おもしろくないかもしれない
そんな不安があるから。
確かに能や狂言といえば、お面をかぶった役者が「ヤマトノオ~~~~オ~~オ~~~」などとうなっていて、なにを言っているのかよくわからないイメージがある。
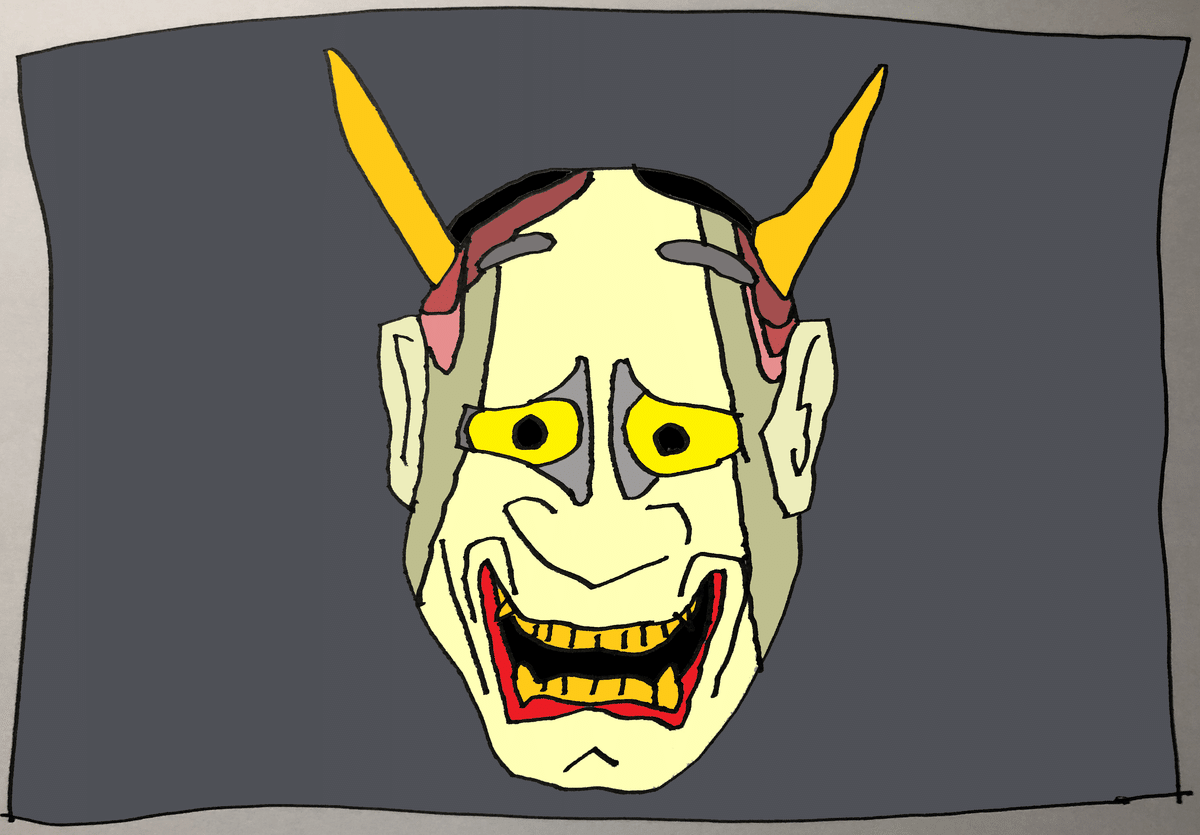
わざわざチケットを買って観にいったはいいが、一言も理解できなかった、そんな目にはあいたくない。
だったら「レッチリのライブの方が数百倍マシ、原始人まる出しのあいつらの音楽を理解するのに、教養なんてむしろジャマだし」と、東京ドームへ走るのもある意味、当然かもしれない。

だが、はたして本当にそうだろうか? 能・狂言を観るのに、古典の教養が必要だろうか?
いいだろう。これまでに一度も観たことがないのもなにかの縁。私が実験台となって、確かめてこようじゃないか。
というわけで、学校で習った古文の知識など、頭から煙のごとく消えうせた私が、ガチンコで検証する。問いは以下だ。
<問>
・教養がなくても、理解できるか?
・理解できたとして、おもしろいか?■チケットを買う
チケットの買い方は、インターネットで映画やライブのチケットを買う方法とほぼ同じ。私はGoogleの検索窓に『能 狂言 チケット 東京』と入力し、出てきたチケット販売サイト「イープラス」で購入した。その後、セブンイレブンで発券するという手順。

ネットで買うのが不安という人は、電話で買うことも可能。国立劇場チケットセンターにかける場合は、電話で座席を予約し、10日以内にセブンイレブンなどで料金を払う形。
※公演ごとに異なるので要確認
今回の目的は、これまで鑑賞したことがなく、古典教養もない私が能・狂言一般を、「理解できるか?」「おもしろいのか?」を検証することにある。
だから、かたよった内容でなければ、どの公演でもよかった。そんなわけでランダムというか、私のヒマな日の公演を選んだ。これだ。


正直に告白する。
狂言:『樋の酒』
能 :『天鼓』
この2つの演目、どちらもまったく知らない。聞いたこともない。
出演する役者さんも、野村萬斎氏のみどうにか知っているものの、申し訳ないがあとは誰ひとり存じ上げない。というか「出演:野村萬斎」が、テレビで見たあの人物かどうかも、確信が持てない。
私のレベルをわかっていただけただろうか。

■国立能楽堂へゆく
先ほど「どの公演でもいい」といったが、せっかくなので、能・狂言の総本山といった感じの国立能楽堂での舞台を選んだ。で、当日。






無事イン!


開場と同時に入ったのでガラガラに見えるが、開演15分前にはかなりの混雑状態。

ちなみに私はそこまで頭が回らず、パーカー+ジーンズ+スニーカーという、普段だったらなんの問題もない服装で行った。
結論から言うと、場違いではない。
しかし、呉服屋の旦那みたいな和装男性や、茶道のお師匠さんのような着物姿の女性もいらっしゃる。慣れない空間にまい上がって奇声を発するような行為は、くれぐれもつつしむように。

気づいたことが。
来場者ほぼ全員が、パンフレット的なものを読みふけっている。
初詣へ行ったらおみくじを引く
ディズニーランドへ行ったらミッキーの耳をかぶる
そういう「ならわし」の一種と解釈したので、私もさっそく購入。


中身を見ると、国立能楽堂で11月に上演される演目のあらすじや解説が載っている。フンフンと読みながら、いざ座席へ。
■これが能舞台だ
とりあえず、この圧倒的な和空間を動画で体験してほしい。
静謐。
まさにそんな感じ。
※重くて小分けにしました。スライドさせてください。
※係の方におたずねしたら、本番公演以外は撮影OKとのことでしたので、ずうずうしく撮りまくりました。ありがとうございます!
で、注目すべきはココ。全座席に小モニターがあって、日本語・英語で字幕を見られる。


なるほど。これなら劇中に話される昔言葉も、理解できそうだ。
だんだん観客でいっぱいになっていく。最終的に、ほんの1、2席を残すだけの満席状態だったのではないだろうか。

そして、本番。
■理解できるか?

わかったことがある。
ザックリ言いかえると、
「能」 =ミュージカル
「狂言」=お笑いコント
ということ。
『樋の酒』という狂言は、主人に留守番を言いつけられた2人組が、蔵の中の酒を勝手に飲んで、大盛り上がりしているところへ主人が帰宅する、というストーリー。

設定からしてコント。20分と短くて見やすいし、役者もうまい。観客は普通に笑っている。おそらく昔からの「型」があり、それにしたがった動きなのだろう。現代の演劇集団っぽい余計な動き・あざとさがそげ落ちていて、私もたくさん笑わせていただいた。
そしてもう一つの演目、能『天鼓』。
ある子供のもとへ、天から太鼓が降ってくる。その美しい音の評判を聞きつけた帝がとりあげようとするが、子供は拒否して殺される。太鼓は帝都へ運ばれたものの、どうやらあの子供以外には鳴らせないらしい。そこで子供の父親が呼ばれて、鳴らすよう命じられるという話。
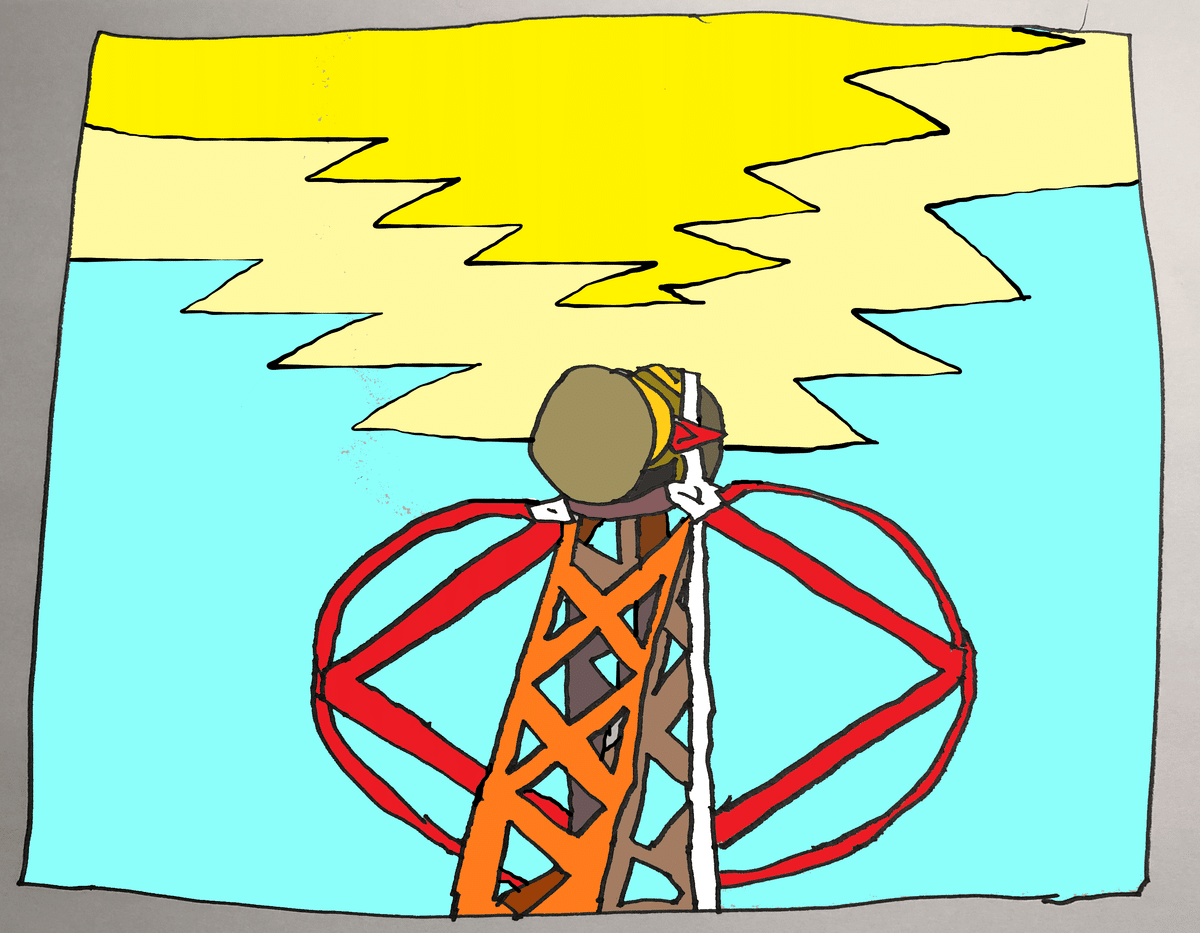
舞台は、子供を殺された父親のもとへ勅使が来て、「帝の前で演奏せよ」と命じる場面から始まる。ということは、観客はストーリーの途中から見始めることになる。
事前にあらすじを頭に入れておかないと、理解できないかもしれない。字幕があっても、たぶんキツい。パンフを読んでいたのが、功を奏した。
あと、80分の「ミュージカル」なので、ダレる部分は出てくる。しかし、それは現代のミュージカルや演劇、なんだったらハリウッド映画でも同じ。
個人的な感想だが、注目すべきは緊張感の盛り上げ方だと思う。
太鼓を鳴らすために「父親」、また「幽霊となった子供」が、能舞台の特徴である橋がかりを通って登場してくる場面がある。

けっこう長い距離を、けっこう長い時間をかけ、しずしずと歩いてくる。まるで時が止まったかに感じる数分間。
その時間は、この世ならぬ音、「天から降ってきた」太鼓の音を客席へ響かせるための、優れた前ふりとなっている。

この種の前ふり、どこかで見たことがある。
そう、1993年第27回スーパーボウルのハーフタイムショーでマイケルが見せた、1分45秒の沈黙と同じ効果だ。

なにが始まるんだろうという不安な状態が、長く続けば続くほど、観客の緊張感は増していく。やがて、ピンと張った糸が一気に緩和。
そして……
■私の答え
今回、私は能楽を観て、和の空間・和の音楽・和の演技を存分に楽しむことができた。古文などとうに忘れた、一般人の私が、である。
(能と狂言、2つ合わせて「能楽」というのだと、あとで知りました)
しかも、特に評判というわけでなく、いわば「フラッと入った」舞台で、こういう感想を持つことができたのである。
これは能・狂言のおもしろさが証明されたと言ってさしつかえないのではないか。

能楽に一度は触れてみたいと思っている人へは、鑑賞する価値は十分にあると言いたい。
能は室町時代末から基本の形はほとんど変わっていないという説がある。
もしその話が本当なら、あなたが目にする景色は、血なまぐさい合戦のさなかに、いっときの休息を求めて戦国武将が観た景色と、似ているかもしれない。
そんなタイムトリップもいい。

ただし、注意点。
チケットを買うときに、上演される演目がわかるはず。鑑賞前に必ずあらすじを頭へ入れておくように。
ネットで調べるか、現地でパンフレットを買えばOK。
余談だが、英訳したものを事前にレッチリのメンバーに読ませておけば、あいつらだって狂言に手をたたいて笑い、能に心うたれるに違いないと、私は信じている。
<問>
・教養がなくても、理解できるか?
・理解できたとして、おもしろいか?
<答>
理解できるし、おもしろい。
ただし、鑑賞前に5分間の予習は必要。この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
