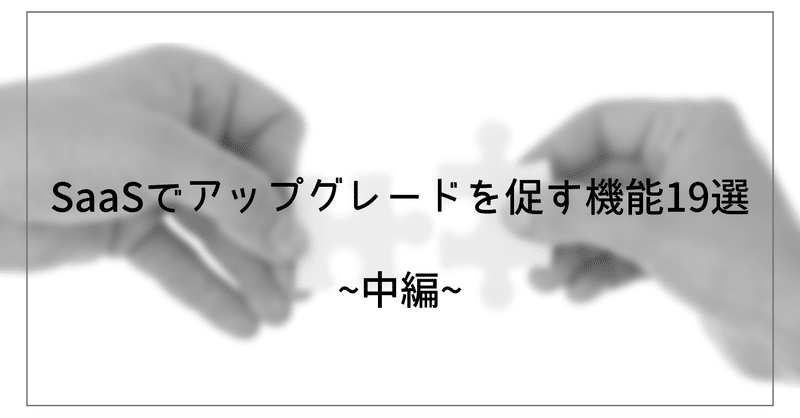
SaaSでアップグレードを促す機能19選 ~中編~
こちらのnoteは前回の続きで、多くのSaaS企業が採用しているアップグレードオプションの機能群から、裏にある課題やニーズをリバースエンジニアリングしようという記事です。
前回のnoteはも貼っておきますので、こちらも是非お読みください。
では早速見ていきましょう。
連携系
6.API(難易度:中、効果:大)
対象SaaS:Box、Dropbox、Zoom、Salesforce、commmune等
API(Application Programming Interface)もアップグレードを促すためによく使われる機能の一つです。
上位オプションでのみ利用可能というパターンと、プランによってコール数が異なるというパターンがあるようです。
SaaSはよく"Best of Breed"と言われますが、特定の課題解決を行うために特化して作られます。ただ、せっかくやり取りされるデータが他で再利用が難しくなる、もしくは再利用するためには人の手を介す必要が出てきます。(データをCSVで落として、エクセルで加工して、別のSaaSにインポートしてといった作業は骨が折れますね・・)
APIはこうした課題を解決してくれます。APIを駆使することで、各SaaSが繋がり、より高度なオペレーションを構築することを可能にします。
ただし、API自体は利用する側にそれ相応のリテラシーを求めます。
"Programming"という言葉が入っているように、非エンジニアで扱うには少しハードルが高いものです。
そのため、まずは安価なプランでしっかりと価値を感じていただき、より高度な使い方として、カスタマーサクセスチームが支援し、APIを利用したデータ連携を通じた価値の創出を行うという流れが良いのではと考えています。
7.他社サービス連携(難易度:中、効果:大)
対象SaaS:Slack、Box、Hubspot、backlog、Asana、Wrike等
この機能は特定のSaaSとネイティブに連携するというものです。APIは自由度が高く、その自由度故に使う側のリテラシーを求めますが、特定のSaaSと連携する場合は、GUIで完結することが多く、非エンジニアでも簡単に連携が可能です。
HubspotであればSalesforceとの連携を上位オプションで提供していますし、AsanaやWrikeではTableauやPowerBIといったBIツールと連携することが可能です。
この辺りは自社で提供しているサービスの特性によって異なってくると考えています。
ベンダー側の立場で言えば、特定サービスの仕様変更に追従する必要があり、あまり手を広げすぎると保守運用が大変になるますので、あくまで密に連携して本当に価値を提供できるもののみに絞るのが良いと考えています。
8.サンドボックス(難易度:高、効果:低〜中)
対象SaaS:Confluence/Jira、Salesforce、Zendesk等
この機能は開発環境としてのサンドボックス環境を提供するというものです。
この機能も他のシステムと連携したいというニーズから生まれていると考えており、まずは検証環境を使って試したいといった大規模なお客様のニーズは拾えると考えています。
ただし、その場合でも別環境を提供すれば良いですし、個人的には開発工数と提供できる効果を考えたときに、コストパフォーマンスが非常に悪いのと考えています。(これを開発するなら他の機能を開発したほうが価値を提供できる気がする。。)
なお、私は国産のSaaSでこういったサンドボックスを提供している会社は見たことがないです。
数での差別化
9. ユーザーライセンス/ストレージ/ファイル数/バージョン管理(難易度:低、効果:大)
対象SaaS:Slack, Box, Dropbox, Zoom, Confluence/Jira, Datadog, Zendesk, backlog, Wrike, Airtable等
プランによって利用可能な数を変えるというある種SaaSの常套手段です。サービスの特性によって何の数を変えるかは異なってくると思いますが、代表的なものを見てみましょう。
・ユーザーライセンス数
→Zoomで100ユーザー以上有償プランを利用したいならEnterpriseプラン一択
・アップロードできるファイルサイズ
→Boxで15GB以上のファイルをアップロードしたい場合Business Plus以上が必要
・保存できるストレージサイズや保管期間
→Slackで1ユーザーあたり1TBの保存領域が必要な場合ENTERPRISE GRIDプランが必要
・バージョン管理数
→NotionではEnterpriseプランで無期限にバージョン管理可能
他にも様々ありますが、この辺の考え方はしっかりと利用データと向き合って検討するのが良いと考えています。
まとめ
今回は他システムの連携と数の差別化を取り上げました。
繰り返しになりますが、SaaSは他のシステムと繋がってより価値を発揮するものと考えています。
国産のSaaSを見ているとまだまだシステム連携が前提に作られていないものも多く、ここには日本のSaaS市場全体として大きな伸び代があると考えています。
例えば、HR系ならATSで採用管理しているのに、採用となった人の情報を人事DB側に手動で登録したりということも多々あると思います。そして、他の領域でも同様のことが発生していると考えています。
それぞれのシステムが繋がることでよりオペレーションが洗練されていくと良いですし、そういった観点で多くのSaaSが今後機能追加されると良いですね。
(利用者としては上位プランではなく標準機能として使いたいところですが。。笑)
次回は対応や直接機能と関係しない差別化ポイントを取り上げられればと考えています。
少しでも参考になりましたらリアクションいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
