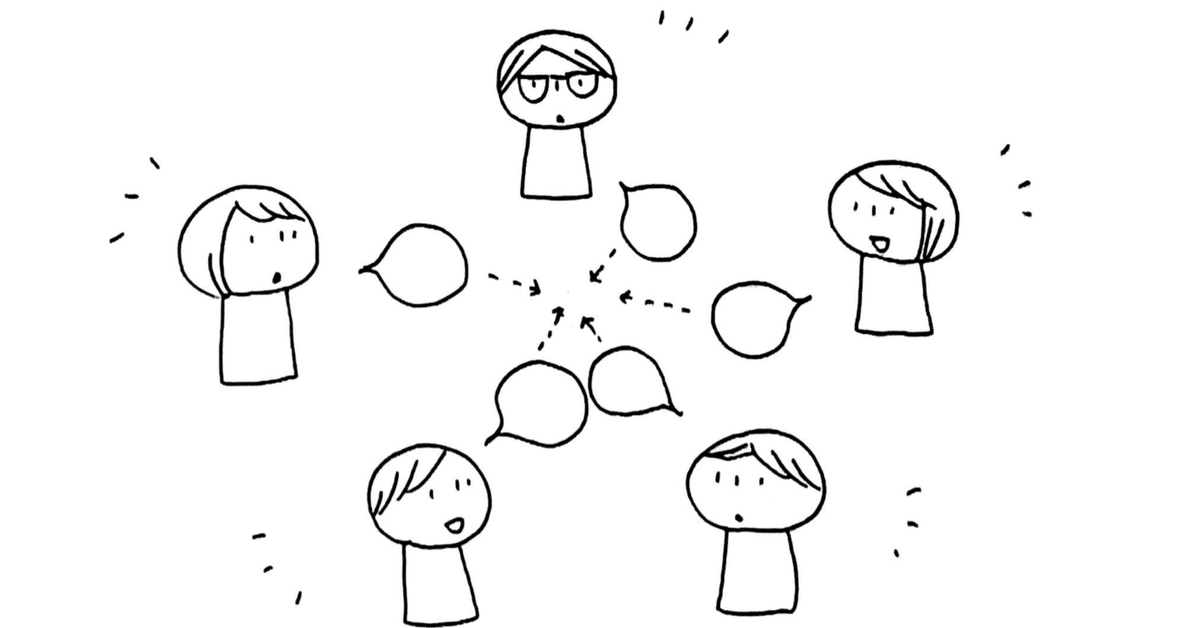
変革のジレンマ
企業変革のジレンマという本を読みました。
「企業変革」と聞いて、想像するものってなんですかね?
私は、色々な自治体の方と話していて、なんとなく多くの人が「下町ロケット」みたいなのを頭に浮かべているんじゃないかという気がしています。
誰かヒーローみたいな人が出てきてババーンと変えるのもまぁアリかもしれないですが、アウトプットが明確な製造業と違って、通常の企業、特に究極のサービス業である地方自治体は、本当に小さな小さな改善の積み重ねをやっていく必要があります。
地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない
地方自治法にもこのように書かれていますが、いかに限られたリソースで住民福祉の増進という壮大な目的に向かっていくのかという、地味ーな活動なわけです。
そして、地味であるがゆえの難しさがあります。
この本も、いわゆるV字回復みたいなものではなく、じわじわと茹でガエルにされるような「緩慢な衰退」をターゲットに書かれています。
ジレンマが引き起こすもの
ジレンマとは、両立し得ない2つ以上の選択肢に直面し、身動きが取れなくなることを意味する。変革は未来から求められるが、私たちは今日の仕事の成果を求められる。未来と今日の間のジレンマは避けられないものだ。
この綱引きは、放っておけば日々の仕事が常に優先され、未来のための変革は後回しにされる。後回しにするほうが、今日の仕事にとっては合理的だからである。だが、こうして日々の仕事の正しさを積み重ねることが、やがては未来の衰退を招く。
インシデントが引き金となって急激に訪れる危機と違い、「緩やかな衰退」であるがゆえに、ズルズルと後回しにして、それ自体が危機を招いていることすら気が付かない。
DX支援業界の片隅にいる自分としては「頷きすぎて首もげそう」というレベルです。
そのうえで、ドラッカーの洞察を引いた以下の一文は、企業(組織)と社会の関係を深くえぐっていると感じました。
後にドラッカーは、人々に位置と役割を提供する存在として、企業という共同体を位置づけた。すなわち、企業とは、人々が社会に参加することを可能にするという、社会を機能させるための基盤としての役割を担っているのだと言える。
これらのドラッカーの洞察は、今日の日本の企業社会、あるいは社会全体の問題を真正面から捉えているように思えてならない。この時代に生き、働く私たちが、社会に参加し、意味を感じられているか、また、そうした実感を生み出す役割を担うはずの企業が、その役割を十分に果たせているか、ということである。
本の中でも「問題のある特定の誰かを想定していない」と書いてありますが、問題の根本は、私もここのところずっと考えている「構造」にあり、善悪とか単純な話で捉えようとすると、逆に深みにハマると思っています。
そして、本書はまさにその「構造」に切り込んで行く構成となっています。
構造的無能化
前に地方公務員アワード受賞メンバーが集まった時に「このメンバーがひとつの組織にいたら、絶対めちゃくちゃになるよねぇーw」と話して笑ったことがありますが、優秀な人が集まれば、それだけで優秀な組織になるかと言えば、私は明確に「NO」と言います。
必要なのは個人が優秀かどうか以上に「構造として機能するように組織が成り立っているか」ということであり、それが阻害されるプロセスが「構造的無能化」です。
本の中では構造的無能化をこういう図で表現しています。

それに私なりの理解を足したものが以下です。

「問題のある特定の誰かを想定していない」という言葉が表すとおり、無能化の過程にあって「単純に除去すれば済む悪い人」というのは存在しておらず、そもそも分業化やルーティン化の発端となる環境適応自体は、決して悪ではなく、過去の様々な活動による「意義ある成果」であると認識することが必要です。
そして、問題はその先に生まれる構造です。
Start!
→環境適応の結果として生まれた断片化から「慣性力」が生まれる
→「視野・認知の狭窄」が起こり不全化に繋がる
→不全化によって組織内が「シラける」ことで起こる問題を、狭窄した視野で見てしまい、有効な打ち手を考えることができない
→結果として、その循環が「構造的無能化」を招く
これは職員数2万人を超える大組織に、30年間所属していた自分としても納得のいくことです。
狭窄した視野のイメージとしてはこんな感じでしょうか。
本書の中では、小さな予兆を見逃して、大きな被害を出すことになってしまった事故の例などが書かれていますが、断片化された白い丸しか見えなくなった結果、その外側にある様々な情報や予兆に気がつくことしかできない状態、というイメージを持ちました。

創業して10年20年でーすみたいな企業と違って、地方公共団体ってのは戦後何十年も続いていて、なんなら明治維新直後くらいからの制度も引きずってたりするわけです。
そんな中で、断片化なんて腐るほど起こっているだろうと想像すると、ちょっと背筋が寒くなったりします。
変革のための対話
ここから先は長くなってしまうので、ぜひ書籍の方でお読みいただければと思いますが、本書の中で最初から最後まで通して度々登場する「対話(dialogue)」という言葉は印象的です。
「我-汝」の関係は、相手(汝)の言語(logos)を通し(dia)て、自分が立ち現れる対話(dialogue)的関係である。
私が「それ」と思って見ている対象について、実は知らないという弱さが見出されたとき、私達は対話の入口に立っている。他者について「知らない」ということが、「それ」を「汝」として見出そうとする働きを生み出し、その行為を通じて、「それ」の「汝」としての側面を新たに知ることができる。
前職の時に、よく会議の中で「トップが思っているであろうことを推測する場面」というものに遭遇しましたが、私はこれも対話を軽く見たことによる構造的無能化のはじまりではないかと考えています。
本書で述べる「対話」とは、、「他者を通して己を見て、応答すること」である。対話と聞いて多くの人が連想するように、それは単に「皆が一同に会して話をすること」だけを意味しない。経営における対話とは、他者との関係性の上でこそ成り立つ、1つの思考の運動の形式である。
ドラッカーは「顧客の創造」と述べるとき、「顧客という他者」を媒介にして、企業が果たすべき役割を見出そうとした。そう考えるならば、顧客の創造とは、対話そのものと言って良いかもしれない。
顧客に対して事業を構築する際に、実行する組織を作り、機能させることもまた対話である。なぜなら、組織とは「異なる階層間」あるいは「同じ階層の異なる部門間」、「同じ部署内の異なる人々」というように、異なるバックグラウンドを持つ他者の集合体であるからだ。
つまり、経営そのものが、他者との対話によって成立しているとも言える。
私は、常に「DXとは『未来はわからない』ということからはじめる必要がある」と言っています。
この「わからない」を乗り越える方法として「対話」はとても重要であり、対話のための技術である「ファシリテーション」に大きな期待をしています。
自分自身もファシリテーターとして対話の促進が後押しできる存在になりたいと思っていますが、組織にいるひとりひとりがファシリテーターになったら、すごく良い世界ができるのではないでしょうか。
最後に
「公務員はツールである」というのは、私が現役時代によく言っていたことです。
「顧客が欲しがっているのはドリルではなく、空いた穴である」ともよく言われるように、目的のためのツールであるはずの組織が、目的そのものになってしまってはいけません。
しかし、人間というのは社会の中で生きるが故に簡単に目的を見失う生き物でもあります。
常に自分の外側を意識しながら、他者との対話の中で、自分の位置や役割を認識し直す作業をしながら、できるだけ広い世界での視野が持てるように経営戦略や対話のデザインをすること。
そんなことがこれからの企業(組織)に求められているんだろうなと思いました。
よければサポートお願いします!めっちゃ励みになります!
