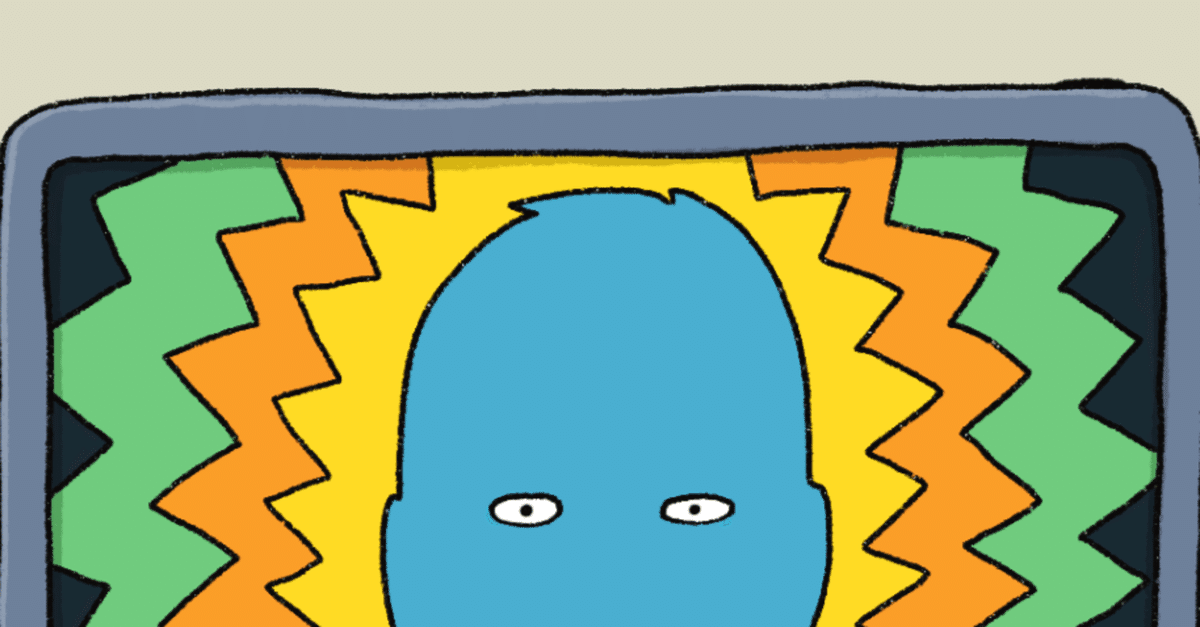
【ショートショート】「オンライン刑務所からの脱出」(5,553字)
どうしてこんなことになってしまったのか。
俺はノートパソコンに取り付けられたレンズを見つめながら考えていた。
あれは確かちょうど半年前のことだった。
このノートパソコンが俺に支給されてからというもの、もともと狂っていた俺の人生はさらに大きく狂ってしまったのだった。
※
願ってもないチャンスが訪れた。そのとき、俺はそう確信していた。
俺は塀の中にいた全員に支給されるというノートパソコンを初めて起動させると、ノートパソコンの上部に搭載されたカメラに映らないように下を向き、ひっそりとほくそ笑んだ。
とある罪を犯して収監されていた俺は、刑務所で長い年月を過ごしてきた。
ひょっとするとこのままここで一生を終えてしまうのだろうか、そんなことを考えていた矢先、状況ががらりと変わった。
新型コロナウイルス感染症とかいう未知のウイルスが中国かどこかから湧き出して世界中に蔓延したのだ。
最初は「どうせそんなウイルスなんてメディアが大げさに騒いでいるだけですぐに無くなっちゃうんだろ。へへっ」と軽く構えていたが、段々とただ事じゃないような気配が強くなっていき、刑務所内でクラスターとかいう集団感染が発生したことをきっかけに、このままじゃいかんと法務省のお偉方と刑務所の所長が話し合った末、一時的に刑務所が閉鎖されることになった。
その報せを聞いた俺たちは歓喜した。
刑務所が閉鎖されるということは、俺たちが収監される場所がなくなるということだ。つまりそれは、再び自由を手に入れたということに他ならないのだ。
俺は隣の独居房だった坂口さんに向かって「やったな!」と叫んで刑務官に怒られた。怒られた理由は私語をしたことに対してではなく、飛沫を飛ばしたことに対してだった。飛沫を飛ばすことはこのご時世、そこそこの悪事になってしまったらしい。
俺は刑務所を出たあとは、飛沫を飛ばさないようにどこかで静かに暮らせばよいと考えていたが、どうもそうはならないようであった。
いくらコロナ禍(新型コロナウイルスが流行って対策を続けないといけない状況をそんな風に言うらしい)とはいえ、犯罪者が野放しになっていたら市民は嫌がるだろう。
犯罪者の俺だって犯罪者が野放しにされるなんて嫌だ。犯罪者はできればどこか遠くに隔離していてほしい。
こうして考案されたのが、犯罪者たちにノートパソコンを支給したうえで自宅に帰し、オンラインで監視する『オンライン刑務所』というものらしい。
もしオンラインで監視するだけならすぐに逃げることができるだろう、と甘く考えるやつがいたら国家権力というものを舐めているというほかない。
俺たち自宅に帰される受刑者の首には、もれなく全員に金属製の首輪が付けられた。
家に帰された後でも、刑務所のルールに違反したり、脱走を企てたりした場合、即座にこの首輪から電流が流される仕組みになっているのだった。
「こんな首輪を付けさせるなんて明らかな人権侵害です」と、俺は人権保護団体に手紙を送ったが無視されてしまった。ひょっとすると人権保護団体もリモートワークとやらで郵便物を見ていないのかもしれない。
そうして俺は家に帰された。
元々一人暮らしをしていたアパートはすでに引き払っていたため、あてがわれたのはよりにもよって六十すぎの母親が暮らす実家の子供部屋だった。
子供部屋の中央にあった机に部屋の全体が映るようにノートパソコンを置き、カメラを起動させ、俺のオンライン刑務所生活は始まった。
俺の首は首輪が取り付けられていた。
過酷な状況ではあるが、自由をものにするチャンスであることは間違いなかった。
俺はカメラの前で笑みがこぼれないように苦労するのに必死だった。
※
「称呼番号一二四三番の田中、起床時間だ、早く起きろ」
「もう少しだけ……」
「あと二秒で起きなければ電流を流す、一、二……」
「すぐ起きます」
俺はすぐに立ち上がり、ノートパソコンのカメラに見えるように綺麗に布団を畳んだ。
オンライン刑務所の起床時間は朝七時。普通の刑務所と一緒である。
起床後はすぐにグリーンの作業着に着替え、朝食をとることになっている。献立は刑務官がメールで指定してくるので、一階にいる母ちゃんにメールで事前に伝えていた。家族でも直接会話することは禁止されているので、支給されたパソコンからわざわざメールを送らなければならない。
電流を流されても嫌なので、ノートパソコンのカメラから外れないように、母ちゃんが部屋の前に置いてくれているお盆を持ってカメラの前に戻った。
ノートパソコンの向こうに座る刑務官にカメラ越しに食事の内容を見せ、「食べていいぞ」と言われるのを待って、ようやく「いただきます」と朝食を食べることが許された。
ちなみに食事は焼き魚やみそ汁、白飯など質素なメニューが指定されていたが、母ちゃんに頼んで、みそ汁のような見た目のすき焼きや下にウニとイクラが敷き詰められた白米を作ってもらっていた。
国も予算がないのか、支給されたノートパソコンのカメラはあまり画質がよくないため、バレることはないだろう。オンライン刑務所万歳だ。
八時からは作業が開始されることになっていた。
俺が従事している作業は洗濯だった。
受刑者は自分の洗い物を自分ですることはできない。洗濯の担当の係がいて、そいつが作業の時間に全員分の洗濯を行うことになっていた。
そろそろかと思うと同時に、家のチャイムが鳴った。
受刑者たちの家を回って洗濯物を回収してきたトラックが、大量の洗濯物を持ってやってきたのだった。
オンライン刑務所においても、かつていた刑務所同様、受刑者全員分の洗濯が自分の仕事であることは変わらなかった。刑務官などは効率のことなど微塵も考えていないらしい。俺たちの血税を使っているという自覚をもってほしいものだ。
母ちゃんに洗濯板を持ってきてもらうと、俺は酸っぱい臭いのする大量の洗濯物を洗い始めた。
俺の働きを見て、ウェブカメラの向こうの、どこか見覚えのある部屋にいた刑務官は満足そうに頷いた。
「しっかり洗うんだぞ、田中」
「はい、誠心誠意、魂を込めて洗わせていただきます」
「辛いだろうが、これもお前が改心するために必要な道だ。まだまだ先は長いが、いつか娑婆に戻れる日が来たら、こんな日々も懐かしく思えるだろうさ」
「二度とあんな悪事は働きません。娑婆に出られたらお天道様に恥じないように真っ当に生きます」
「そうだ、分かったら素直に手を動かせ」
「はい」
俺は洗濯物を洗濯板に擦り付ける手に力をこめるが、これももちろん作業を行っているフリである。
刑務官だって他にも何人もの受刑者を同時に監視しなければいけない。俺は適当に手を動かしながら、刑務官がよそ見している隙を見計らって洗濯物を部屋の入口へと放り投げていった。
放り投げられた洗濯物はこっそり母ちゃんが回収し、ドラム式洗濯機で洗濯から乾燥まで全自動で行ってくれる。母ちゃんが柔軟剤をたっぷり入れるから、洗濯物からはフローラルな香りがしているが、どうせトラックで受刑者に直接配られるのだからバレようがなかった。
昼には運動の時間もあった。
運動の時間だけは、刑務所と同じように外に出て体を動かすことが許された。
ただし、当然見張りなしで外に出すわけにはいかないので、俺たちは両手でノートパソコンを持ってカメラ越しに刑務官に監視されながら公園をうろうろするという、明らかに不審な人物にならざるを得なかった。
あまりにたくさん通報されるので、警察もノートパソコンを持った怪しい男がうろついているという通報を受けても様子を見に来なくなってしまった。
何度か小学生に「ユーチューバーですか?」と声を掛けられたが、ユーチューバーがなんなのか知らなかったし他人との会話は禁止されているから、走って逃げることしかできなかった。
午後からはまた作業を行い、夕方には濡れタオルで体を拭いた(ノートパソコンが壊れるという理由で、浴室に行くことは許されなかった)。
そんな日々をくり返すうちに、俺はこんなことを考えるようになった。
(この状況なら脱獄することも難しくないはずだ。必ず本当の自由を手に入れてやる……!)
そして数ヶ月の準備期間を経て、俺は計画を実行に移すことにした。
※
決行時刻は深夜のほかにあり得なかった。それ以外の時間帯は常にカメラ越しに刑務官の目が光っていた。深夜も見張りはあるが、電気を消すことができるので、カメラの前からいなくなってもすぐには気づかれないだろう。
就寝時間は夜の九時だった。
俺は電気を消すと、布団に入り込んだ。
「おい、豆球はつけておけ」
パソコン越しに聞こえる刑務官の声に、俺は布団から出て電気の紐を引くが、いくら引いても豆球が付くことはなかった。
「おかしいな、電球切れちゃったみたいですね」
「……明日、必ずお袋さんに買ってきてもらえ」
「わかりました」もちろん紐を引いたふりをしただけだった。
俺は(どこまで相手のパソコンのモニターで判別できるか分からないが)なにくわぬ顔をすると再び布団に入り込んだ。
布団の陰から体を出すと、真っ暗な部屋を匍匐前進でカメラに映らない場所まで移動し、事前に母ちゃんに用意させておいたマネキンを布団に押し込んだ。
これで明日の起床時間までは、俺はこの部屋にいるものと思われるはずだ。定期的にいびきが流れるよう、母ちゃんからスピーカーもセットしてもらっている。
そして朝が来るまでの間にできるだけ遠くに移動して、電流が流される前に首輪を外すことができれば、俺は晴れて自由の身になれるはずだった。
なるべく目立たない服装に着替え、首には金属の首輪を隠すためのマフラーを巻いた。まだマフラーを巻くには少し時期が早かったが背に腹は代えられない。
ちらとノートパソコンを見ると、画面に映る刑務官は下を向いてなにか書き物をしているようだった。部屋の入口はノートパソコンのカメラにどうしても映ってしまうが、今は部屋を抜け出すチャンスと言えた。
心臓がどくどくと跳ねるように動いていた。
このチャンスを逃せば、二度とチャンスは訪れないかもしれない。だが、失敗したら――?
迷ううちに永遠のような時間が経った気がしたが、実際には二、三分だったかもしれない。
俺は覚悟を決めて忍び足で部屋の扉から外に出た。
モニターの向こうから声がかかることはなかった。
(やった! これで俺は自由の身だ! ――いや、まだ安心はできない。この首輪をなんとかするまでは。とにかく母ちゃんに別れを言って、外でタクシーを拾おう)
俺は母ちゃんがいるであろうリビングの扉を開けた。
そこにあったのは、先ほどまでノートパソコンの前で書き物をしていた刑務官の姿だった。
「ど、どうしてここに……?」
俺の声はかすれてほとんど声になっていなかった。刑務官は書き物の手を止めずに言う。
「刑務所が閉鎖されたからな、刑務官の監視場所は受刑者の家の一部を順繰りに借りることになった。偶然、今日が称呼番号一二四三番の田中――お前の家だったという訳だ」
俺はいつか、刑務官が見覚えのある部屋から俺のことを監視していたのを思い出した。それは俺の実家のリビングだったのだ!
「違うんです、これは――」
次の瞬間、俺の首に稲妻に打たれたような衝撃が走った。
首輪から電気ショックを流されたのだと理解すると同時に、俺の意識は深い闇の中へ沈んでいった。
※
数か月後、俺の首からようやく首輪を取り外すことが許された。
俺は自分の部屋の床に、その重たい、鉄製の首輪を置いた。いつかこの首輪から電気ショックを受けた日のことが、昨日のことのように思い出された。
あれから、新型コロナウイルスの感染者は数を増やしたり減らしたりしながら、いまだ収束の気配はみせていない。それに伴い、刑務所も閉鎖されたままだ。オンライン刑務所もまだ継続している。
だが、やはりオンラインであると、一人の刑務官が監視することができる受刑者の数には限りがあった。俺のようなオンライン脱獄未遂も多発したらしい。そこで、お偉方たちの話し合いの結果、受刑者の数を減らすことにしたのだった。
俺はノートパソコンの前で立ち上がった。
目の前には一本のロープが天井から伸び、先端には輪っかが作られていた。
『オンライン死刑』
その記念すべき第一号になぜ俺が選ばれたのか分からない。ただ、俺には拒否する権利はなかった。逃げようにも、俺の家のリビングでは刑務官がカメラ越しに俺の様子を見つめているのだ。
俺は丸椅子に両足を乗せた。すでにノートパソコンのカメラには俺の足しか映っていないことだろう。
どうしてこんなことになってしまったのか、今さら考えても仕方がなかった。
俺は覚悟を決めた。
ぎゅっと目を閉じてから祈りをささげると、椅子を思い切り蹴り倒した――。
※
椅子が足から離れた瞬間、俺は必至にロープを握りしめた。
腕力には自信がなかったが、ここは絶対に耐えなければいけない。それでいて足は脱力させ、死んだように見せかける必要がある。ノートパソコンの向こうでは、刑務官が神妙な面持ちで画面を見つめていた。彼が見つめる画面には弛緩した俺の両足が映っていることだろう。
俺の『オンライン脱獄』は続いていた。
こんなところで諦めてなんかやるものか。俺は俺のやり方で、どこまでだって逃げ切ってみせる。
ノートパソコンに付いたカメラに映らない場所で、はひっそりとほくそ笑むと、あらかじめお袋に頼んで天井に張り付けさせていたマネキンの足に手を伸ばした。
こちらもどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
