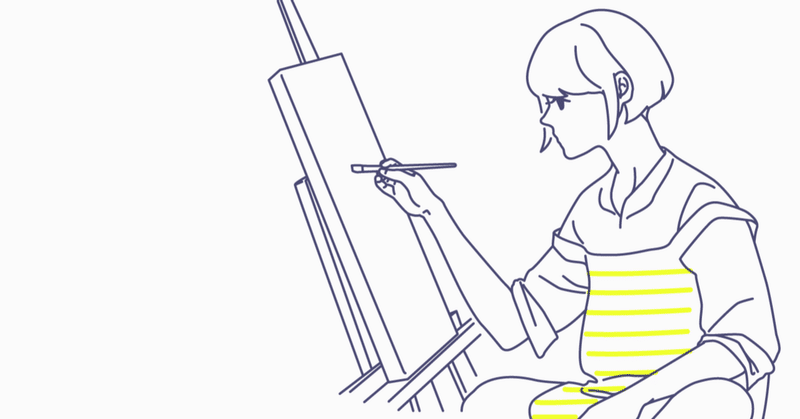
【ショートショート】「鼻歌の響く美術館」(5,403字)
私が意識らしきものを持ったのは、ちょうど私のおかあさんによって私の右眼が描かれたころでした。
それを意識と呼んでよいのか分かりませんが、私がこのようにものごとを考えたり話をしたりすることができるのは、それはやはり私に意識があるからということにほかならないでしょう。
私はおかあさんによって描かれた、絵の中にだけ存在する人物です。
おかあさんというのは私を描いてくれた(まだ私には顔から肩にかけてしか存在しないので、正確には描いてくれている)二十歳前後の女性でした。私をキャンバスの上に生み出してくれたから“おかあさん”です。
おそらく大学生でしょう。彼女は月曜日から金曜日まで毎朝、私服にトートバッグを背負って出かけます。夕方、部屋に戻ってくると、私が描かれているこの絵を描き始めます。美大生なのか分かりませんが、彼女はとても絵が上手でした。
描かれている私が言うので間違いありません。この絵は皆が注目する絵になる、まだ全体の一部分しか描かれていませんでしたが、私はそのことを確信していました。
そんな訳で、私はおかあさんが私を描いてくれるのが楽しみでなりませんでした。私はどんな服装で、私の周囲はどのような景色で、私はなにをしているのか、それらが全て描かれてしまうのを私は心待ちにしていました。
私からおかあさんに話しかけることは難しいでしょうから、私はいつも絵の中からおかあさんのことを眺めるだけでした。
覗きをしているようで少し気が引けましたが、私はおかあさんのことを眺めるのが好きでした。
友達が少ないのか、彼女は学校にいる以外は家にいて、私を描いているか字幕の映画を見ているかどちらかでした。あの年ごろの女性は、友達と長電話で話をしたりするのでしょうが、そのような姿も見たことはありません。
それでも、私はおかあさんを眺めたり自分が少しずつ描かれたりしてゆくこの静かな生活を愛していました。
私に意識が生まれて三週間が過ぎたころには、この絵も少しずつ全体像が分かるようになっていました。
私は、隣に立っている髪の長い年の女性となにか楽しそうに話しています。
描かれている舞台は学校でしょうか。そういえば私も隣の女性もセーラー服を着ているようです。それはおかあさんの頭の中の世界でしょうか。それとも過去に実際にあった場面でしょうか。それはどこまでも幸せそうな光景でした。
その光景を目にして初めて、私の中にある感情が生まれました。
“この絵に描かれている景色についておかあさんと話がしたい“、初めは単なる思い付きに過ぎなかったその考えは、おかあさんが私を書き足すにつれて大きくなりました。
絵画の作者と、描かれている人物がその作品について話をするなど、聞いたことがありません。
でも、もしそんなことが実現できたなら、そんな素敵なことはありません。それこそ奇跡と呼べるような時間になるでしょう。この絵はどのような瞬間を切り取ったものなので、私はどのような気持ちで友人と話をしているのか、それらがすべて明らかになるのですから。
おかあさんはちょうど私が描かれているキャンバスの前に腰かけて、絵の具で窓の外に広がる空の青を足していました。私が声を掛ければ、必ず聞こえる距離にいます。幸い、私にはすでに口が描かれていました。
おかあさんの額には汗が光っています。私が声を掛けたらおかあさんはどんな表情をするでしょう。驚き、怯えるでしょうか。それとも受け入れてくれるでしょうか。
「おかあさん!」
思わず私は口に出していました。
いけない、と思いすぐにおかあさんに目をやります。
幸い、といっていいのでしょうか――おかあさんに私の声は届いていないようでした。
集中して声が届かなかった、という訳ではないようです。なぜならおかあさんはキャンバスにほとんど密着して絵を描いていましたから。
それから毎日、私はおかあさんに声を掛けましたが、最後まで私の声がおかあさんに届くことはありませんでした。やはり絵の中にいる私から、絵の外にいるおかあさんに話しかけることなんて不可能だったのでしょう。
さらに三週間が経ち、絵も完成に近づいてきているようでした。
既にキャンバスの全体に油絵の具が塗られ、このごろは微細な部分を整える作業に入っているようです。
自分で自分の顔を確認することはできませんが、隣の少女の完成度からすれば、私もきっと生き生きとした表情で、彼女となんでもない、それでいてかけがえのないような話をしていることでしょう。
その日は朝から雨が降っていて、おかあさんは少し憂鬱そうな表情で出かけていきました。そういえば数週間前から、おかあさんはそのような表情を浮かべることが多かったように思います。なにかあったのか、私は少し心配でした。
男が部屋に入ってきたのは突然のことでした。
私は男が彼女の了解を得て部屋に入ったのではないと、すぐに分かりました。
上下ともに黒っぽい服装の男は靴を履いたままでしたし、明らかに周囲の物音に過敏になっているようでした。良からぬ考えがあって部屋に侵入したことに間違いありません。
男はワンルームの部屋を一通り検めてから、最後に私が描かれた絵をじっと見つめました。
その目は少し血走っており、私は恐怖を覚えました。もし自由に動くことができるなら、私は叫び声をあげてすぐにこの場から逃げ出していたでしょう。
あろうことか、男はそのままキャンバスの裏に隠れてしまいました。なにが目的なのでしょう。このまま夕方になれば、おかあさんはこの部屋に帰ってきて、男と鉢合わせしてしまうはずなのです。
外が少しずつ薄暗くなっていきました。そしてついに、おかあさんが帰ってきてしまいました。
鍵を開ける音に続き、ドアが開く音が聞こえます。キャンバスの裏では、息をひそめた男が緊張感を強くするのが分かりました。
なにも知らないおかあさんがキャンバスのある部屋に入ってきました。そしてキャンバスの裏から、男が飛び出す気配がしました。
幸い(と言っていいのか分かりませんが)男がおかあさんに急に飛び掛かるようなことはありませんでした。それでも突然の出来事に、おかあさんはひどく怯え、悲鳴も上げられないほど狼狽えていました。
男は興奮した様子で、おかあさんを罵るような言葉を投げました。身振り手振りを交えて、男は大声を出し続けます。
おかあさんはなにが起きているのかまだ完全には理解できていない様子でしたが、どうやら男はおかあさんの知り合いであったようで、逃げ出すこともせずに男の動きをじっと見つめていました。
男の話を聞いていると、どうやら男はおかあさんと同じ大学に通う学生のようでした。男はおかあさんに気があったようで、これまで幾度となくおかあさんに親切にしてきて、おかあさんも男の気持ちに気づいて二人はいい関係にあった(少なくとも男はそう感じていた)ようです。
しかし、おかあさんが最近になってほかの男と仲良くしている。それが、男が激昂している理由のようでした。
おかあさんもなにかを言い返そうとしているのでしょうか、両手を顔の前で動かし、なにか言葉を発しようとしているようでした。
しかし、言葉は出てきませんでした。それも当然です。こんな状況でまともな反論などできるはずがないですし、そもそも興奮した男に反論などしてもとても有効とは思えませんでした。いま必要なのは、ここから逃げ出して、然るべきところに通報することです。
そこではじめて、私は自分になにかできることはないかと考えました。しかし、そのようなことは一つもありません。私は初めて、自分がただのキャンバスに描かれた“絵”であることを呪いました。
おかあさんから反応が返ってこないのが癪に障ったのでしょうか、男はおかあさんの両肩を掴むと、おかあさんを床に押し倒しました。そしておかあさんに馬乗りになると、ポケットからカッターを取り出しました。
おかあさんは必死で抵抗します。
しかし、そこには明らかな体格差がありました。このままではおかあさんが殺されてしまう、私は頭が真っ白になり、気が付けば声を大にして叫んでいました。
「あなた、おかあさんから離れなさい! すぐに警察が来ますよ!」
今にもおかあさんにカッターを刺そうとしていた男はぎょっとして飛び上がりました。
「だ、誰だ!」
男が立ち上がり、きょろきょろおと辺りを見回します。ですがこの部屋には、おかあさんと男しかいないはずでした。
「お前、誰かに電話してやがっただろ!」
男は叫びます。ですが、おかあさんにはなにが起きているか分かっていないようでした。
カッターをその場に残し、男は何度か転びながら走って逃げていきました。
一人だけ残されたおかあさんは呆然としていました。そして震えだし、やがて意を決したように部屋から出て行きました。
やがて戻ってきたとき、おかあさんは二人の警察官と一緒でした。
おかあさんは警察官と話をすることができませんでした。
恐怖からではありません。おかあさんははじめから”耳が聞こえなかった”のです。
私はそのことを、二人の警察官が話す内容から知りました。
おかあさんは二人の警察官に、ノートにペンを走らせて、そこでなにが起きたかを説明したようでした。聞けば、おかあさんは数週間前から男に嫌がらせを受けていたようでした。
すでに帰ってしまった後でしたが、警察官たちにはひとつだけ不思議なことがあったようでした。
それは男――田中一という手話サークルの仲間だそうですが、それはもうどうでもいいでしょう――が、どうして逃げ出したかということです
私自身、信じられないことですが、それはひょっとして私の声が聞こえたからではなかったでしょうか。
どのような奇跡がそこで作用したのか分かませんが、私の声はずっと絵の外まで届いていて、それをおかあさんが聞き取れなかっただけで……いえ、やめておきましょう。おかあさんが助かった、その結果が残されただけで私は十分なのです。
そしてそれは、私が助かったということでもありました。
その後、無事、その絵は完成しました。
舞台は音楽室でしょうか、後ろにはピアノを弾く女性の姿があります。そして前面では私とセーラー服を着た少女が、なにかを話して笑っています。青春の一ページをそのまま切り取ったような、(自分で言うのもこそばゆいですが)それは素晴らしい絵画作品でした。
その絵はあるコンクールに出品され、たくさんの審査員たちが私たちを眺めて、感心した表情を浮かべました。私はこの絵の素晴らしさや、この絵を描いた一人の女性の才能について語りたかったですが、ぐっと堪えました。
絵の中から人びとに話しかけることはこの世界において決して健全な行いではないでしょうし、結局のところ、私が本当に話したい人は(それは決して叶わないことではありますが)一人しかいなかったのです。
ある日、私はトラックに乗せられてある場所に運ばれることになりました。
そこはおかあさんが住んでいたアパートのほど近くにある市立美術館でした。
ガラス張りの美しい建物でした。私が館内に運ばれる途中、そのガラスには額に汗を浮かべながらこの絵を運ぶ、二人の運送会社の人の姿が映っているのを見て取ることができました。
そして初めて、私はその素晴らしい絵に描かれた自分自身の姿を見ることができました。
そこに描かれていたのはおかあさんの姿でした。私はおかあさんとうり二つの姿で、楽しそうに友達となにかを語り合っていたのです。
展覧会にはたくさんの人が訪れました。
私を眺めるお客さんが、隣の人に言った言葉が聞こえます。
「この絵ってね、作者の女性が、いつか生まれてくるかもしれない自分の娘を描いた作品なんだって。自分の耳が聞こえないから、子供には自分と違って、ピアノとか友達の声とかいろんな音を聴いて、素晴らしい青春時代を過ごしてほしいって、そんな願いが込められているんだって」
その日の夜、閉館した後の美術館を訪れたおかあさんが、私の前にやってきました。
おかあさんは手話と呼ばれるコミュニケーションツールで私になにごとかを伝えて帰っていきました。
そのときおかあさんがなんと言っていたのか、正確なところは私には分かりませんでした。
ですが、その瞬間、私とおかあさんは確かに心が繋がり合うのを感じました。おかあさんがどのような心持で私のことを描いたのか、その表情や手の動きによってはっきりと理解することができたのです。
その日から、美術館にはある噂が流れるようになったそうです。夜になるとどこからか鼻歌が聞こえてくると、噂はそのような内容でした。
私の意識はやがて消えてなくなってしまうことでしょう。なんとなく、最初からそのような気がしていました。
ですが、それは一時的なものではないか、いつか私の意識はあるべき器に宿るのではないか、今ではそのように思うのです。
そのときまで、私は鼻歌を歌うことでしょう。聞こえるとか聞こえないとか、それは重要なことではないのです。私には意識があって、愛しい人と心が繋がり合っています。
夜の美術館に鼻歌が響くのに、それ以上に理由が必要でしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
