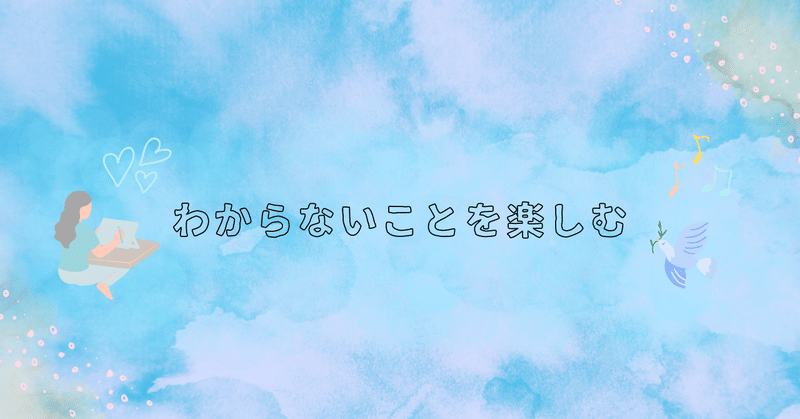
ネガティブ・ケイパビリティ
必要な能力は時代と共に変わる
わからないでいる状態
ネガティブ・ケイパビリティという言葉ご存知でしょうか?
いくら考えてもわからないこと、
どうしにも対応の仕様がない状態に耐える力、のことです。
反対がポジティブ・ケイパビリティ、
迅速に物事に対応し、解決し、対処する脳力のことです。
学校教育ではこれを教えます。
というか、これしか教えません。
そして、職場も同じです。
ポジティブ・ケイパビリティ
より早く、より効率的に、より良い解決を見出し
そしてそれを行動に移す、
こういった感じです。
でも、それができないと、
わかったつもりになって、手近な解決策に飛びついたり、
思考停止状態に陥る、
もしくは、できない自分を責めて自己肯定感を下げる。
そういうことが起きます。
実際、そういうことが起きています。
メリトクラシーの問題
出自や身分ではなく、
自分の能力と努力が地位を決定するというメリトクラシー、
この理論は長い間、
機会均等、がんばればみんなできる、という
能力=平等主義として礼賛されてきました。
しかし、この理論はすでに1970年には
欧米で破綻しかかっていたと言われています。
日本でも1990年代以降、高度経済成長の終焉とともに、
メリトクラシーで国民を包含することへの矛盾が見え始めました。
自己責任という言葉が、とても冷たく聞こえはじめました。
脳の早わかりシステム
私たちの脳は「わからない」という状態を嫌います。
わからない状態は不安を呼び
その不安から逃れるために
脳はとりあえず目の前の出来事に辻褄を合わせ、
なんとか、わかったつもりになりたがる、
だからこそ、このネガティブ・ケイパビリティ、
つまり「わからない状態に耐える力」を培うことは、容易ではありません。
こんな時、共に考える人の存在が大きな意味を持つのです。
対話によってサポートする人
コーチと呼ばうが、サポーターと呼ぼうが、
答えを急がせずに共に考える人の存在があれば、
もしかしたら、今「わからない」ことを認めることができる、
「わからない」状態でもOKだと、自分に許可することができる、
とりあえず、棚上げしておくことを自分に認めることができる、
そうして、前に進んでゆくことができる。
私はこのネガティブ・ケイパビリティのことを
「棚上げ能力」と呼んでいます。
今は亡き、田辺聖子さんから教わった、幸せになるための大きな力です。
目の前の草、棚上げ能力
「なんで庭一面の草を抜きたがるかなぁ、
邪魔になる眼の前の草だけ抜いといたらええねん」
「今、考えてもわからんことを
ごちゃごちゃ言うてんと、棚上げしとき〜」
原著を当たってないから不正確かもしれませんが、
中年おっちゃんのこんなセリフが蘇って来ます。
興味ある方は、ここを覗いてみてください。
▼▼▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
