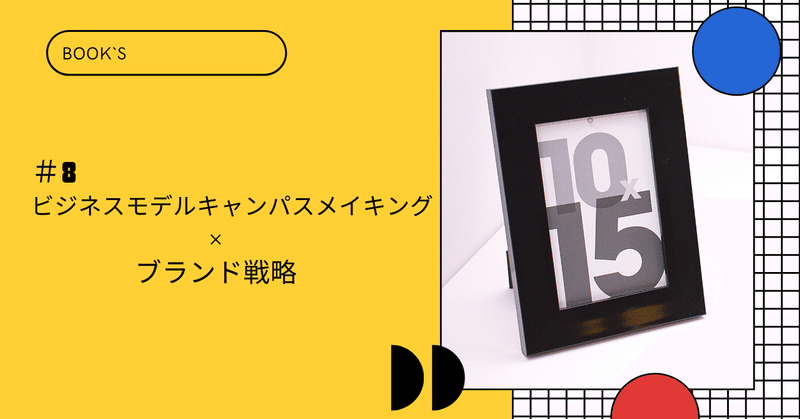
ビジネスモデルキャンパスメイキング×ブランド戦略 #8
皆様、こんばんは。
梶川 龍之介(かじかわ りゅうのすけ)です。
前回投稿では、「11月に入りましたね」とか言っていましたが、気づけば11月も終わろうとしています。
11月7日は、なんと私の誕生日でして更新が遅れてしまい、申し訳ございません。
25歳になりました。
「若いね」と言われて上の世代から可愛がられる年齢。
から更に責任のある大人として扱われるタイミング。
いわゆるアラサーの仲間入りでもあります。
25歳も挑戦とワクワクを楽しんでいきます♪
これからも宜しくお願い致します。
さて本日は、ビジネスモデルキャンパスメイキング×ブランド戦略ということで2本分をまとめて投稿していこうと思います!
ここのフレームワークは、事業計画書を作成していると当たり前に検討せざるを得ないポイントなので説明なしでも良いと思って飛ばしてましたが、やはり大事だったこと、質問もいただきましたので投稿します。
(本当は、〇〇戦略とかの前に投稿すべきでした、、、)
改めて事業内容を見直すことにも使えますし、初心に戻ったと思ってご覧くいただけますと幸いです。
今回でビジネスモデル・事業計画書 を考えるためのフレームワークや考え方は終了になります。
次回以降は、マーケティングやブランディングなど、実際の事業を成功させるための戦術や考え方を学んで行こうと思います。
◉ビジネスモデルキャンパス
BMC=Business Model Campusという意味です。
言うまでもないですが、ビジネスアイデア・ビジネスモデル は形にしないと無価値です。
もっというと、行動しないと事業化はできません。
行動する為には、実際にやりたい事業やビジネスモデルを明確に理解している必要があります。
理解して人に伝えることができるようになることで事業化することができます。
明確に理解するために考えるべきポイントを下記、記載致します。
①需要と供給がマッチすることで「価値」が生まれる
②「不」の中のジョブを細分化する
では、早速内容をみていきましょう。
①需要と供給がマッチすることで「価値」が生まれる
価値とはどのように生まれるのかというと、
需要(お客様が求めている物)と
供給(自分達が提供したい物)が
マッチして初めて”「価値」”が生まれます。
たまにいらっしゃる
〇〇ビジネスは儲かりますか?
〇〇を作ったら、ビジネスチャンスありますよね?
というような提案をよく聞きますが、これは全て供給者側からの
目線で考えられていて需要を理解できていない発言です。
たまたま需要とマッチした場合は別ですが、
これでは自己満足のビジネスになってしまい、
正しい「価値」を提供することが出来兼ねます。
正しい「価値」を生むためには顧客セグメントを絞り、その市場の中にあるニーズを更にセグメントしてフォーカスしてあげることが、大切です。
前の投稿でも記載していますが、ポジショニングはする必要はなく、セグメントをすることが大切です。
例えば、アルコールの場合でいうと、
「日本酒が飲みたい」「ビールが飲みたい」「ワインが飲みたい」
という市場があるとします。
その中で、「日本酒が飲みたい」という需要にセグメントを絞ります。
そこから利便性や快楽性、価格などをその市場内で更にセグメントしてフォーカスさせることができると、具体的なサービスが見えてきます。
一番重要なことは、優れたマーケティングでもなく、豪華な内装でもなく、お腹を空かせた人(ニーズ)がそこにいるかどうかです。
つまり「そこにニーズがあるかどうか」が最重要なのです。
②「不」の中のジョブを細分化する
ニーズが生まれること = 何かに「不」を持つことです。
「不満」「不安」「不経済」「不幸」「不足」「不効率」など
何かをすることによって生まれる「不」を改善することがビジネスになります。
では、「不」を見つける為にすることはなんでしょうか?
下記のフレームワークを使って「不」を見つけていきましょう。
世の中の不
<自分の生活で不を感じるとき> <共感人数>
|ー育児からひとときの開放 ーーー / 人
|ー家事を毎日するという手間ーーー / 人
|ーライフーー賃貸の2年更新 ーーー / 人
| |ー役所の手続きが時代遅れ ーーー / 人
不ー|
| <通勤・仕事・職場で不を感じる場>
| |ー出張の多さと手間 ーーー / 人
|ーワークーー上司との飲み会 ーーー / 人
|ー紙での手続きの手間 ーーー / 人
|ー満員電車 ーーー / 人
ここから更に「ライフ」「ワーク」の項目毎に<共感した人の特徴>まで記載できると良いです。
例えば、満員電車に対する「不」を解決する為に通勤バスを提案することになったとします。
投資家や事業パートナーからの質問がこう飛んできました。
あなたならなんて答えますか?
Q1.顧客はどんな人?
Q2.何がその人の価値になるの?
Q3.どうやってそれを広げていくの?
Q4.どうやって顧客をリピートさせるの?
Q5.いくら儲かるの?
Q6.自社の何を使ってそれを提供するの?
Q7.どういう風にそれを提供するの?
Q8.誰と一緒にやるの?
Q9.いくら掛かるの?どれくらい利益が出るの?
身近な内容なので自分では分かっているつもりでも、言葉に出てこないですね。
まずは頭の中を整理して、書き出す必要があります。
その際にに使うのが下記のワークシートです。
※上記の質問項目の数字(Q1〜Q9)と下記シートの数字(①〜⑨)は一致してます。

Q1.顧客はどんな人ですか?
この質問に対しては、A.満員電車が嫌いな人
と想像しがちですが、もう少し細かくみていきましょう。
以下の2択の質問、アナタならどちらを選びますか?
1.満員電車で30分の通勤
2.空いているバスで1時間30分の通勤
ほとんどの人が1を選ぶと思います。
「満員電車が嫌い」が顧客セグメントではないのです。
もっとジョブ、ニーズを細分化してみましょう。
満員電車が嫌いな理由はなんですか?
とアンケートをとったとします。
アンケートの結果、以下の5つがあげられました。
・パソコンを開いて仕事をすることができない
・時間が非生産的でもったいないと感じる
・通勤時間に寝たり、本を読んだりすることができない
・朝食がとれない
・満員で乗れない日もある
人々が本当に求めている物は「満員電車に乗らないで通勤すること」ではなく、
「満員電車に乗っている間の非生産時間を生産時間に変えること」でした。
つまり顧客セグメントは「通勤時間を非生産的だと感じている人」となります。
この「非生産時間」を「生産時間」に変えることが、価値提供になります。
例
・移動中の食事
・予約制で座れる
・寝れる安心感
・移動の快適さ
・コンセントがある
※ここの考え方は、#4の起業の種類・アイデアのところに詳しく記載しております。
お客様のニーズと提供するソリューションがマッチして初めて価値提供できるのです。
Q2.何がその人の価値になるの?
では、この「非生産時間」という課題に対して、どのようにして「価値提供」を行うのか。を考える時に使えるのが「ダブルダイヤモンド思考」です。
WHAT HOW
|ーアイデア アイデア |ーアイデアーアイデア
課題ー|ーアイデア アイデア |ーアイデア アイデア
|ーアイデアー アイデアーーーアイデア アイデア
拡散 収束 拡散 収束
課題に対して、広げて→絞る→広げて→絞るを繰り返し、最適解を導き出します。
まず「何が」解決するのかを考えてから「どうやって」解決するのかを導き出します。
ここで重要なことは「課題」を間違えないことです。
課題は「非生産時間」です。「満員電車」ではありません。
WHAT HOW
|ー自転車通勤 アイデア |ー定額制 ー 定額制
非生産性時間ー|ーテレワーク アイデア |ー予約制 アイデア
|ー通勤バスー 通勤バスーー ー起業提携 アイデア
拡散 収束 拡散 収束
自転車通勤/テレワーク/通勤バスと広げて、通勤バスと絞ります。
その通勤バスをどうやって提供するのか?
定額制/予約制/企業提携と広げて、定額制と絞ります。
こうして生まれたのが「YuGa×ネスカフェバス」です。
実際には、もっと広げてWHYをつなげると更に説得力がつき、具体的になるので良いのですが、ここでは簡易的にお伝えしています。
Q3.どうやってそれを広げていくの?
企業の福利厚生
ネスレ自社顧客へのアプローチ
一般広告(電車吊革、バス車内広告等)
Q4.どうやって顧客をリピートさせるの?
ヘルスコンディション管理(朝食や睡眠)
契約者割引
Q5.いくら儲かるの?
朝にコーヒーを飲む文化の定着で長期的リテンションの獲得(サブスクリプション)
法人契約でオフィスネスレ獲得(福利厚生での企業収益)
見込み売り上げ/見込み収益
ネスレマシンPRでの収益
Q6.自社の何を使ってそれを提供するの?
KMバスとの提携(渋滞情報)
ネスレ自社顧客リスト
ネスレブランド(優雅なブランド)
Q7.どういう風にそれを提供するの?
運営はKMバスに委託
バスは自社購入
朝食はネスレ提携
Q8.誰と一緒にやるの?
KMグループとの提携
ネスレ朝食外注先との提携
Q9.いくら掛かるの?どれくらい利益が出るの?
初期コスト1,000万、運用コスト100万
これでワークシートが完成です。
投資家や事業パートナーも話ができるようになりますし、
お客様への説明も当たり前のようにできるようになります。
簡易的に記載しておりますが、あとはご自身の事業に転用させるだけです。
もっと深堀りができれば、更に具体的なBMCが完成することでしょう。
是非、試してみてください。
◉ブランド戦略
では、実際にBMCが具体的になったら、ブランドの戦略を学んでいきましょう。
無印良品のイメージを一言で考えてみると、
「シンプル」と考える方が多いのではないでしょうか。
ブランドにはブランド価値(BRAND EVALATION)があります。
無印良品のブランド価値は1760億円にもなります。
無印で柄物の服を売ったら見込みの利益が1億円だとしても、無印のブランドイメージを壊してしまうことになるので売るべきではありません。
このように売上に価値があるのではなく、無印良品というブランドに価値があるのです。
ブランディング戦略とは、顧客に対して自社強みに対する共通認識を与えることです。
この強みをお客さんが知らないとファンになりづらい、後々のマーケティングにも響いてきます。
ここを知ってもらうことで、価格競争に巻き込まれずに、長期集客が可能になり、さらに高利益率につなげることが可能です。
言うまでもないですが、ブランドは大手だけでなく、中小企業にも必ず必要になってきます。
大手のブランディングを逆手に取ることも可能であり、さらに、中小企業の方が早く実施可能です。
ここでは、
①バリュープレミアム
②ブランドの構築方法
を説明していきます。
自分の事業を作って、サービスや商品を提供していきたいと考えている方は必見の内容です。
①バリュープレミアム
以前、サービスや商品の値段の決め方について、
一般的な思考の順番が
「メニューを決める」→「値段を決める」→「売る」
という順番なのに対し、もっと効果的で実践すべき思考の順番は、
「値段を決める」→「メニューを決める」→「売る」である事を伝えました、
普通に売ったら500円のハンバーガーでも箱に入れて、開けたら煙が出るようにするなど工夫をしたら1000円やそれ以上で売ることができます。
このように値段を上げるには、どのようなことをやっていけばよいでしょうか?
「商品のボリューム?」「サービスのクオリティ?」「商品のクオリティ?」「パッケージ?」
どれも大切ですが、わざわざこれらを考えなくても価格を上げることができます。
ここで考えるべきなのは「VALUE PREMIUM」についてです。
例えば、カメラを買おうと思ったとき、Amazonでは92000円、楽天では90000円だとします。あなたは、どちらで買いますか?
また、スタバとドトールで同じサイズ、同じ種類の豆を売ろうとしたら、あなたならそれぞれいくらで売りますか?
人によって異なるかもしれませんが、「値段が高くてもAmazonで買う」「スタバの方が100円以上高く売れるな」と考える人も多いと思います。
このカメラの2000円の差、自分の価値観で考えついたコーヒー豆の値段の差が「VALUE PREMIUM」なのです。
つまり、
いい商品を作ろうとせず、いいブランドを作るべき
ということです。
しっかりとして顧客セグメントと提供したい価値が明確であれば、一瞬でブランドを作れてしまいます。まず、意識してみることが大切です。
②ブランドの構築方法
ブランドを構築には、「FES戦略」の理解が重要です。
FESとは、
②-1.FUNCTIONAL(機能的)
②-2.EMOTIONAL(情緒的)
②-3.SELF-EXPRESSIONAL(自己表現的)
の頭文字を取ったものです。
それぞれ見ていきましょう。
②-1.FUNCTIONAL(機能的)
〇Unique Selling Point
顧客のニーズ、自社の強み、競合の強みを書き起こします。
そのうえで、自社の強みと顧客の需要がマッチしている部分から、
競合の強みもマッチしている部分を引いた部分をUnique Selling Pointといい、そこで勝負することで、顧客にとって機能的な強みを持つことができます。
※前回投稿にも記載しておりますので図はこちらにも貼っておきます。
ーーーーーーーーーーーーーーー
| |
| 顧客ニーズ |
ーーーーー|ーーーーーーーーーーーーー |ーーーーー
| | USP | | | |
| ーーーーーーーーーーーーーーー |
| 自社の強み | | 競合の強み |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〇20−80ルール
20‐80のルールとは、構成要素を大きい順に並べた時、上位20%の要素で全体の80%程度を占めることが多いという経験則。
ビジネスに限らず様々なケースにおいて、一部の要素が全体のかなりの割合を占めることが経験的に知られている。
ビジネスシーンでの典型的な例としては、「上位20%の顧客で売上げの80%を占める」「上位20%の商品で売上げの80%を占める」「故障原因の上位20%で80%の故障を説明できる」などがあります。
ここでは売り上げをなりたたせているのは、20%の顧客だと捉えましょう。
その20%に特化することで、売り上げの向上を更に見込めます。
今まで来てくれたお客さんが来なくなってしまって、売り上げが減ってしまうのでは?と思いがちですが、売上が減るのではなく、他から同じ悩みをもった人を取り込めるので、むしろ売り上げが上がるのです。
②-2.EMOTIONAL(情緒的)
すべてのコンテンツ、サービスは感情に刺さらなければいけません。
そのためにはストーリーを伝える、Story Tellingが重要です。
商品やサービスではなく、体験やストーリーを売ることも大切ということです。
〇JUST DO IT!
〇I’m loving it!
〇お値段以上
など、文をつけることが重要です。
スタバのように看板自体の知名度が高くなることで
ロゴからもストーリーやイメージがは、伝えられます。
このような施策を設けてみましょう。
②-3.SELF-EXPRESSIONAL(自己表現的)
〇インナーブランディング
ガイドラインの設定をすることが重要です。
「五感を刺激」 → 匂い、カラー、音、感触など
「コミュニケーション」 → 禁止語、接客方法、販売方法
「コンセプト」 → 価格、ボリューム、質など
〇アウターブランディング
Aware 知ってる(認知)
Appeal 好きかも(欲求)
Ask 調べる(調査)
Act 買う(購入)
Advocate 教える(推奨)
このインナーブランディングとアウターブランディングまで考えることができると、更に知れ渡るブランドが出来上がり、ファンが育つことにつながります。
このあたりは、マーケティングファネルとかを検討する時にも、かなり大切な考え方になります。
事業計画書やビジネスモデルを考える時に頭に入れておくと、アイデアも具体的に考えやすくなります。
◉最後に
今回もだいぶ長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。
まず、ここまで読んでいただきありがとうございます。
ビジネスキャンパスを作る時に抑えるべきポイント
○事業計画やビジネスモデルの基盤となる
○顧客は誰か?顧客への提供価値は何か?を具体的考えることで他も見えてくる
○競合のビジネスモデルやアイディアの分析に有効的
ブランド戦略を考える時の抑えるべきポイント
〇VALUE PREMIUMを生み出す
〇顧客に対し自社の強みの共通認識を与えること
○FES戦略が効果的
これは事業計画書やビジネスモデルを作成するにあたって、必要になるフレームワークや考え方になりますので、最初らへんの投稿と一緒に拝見していただくことをオススメします。
長くなりましたが今日はここまで。
勉強になった方は是非、フォローとイイねをお願い致します。
(SNSもお待ちしております。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
