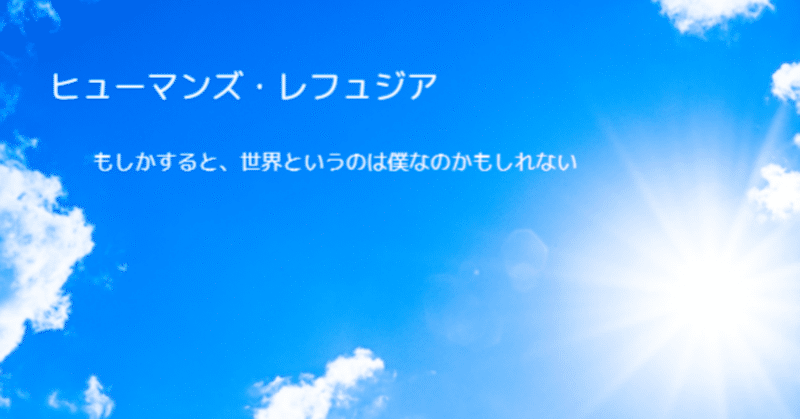
【短編小説】ヒューマンズ・レフュジア
「世界は二人にとって広すぎるんだ。邪魔をしないでくれ」
木製の扉が開きかかっていることをいいことに、覗き込んだことを今更になって後悔した。手土産に、と買ってきた饅頭の袋をきゅっと握り締め、意を決して中へ声を掛けた。
「それは、僕のことでしょうか」
おおよそそれは、家を訪ねる来客の態度ではなかった。呼び鈴も鳴らさない、非礼を詫びる様子もない。だが、呼び鈴の一つも用意せず、門前払いのようなことを言われれば、そんな態度にもなるというものだ。
「それならば、このまま帰ります」
「いいや違うとも」
奥の方から、またしてもそんな声がした。今度は間違いなく僕に向けられた声だ、と彼は確信した。
「入り給え。靴の泥を落としてからだがね」
言われてから、玄関前に泥落としが敷いてあることに気づいた。自分の利益にしか人は興味を示さないと聞くが、ここまで極端なのも珍しい。
「そら、そこの蝶のことだ」
狭い部屋だった。というよりは、たった一つの部屋に家を落とし込んだような感じだった。そこらかしこに分厚い本と紙束が折り重なって、まるでキノコのようにあちこちに積んであった。その中で、背中を猫のように丸めた老人は、何処からか入ってきた蝶の羽ばたきを指さした。
「カラスアゲハ」
淡い鱗粉を撒くように、碧い羽が優美に飛んでいた。
「もうそんな時期ですか」
「そうだとも。時間はいつだって、私たちを置き去りにする」
積み上げた本が崩れて、床にバサバサと落ちた。しかし、それを気にも留めず、拾い上げる様子もない。
「ひさしぶりだね、イヴ」
彼はふと、傍らに立っていた手間使いに挨拶をした。
「お久しぶりです。お変わりありませんか」
にこやかに笑う顔の下で、人工筋肉が擦れる音がした。
動きも言葉も流暢で、もはやその動きに違和感はない。
「あぁ。君の方こそ、大丈夫なのかい。先生の相手ばかり」
手土産を丁寧に受け取って、彼女は丁寧に頭を下げた。
「未熟者です故、私に博士の相手は務まりません」
「機械だてらと舐めてやるな。お前より随分勘がいい」
と、彼は声にならない笑いを見せた。
*
「季節に沿って生きる、彼らがうらやましいよ」
椅子に深々と座り込んだまま、先生はそう言った。窓の向こうには、先ほどカラスアゲハが帰って行った雄大なる自然の、ほんの一部が腰を下ろしている。
「東京はどうなんだ?こことは違うのだろうに」
用意された茶を啜り、饅頭には目もくれず、そう訊いた。
「えぇ、便利ですがね、窮屈ですよ。『東京は人の住むところじゃない』って先生の言葉、案外的を射ています」
先生は何も言わず、またその沈黙に耐え切れず、饅頭の半分をゆっくりとかじった。はがれやすい皮をうまく口に押し込んで、あんこの奥深さに身を任せているようだった。
「――君のようなのが、人口の八割もいるそうだ」
幾数回の咀嚼の後、傍らで同じく茶をすするイヴに向かってそう言った。イヴは、華奢な体をビクリと震わせ、それでもその事実を、なんとか受け止めようとしていた。
「イヴは違うでしょう。彼女はロボット。増え続けているのは機械人間、サイボーグですよ」
どっちだっていい、と言わんばかりに首を振った。嘆かわしや、と言わんばかりに先生はなおも続ける。
「純然たる人間は減っていくばかり。そんなに死が怖いかね」
「先生はほら、変人ですから」
僕は思わず冷笑した。そうでもなければ、こんな田舎にわざわざ家を移して籠ったりしない。
「――死ぬのは怖いと思います」
先生が何か言いかける前に、口を開いたのはイヴだった。
「――ほう」
先生の目の色が、ふと変わった
――ように見えた。
「お前もおもしろいことを言う」
「先生、それは『滑稽』ということで?」
「違う。興味深いということだ」
湯呑を静かに置いて、イヴがおそるおそる言葉を紡ぐ。
「だって死が怖くないなんて、おかしいじゃありませんか」
その声は、どこか震えていた。それが機械の不調でもなく、
単なるノイズでもないことを、彼らは十分に理解していた。
「死んだ人は沢山います。でも『死んだことがある人』は存在しません。 ――死は未知なんです」
「だろうな。もっとも、そういう自問自答を幾度となく繰り返して、私はここにいるわけだけれども」
「先生も考えたことが」
思わず僕はそう尋ねた。人間、一度は生きる意味や死について考えるものだと思っていたが、先生もまたそうだとは思わなかったのだ。
「あるよ。数えきれないほどにね」
「して、先生はどんな答えを?」
「――愚問だな」
ぴしゃり、とたしなめられて、僕は押し黙った。
「答えが出ることがすべてじゃない」
ぬるくなったお茶を喉へ押しやってから、先生は続けた。
「それに、私の答えを聞いて、納得してしまう君たちが怖い」
「そうでした」
僕の声を聴いて、先生はようやっと安堵したように、残りの饅頭を口に入れた。
*
イヴの声に耳を傾ける間、先生は微塵も動かず、ただ眼をつぶって、一言も聞き漏らすまいとしていた。
「人間の死と、私達機械の死はきっと別物でしょう」
「そうだろうね」
僕の同意に、彼女はほんの少し語気を強める。
「体を変えて、生きながらえることができる機械にとって人間はなんて不便なんだろう、と思います」
「便利だろうね、体を変えられるのは」
ようやっと、先生は口を開いた。
「都合が悪くなったら変えてしまえばいい」
その言葉尻には、棘があったように思えた。まるで、老いを知らない機械の彼女を、妬む様な口ぶりだった。
「でも、人はそうはいかない。生まれ持った体で、その瞬間から死へ歩み続けるしかないんだ」
「先生はサイボーグになりたくないんですか」
僕はそう尋ねた。新しく注がれたお茶の湯気と、カスが残った饅頭の包装紙を某っと眺め、しばらく考え込んでいたが、やがて
「なりたくないな」
とだけ呟いた。
「寿命には理由があるんだ。不必要に伸ばしてみたところで、虚しいだけだろう」
それは、博士の口からこぼれたにしては随分よわよわしくて、信憑性に欠けた言葉であるに違いなかった。心のどこかで、本音を隠している。そんな表情だった。
もしかすると、世界というのは僕なのかもしれない。
彼は、心のどこかでそう感じた。
あとがき
レフュジアとは、「生物種が絶滅する環境下で、局所的に種が生き延びた場所」の意。英語ではRefugiaと表記。
いわゆる「人間種」文明の未来が、ここ数十年で決まる。
これは何も大げさな話ではない。現に、取り返しのつかなくなったものは幾らでもあるし、人間社会が立ち行かなくなる可能性は、決して低くない。
とはいえ、私は「人間絶滅」も悪くないと思う。どんな文明にも終わりはあるものだし、この辺で一度 他の生物に変わってほしいな、とか思っている。
どうせ、そんなに長くはもたないのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
