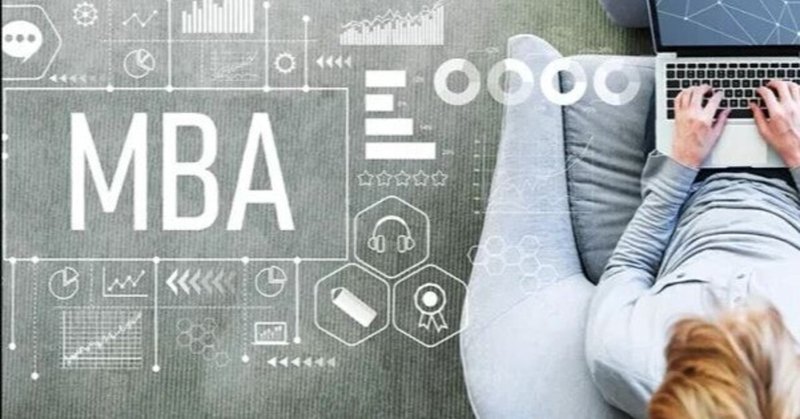
【ブルーマウンテンMBA戦記-23】▶2年次前半①競争戦略(2022/8/19)
MBAも残すところあと半年、最終コーナーとなりました。
2年次前半は位置づけ的には1年次のベーシックな内容を踏まえてアドバンスト的な、または各論に入っていきましょう、というところかと思います。
ということで、このあたりで振り返りとしてメモを残しておきます。
まずは「競争戦略」というMBAの代名詞みたいな講義についてです。
青山学院大学のMBA(ABS)では1年次は「企業戦略」について学び(総論的な感じ)、2年次は各論として「競争戦略」となりました。
1.企業戦略と事業戦略の違い
この点は当たり前ですが非常に重要で、「企業戦略」と「事業戦略」って何が違うの?って言われて、明確な回答があることは重要だと言えます。
※競争戦略はつまり事業戦略の一つの側面からとらえ方、いい方で、イコールととらえてもいいのだろうと自分では理解しています。一般名詞としては「事業戦略」となります。
【企業戦略】
企業全体の事業ポートフォリオをどうとらえるか?全社戦略のことであり、つまりは多角化していたりある程度事業部が存在する一定以上の企業のトップマターの問題。または意思決定方針。
【事業戦略】
事業としてどう勝ち残るか?市場(ここでは事業上、競争する「市場」)において、どのような立ち位置、戦略をとるか?を考える学問。または事業を行う上での意思決定方針。
なぜこれが重要かというと、当たり前ですが、「戦略」といっても、事業部単位での話なのか、全社戦略なのかでアサインするプレイヤー(メイン・サブ)から意思決定権限の階層、スケジュール感まで全く異なるので、前提条件として頭を切り替えることが重要だからです。実務的にこのあたりに触れている人からすると「あたりまえでしょう。」となりますが、実務で事業計画策定や取締役会、または経営会議のようなトップ会議に出ている経験が無い場合、この辺りの話をごっちゃにしていると特に大学院という空間での学びに差がでると思います。(今後MBAを検討する人についてのメッセージとして。)
実際のところ、多くの人にとっては事業戦略が重要だと思います。
企業と言っても、一つ一つの事業のカタマリであって、少々暴論ですが、事業一つ一つの勝利が全体に寄与するのであって、ここに関して戦略レベルで合成の誤謬はさして起きないように思います。当然、資金配分や人員配分(特にトップ近隣人事)については全体適格を考えなくてはいけないと思いますが、MBAを取得する年代(多くは30-40代)では、ひとまず事業部、自分がトップを張っていく事業の戦略を必死に学ぶ、ということに重要性があり興味が向くことになると思います。
2.何を学んだか?
講義内容としては、各戦略の類型とそれに即したケース、実例の紹介が主であり、各所でレポートやグルーワークが差し込まれます。
重要なところとしては
①5フォース
②VRIOフレームワーク
(私は特に演習でゼミみたいなものがあったので特にコレ)
③垂直統合・水平統合
④合併・提携のpros/cons
⑤事業の評価指標としてのROIC
⑥参入障壁(5フォースの一環ではありますが、特に重点)
であったと思います。
そもそもなのですが「座学で経営を学ぶ意味って何か?」というところでいくと、それは「思考をMECE的にする」「経営用語から来る想起集合の訓練」だと思っています。
「~という方針でこの事業やりたいんだよね。」となった時に「ああ、その場合はこうだよね。」ということで、あくまで一般論ではあるけれども、検討事項やプラスマイナスが反射的にパッと浮かぶ、というのは知識として修得していることの一つの意味であり、ここに関しては先達の学者様達の知恵にあやかることに意味があるわけです。自分で一から紙とペンでやるよりも早くて、検討対象に漏れが無い(少なくとも致命的な)のです。結局は紙とペンで戦う瞬間が来るのですが、スタートダッシュとして早いくらいの意味合いです。これが「思考をMECE的にする」です。
次に「経営用語から来る想起集合の訓練」ですが、これはそのまんまの意味です。ROICとかROEとか、指標の話になったときに頭の中にデュポン式がパッと浮かび、その数字が、どこの勘定科目が改善するとどう動くか?というのが感覚的にわかっているのとそうでないのとでは、話の土台が違うので、「目線合わせ」という意味で、概念の使い慣れが必要です。
チープな話ですが
「ROEが悪いのは資本効率が悪いからだね。」と言われて
「じゃあどうする(=どんな選択肢があるか?)」
「レバレッジはどうなの?(=なぜその話になるのか?)」
とか話をするたびに、いちいち「えーっと」
となっていると、話が遅くて、土台(基礎体力?)が違うね、となるわけです。
一方で、こんな指標だとかデュポン分解みたいな話が経営会議で出るのはあまりなく、IRとか定期的な健康診断としての観察の時に小噺として出るだけで、実際のところベンチャー企業とか中小企業、大企業であっても営業端の人がこういった話に精通するか?する必要があるか?については「別に分からなくてもやっていける。」といのが正直な的感想です。
ただ、私自身がIRや決算、事業計画に携わる身としては、やはり基本的な道具として持ってた方が当然スムーズにいくよね、というようには感じています。
これまでも、独学や実務の中で局所的に学ぶこと、一般論として認識していることも多かったのですが、やはり体系的に整理ができ、「競争戦略ってこういうもの。これくらいの幅で話ができれば及第点だ。」ということが、つかめたのは意味があったと思います。
あと、経営と数字というのは絶対に切り離せないものであって、数字というのは、まずは「財務諸表」の数字であり、事業部レベルでは「管理会計における数字のハンドリング」なわけです。その意味で、特にアカウンティングの知識に不足があると、数字を見た時に感度や読解力、理解力について、控えめに言って段違いの差が出ると思います。
これからのMBA受講者へのメッセージとしては「会計は必須」、自分への戒めとしては、継続的なレベルアップを怠らず、というところです。
3.競争戦略をMBAで学ぶ意味とその問題
身も蓋も無い話ですが、知識だけで言えば、本で十分だと思います。
一方で、自分が属さない業界の話や実例を、学ぶこと、グループワークで自分の思うことを発信することには一定の意味があると思います。プラス、レポートにおいてはやはり説得力や論旨を考えるため、「戦略という側面でのストーリー構築」の練習にはなると思います。
話の土台が違う場合、関係する情報を集めて、適切な形に取りまとめて、発信する、レスポンスをまた組み替えて、必要な提案やストーリーを構築する、というのは戦略コンサル系の仕事のド真ん中なのだと思いますが、このあたりは筋肉的なところで、トライ&フィードバックが必要だなと感じました。リクルートとかDeNAのような環境とか、コンサル、お家芸なのであまり意味はないと思いますが、一般的な事業会社だとあまりこうした他社例、戦略検討みたいな筋肉は使わないので、良い機会かなと思います。
個人的には、マネジメント演習という少数制のクラスで戦略系のゼミみたいな感じでVRIOフレームワーク(ジェイ・バーニー大先生)を学びまして、それは純粋に議論として楽しかったです。
4.この先
やはり知識は使ってなんぼですし、実際に使った結果「こうだった」というように過去形で語れる経験値になることが重要だというのは間違いないと思います。
自分は事業会社に属する立場ですが、幸いに新規事業やIRに携わる立場であるため、この分野の知識を使う場面は多いです。
ハーバード・ビジネスレビューとかは、読みやすくなった感じがしますね(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
