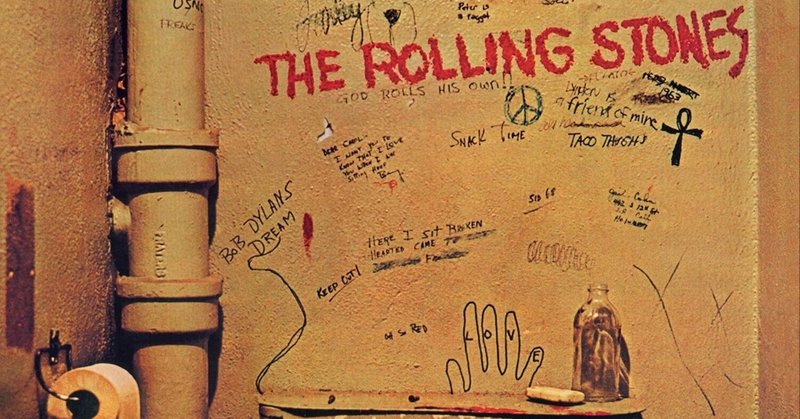
ザ・ローリング・ストーンズ べガーズ・バンケット その③ オリンピック・スタジオとグリン・ジョンズ
<オリンピックスタジオとグリン・ジョンズの存在>
ここから先は、ミュージシャン目線からさらに一歩突っ込んで、エンジニア的な目線。裏方的な目線からも書いてみたいと思います。
前の記事はこちらですが、単独で読んでもらっても大丈夫です。
では、続きとして③行きます。
レコーディング・エンジニアはグリン・ジョンズおよびエディ・クレイマー(エディー・クレイマーはジミヘンとの仕事が有名ですかね)。グリン・ジョンズは、イアン・スチュアートとルームメイトだったこともあり、デビュー前のストーンズのデモ(いわゆるIBCデモ)を録ったことでも有名ですね。ストーンズとの関係は、後年、少しよくなくなってしまっていて残念です。
ジミー・ミラーをミックに推薦したのも彼らしいですしね。
『ビトウィーン・ザ・バトンズ』から『山羊頭』までは、ほぼ、彼の仕事ですね。遡って、IBCデモは彼の仕事ですし「サティスファクション」もそうらしいですし、「山羊頭」以降も、「ブラックアンドブルー」までは、部分的には手伝っていたらしいですし、とにかく、ストーンズとの仕事は多い人です。「エグザイル」は、彼の弟「アンディージョンズ」がやってます。

彼はエンジニアとしては、恐るべき経歴の持ち主で、彼の本を読んだことがありますが、大変面白かったです。※ボンゾのドラムの録音の手法とかがかなり有名で、YouTubeで動画とかも有ったりします(本論から外れるの書きませんが)

余談ながら、ストーンズでいえば、ブートレッグのなかに正規版とは違った「グリン・ジョンズ・ミックス[THE ROLLING STONES / GLYN JOHNS MASTER REELS]」というのがあって、これも聞いてみると面白いです。
※日本ではグリン・ジョンズ・ミックスと通称で呼ばれていますが、実際は、代替テイクとか、でも段階のバージョンなどが入っていますので、いわゆる完成版としてのグリン・ジョンズのミックスではありません。

<録音方法やその他の雑談>
このアルバムでやっていることの一つに、「仮で一発録りしておいて、それを流しながら、各パートを録りなおし、オーバーダビングしてる」曲が結構ありますね。

これにより「バンドサウンド、ライブな演奏を保ちつつ、オーバーダビングでじっくり狙った感じに仕上げる」ということをやっています。
ストーンズは、いわゆる「天才系ミュージシャン」ではないので、何度もセッション的に演奏を重ね、その中から「偶発的に良かったものを、自分達で聞いて(プレイバック)して、採用している」というのが多い気がします。
スタジオ盤の色んな段階でのブートレッグを聞き比べると、これがよーくわかります。先に書いた「グリン・ジョンズ・ミックス」とか、これはいろいろありますけど。完成版とは、それなりに違っているものが多数存在しますので、少なくとも、色々やって、試しているのがわかります。
ただ、それらはやはり「セッション色が強い」ですが、完成版は「作品度」が高くなっているので、このことは裏付けを持って言えます。
「そういうやり方をしていた」というエンジニアの証言もありましたしね。
ある程度以上の精度をもったシステムで聞くか、ヘッドホンで聞くと、少し、仮テイクのミックのボーカルの残っているのが聞こえたりしますので、その痕跡があることはわかります。

余談ながら、このアルバムは製品化する際(だったか、オリンピックからサンセットに持ちこんだ際だったかもしれません)に、再生装置のスピードの設定を間違って、再生が速くなってしまったのをそのまま使ってしまったということもあり、アナログ盤やCDの多くは、少しピッチ(と速度)が早いんです。いつだったか、それを正常な状態に戻したのも発売されていましたね。
※「オリンピックスタジオ」66年から72年まで、6枚のアルバムにこのスタジオは関与している。ストーンズがホームとして使っていたスタジオ。
※ただし、ストーンズの場合、そこですべてやっていたわけでななく、他のスタジオも併用しているケースがほとんど。
※「オリンピックスタジオ」は、66年だったかに一度、引っ越しているが、ストーンズの「カム・オン」は、引っ越す前の「オリンピックスタジオ」で録音している(つまりデヴューシングルは、はじめのオリンピックスタジオで録音した)
※このスタジオで録音した有名ミュージシャンはThe Rolling Stones, Jimi Hendrix,Led Zeppelin, The Who,the Beatles, David Bowie, Queen, Ella Fitzgerald, Ray Charles, B. B. King, Traffic, Prince, the Eagles, Eric Claptonなどきりがありません。

『ベガーズ』絡みでは、録音中に火事が発生し、機材を搬出したり録音していたデータをもって避難したというエピソードが有名です(ワン・プラス・ワンの映画のスタッフが持ち込んでいた照明機材から出火したらしいです)
当時のオリンピックスタジオはイギリスでは最先端であった(早い時期から真空管のミキサーを排し、トランジスタ搭載のミキサーを使っていた)
※当時のイギリスは戦後の影響もあり、実は、アメリカより10年位遅れていたという証言が結構あったりしますが、ここはかなり最新の機材を使っていたことで有名です。
ここで、少し話を機材のことに移しますが、当時使われていた「Mixing Console」は「Olympic desks」とか「Olympic console」と呼ばれているんですが、これがなかなかに興味深い機材です。
楽器をされる方であっても、録音のことになると、普通は、そこまでご存じないことも多いと思いますので、書いてみました。
これは、たとえ、それがライブ盤であっても、販売されているCDやLPは全て、なんらかの機材(ミキサーやコンプレッサー、EQなど)を通した音であり、いい意味で加工されています。されていないものは、存在しません(クラシックであっても、程度の差はあれ、やっていますので)。
「そういうものなのだ」ということ前提にして、聞くと面白さが増す部分もあります。もちろん、これらの処理は処理に過ぎず、音楽そのもの価値とイコールではありませんが、重要なファクターではあります。
楽器奏者は、たとえば、ギタリストであれば、どうしてもギターやアンプばかりに目が行きますが、実際のところは、こうした機材たちを通して、最終的な音が出来上がっています。
余談ながら、この時代のミキサーは「メーカー製」ではなく、エンジニアが個別に注文に応じて特注で作っていたのが多いんですよね。それがその後、製品化されたりしているというのもあったりするんですが、機材好きとしては、ギターアンプやマイクを超えて、そういう機材たちのことが興味深いんです。
英語になりますが、伝説のキース・グラントの記事とか面白いです。

このミキサーを発展させたミキサーが、「Helios」で、その機材は、このアルバムの翌年69年から、使われ始めて、当時のイギリスの多くの名盤でつかわれています。また、この「Helios」は、ストーンズのモバイル・レコーディング・システムでもその派生型が使われていたことで有名でもあります(移動式録音システム。いわゆるトラックを改造して、ミキサーやレコーディング機材を搭載していたあれです)
※この「Helios」は、UADの製品でこれのモデリングが発売されていて、私もよーく使っています。たしかに「あの音」を創れますので、これは重宝しています。
ちなみに、アビーロードは、逆にすごく旧式だったというのがあります。ビートルズはあれだけ録音系でいろいろやってますが、基本的にはあれは「工夫」でやってるのであって機材はむしろ遅れていたという、、、。これは貶しているのではなく、「それなのにすごいな」と思うという話です(アルバム、アビーロードまでは、機材については、ほんとに10年位遅れていたといわれています。主に真空管のミキサーでしたし、色々、当時の資料を読めば読むほど、それが明確にわかります。といっても、それは「機材が」であり、「ビートルズ以外のスタジオエンジニアの頭の固さ」とかに起因するものです。
ちなみに、EMIとデッカはクラシックでも有名ですが、こちらはあきらかにデッカの方が音が良いですね)

次回は、「べガーズ・バンケット」最終回 その4として、「悪魔を、、、」のライブバージョンの変遷を取り上げます。
しかし、引っ張るなw
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
