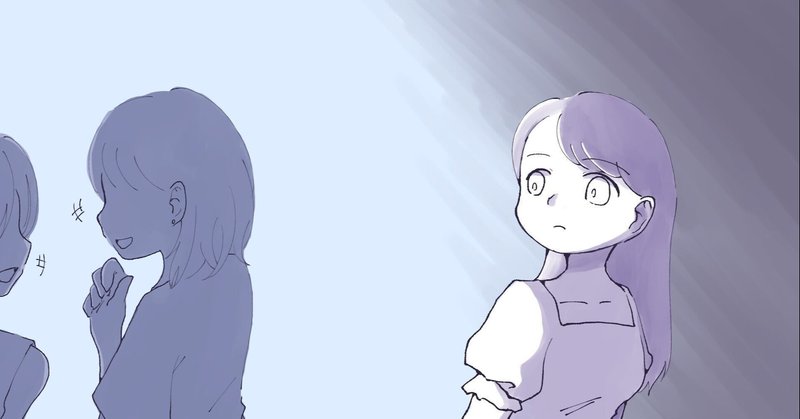
僕が見た怪物たち1997-2018 第一話「死にゆく者の祈り、2002」まとめ読み版(約11000字)
年齢のせいではないはずだが、最近はひどく記憶が曖昧で困ってしまう。
そもそもこの住所を知ったのは、いつだったか、それさえもはっきりとしない。
どうやってここまで来たのかはよく覚えていないのだが、気付くと私は見慣れぬ商店街の見知らぬ建物の前に立っていた。二階建てのそこには特に看板もなく、外観からは普通の家屋にしか思えず、引き戸になっている玄関のドアに貼られた紙がなければ、何を営んでいるか分からないまま通り過ぎてしまっていたことだろう。
〈人生の苦しみから心霊の悩みまで、あらゆる相談お受けします〉
という怪しい文言の後には店舗名もなく、その下には電話番号が書かれている。もう亡くなってしまったが、かつての友人の恵美ならこういう場所の存在を面白がっただろう。不思議な雰囲気だ。ただ、普段の私だったら、たとえ興味を持ったとしても、こんなうさんくさくて、危険なにおいのする建物に入らなかったはずだ。
私は一葉の写真を握るその右手にちいさく力を込める。私にはもう時間がないかもしれない。
時代を感じさせるその建物には呼び鈴らしきものは付いていなくて、とりあえずノックしようと握りこぶしをつくった手の甲でドアを叩こうとしたが、それは空振りに終わってしまった。私が手首を振るのと同時に、ドアが開いたからだ。
「こんにちは。お客様ですか?」
私を出迎えたのは、幼さの残る声だった。
「あ、うん。きみはこの家の子?」
「ここで、先生の助手をさせてもらっているコウと言います」
中学生くらいだろうか。こんなちいさな子が助手……?
もしかしたらコウと名乗る彼は、その彼の言う、先生……彼女の息子さんかもしれない。店番を任されているとか、きっと、そんな感じだろう。
「きょうは、その先生、いるかな?」
「はい。もちろんです。では、上がってください」
丁寧な言葉遣いだが、礼儀正しい、というよりは、感情を殺したようなしゃべりかたをする少年だ。口調は柔らかいが、どこか冷めている。私が一番苦手とするタイプだ。異性同性関係なく、こういうひとはどうも好きになれない。いつも一緒のグループにいた咲なんかはまさにそういうタイプだった。素っ気なくて感情が読めなくて、でもその態度が私のことをすこし見下しているように感じられる。実際にそう言われたわけではないが、私にはそう見えて仕方がなかった。
そんな咲も、もう亡くなってしまった。一緒に旅行した時はあんなに元気だったのに……。
少年が私に案内してくれたのは、〈カウンセリングルーム〉と書かれた看板が吊り下げられている部屋で、入るとそこには私が求めていたひとがいた。顔を見るのは人生で二度目だが、いまはサングラスをしていて素顔は分からない。
椅子に座って、先生と机を挟んで向き合う私を見届けると、少年は、ぺこり、と深く頭を下げて、部屋から出て行く。
「初めまして……じゃなかったよね……、えぇっと、以前どこで会ったかしら」
「以前、長崎に友達と旅行した時、ガイドをしてもらったんですけど、覚えていないですか?」
私が、そう言うと、彼女がちいさく口の端を上げた。
「あぁ思い出した。そうだった、そうだった。それで今日は何のご用?」
何年か前、いつも一緒にいた四人グループで旅行した際、たまたま目的地に向かう電車の中で隣り合わせたのが先生で、その不思議な雰囲気が妙に私たちの興味を惹き、そのまま旅先でも行動を共にすることになったのだ。実はその時に彼女の名前は聞いていなくて、ただ周囲からは、先生、と呼ばれている、と彼女自身が言っていて、私たちも旅の間、先生、と彼女のことを呼んでいた。
私の存在はひとつの職では収まりきらないの。まったく自慢げに感じない口調で、自慢としか思えないことを言った彼女は、その時、私たちに名刺を渡してくれて……あぁそうだ、そこに住所が書いてあったんだ。名刺には〈相談請負人〉と本気か冗談か分からないような肩書きが付けられていたが、彼女がその名刺を配りながら、カウンセラーや占い師、霊能者やら探偵なんかも兼ねている、なんて言っていて、そんなに手を広げたら全部が中途半端になるだけなんじゃないか、と思ってしまったが、でもあの時の霊能者という言葉が頭に残っていたからこそ、私はここを訪ねようと思ったのだろう。私たちのグループでもっとも、恋多き女、というあのちょっと古くさいフレーズの似合う女性だった早苗は、占い師、というワードに惹かれたのか、彼女に厚かましくも無料で恋占いをせがんで、一喜一憂していた。そんな早苗も、もう……。
「実は私、死ぬかもしれないんです」
私は手に持っていた写真を彼女に差し出す。
そこには私も含めて四人の女性が写っている。恵美、咲、早苗、そして私の四人が集まって、あの日、長崎で撮ったものだ。
あの旅行からまだ大した期間も経っていないのに、私以外の三人が、異常とも言える死に方をしている。こんな偶然が本当にあるだろうか。
私たちは呪われているのかもしれない。
だとしたら次は最後、……私の番だ。
※
私たち四人はかつて同じ高校に通っていた。
長崎への四人旅行は、卒業してから久し振りに集まらないか、という話をきっかけに、じゃあせっかくなら旅行でも、と早苗が計画したものだった。旅行の計画を話した時、あんたたち相変わらず仲が良いわね、と呆れたように言っていたのは、誰だっただろうか……、確か同じ高校に通っていた双子の姉だったはずだ。姉と私の見た目は、瓜二つとまではいかないがすごく似ている。ただ性格は対照的で、私はひとりだとすぐ不安になるし、いつも誰かの後ろにくっついているタイプで、反対に、姉はひとりで何でもこなしていて、誰かといる時は、よく周りから頼られていた。同い年でも、私にとって、姉は憧れだった。
自分を変えよう、と思ったのは、大学に入ってからだ。
大学デビューなんて言い方は、自分の冴えない過去を認めるみたいで、ちょっと嫌だが、かなり無理して新たな自分を作り込んだのは事実だ。
『ねぇ、早苗から旅行に誘われてるんだけど、一緒に行かない?』
と恵美から電話が来たのは、大学三年の秋頃だっただろうか。
恵美は高校だけでなく中学も一緒で、グループの中ではもっとも付き合いの古い相手だった。彼女はオカルトとか幽霊とか、そういった類の話が好きな女の子で、まぁでも私たちが中学、高校くらいの頃はノストラダムスの大予言を前にして、テレビでオカルト番組がよく放送されていたこともあって、そういう生徒は決してめずらしくなかった気がする。
恵美は悪い子ではないのだが、思い込んだら一直線で、周りが見えなくなるところがあった。
久し振りの恵美の声に、私は安堵とわずらわしさの混じった感情を抱いた。
大学生活を送る中で、私はいつも気を張っていた。だから旧知の間柄である恵美の声は私を隠し立てのいらないあの頃に戻してくれたが、自分を変えようと敢えて捨てた関係がまた近付いてくるのは、どうもわずらわしい。
「……うん。良いよ」
ほんのわずか悩んだのち、私がそう答えると、
『良かったぁ、断られたらどうしよう、思ったよ。渚はもう都会の女だからね』
冗談めかした口調だった。渚は私の名前だ。恵美が、渚、と呼ぶ時のイントネーションは他のひとと違っていて、私は初めて会った頃からそこに小馬鹿にしたような色を感じ取っていた。
何が、断られたらどうしよう、だ。断られるなんて思ってもいなかったくせに。
姉にもそう思われていたように、私たちは周囲からとても仲が良いと思われていた。
恵美との通話を終えると、またすぐに電話の音が鳴った。恵美だと決め付けて取った受話器から聞こえてきた声に、私は慌ててしまった。ちゃんと着信の登録名を見てから、出るんだった。
「ごめん。急に。もしかして寝てた。声がちょっと怒っている感じだったけど」
「ううん。そんなことないよ」
声の主は、現在の恋人で、そして彼は私の最後の恋人になる予定だ。
彼は業界のことを知らない人間でも、聞けば大抵はその名を知っている電機メーカーの社長の息子で、大学を卒業したら、その会社に縁故採用されるだろう、と言われている。周りもそう噂していたし、本人もそのつもりでいることを自分で口にしていた。彼は小説を書いていて、分かりやすい文学青年を気取っているところもあり、卒業したら一切書かない、在学中に芥川賞でも取ってやるぜ、なんて公言していたが、たぶんそれは無理だろう、というのが実際に作品を読んだ私の正直な感想だった。
社長の息子、というステータスに惹かれて交際しているのだろう、と陰で言われていることは知っていた。彼は決して見てくれが良いわけでもなく、才能や知性に溢れているような雰囲気に対して、首を傾げてしまう部分があまりにも多かったからだ。ただ私は彼と付き合いはじめるまで、彼の家族のことなんてひとつも知らなかった。
彼には才能がない。そんな才能を持たない人間が苦しんでもがいている姿に、私はどうしようもなく惹かれてしまうのだ。周囲には理解されないだろうし、プライドの高い彼には絶対に知られてはいけない私の本心だ。
とはいえ……、
もともとは結婚のことなんてまったく頭になかったが、交際の後のその先まで考えるようになったきっかけは、彼のステータスを知って、だったのだが……。
「それなら良いんだけど……」
「さっき高校の頃の友達から電話が来て、長話になっちゃったから、すこし疲れてただけ」
「へぇ、きみの友達……確か和歌山の田舎って言ってた、っけ?」
「そうよく覚えてたね。本当に何もない田舎。大嫌いだった」
「でも、離れても連絡を取り合える友達がいるなんていいじゃないか。僕にはそんな相手、誰もいないよ」
「都会でうまくいってない人間を見つけて、馬鹿にしたいだけよ、きっと」
「ありゃ、もしかして仲の悪い相手だった?」
「嫌い。あの田舎と同じくらい」
※
「死ぬ、というのは、穏やかな話じゃないね」
掛けていたサングラスを外して私を見る先生の眉間には、かすかにしわが寄っている。
机の上に置かれた写真の先には長崎のハウステンボスの風景があり、私たち四人の姿があった。ハウステンボスを旅行先に選んだのは確か早苗だと言っていたはずだ。早苗が以前に付き合っていた男性と長崎のハウステンボスに行く約束したまま、結局それが叶わなかったので、その嫌な名残りを払拭するために長崎を選んだんじゃないか、と恵美が私とふたりの時に、からかうような口調で言っていた。
「先生はあの時の私たちを見て、どう思いましたか?」
「答えてあげたい気持ちはあるけど、正直なところ覚えていないのよね。短い時間の話だったし」
「まぁ、そうですよね。よく周りから私たちは、仲良しグループと言われていました。ただ本当はそんなに仲も良くなかった……。だからあの日、私たちは先生と別れた後、その夜だったかな、旅行先のホテルで大喧嘩になったんです。きっかけはなんだったか、私自身、しっかりと覚えているわけじゃないんですけど……。私、実は最初から乗り気じゃなくて、なんか不吉な予感も抱いてました。その予感って、たぶん当たってたんです。私はあの旅行を終えてから、三人とはほとんど会っていません。恵美と一度会っただけで、でもその時は喧嘩のことなんて話せる状況じゃなくて。謝りたい気持ちはあるんです」
「んっ……? 人生相談だったの? 謝りたい気持ちがあるなら、謝るのが一番だと思うかな、私は。それとあなたの死にどんな関係があるの?」
「いえ、そうじゃないんです。もう会いたくても、誰とも会えないんです。だって三人とも死んでしまったんですから」
「死んだ、と?」
私は事前に用意していた新聞記事と週刊誌の切り抜きを取り出すと、机の上にそれを並べる。その途中に、先ほどのコウと名乗った助手の青年が戻ってきて、私と先生の前に水色の液体の入ったグラスを置く。口に含むと、それは味から判断する限り紅茶のようだった。ただ私は紅茶の類に詳しいわけでもないので、種類や名前はさっぱり分からない。ただなんとなく高級なものなんだろうな、というのは想像がつく。
「美味しい?」
「は、はい。紅茶に詳しいわけじゃないですけど、これ、かなり高級な感じが」
申し訳なさを含めて私が言うと、先生が首を横に振る。
「大丈夫、気にしなくていいのよ。私はお金に困っていないから」と先生がひとによっては憤慨しそうなことを何気ない口調で言った。「紅茶はリラックスにちょうどいいからね。そういうものに、ちょっとしたお金を惜しんではいけないのよ。それで話を戻すけど、この新聞とかの切り抜きは?」
「私が集めたものです。例えばこれを見てください――」
「あっ、ちょっと待って、いつも最初に聞くことを忘れていた……。あなたの家族構成を聞いてもいいかしら」
「家族構成……ですか?」
「いえ、ね。心霊相談にしても人生相談にしても、やっぱり家族って、切り離せないものだから。それが良いものか悪いものか、そのどちらにしても、ね」
「そう……、なんですね。いまはひとり暮らしですけど、実家には父と母、あと双子の姉がいます」
「双子の、ね。あぁごめんね。じゃあ話を戻そう。じゃあ今度こそ切り抜きについて教えてもらってもいい?」
その切り抜きは週刊誌の一部だ。和歌山のローカルタレントが絞殺された、という文章が載っている。被害者の名前は清水咲……もちろん彼女は同じグループにいた咲のことだ。彼女は高校時代から地元でタレント活動をしていて、週刊誌の文章には、地元では有名な、と誇張された表現が使われているが、咲は別に有名でもなんでもなかったし、高校の頃も仕事が多忙で学校に来られなくなるなんてことはなく皆勤賞だった記憶がある。
長崎に行った時、ちょうどそのタレント活動の話が出て、ようやく彼女がタレントだったことを思い出したくらいだった。
ただ本人は自分が他のひとよりも秀でた、選ばれた人間だ、と強く意識しているようなところがあり、言葉遣いは丁寧で、はっきりとそう口にするわけではないものの、周囲をどこか見下している雰囲気を外に放っていた。
自宅へ帰る途中、夜闇の中で突然襲われた咲は首を絞められて殺されてしまった。あの旅行から三か月後のことで、犯人はいまだに捕まっていない。その週刊誌に書いてある情報によると、彼女には恋人だった地元テレビ局のアナウンサーがいて、別れ話がもつれた上での出来事だったのではないか、と警察に疑われていたらしい。とはいえ証拠がなく、逮捕されることはなかったみたいだ。
「ふむ……じゃあ、残りのふたつの記事も、そういうことよね」
私は頷く。
次に私は新聞記事の切り抜きを指差す。〈篠塚市女性刺殺事件〉と書かれたその事件の被害女性の名前は大倉早苗となっている。篠塚市は和歌山県の地名で、そこには私たちの通っていた高校がある。
「早苗は仕事が終わって帰宅の途中に背中を刺されたそうです」
「この記事には、捜索中、ってなっているけれど、そのあと犯人が捕まったり……はしてないのよね」
聞くまでもないか……という表情で先生が頷いている。
「咲の次が、早苗でした。だから不安になったのもあって、早苗とその頃にもまだ付き合いのあった学生時代の知り合いを頼って、私、事件のことを聞き回ったんです。あくまで噂の域は出ませんけど、疑われていたのは早苗のストーカーをしていた男だったみたいです」
私はすこし嘘をついた。
実際に私がその早苗の知り合いたちから聞いた話によると、ストーカー、というか、相手にしつこく付き纏っていたのは早苗のほうだったらしい。そのトラブルの果てに、反対に彼女が刺された、というのが、早苗の周囲が想像する事の顛末だったみたいだが、話の中にでてくる早苗の評判があまりに悪すぎて、真に受け過ぎないほうがいいと思っていた。嘘のように思える話で、わざわざ彼女の名誉を貶める必要はないだろうし、それに私の知る生前の早苗はいつも男性関係が派手で、恨まれる姿のほうが想像が付きやすかった。
「ふぅん。でも、まぁ……その男は犯人ではなかった、と」
「アリバイがあったそうですよ。通り魔だったのかもしれませんね」
「切り抜きはこれで終わりだけど……」
「最後はこんなに大きく報じられる死ではありませんでしたから」
「教えて」
早苗の死について聞き回っていた時、最後に会いに行ったのは恵美だった。私も不安は大きかったが、恵美の怯えはそれ以上だった。私の顔を見た瞬間、死ぬのが怖い、と泣き出して、疑心暗鬼になっているのか私からつねに距離を取ろうとしていたのを覚えている。
こんな短い間に同じグループにいた人間が、ふたりも死んでいるのだから、それは当然の反応に思えたが、私は恵美のそんな姿を見ながら、変な感情になってしまった。学生の頃、恵美はいつもノストラダムスの大予言でみんな死ぬんだから人生なんてどうでもいいじゃないみたいなことを言っていて、その世紀末を過ぎても生きていたんだから、なんで生にしがみつこうとしているんだろう、と不思議な気持ちを抱いてしまったのだ。
そんな恵美も、そのあとすぐに死んでしまった。
「転落死だったそうです。不審死、と言ったらいいんでしょうか。これだけはまだ自殺なのか殺人なのかも分かっていません。でもふたりが亡くなったあとに恵美と会っているんですが、あんなに死に怯えていた恵美が自ら死を選ぶでしょうか?」
「私はその恵美ちゃんの怯える姿を見ていないから、なんとも言えないけれどね」
そして最後に残ったのが、私だ。
半年くらいしか経っていないはずだ。あの旅行からその短い期間に、私たち四人グループの内、三人がいなくなってしまうなんて……。
「助けてください」
「誰を、助ければいいのかしら?」
先生の声音は静かだった。
「何を言って……だって私たち四人の内の三人が死んでしまっているんですよ。どう考えたって、次は私、としか……」
「何を言ってるの?」
「何、って……」
私は先生の言葉に怖くなって目を逸らすと、その視線の先には助手の少年がいる。その瞳の奥に私を哀れむような色がある。
やめろ……、そんな目で私を見るな……。
「四人とも、もう死んでいるんだから。救われるべき人間は、その写真の中にはいないのよ。まだ思い出せないの?」
「やめて……」
「三人が死んで、現世にしがみつく理由がまだあなたにある? 本当に姉を大切に想うなら、早くお姉さんの中から出て行きなさい。自由にしてあげなさい。救えるのは、あなただけよ」
※
「ベッドに寝かせてきました。多分、当面は起きないんじゃないでしょうか?」
「そう……。力仕事ありがとう。コウ。あなたもだいぶ頼りになってきたじゃない」
先生が僕の言葉に、にこやかにほほ笑む。その笑顔がどうも苦手な僕は、さっきまで先生と彼女が対面していた机の上に目を向け、先生の顔は絶対に見ない。
「この新聞と週刊誌の切り抜きはどうしましょうか?」
「何、言ってるの。ゴミは捨てるに決まっているじゃない」
「いや……でも……、あ、いえ、そうですね。それにしても、先生はいつから気付いていたんですか? あのひとが、渚さんではない、って……」
「最初から違和感はあったね。私の力を舐めちゃだめよ」
「すみません……」
まるで何でも屋のように、いくつもの役割、職業を兼ねているからか、先生はうさんくさい人間と思われがちだが、ひとつひとつの能力は本物である。気軽に疑える先生をよく知らないひとたちが羨ましい。長く間近で見てきた僕には、もう疑いたくても疑うことができない。
「大好きな家族に憑くなんて、渚ちゃんもそんなひどいことはやめてあげればいいのに」
「あれ、大好き、なんて言ってました?」
「旅行が一緒になった時、渚ちゃん、お姉ちゃんに憧れている、って言ってたからね」
「よく覚えていますね。さっきは記憶が曖昧な振りをしていたんですか?」
「まぁね。私は記憶力には自信があるの。渚ちゃんのほうは、本当に記憶が曖昧になっていたみたいだけど、彼女たちに会ったのは、たった一年前のことだから。まぁでも実を言うと、本当に渚ちゃんに姉がいるのか、もしかしたら私の記憶違いかもしれない、って、ほんのちょっと不安な部分もあったから、念のために家族構成を聞いたりして、それで確信したの」
「彼女に、何があったんでしょうか?」
「最初に死んで悪霊となった渚ちゃんが残りの三人を死に追いやったのだから、まぁあの三人が、渚ちゃんを殺したんでしょうね」
「でも、仲の良いグループだったんですよね?」
「あぁそうか、コウはちょうど紅茶を取りに行っていたから知らないだろうけど、渚ちゃんの霊……お姉さんなのか渚ちゃんなのか混同しちゃうから、そういう言い方にするね。渚ちゃんの霊自身も認めていたよ。仲が良いわけじゃない、って。私が会った時の印象も、上辺だけ仲が良いグループ、って感じだった。導火線に火が点くのを待つような関係、というかね。いつ爆発してもおかしくないような」
「旅行先で、ひと……それも、たとえ関係が良好ではないにしろ、一応は友達になる相手を殺すような出来事って、いったいどんなことがあったんでしょうか?」
「ひとがひとを殺す理由なんて、他人が聞けばたいしたことのないものばかりよ。それは、ね。コウ。あなたもよく分かっているはずでしょ」先生が意地の悪い表情を僕に向ける。僕が何も答えずにいると、彼女はくすりと笑って、話を続ける。「ごめんごめん。まぁなんとなく想像は付くけど、つまらない理由よ。想像が付かないなら知る必要もないこと。まぁでも今回の一番の被害者は渚ちゃんのお姉さんね、間違いなく。本人の知らぬところで加害者になってしまう、というのは本当に可哀想だ、と思う」
「ということは、やっぱり実行犯、というか、実際に殺人に手を染めたのは渚さんのお姉さんなんですね」
「幽霊そのものは人の首を絞めたり、刺したり、あるいは突き落したりはできないから、ね。だとしたら犯人はお姉さんの肉体を操った渚ちゃんと考えるのが妥当かな」
先生はそこで話を終わらせるつもりだったのか、ふぅ、とひとつ息を吐いたが、僕としてはまだまだ腑に落ちないところは多い。
「なんで、お姉さんの肉体に憑いたのでしょうか?」
「まだ続けるの? そんなの、本人しか分からないに決まっているでしょ。どうしたの急に探偵にでもなりたくなった?」
「探偵になりたい、と思ったことはないですが、探偵助手の役目を担うことはありそうですからね。先生の推測を教えてください」
「さっき頼りになってきた、って言ったけど、前言撤回。生意気、のほうが適切ね。最近、どんどん生意気になっていくね。それに中学生の子たちと同じ年齢とは思えないくらいに大人びてきたし……」
「学校も行かず、先生とばかり一緒にいたら嫌でもこうなります。同じ先生でも、学校の先生とは違って、毒のあることしか教えてくれませんからね」
さっきの意地悪への仕返しを込めた冗談に、先生は楽しそうに笑った。
「本当に生意気だ。……まぁ行方を消した妹の消息を追う姉の執着心と悪霊になった妹の復讐心がシンクロしたんじゃないかな。離れて暮らしている、とはいえ、可愛い妹と長く連絡が取れなければ、必死に探すだろうしね。彼女たち姉妹の仲の良さまで私は知らないけれど、もしかしたら意外と復讐には姉自身の想いも重なっているのかもしれない。可愛い妹の復讐心が自分の肉体と心に宿って、それで霊に乗っ取られやすくなっていた、みたいなね」
「最後にひとつ……、渚さんの霊にひとを殺した自覚はあったんでしょうか? どうもそんなふうには見えませんでした」
「もちろん気付いてなかったでしょうね。気付いていたら、ここに来るわけないでしょ。除霊してください、って言ってるようなものよ。いや消える瞬間にもしかしたら思い出したかもしれないけれど、そればっかりは推測もできない。残念ながら、ね」
「そもそも、なんでここに――」
「はい、最後の質問はもう終わったはずよ」
と僕の言葉をさえぎって、先生が部屋から出て行く。
偶然、旅行先で一緒になった先生は、もしかしたら彼女たちの間に流れる雰囲気に気付いて、そっと背中を押したんじゃないだろうか。人間には理性がある。その理性を払うような言葉を囁いたのではないだろうか。僕の知る先生は、そういうことを平気でする人間だ。
悪魔が、殺せ、と耳打ちするようなイメージがふいに浮かぶ。
やめておこう……。どうせ先生が真実を教えてくれるはずなんてないのだから、考えるだけ無駄だ。
その夜、僕は夢を見た。目まぐるしく場面は切り換わり、それはひとりの人間が死にいたる過程を表していた。
「私、いまの彼氏と結婚しようと思ってるの」「ねぇ渚の奴のあの話……社長の息子と結婚する、って……、しかもあんな有名な」「馬鹿にした言い方だったよね」「うん。絶対に私たちのこと見下してた。私たちがあまり彼氏とうまくいってない、って聞いた途端、あんな話するなんて」「早苗……、別に渚だって悪気があったわけじゃ」「悪気しかないよ、あんなの」「恵美まで……」「正直に言ってよ、咲。あんな小馬鹿にした顔で彼氏の自慢してきて、むかつかなかった?」「それは……」「知ってるからね。あんただって、そんなふうに言ってるけど、高校の時、自分をよく見せるために、渚をそばに置いてたこと。事務所のオーディション、渚を無理やり一緒に参加させてたのも知ってるよ。引き立て役にされた、って――」「それ、渚が言ったの?」「まぁ、ね」「あいつ、黙ってろ、って言ったのに」「ほら、本性、表した」「あいつはそういうやつなのよ」「自分をわざと一番下に見せておいて、陰では私たちを馬鹿にしていたのよ」「初対面のあの先生なんて、たった数時間しかいなかったのに、あなたたち仲悪いの、なんて聞いてきたくらいだからね。あいつがいない時の私たちはそんなことないのに、あいつがその輪に入ると、いつもそう」「私たち三人は仲良いよね?」「もちろん」「悪いのは、全部あいつ。あいつさえいなければ、私たち三人はうまく行く」「ねぇ、どうするの。早苗」「もちろん決まってる。調子に乗った下っ端の末路なんてね」「それ、って……」「そんな不安そうな顔はしないで、咲。大丈夫、絶対に失敗なんかしない」「でも、いくら嫌いだから、って……」「でも、さぁ」「何よ、恵美」「こんな話聞いちゃって、逃げられると本当に思ってるの? 同じ目に遭っちゃうかもしれないよ」「いや、別に逃げるなんて……」「本当に大丈夫、大丈夫だからね、咲。絶対にばれないから」「……分かった」「準備、できたよ」「ねぇ恵美」「何よ。もう咲がすることなんて何もないんだから、後はゆっくりと待ってたらいいよ」「恵美、って私たちと違ってさ、中学の時から渚と一緒にいたわけじゃない。なのに、……いいの?」「何が? 一緒にいたけど、ずっと嫌いだったからね。ほら、いまも私、笑顔でしょ。嬉しくて仕方ない」「ねぇ、早苗。私、もうこれが終わったら、恵美とは関わりたくないな」「私も、同じ気持ち。あれは、ちょっと……」(ん…。うん……ここ、どこ。わっ。土。何、これ。身体が動かない。あれ、なんで恵美、そんなに高いところにいるの。やめてっ、土を落とさないで。なんでなんで、そんなことするの。なんで、笑ってるの。早苗まで。やめて。声が出ない。う。苦し、苦しい。咲、なんで悲しそうな顔してるの? そんな顔するくらいなら、助けてよ……助けろよ。なんで、なんでよ。……許、さ、な、い。お前たち、絶対に許さない、から……)
第一話「死にゆく者の祈り、2002」まとめ読み版(終)
