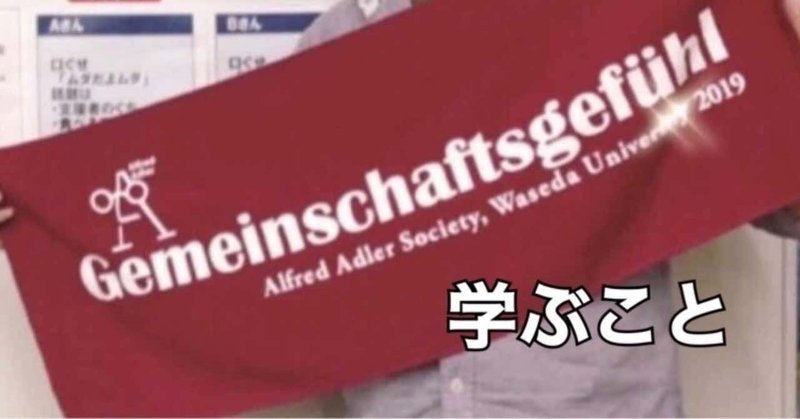
アドラー心理学を福祉現場に活かそうと思ったきっかけ(アドラー心理学実践講座 第5回目より) ①
10月03日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「アドラー心理学実践講座」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面でどのように活用できるか実践報告を交えて考えていきます。
10月31日、第5回目のテーマは「感情は価値観のセンサー」でした。まず、グループによる質問会議から始まりました。今日はその質問会議で取り上げたテーマから思いあたる事例を書きます。
その質問は、いつも怒っている人はそれがその人のライフスタイルととらえてよいのかというものでした。
向後先生から、その人が怒る目的についてアドラー的な解説がありました。いつも怒る、怒鳴るということはそのことで、自動的に自分は相手より上、相手は自分より下ということを確認していると言います。さらに相手よりも自分は常に上にいるべきというのがその人の信念ということになります。
私たちは、怒る必要のないことで、声を荒げることがあります。それは、アドラー的に言えば、怒りで相手を操作しようとしていることです。私がアドラー心理学に出会って、一番最初に改善しようとしたことがこの怒り感情に対する対応です。
障害のある人の支援場面でのことです。日中活動で利用者がトイレに入ったあと、電気を消し忘れることがあります。また、グループホームでは自分の部屋のテレビや電気を消し忘れてリビングに来ることがあります。支援者はそれを見つけると強い口調で、電気の消し忘れを指摘します。周りで見ていると怒っているように見えます。支援者が怒った口調で物を言うと、他の利用者もその利用者に対して怒ったような口調で物を言うようになります。その人はいつも怒られている人になってしまいます。
支援者に、なぜ怒ったような口調で物を言うのか聞きました。支援者は、何回言っても言うことをきかないから少しきつく言った方がいいと思います、と言います。それを聞いて思いました。何回言っても伝わらないのは、支援者の伝え方が悪いのではないでしょうか。
しかし、アドラー心理学に出会う前の私は、同じように怒った口調で物を言っていました。今は、そのような場面では、感情を使わずに「電気を消してきてくれる?」と言えるようになりました。怒らなくても十分伝わります。また、電気を消して来たら「ありがとう」と言います。すると他の利用者もマネをするようになりました。それまで怒られる人だった利用者が感謝される人に変わりました。
このエピソードが、アドラー心理学をもっと支援に活かしていこうと思ったきっかけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
