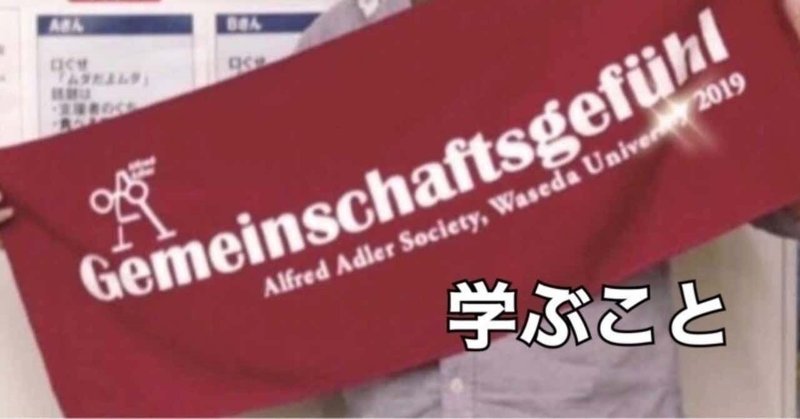
怒りの仕組みを理解しよう(アドラー心理学実践講座 第7回目より) ③
10月03日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「アドラー心理学実践講座」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面でどのように活用できるか実践報告を交えて考えていきます。
11月14日、第7回目のテーマは「感じられたマイナスとその反応」でした。今回の講義では、質問会議の解説から、怒りについて、アドラー派とアンガーマネジメントを対比させた説明がありました。今日は、その話を聞いて思い出したことを書きます。
私は、5年前に私の法人の役員のすすめで、アンガーマネジメントの入門研修を受講しました。その後、しばらくしてある支援者が、独学でアンガーマネジメントの本を読み、それに影響されて研修の企画を立てました。参加した支援者たちからは、実践的な研修だったと好評でした。その後、どの程度、日常的な怒り感情が削減されたかは検証できていません。しかし怒りたい人は、やはり怒りたいらしくいまだ怒りを武器や鎧にしています。
利用者の行動に対して、「何度言ったらわかるんだ!」と興奮している支援者がいました。言葉や態度をあらためるように話をすると、「ダメなことをダメと言って何がいけないんですか」とまた興奮しました。
事業所間のトラブルで相手の事業所に対して言葉を荒げている支援者がいました。もう少しやわらかい物腰で対応するようにと話をすると、「これぐらい言わないとわからないんです」と言い返されました。
怒りを武器に戦っています。
また、事故の再発防止会議で「そんなこと言っても仕方ないじゃないですか」と大きな声でバリアーをはる支援者もいます。
怒りを鎧にしています。
いろいろな支援者がいます。その中には、怒りを武器や鎧にするのが得意な人がいます。その人たちは相手よりも強い位置にいるために怒りを使っています。怒ってはいけないということではありません。怒りを武器にして問題解決にあたっても真の解決にはなりません。怒りを使えば相手を服従させることはできます。しかし、相手は遠ざかります。
アドラー心理学では、怒りは自分の信念に触れたとき発動されるとしています。また常に目的論です。怒りの目的を考え、破壊的ではなく建設的に解決策を探します。
アドラー心理学に出会って5年が経ちました。なぜ、あのとき私から利用者が遠ざかったのか、私は正しいことを言っていたのにあのご家族からクレームが来たのか、わかってきたことがたくさんあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
