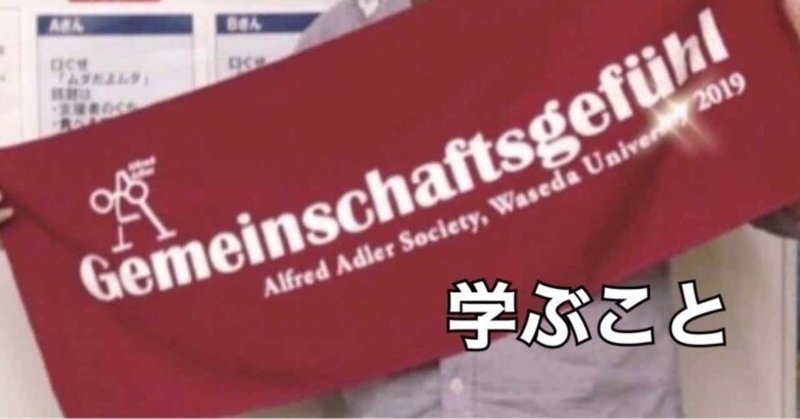
結びつける感情と切り離す感情(アドラー心理学実践講座 第5回目より) ②
10月03日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「アドラー心理学実践講座」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面でどのように活用できるか実践報告を交えて考えていきます。
10月31日、第5回目のテーマは「感情は価値観のセンサー」でした。講義では2種類の感情について説明がありました。
感情には、結びつける感情と切り離す感情があります。結びつける感情は、喜びや思いやりなどポジティブな感情で、自分と相手の距離を近づける感情です。反対に切り離す感情は、怒り、悲しみ、うんざり、恐れ、不安などネガティブな感情で、自分から相手を遠ざける感情です。さらに私たちは、感情を発動させて対処行動を起動すると説明がありました。
障害のある人の中には、言葉で自分の状況を伝えることができない人たちがいます。そういう人たちにとって、感情は大切な意思表示です。しかし、実際の支援場面ではその感情が正しく評価されないことがあります。
障がいのある利用者が、陽気に浮かれて笑いながら声を出していたり、誰か特定の人の前ではしゃいでいると、支援者は「少し落ち着きなさい」と言います。反対にイライラしたり泣いたりしていても、支援者は「少し落ち着きなさい」と言います。支援者は利用者が感情を表出することを苦手とします。
今回の講義内容を参考にすると、ポジティブなときは、もっとここにいたい、もっとこの人と一緒にいたい、というメッセージです。反対にネガティブな感情は、一刻も早くここを離れたい、この人とは一緒にいたくない、というメッセージです。言葉による意思表示が苦手な利用者の感情を正しく受け止めることは、意思決定支援に欠かせないスキルになります。
人との付き合いでは、感情を強く出すことは良くないことという風潮があります。アドラー心理学では、自分が感情に支配されることを「所有の心理学」、目的のために感情を使うことを「使用の心理学」と区別しています。
言葉による意思表示が苦手な利用者は、感情を使って目的を果たそうとしていることもあるということを理解する必要があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
