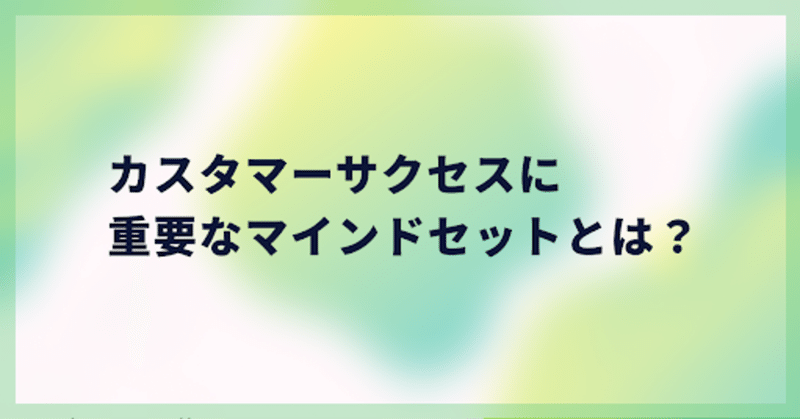
カスタマーサクセスに重要なマインドセットとは?
こんにちは。アルプのカスタマーサクセスの水谷(@ryoji0112)です。
アルプは、サブスクリプションビジネスを行う企業向けに、今まで手作業や自社開発がスタンダードだった契約や請求管理を SaaS として提供する Scalebase というプロダクトを開発しています。
前職で10年以上従事してきたセールスからキャリアチェンジし、アルプではカスタマーサクセスとして日々スキルを研磨しています。
そのスキルを試すべく、12月16日に開催される「カスタマーサクセス天下一武闘会2021」という、カスタマーサクセスの取り組みや事例などをプレゼンする大会の本戦に出場します。
「カスタマーサクセス天下一武闘会2021 presented by Growwwing」本戦出場者紹介!
— CS HACKのひと (@cshackJP) November 20, 2021
BtoB Sales 10年から CS への転身
水谷 亮道さん
アルプ株式会社
カスタマーサクセス
プレゼン対象プロダクト:Scalebasehttps://t.co/zxn45Osot8
参加はこちら → https://t.co/YBlqeuz7AR#CSHACK pic.twitter.com/FuoIbVyStI
今回は、本大会に向けた思考の整理を兼ねて、「カスタマーオンボーディング(以下、オンボーディング)」で心掛けていることをお話します。
オンボーディングとは、製品の導入プロジェクトを立ち上げて、進捗の管理や課題などを洗い出しながら、実際の稼働までサポートするカスタマーサクセスの役割の1つです。
アルプのカスタマーサクセスの役割については、前回の記事をご覧ください。
お客様の理想との乖離を埋めて、明確なゴールを設定する
お客様は、プロダクトの導入前から高い期待と理想を持ってくれています。
Scalebase は、本稼働までに機能を開発したり、運用でカバーしたりとお客様の要望を可能な限り実現できるように取り組んでいます。しかし、全てに対応できる訳ではありません。
オンボーディングは、プロダクトの機能や導入までの期日などを鑑みながら、お客様の期待とプロダクトが実現できることを擦り合わせる必要があります。そのため、コミュニケーションやゴール設定が重要です。
1. 期待値を擦り合わせる
プロジェクトは "期待と現実との乖離の判明" からスタートします。
セールスの実体験に基づきますが、契約時は自然とお客様の期待値が高くなるため、セールスの提案以上に過度な場合もあります。
オンボーディングで重要なのは、(至極当たり前のことですが)絶対に嘘をつかないことです。場を取り繕う言葉ではなく、真摯な態度でお客様と接することで、プロジェクトのゴールの方向性を補正します。
コミュニケーションのポイントは、「個々の機能でできること」より、お客様のシステム導入における「大きな目的は何か?」へ常に目を向けるようにし、そこから逆算してその大きな目的を達成するための設計図を共有していくことです。
2. キックオフ時点のゴール設定の重要性
スタートからゴールまでに時間を要するプロジェクトでは、お客様の描くイメージが当初から変わる場合もあります。そのため、キックオフ時点のゴール設定が重要です。
細かな機能要件ではなく、要所をおさえることです。「その要所は何か?」を徹底的にお客様とコミュニケーションを取り、要所以外を絞ることです。
絞るというと「できない」というネガティブなイメージを持たれるかもしれませんが、そうではなく、ゴール設定がブレる要因の中でも「欲張りすぎてしまう」という大きなリスク、それにともなって発生する摩擦係数を少なくすることで、早く利用を開始する方がお客様にとってメリットが大きくなります。
加えて、キックオフ時点で「できること」と「できないこと」をお互い認識することで、プロジェクトの途中で「できないこと」が出てきても、要所を抑えて同じ方向を見ての相談ができます。
信頼と納得でプロジェクトは成り立つ
前職のセールス時代は、既にプロダクトが成熟していたこともあり、機能不足が発覚しても基本的には追加開発がなくても運用が回る前提がありました。そのため「できません」というコミュニケーションをカスタマーサクセスがしてしまい、トラブルに発展してしまった案件のフォローに入ったことがありました。
スピーディーかつ効率的にプロジェクトを進める上で、議論や検討する時間は遅延リスクだというのは理解できます。ただ、コミュニケーションの基本の「人の話をちゃんと聞く」スタンスがないと、仮にこちらの主張が正しかったとしてもお客様に「この人は自分の話を聞いてくれない」と受け取られてしまいます。
「まず話を聞くこと」の重要性はセールスもカスタマーサクセスも等しく高いです。
Scalebase は、本稼働までの期間でお客様に必要な機能を実装したり、将来的にお客様が期待される機能が実装される可能性を持ったプロダクトです。そのため、すぐに結論を出すようなコミュニケーションはしません。
ご要望については「おっしゃることはわかります」ということも多いため、そう感じた際には素直にその気持ちを言葉として伝えた上で、「ここができないかもしれません」と期待値を上げすぎないように留意しています。また、「一度できる方法を考えてみます」と社内でも実現や代案の可否を確認し、経験則だけで判断しないように気を付けています。
結果的にお客様のご要望を叶えられないケースもありますが、しっかりと検討して案を出した、という事実が納得と信頼を生むことを実感しています。
進行の課題例と解決方法
プロジェクトでは、お客様で作業が進まず、停滞する場面によく遭遇します。そんな時に取るべき対策や解決方法などの一例を紹介します。
1. 導入後のイメージがついていない
こちらの話を納得しているように見えても、お客様の中でちゃんとイメージできていない場合があります。口頭で伝わらなければ、画面上で一緒に手を動かしてナビゲーションしながら作業するのが最も効果的です。お客様が実際に製品に触れることで、やりたいことや課題もより明確になります。
2. 工数がたりない
マイルストーンを決めることが重要です。マイルストーンを細かく決めてこちらから能動的にチェックをしていきます。課題の数、課題の消化率などを数値に落として管理する力が必要です。
ただし、プロジェクトは常に変化しながら進行します。期日管理の妥当性はとても難しく、ただ単純に課題の管理をしているだけでは意味はありません。期日やステータスの置き方、バッファーなどをどこに置くかが腕の見せ所です。
また、導入が大きく遅延するなど、プロジェクト進行に致命的な問題が起きた際の対応プランと、そのプランを発動する条件を事前に決めることも重要です。
遅延リスクがあれば、お客様の上長に事前にインプットし、キックオフ段階で合意しておくのも良いやり方です。お客様の上長にも、どのタイミングでプランを実行するのかを事前に合意してもらうことで、スピーディーに問題を解決し、影響を最小限に抑えられます。
3. 相手を思う
Scalebase は、基幹システムのような立ち位置なので大規模なプロジェクトになりがちです。先方も相当のコストをかけているので、矢面に立っている担当者の方は、社内でプロジェクトがスムーズに進行していることを報告したいはずです。共有する場面では、例えば上司に伝えるシーンを想像し、私たちが上司に報告するような気持ちで、状況を担当者の方に話しています。
終わりに
オンボーディングを担当する価値は、「お客様の成功を一緒に喜べること」に尽きます。スタートからゴールまでを全力で伴走し、最後までお客様に寄り添いながらプロジェクトに取り組む関係は、オンボーディングならではの特権です。
また、オンボーディングは、事業内容が異なるたくさんのお客様を対応するため、自分に向き合う力がつきます。いくら応用力や対応力があってもお客様から100点の評価をもらうのは、ほぼ不可能に等しいです。自分の力が20点だとしても、及第点まで持っていこうとする過程が成長のポイントです。
今回の記事で、頭の中でなんとなく曖昧にしていたことを言語化して整理さできました。Scalebase は常に進化しているので、より大きなプロジェクトになっても有用な思考にできるよう、引き続き経験知をアウトプットしていきたいと思います。
アルプではカスタマーサクセス含め、積極的にメンバーを募集しています。今回の記事を見てご興味を持ちましたら、ぜひ Meety で私とカジュアル面談しましょう!よろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
