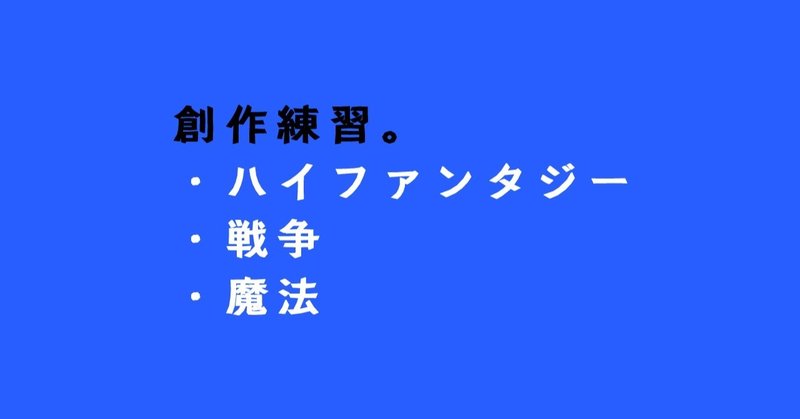
戦争ものファンタジーな創作練習。
小説執筆の練習です。
ゲームシナリオよりもしっかりと描写を意識。
灰の使い(仮題)
昨日笑ってたやつが、今やどこかで静寂に身を浸している。
そんなことは戦場において当たり前、そう自覚していたはずなのに鉄の塊を持った手は震えて仕方ない。
「——なんで。なんでこんな事に、俺が一体何をしたって言うんだよ」
命の保証なんてものは戦場において一つもなく、豊かな自然で彩られていた世界は赤黒い液体に染まっていく。
俺の手も、足も、心も。身体すべてが気味の悪い錆臭さに包まれていて、呼吸するだけで何重もの吐き気が胃からこみ上げてきた。
「あんなの勝てる訳がねえ……。おかしいだろッ。本を開くだけで世界を灰にしてしまう程の炎が、目の前に一瞬で」
あの時。十九歳である自分よりも四つは下であろう少女と対面した時。起きたのは神に選ばれた女性だけが使える“魔法”とかいう謎の現象。
一万分の一よりも少ないその才能の持ち主が、眼前で幾多の仲間たちを焼き尽くしていた。
助けての一言を零すことも許さず、何が起きたかを理解する前に炭へと還る。まさに地獄のような光景だった。
「生まれ、性格、体質、性別……結局、努力よりも運で得た才能には勝てる訳がない。どれだけ鍛えても、どれだけ戦場を潜り抜けても、あんな化物にどうやって勝てって言うんだ」
数日前までズラリと並んでいた何万もの兵士が今何人残っているのかも分からない。
少なくとも俺が背を預けている二メートルの塹壕には一人も見当たらない。正確には生きている人間は、だが。
「デビット、コール、シャンティ……生きてはいないよな」
少し前に別れた仲間たちの顔を思い出す。
燃えていく恐怖に染まった表情ではなく、昨夜酒を片手に“生きて帰ったら何をするか”を語り合った笑顔を。
俺も馬鹿みたいに笑いながら、交際している彼女にプロポーズをするのだと意気込んだ覚えがある。
「カール少尉はよりにもよって俺の目の前で炭化した。あの光景を思い出すだけで……。ああ、もう吐ける物もありやしねえ」
吐き気はする。だがもう既に片手の指の数くらいは戻した。
辺りから聞こえる鼓膜を劈くような爆音。その度にビリビリと煤けた肌は痺れ、未だ止むことのない悲劇に酷い頭痛が起きる。
「ああ、クソったれが……。一体、俺が何をしたって言うんだよッ!」
その矛先にいるのは選ばれし魔法使いか、この世の果てに存在する神々か。
少なくとも自分が死ぬかもしれないという状況で、弱さや努力の少なさを悔いる程に、俺はできた人間ではなかった。
ただ降り掛かった理不尽という名の運命に、怒りを込めた拳を土へと打ち付けるしかできない。
「ああ、何でもいいから助けてくれよ」
震えを止めようとして、胸前で両手を祈るように強く握る。
もう銃弾もなければ食料もない。生き残る確率はほとんど無し、今の自分が生きているのかどうかすらも怪しい。
ただそれでも。感じている心臓の鼓動が本物ならば。
「誰でもいいから……俺を、生きて、帰らせて——」
絞り出すような乾いた声。当然返事など有り得ない。
そう、有り得ないはずだった。
「——君は、生きたいの?」
感情のない、冷たくも幼い声。反射的にその音が聞こえた方向、塹壕の上を見上げた。
そこは戦場で、生き残る為に作られた堀の外。つまり仲間であるはずがなく。
「お、お前は」
頭まで覆うような灰色のローブを着た、腰まで銀髪を伸ばした少女。その手には仲間を燃やし尽くした奴と同じような、抱える程度に分厚い、革表紙の本がある。
この戦場にどれだけの数のこいつら——魔法使い、と呼ばれる女性——がいるのかは分からないが、彼女に見覚えはなかった。
必死に逃げながら見た光景は一生忘れることができない程に網膜にこびり付いている。あの時高笑いしながら迫ってきたのは、赤い本を持った狂気を具現化したような女だったから。
「……もう一度問う。君は生きたいの? それとも死にたい?」
抑揚を忘れた声で問いかけられても返事が出来ない。
改めて死が目前に迫っているのを見て、過呼吸気味になりながらそれを見つめる。
長い睫毛によって包まれた左右で色の違う瞳。死の象徴でありながらも、見惚れてしまいそうなその虹彩の輝きに視線は吸い込まれていた。
「返事をして、くれない? なら、死ぬ?」
彼女の言葉にまるで自身を心配しているようなニュアンスを感じた。
例え感情が乗っていなくとも、そのような問いかけをする時点で敵国の兵士である俺に情けを掛けているようなものだ。
普通ならそんな問いかけなどせずに殺すだろう。これまで出会った奴らは全員そうだったのだから。
「お、俺は……俺は……」
喉の皮が割れてしまいそうなくらい、渇く。
どれだけ唾を飲み込んでも湿ることはなく、ひゅーひゅーと自分の物だとは思えない無声音が響いていた。
それでも、もしもこの理不尽に抗うことが出来るというのなら。
「…………俺は?」
彼女はそう聞き返しながら、ここが戦場であることすら分かっていない、可愛らしい子供のように首を傾げていた。
あまりにも場違いな雰囲気に、俺は一縷の望みを抱いて。
「生きたい。死にたくない……ッ。俺は、まだ、生き残ってやりたいことがあるんだよ」
好きな人がいるんだ。故郷であるフルレミアに帰り、軍役で得た金で指輪を買って、愛する彼女に婚約を申し込むのだから。
そんな理由を知りもしない少女は、相変わらず冷めた瞳で。
「なら、契約を求める。君が裏切ることのできない絶対を」
「……は?」
彼女の思惑がまったく分からないから、期待させてから殺すような最悪の事態は想像していた。
だが、その小さな口から出てきたのは考えもしなかった契約という二文字。奴隷になれだとか、そういうことを言っているのか?
「違う。でも、私は君を欲している。共にこの世界を壊してくれる、運命に抗うことが可能な存在を」
「世界を、壊すだと……?」
こちらのオウム返しを聞いて彼女はようやく表情を変えた。戦場には似つかないような至極嬉しさを含んだ笑顔へと。
それを見た俺は理解した、少女こそが一番狂っている存在なのだと。
だってそうだろう。殺し合いが当たり前のこの場所で、尋常ではない程に純真な笑みを浮かべて敵兵に手を差し伸べているのだから。
しかし狂気を魅せられたのか、またその双眸から視線が離せなくなって。
「君に選択肢はない。だから、まずは私について来て」
元からこの手を取るしかないのだと、そう告げられてしまえば出来ることは二つだけ。
このまま野垂れ死にを迎えるか、彼女の契約を受け入れるか。
「そんなの……ついて行くしか、ないじゃないか」
諦めのような、そんな言葉を零して。俺は彼女の手へと触れた。
「私はミラ・エルフィス。君は?」
「……アレン。貴族じゃないから姓はない、フルレミアのアレンだ」
そう告げると彼女——ミラはまた無表情に戻ってよろしくと返してきた。本当に思っているのかも疑わしく思うが、一々疑っていても仕方がない。
俺はこの瞬間から生殺与奪権を奪われた、少女の契約者となったのだから。未来を生き残って恋人と再会するには、どんなことであっても従わなければならない。
それが例え、祖国に弓を引くことであっても。
「仲間にバレると拙い。君にはこれから数日身を隠してもらわないといけない、ごめんね」
ミラは自身の別荘で過ごすようにと通達しながら、本を開いて手を当てた。
「本よ、身隠しの布を出して」
暖かい光を放ちながら、本のページは誰の手を借りることなくパラパラと捲れ、彼女と同じ灰色のローブが現れた。
この戦場に来る前ならば有り得ない光景だと叫んでいただろうが、この超常現象を何度も見たことで慣れている。
とはいえ不気味さは拭えない。ん、と小さく声を出しながら差し出される衣服を震える手で受け取った。
「それじゃあ、隠れながら行く」
「行くって……どこに別荘があるんだ?」
彼女は振り返ってまた小さく首を傾げた。
そして言っていなかったことに気付いたのか、小さくあっと声を零してから俺の方へと向き直った。
「私の国、セルフィリア帝国の帝都」
「帝都って……お前」
「——連れて行ってあげる。私たちの心臓部へ」
声も顔も、無表情だと言うのに。
年相応に俺をからかっているように見えたのは、きっと気のせいなのかもしれない。
執筆終わり。
描写は以前よりも上手く出来たかな、と思うが話が微妙かもしれない。
掴みとして長過ぎるか否か。
第1話を想定して書いたけれど、どうだろうか。
もしも記事が参考になったら、スキやフォローよろしくね! 気が向いた時はサポートで支援していただけると嬉しいです。
