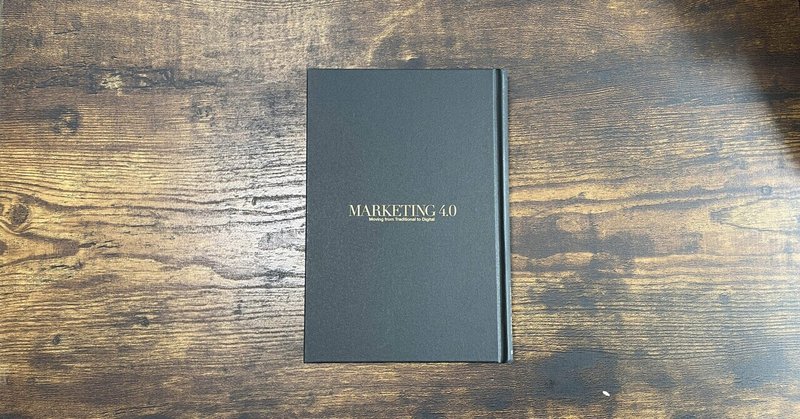
読書メモ#3 コトラーのマーケティング4.0
ブックカバーを外してみたら、あまりにも好み過ぎてヘッダー画像は剥き出しのままに〜。読む本ってその人の今の興味関心をそのまま映してるからなんか恥ずかしいよね。フレームワークたっぷりの本は感想とメモが書きづらいことも今回よく分かった。でも振り返りには最適だったー!
全体感想

マーケティングの専門書の類は基本消費者向けのビジネスや起業を例に取っている場合が多いので、B2Bかつ無形商材のビジネスをしている私にとっては理解はできるが実践するにはある程度、思考の転換をしないといけない。一部カスタマージャーニー「金魚型」のようにB2Bの事例も出てくる。加えて、最後の章にあるコンテンツ作りに関しては実践的にも参考になった。
より強いつながりを持つこと、繋がっているという認識を持ってもらうことが、意思決定プロセスが長く、重いB2Bのマーケティング重要なテーマだと改めて考えるきっかけになった。フレームワークがたくさん出てくる本なので、自社と照らし合わた際にもう一度気になってチェックつけたところを読み直したい。
メモ:第2章 繋がっている顧客に対するマーケティングのパラドックス
<パラドックス①> オンライン交流 対 オフライン交流
技術はオンラインの世界にもオフラインの物理的空間にも影響を及ぼし、オンラインとオフラインの究極の融合を可能にする。NFCや位置情報に基づくiBeaconなどのセンサー技術、分析エンジンによるビックデータ解析はパーソナライゼーションを可能にする。インターネット登場前のマーケティングである根幹だった伝統的なヒューマン・インターフェースを補完するのである。
<パラドックス②> 情報を持っている顧客 対 注意力散漫な顧客
探究心や知識レベルが上がっているにもかかわらず、何を買いたいと思うかを自分でコントロールしていない。購買決定を下す際、顧客は基本的に3つの要因に影響される。
(1)テレビ広告、印刷広告、広報活動などの媒体を通じたマーケティングコミュニケーション
(2)友達や家族の意見
(3)過去の経験に基づいた、特定のブランドに関する個人的な知識や態度
顧客は他者の意見に大きく依存するようになっており、他者の言葉は、個人の好き嫌いやマーケティング・コミュニケーションよりも重みを持つ。それは接続性そのもので、大きな保護と信頼性をもたらしている。
<パラドックス③> 批判的な意見 対 好意的な意見
ブランド推奨の最も有名な測定基準はフレデリック・ライクヘルド考案「ネット・プロモーター・スコア(正味推奨者比率)」。
<顧客の3タイプ>
・ブランドを推奨するプロモーター(推奨者)
・中立的なパッシブ(中立者)
・ブランドを推奨するとは思えないデトラクター(批判者)
ネット・プロモーター・スコアは、批判者の割合を差し引いた推奨者の割合によって表される。批判的な口コミの悪影響は好意的な口コミの好影響を弱めるということで、ロイヤルティを追跡調査するために役立つ考え方。ただ接続性の文脈では、好意的な意見を贔屓出すために批判的な意見を必要とする場合がある。批判的な意見が表明されなければ、好意的な意見は表に現れないままになる。両方の意見がなければ、人々を魅了しなくなる。
メモ:第4章 デジタル経済におけるマーケティング4.0
マーケティング4.0とは、企業と顧客のオンライン交流とオフライン交流を一体化させるマーケティング・アプローチである。またスタイルと内容を融合させるものである。技術トレンドの変化の中で、ブランドがより柔軟に適応することは必要不可欠だが、ブランドの本物の個性がかつてないほど重要になっている。
<セグメンテーションとターゲティングから顧客コミュニティーの承認へ>
伝統的には、マーケティングは常にセグメンテーションからはじまる。セグメンテーションとは、地理的・人口動態的・心理的・行動的プロフィールにもとづいて、市場を均質な集団に分けることである。セグメンテーションの次には、通常、ターゲティングが行われる。これはセグメントの魅力どやブラドとの相性にもとづいて、ブランドが売り込み対象にするセグメントを選ぶ作業である。この二つを行うことで、効率的な資源配分と良いより明確なポジショニングが可能になり、マーケターは複数のセグメントに、それぞれ差別化されたオファリングを提供しやすくなる。
<ブランド・ポジショニングと差別化から、ブランドの個性や規範の明確化へ>
伝統的な意味でのブランドは、企業の製品オファリングやサービス・オファリングを競合他社のものと区別する一連のイメージ(ほとんどの場合、名称とロゴ、タグライン)である。またブランドは企業のブランド・キャンペーンによって生み出されたすべての価値を貯蔵する容器の役目も果たす。近年では、起業が顧客に提供する総合的な顧客体験の象徴にもなっている。だからこそ、ブランドは企業の戦略の土台になりうる。企業が関与するいかなる活動も、すべてブランドと結びつけられるからだ。
<ブランドの個性と規範>
個性はブランドの存在理由である。ブランドの中核部分がそのルーツに忠実でありつづけるとき、外側のイメージは柔軟に変化しても構わない。
例)グーグル→Google Doodle
ロゴを何度も変えることによって賢個で、それでいて柔軟なブランドでありつづけている。
<4Pを売り込むことから、4Cを利益につなげつことへ>
マーケティング・ミックスとは、顧客に何を提供するか、どのようにして提供するかを計画する上できわめて重要なツールである。
◆マーケティング・ミックスの枠組みを構成する"4P"
製品(Product)
価格(Price)
流通(Place)
プロモーション(Promotion)
◆顧客参加の増大に対応できるように発展した"4C"
・共創(co-creation)
▶︎デジタル経済では、共創が新しい製品開発戦略になる。
・通過(currency)
▶︎デジタル時代には標準価格設定からダイナミックプライシングに進化している
・共同活性化(communal activation)
▶︎チャネルの概念もシェアリング経済、ピア・ツー・ピアなどの変化がある
・カンバセーション(conversation)
▶︎一方通行の活動ではなくソーシャルメディアやネト状での直接的な会話が重要になる。
メモ:第5章 新しいカスタマー・ジャーニー
◆カスタマージャーニーのフレームワークで広く活用されている"AIDA"
・注目(attention)
・興味(interest)
・欲求(desire)
・行動(action)
広告部門が広告をデザインしたり、販売部門が見込み顧客にアプローチしたりするときに簡単なチェックリストもしくは注意メモとして役立つ。
◆AIDAの修正版を提唱している"4A"
・認知(awereness)
・態度(attitude)
・行動(action)
・再行動(act again)
この新しいフレームワークでは、興味と欲求の段階が態度という一つの段階にまとめられ、再行動という新しい段階が追加されており、購買後の顧客の行動を追跡し、顧客維持率を測定しようとしている。最高ばいという鼓動を顧客ロイヤルティの強力な代用値としてみなしている。
接続性以前の時代に活用されているAIDA、4Aは顧客個人がブランドに対する態度を決めていたが、接続性の時代には、ブランドの当初の訴求力が顧客を取り巻くコミュニティの影響を受け、顧客の最終的な態度を決定する。一見、個人的に見える多くの決定が、事実上、社会的な決定である。新しいカスタマージャーニーは、このような社会的影響の増大を反映していなければならない。
◆ロイヤルティ=(究極的に、ブランドを推奨する意思)のあ新しい定義と整合された"5A"
・認知(awere)
・訴求(appeal)
・調査(ask)
・行動(act)
・推奨(advocate)
マーケティング4.0の究極の目標は、顧客を認知から推奨に進ませることである。
メモ:第6章 マーケティングの生産性の測定指標
5Aに沿って、測定する価値があるのは二つの指標。これを用いて、認知(AI)から行動(A4)へそして最終的に推奨(A5)へと進む顧客の割合を調べる。
①購買行動率(PAR)
起業がブランド認知をブランド購買に「コンバート」することにどれくらい成功しているかを示す
②ブランド推奨率(BAR)
起業がブランド認知をブランド推奨に「コンバート」することにどれくらい成功しているかを示す
例えば、
市場に100人おり、ブランドXを自発的に想起するのはそのうち90人とする
その90人のうち、ブランドXを購入する者は18人しかいないとする
ブランドXを自発的に推奨する者は9人しかいないとする
その場合、
ブランドXのPARは18/90で0.2%
ブランドXのBARは9/90で0.1%
ブランドXは認知率が0.9%なので表面的には有望に見えるが、実際にはかなりパフォーマンスが悪い。ブランドを認知している人々の80%を販売にコンバートできなかったからである。
この二つの単純な測定指標は、財務責任者が財務の健全さを測定するために用いる株主資本利益率(ROE)のような比率に倣って作成したもの。ROEは投資した資本で起業がどれくらい利益を生み出しているかを測定しているもので、株主が自分のカネの「生産性」を把握する助けになる。同様にマーケターが自分の使ったカネ、とりわけブランド認知を生み出すために使ったカネの生産性を測定することを可能にする。
PARとBARはマーケティング投資収益率(ROMI)の優れた測定指標である。ほとんどの産業で、最大のマーケティング支出は広告によって認知度を高めるために使われるので、ROMIの算出式ではブランド認知度を@マーケティングの投資額」の代用とみなすことができる。それに対し、「収益率」は二つの要素を含んでいる。一つは「購買行動」で、直接売上に変換される、二つ目の「推奨」は間接的に売上増大に変換される。
<PARとBARを分解する>
認知から推奨へのコンバージョン率(転換率)を測定できれば、企業は最も重要な問い、すなわち必要な介入を行なって忠実な推奨者を増やすにはどうすれば良いかということがわかる。
ROEの構成要素の知見からPARとBARの構成要素を分解できる。
ROEの三つの構成要素
・収益性(準利益率によって示される)
・資産活用の効率性(資産回転率によって示される)
・借入比率(自己資本乗数によって示される)
PARの場合、
市場シェアをブランド認知率で割ることによって算出できるので、ブランド認知率を高めたら市場シェアがどのくらい伸びる可能性があるかを大まかに測定できる。
メモ:第7章 産業類型とベスト・プラクティス
金魚型:代表的な特徴は高い関心レベル。金魚型のカスタマージャーニは主に企業間(B2B)取引で見られる。競合しているブランド間の評価結果は概ね類似している。多くの場合、顧客との親密さが決定要因となる。

目指すべきカスタマージャーニは、蝶ネクタイ型。コミットメントと親近感のレベルを高めるだけでなく、好奇心のレベルを最適化する必要もある。

メモ:第8章 ブランドの誘引力を高める人間中心マーケティング
自分の立場を強くするためにコミュニティを築くことが大切。
人間中心マーケティングのプロセスは、顧客の心の奥底にある不安や欲求を明らかにすることによってスタートする。それには、共感的傾聴やデジタル人類学と呼ばれる手法を使った没入型調査が必要となる。
有名な手法には、三つある
1、ソーシャル・リスニング
ソーシャルメディアやオンラインコミュニティでブランドについてどのようなことが語られているかを積極的にモニターする作業
2、ネトノグラフィー
ネトのグラフィー(=インターネットに焦点を当てた民族学)は、民族学(エスノグラフィー)の手法を使って、オンラインコミュニティにおける人間の行動を理解しようとするもの
3、共感的リサーチ
人間中心デザイン(HCD)。ネトノグラフィーとは異なり、リサーチャーがコミュニティメンバーに直接会って、観察したり、大和やブレーンストリーミングや協働を通じて最も的を得た知見を統合する。
<ブランドが持つべき、六つの人間的特性>
横の関係のリーダーは他者を支配する権限は有していないが、他者を惹きつけ六つの人間的特性を兼ね備えている。これらの特性を備えていれば完璧な人間であり、ロールモデルになる人間と言える。ブランドが威圧的何ならずに友人として顧客に影響を及ぼしたいと思うなら、これら六つの人間的特性を備えなくてはいけない。
・身体的魅力
▶︎すぐれたデザインのロゴや巧みに作成されたタグラインなどのブランド・アイデンティティから生まれる(ex.アップルのユーザー・インターフェース、グーグル・ドゥードゥルは動的なロゴ・システムを有している)
・知性
▶︎顧客から賢いブランドとみなされている。(ex.テスラ、ウーバー、Airbnbなどの破壊的イノベーター)
・社交性
▶︎自信を持って他者と関わり、優れた言語的・非言語的コミュニケーション・スキルを示す。(ex.デニーズ・ダイナー、ザッポス)
・感情性
▶︎感情に売ったあえるメッセージで、顧客と感情レベルでのつながりを築く。(ex.ユニディーバ「ダブ」、ドリトス「超音波」広告)
・人間性(パーソナビリティ)
▶︎事故をきちんと認識できている。自分は何が得意かを自覚しており、何をまだ学必要があるかを認めている。自分が何のために存在しているのか、自らの存在理由を正確に知っている。(ex.Patagonia、ドミノ・ピザ)
・道徳性
▶︎適切な倫理的配慮があらゆるビジネス決定の重要な一部になるように行動する。顧客が見ていない時でも約束を守る。(ex.ユニリーバ・サステナブル。リビング・プラン)
メモ:第9章 ブランドのへの好奇心をかき立てるコンテンツ・マーケティング
割愛しますが、コンテンツマーケターは必須の章でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
