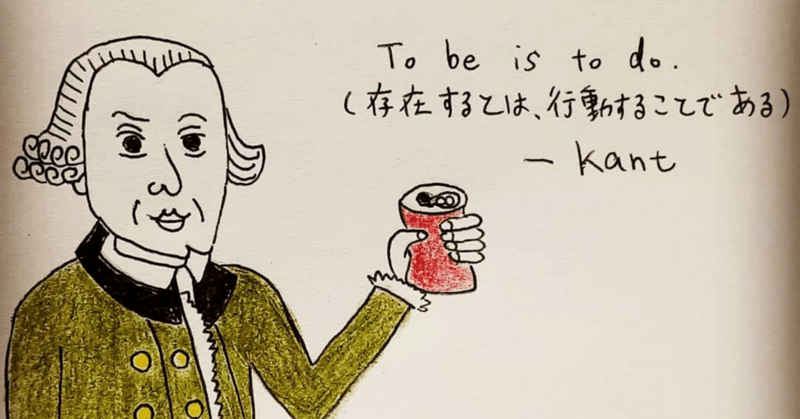
「現代思想入門」の感想 脱構築と哲学の有用性と
千葉雅也さんの「現代思想入門」を読んだ。
かなり面白くて友人にも薦められる一冊だと思った。
本のテーマは脱構築。
現代思想を代表するデリダ・ドゥルーズ・フーコーに共通するのは「二項対立」の脱構築だった。
彼らは、物事を良し悪しで決める二項対立的ものの見方ではなく、それを俯瞰したかのような脱構築的視点を打ち出す。
デリダは「概念の脱構築」を考えた。具体的には、二項対立において、あえてマイナス側の視点に立ち味方するなどして、別の論理を考える手法などが該当する。
ドゥルーズは「存在の脱構築」を考えた。すべての事物は「ある」のではなく、その無限の関係性から生まれている。
まず関係性があり、その後に事物が仮固定的に変化する。
安易な同一性を求める必要はない。ただ多様な関係の中で経験を積み重ね、従来とは異なる仮固定的視点である逃走線をつくりあげるのが良い。
フーコーは「社会の脱構築」を考えた。
私たちは権力者を二項対立的にとらえ、ヒーローを期待しがちである。しかし、フーコーは「権力は上から押し付けられるだけでなく、下からそれを支える複雑な循環構造になっている」と主張する。権力もまた単純には捉えられない。
単なる二項対立的な抵抗運動ではパノプティコン的にシステムにとらわれたままになってしまうため、秩序の逃走線を引く必要がある。
こんな感じで、1970年代あたりの現代思想を興味深く解説してくれている。
なにより著者の語り口が素晴らしい。読んでいると哲学の難しい世界に入りつつも著者の優しさに触れ、暖かい気持ちになれる。
もっと千葉雅也さんの本を読んでみようと思いました。
※補足
2000年以降の現代思想も解説してくれているが、これはあまり面白くなかった。
というか、著者自身も問題にしているが、現代思想自体がマンネリ化しているのだ。
デリダたちの時代の現代思想は量子力学的・東洋的 ものの見方を西洋で再構築しているように感じられ、社会と ある種 密接にかかわっていたと思う。
しかし、2000年以降の現代思想は社会システムと密接に結びついた新規性のある思想を打ち出せないでいる。
抽象度が高まりすぎたせいなのかもしれない。
単なる逆張りの連鎖としての現代思想ではなく、本当に社会に刺激を与えるような思想は出てくるのか。
マルクスの資本論やルソーの社会契約論は、良くも悪くもたった一人の思想の力が社会を大きく変えた。
このような力を持った思想家が現代にも現れるのか、実に楽しみだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
